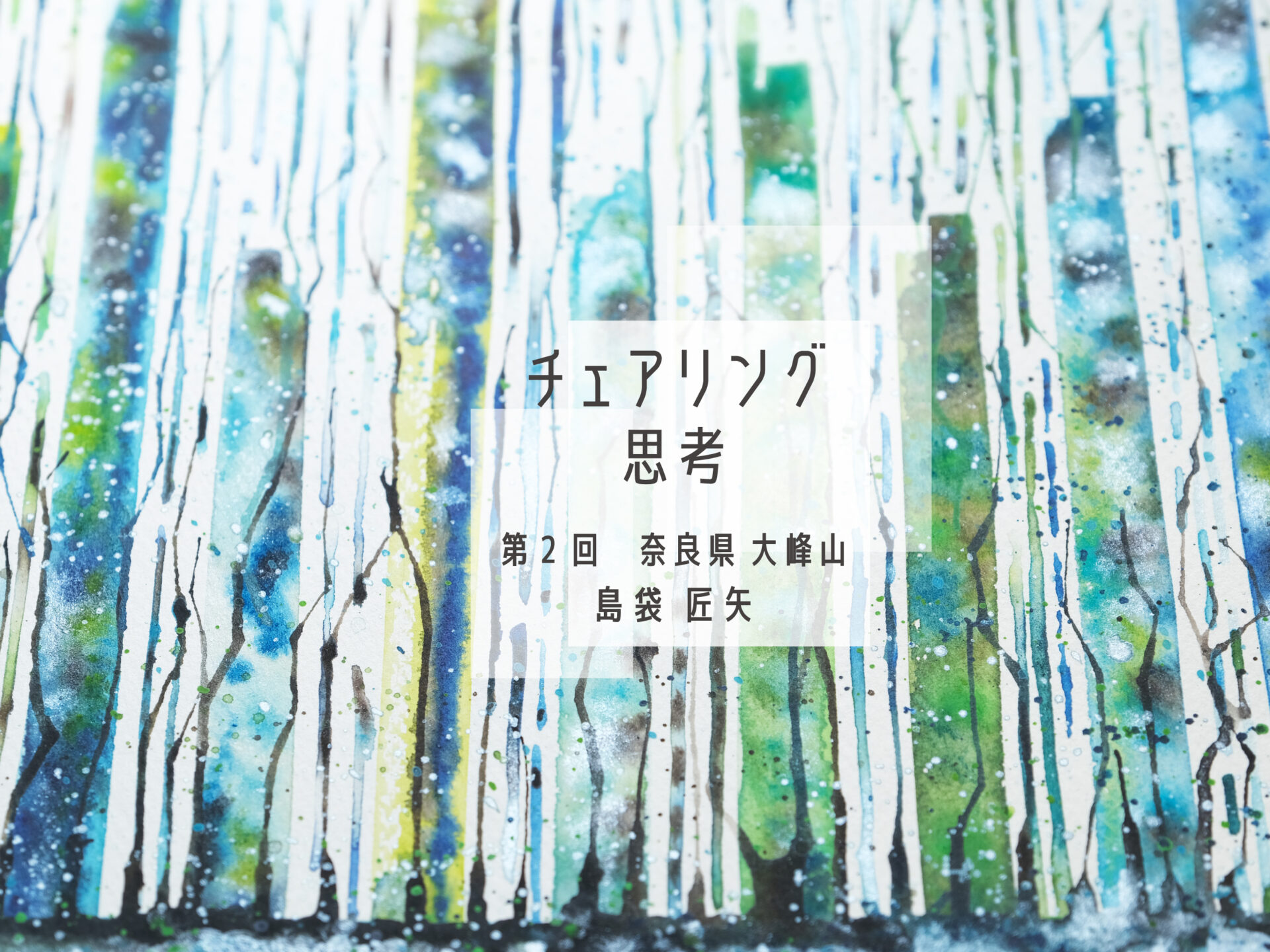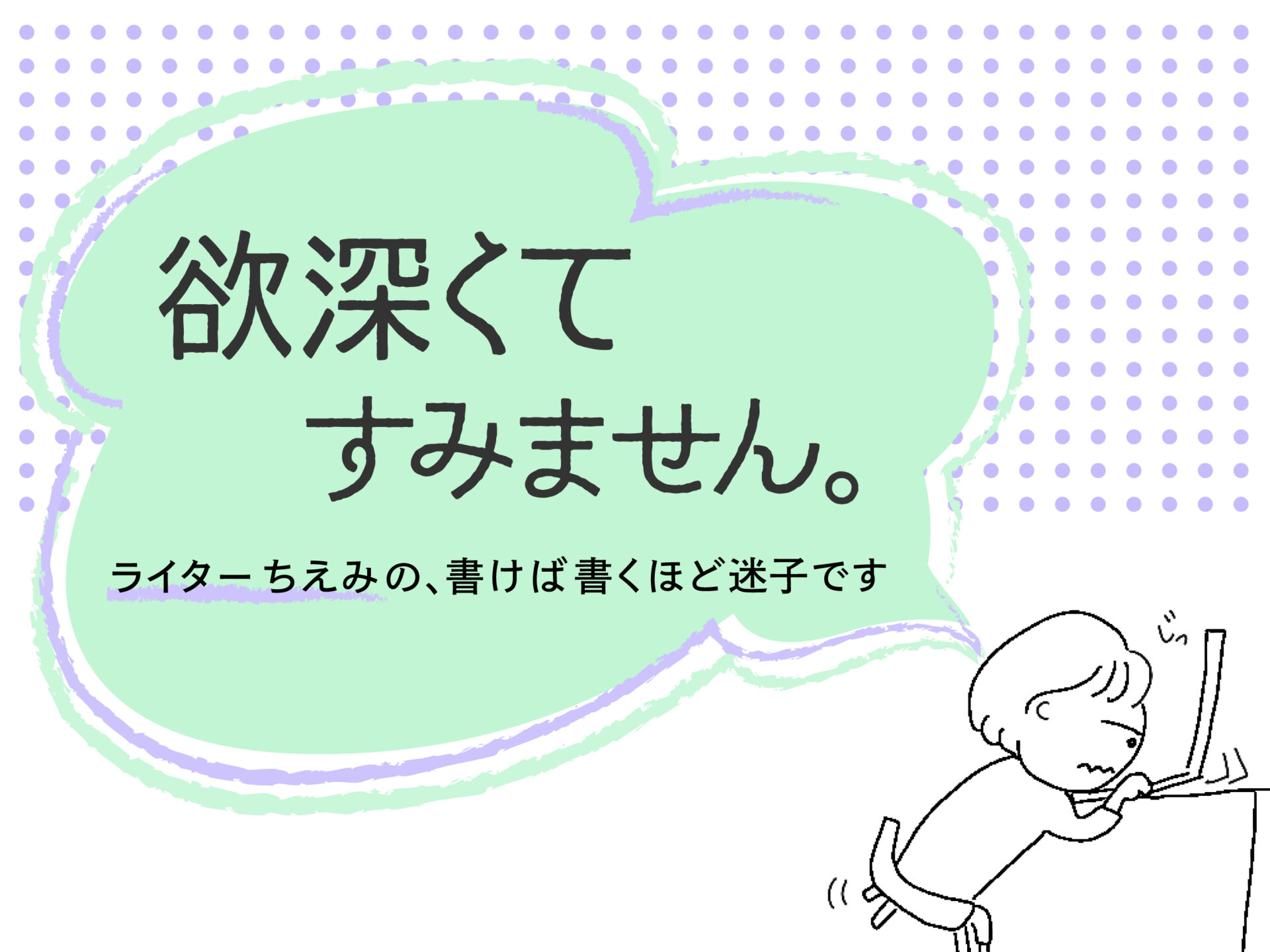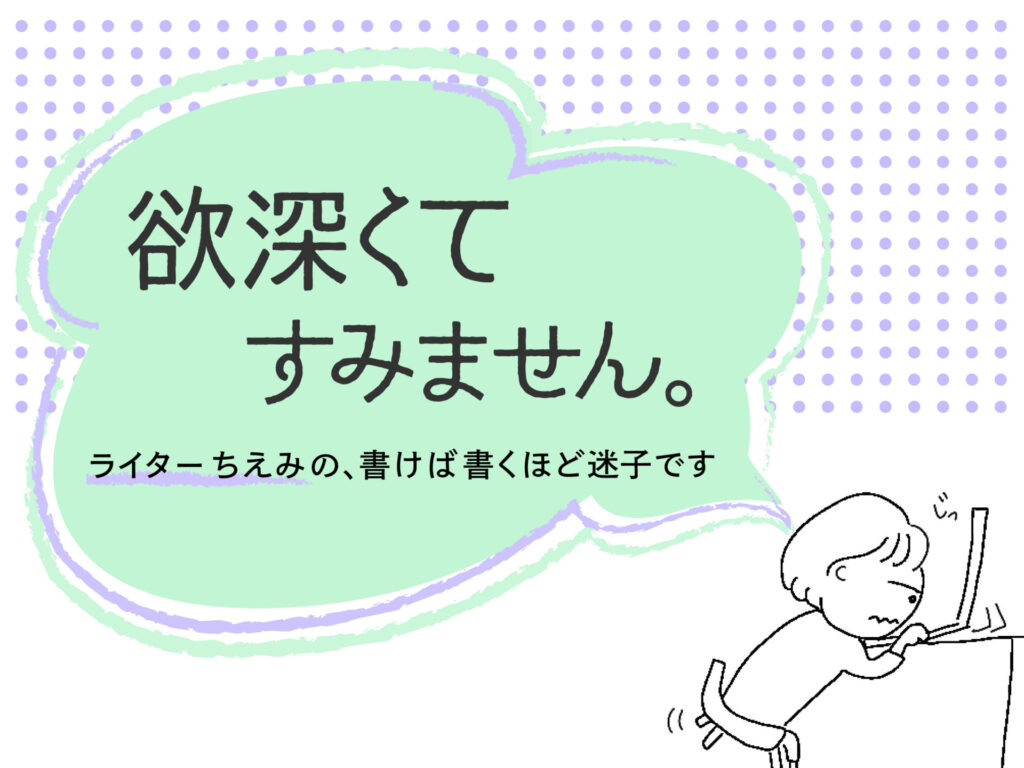
「あなたが感じたことを書いてください」書き手としての責任を考える【連載・欲深くてすみません。/第30回】
元編集者、独立して丸9年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日は、話題になった記事を読んで、書き手の立場について考えています。
先日、インタビューのあり方を考えさせられる記事を読んだ。日刊スポーツの村上幸将記者が、俳優の寺尾聰さんにインタビューしたところ、取材の冒頭で「録音、やめてくれる」と言われたという。
インタビューの現場では、ボイスレコーダーやスマホを取材対象者の前に置いて、録音するのが通例になっている。それを「やめて」と言われるとは。若輩ながら俳優へのインタビューを行うこともある身からすると、想像するだけでぞっとするようなシチュエーションである。
しかし、村上記者のコラムを読むと、寺尾さんは単に録音を嫌がったのではなく、自分の発言を一言一句書き起こすような記事にしてほしくなかったのではと推測できる。「間違えてもいい」「俺の言葉を書き起こされると、つまんないんだよ」と記者に言ったそうだ。記者が感じ、考え、書くことを尊重しているように感じられる。
コラムにはこうも書かれている。
「記憶は時の流れとともに、おぼろげになっていくことは止められないにしても、本質的な部分、強烈なものは残る。寺尾は『あなたの言葉で、書いて欲しいと言っているんだ。記者として、どう感じたかを書けば良い』とも言ったが、記者が自分の言葉で書いたものは、終生、残るに違いない。そういうことを、寺尾は言いたかったのではないか、と今は受け止めている。」
※村上幸将『インタビュー開始29秒で「録音、やめてくれる」寺尾聰から投げかけられた記者としてのあり方』(日刊スポーツ)より引用
これはインタビューの仕事をするようになってから私が気づいたことだが、録音した発言の上面を切り貼りするだけでも、記事の“体”にはなってしまう。さらに、いまどきは文字起こしをAIに読み込ませれば、“それっぽい”記事が出力できる。
頭や心を通過せずに生成された文章というのはまったくひどいもので、と言いたいところだが、実際にAIにやらせてみると、曖昧なところを削ぎ落としてシンプルに論理構成する分、無味無臭の読みやすい文章にまとめてくる。稚拙なライターが書くよりよっぽどマシだ、と言いたくなる人がいるのもわかる。
さらに言葉を書かれる側(本人に限らず、俳優を守りたい事務所や作品関係者など)としては、書き手の主観に満ちたでこぼこの感想文にされるくらいなら、発言の内容を切り貼りした“それっぽい”記事のほうが安全だ、と考える人もいるかもしれない。人が自由に主観をまじえて書けば、どうしたって事実誤認や過剰な解釈のリスクをはらむ。
コラムを読んで勝手に想像をめぐらせると、寺尾さんはそういう予定調和や血の通わないやりとりに、内心うんざりしていたのではないだろうか。
言葉がすべてではないのだ。むしろ言葉にできることなどわずかと言っていい。寺尾さんは「情報」としての言葉ではなく、人を介すことで形を変える、柔らかさや曖昧さをきっと楽しんでいる。だから記者に対し、“あなたがどう感じ、どう考えたかを大切にしてほしい”と言っているのかもしれない。
もしそうだとしたら、愛に近い眼差しすら感じる。
*
この文章に胸を打たれるのは、私にも似た経験があるからだ。しかし私の場合、寺尾さんの言葉に誠実な文章をもって返した村上記者とは異なり、極めて残念な振る舞いをしてしまった。
ある著名な方にインタビューしたときのことだ。取材の前に、記事のレイアウト見本を見せたところ、その方は、自分の名前が大きく入る予定の箇所を指して「ここは私ではなく、ライターのあなたのお名前にしてくれませんか」と言った。
意図がわからず困惑していると、私の目をじっと見つめて「あなたが私の話をどう聞いて、どう感じたかを記事にしたほうが良いのではないですか。それなら自由に書いてください。私は一切赤字を入れませんから」とおっしゃる。
数えきれないほど取材を受けてきた方である。これまで意に沿わない編集をされたこともたくさんあったのだろう。私はこの発言を「自分の言葉を、稚拙な文章に変換されたくない」というメッセージだと受け取った。
それでも、ライターの名前のほうを記事に大きく載せるわけにもいかないだろうと忖度し「いえ、無名の私ではなく、あなたの名前で記事を出させていただきたいのです。頑張って書きますから、まずは原稿を読んでください」と返してしまった。現場の空気が悪くならないよう、ニコニコと笑いながら。
その方は、何も言わずに頷いた。
今思えば、その方は「自分の言葉」を大切にするのと同時に、聞き手としての私、書き手としての私も尊重してくれていたのではないか。だから、主語を明確に分けて「あなたの言葉を『(ライターの)私は』こう聞いた」「『(ライターの)私は』こう感じた」と書いてほしかったのかもしれない、と思う。
この世には、主語が曖昧な文章がたくさんある。その中には、意図的に主語をぼかしているものも多い。
たとえば、よくあるウェブのまとめ記事で「〇〇のポイント3選、まとめてみた」のようなもの。ポイントとは何か。誰が、どのような基準で選んでいるのか。記事には主語がまったく書かれていない。一般的な視点を装いながら、あるメーカーの宣伝記事であることも少なくないからだ。
私が仕事をしているメディアでは、インタビュー記事の場合、必ず聞き手のクレジットを明記する。しかし文章の中で聞き手が「私はこう思うのですが」と登場することはあまりない。聞き手はあくまで黒子であるべきだという意識もあるだろうが、無意識に主語が隠され、発言者、聞き手、そして実在するかわからない世間といった、異なる視点が溶け合っていることもある。たとえばこのように。
「本を読むのが苦手な若い世代も増えている昨今ですが……」
「生きづらさを抱えた私たちに、エールを送ってくれているようです」
本当にそうか?
誰がそう言っているのか?
「私たち」とは? 誰の代弁をしたつもりになっているのか?
遠慮深く控えめに、書き手としての自分を消しているようで、その実は、卑怯な言い換えやご都合主義の思い込み、責任逃れをしていないか?
せっかく「あなたが何を感じ、何を考えたかを、あなたの文章で書いてくれ」と言ってもらえたのに。その人は「私」を見ていたのに。
「無名な私ではなく著名なあなたの名前で……」と控えめなふりをして、私は、対等に向き合うことから逃げた。
あのとき「はい、では私の名前で、私が聞いたこと、私が感じたことを書かせてください」と言っていたら、聞けた話も違ったのだろう。どうすればそう言えたのだろうか。どうすればその覚悟がもてたのだろうか。
今も悔いが残っている。
文/塚田 智恵美
【この記事もおすすめ】