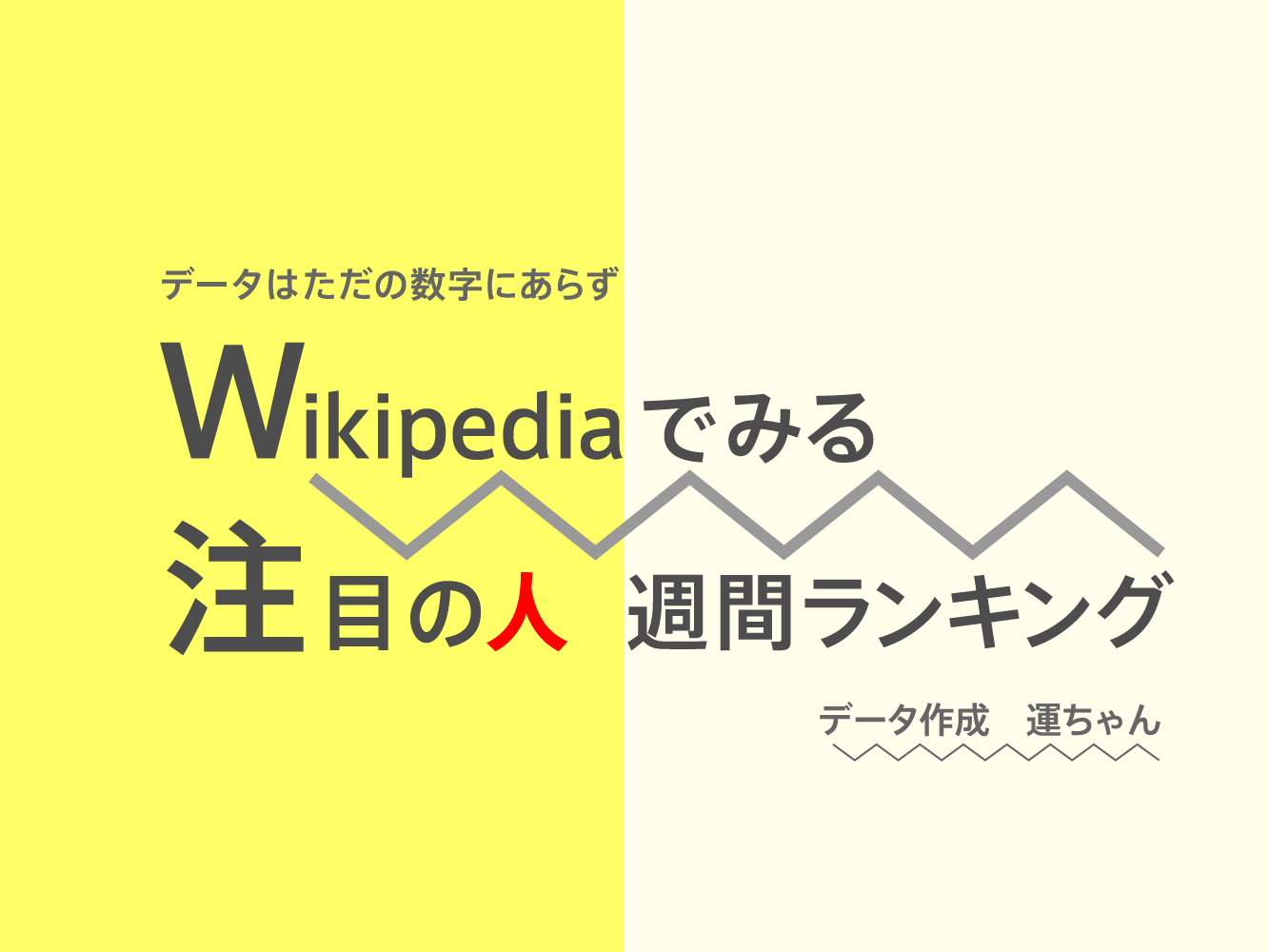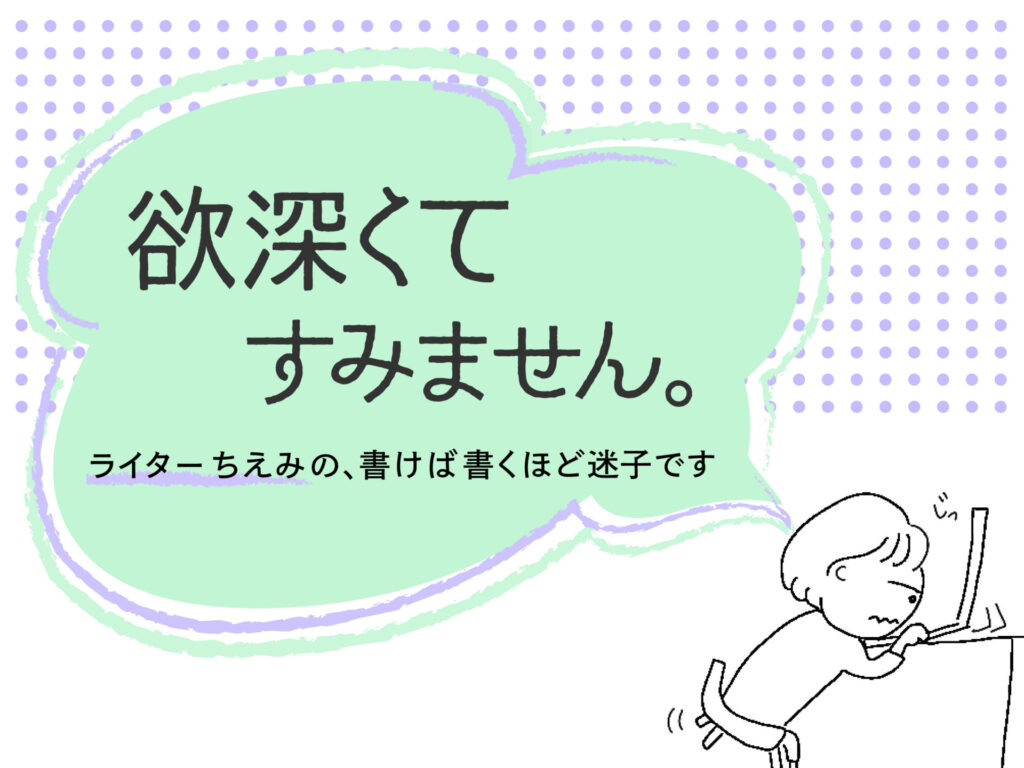
潰れないための「自分の取説」を自分でつくる。ライターを続けていくにはどうすればいいか【連載・欲深くてすみません。/第34回】
元編集者、独立して丸9年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日は、仕事上でのストレスに押し潰されそうになっているようです。
ストレスしかない。
30分で終わると思っていた構成案作りに、3時間かかった。気を取り直して取材の文字起こしを読み始めたら、自分の質問の甘さに「なぜそこで一歩踏み込まないのか」と苛立つ。ようやく集中してきたと思ったら、デザイナーさんから電話がかかってきて、送ったはずのデザイン依頼資料が届いていないという。ちゃんと送りましたよォとプリプリ怒って、電話を切る。下書きボックスに未送信のメールを見つけた。電話をかけ直し、平身低頭して許しを乞う。電話を切って立ち上がったら、机の脚に、足の小指をぶつけた。
マルチタスクがストレス。人と関わるのがストレス。
だけどそれ以上に、孤独がストレス。
退屈がストレス。刺激がストレス。
自由度の低い会社勤めもストレスが多かったけれど、何もかも自分で決定できるフリーランスになっても、それはそれで別のストレスがある。
そろそろ「ストレス」の文字に、ストレスを感じてきたことでしょう。しょうがない。そういう性格なのだ。打たれ弱く、ストレスを溜め込み、ネチネチと人を恨み、しかし人にすがって生きている。
生まれ変わったら、ナチュラル健やかな人間になってみたい。明るく元気、危機にぶち当たってもしなやかに対応し、回復力のある人に。憧れの言葉は「レジリエント」。ギリギリ読めるか読めないかの達筆さで書道家に書いてもらい、額に入れて壁に飾っておきたい。
だけど、そんなわたくしとて、フリーランスで働き始めて、もうすぐ丸10年になる。
常にストレスにさらされ「疲れた」「病んだ」「もうだめだ」とか言い続けながら、なんとか致命傷の一撃だけは避けて生き延びてきたということ。
それはおそらく、この10年の間で、自分の取扱説明書を1ページずつ執筆してきたからだと思う。
*
どんな状況になると、機嫌良く自分が動くのか。自分が好きな仕事。やりたい企画。――こうした自分の「強み」を知っておくのは、もちろんいいことだ。
でも、生き延びるには、どんな状況が自分をもっとも痛めつけるのか、息ができなくなるほど追い込むのか、の「弱み」のほうを知っておいたほうがいい。
20代のうちは、さっぱりわからなかった。あるところは鈍感すぎて人から心配されるくらいなのに、なぜかときどき、神経質すぎるハリセンボンのようになってしまう。ちょっとの刺激でピーっと針が立ち、時にその針に自分が刺される。「私ったらメンタルが弱いのかしらん」としくしく泣いた。
これが30代になると、「しくしく泣いてばかりいたら、食っていけません」という極めて現実的な理由で、自分がどういう状況に弱いのかを観察するようになった。
フリーランスは、仕事を選べる。自分にとって苦手な仕事があるのなら、はなから受けなければいい、と思った。
ところが、である。
観察するたびに、そんな単純な話ではないなとわかってくる。
例えば、自分の弱さが「長い文章を書く仕事が苦手」「スポーツ系のインタビューがしんどい」のようなものであれば、仕事選択にもすぐに活かせる。世の中には、短い文章を書く仕事も、スポーツ以外のジャンルの仕事も、たくさんある。そちらを選べばいい。
では、実際の「弱さ」はどのように表れるか。
ここからは私の弱さを赤裸々に書くが、読んでくださっている方は自分の場合を考えながら、ぜひ読んでいただきたい。同じ仕事をしていても、おそらく弱さの質や単位が全然違うはずだ。
さて、私の場合。自分でも発見だったのだが、私はライターの仕事の中でも「編集的な仕事」をしているときと「書く仕事」をしているときで、自分がストレスを強く受けるシチュエーションが変わる。
編集の場合は「一体なぜこうなっているのだろう」の連続に、もっとも弱い。編集は大抵、チームで動く。全体の仕組みや向かって行く方向が理解できなかったり、よくわからない“鶴の一声”みたいなものが飛んできたりするとき。
「なんでだろう」が脳のリソースを圧迫し、思考力が下がる。
うーん、それって「チームで動くのが苦手」ってことぉ?
なんて、ざっくり考えてはならない。ここで、うっかり取説に「チームで動くのが苦手」なんて書いてしまうと、編集の仕事ができなくなってしまう。
「弱み」の取説をつくるポイントは、もっと明確に「何が致命的につらいのか。どうすれば、自分は少しでも楽になるのか」を言語化することだ。
私の場合は「なんでだろう」が続くことが、単純につらいのである。「『ネコ特集』を『ウサギ特集』にせよ」といきなり言われる。なんで?? 誰に聞いてもよくわからない。――その状況がつらいのだ。
これが「いやー、実はスポンサーがウサギ好きでさあ……」とわかれば(それで企画を変えるのはどうなのだろう、とは思いつつ)息ができないくらいのつらい状態は脱する。
ここまで言語化できて、ようやく取説ができる。例えば、よくわからないときは一人で考えていないで、相手に聞いてしまったほうが早い、と対策が打てる。立場を超えて「ぶっちゃけ話」ができる関係をつくっておくのもいいし、自分より俯瞰で捉えるのが得意そうな人に、最初から甘えて頼るのも一手である。
では、書く仕事の場合は。
これはもう一択だ。私は「自分の理想がつり上がっていき、書けば書くほど自分に叱責される」ことに、一番弱い。
たぶん文章が下手になっているのではない(なっていたらどうしよう、かなしい)。おそらく文章を見る目が少しずつ育ってきたことで、「こういう文章を書きたい」といった欲がどんどん高まっている。それが行き過ぎると、書き始める前、もしくは構成を考える段階から「そんな立派な文章は書けない」と手が止まってしまうのである。
その状態で現実的な締め切りが迫ってくると「書けない」「手が進まない」「迷惑をかけてしまう」と、息ができなくなる。
「ライターの仕事においては、文章の流麗さやうまさが第一に求められているわけではない。まずは人に求められていることに応えろ」
そのとおりです。わかってます。しかしですね。
イノシシ科の動物・バビルサのオスは、メスにモテたいあまり牙を伸ばし続け、自分の牙が頭蓋骨を突き破って死ぬこともあるという。他人事とは思えない自滅ぶりである。
うっかり死ぬくらいの強い欲に体を乗っ取られたバビルサ(私)に、「欲を捨てろ」と言うのは、無理な話だ。
その現実を受け入れて初めて、ようやく取説ができる。例えば「もっとうまく書きたい」欲と、締め切りとの間でつらさが募るのだから、欲が暴走する前に「プランB(最低限の原稿)」を先につくっておくだけでも、精神面はかなり安定する。
*
もっとも致命的な弱みがどこにあるかは、人それぞれに違う。編集者との対人関係や赤字、読者からのアンチコメントの場合もあれば、やりたい企画が通らないことが最大のストレスの人もいる。だから、人の取説をそのまま借りるだけでは、うまくいかないことも多い。
誰かと話しながら、視点を変えながら
(ChatGPTと話すのでもいい)
自分の取説を、自分でつくる。
そして日々、更新していく。
ちなみにこの原稿は、春の日差しのように柔らかく健やかな編集長から「ライターを健やかに続けていくために、というようなテーマでも書いてほしい」と言われて、書いている。
編集長、私には「健やか」の背中は、まだまだ遠いです。
それでも、絶対生き延びてやる。
文/塚田 智恵美
【この記事もおすすめ】