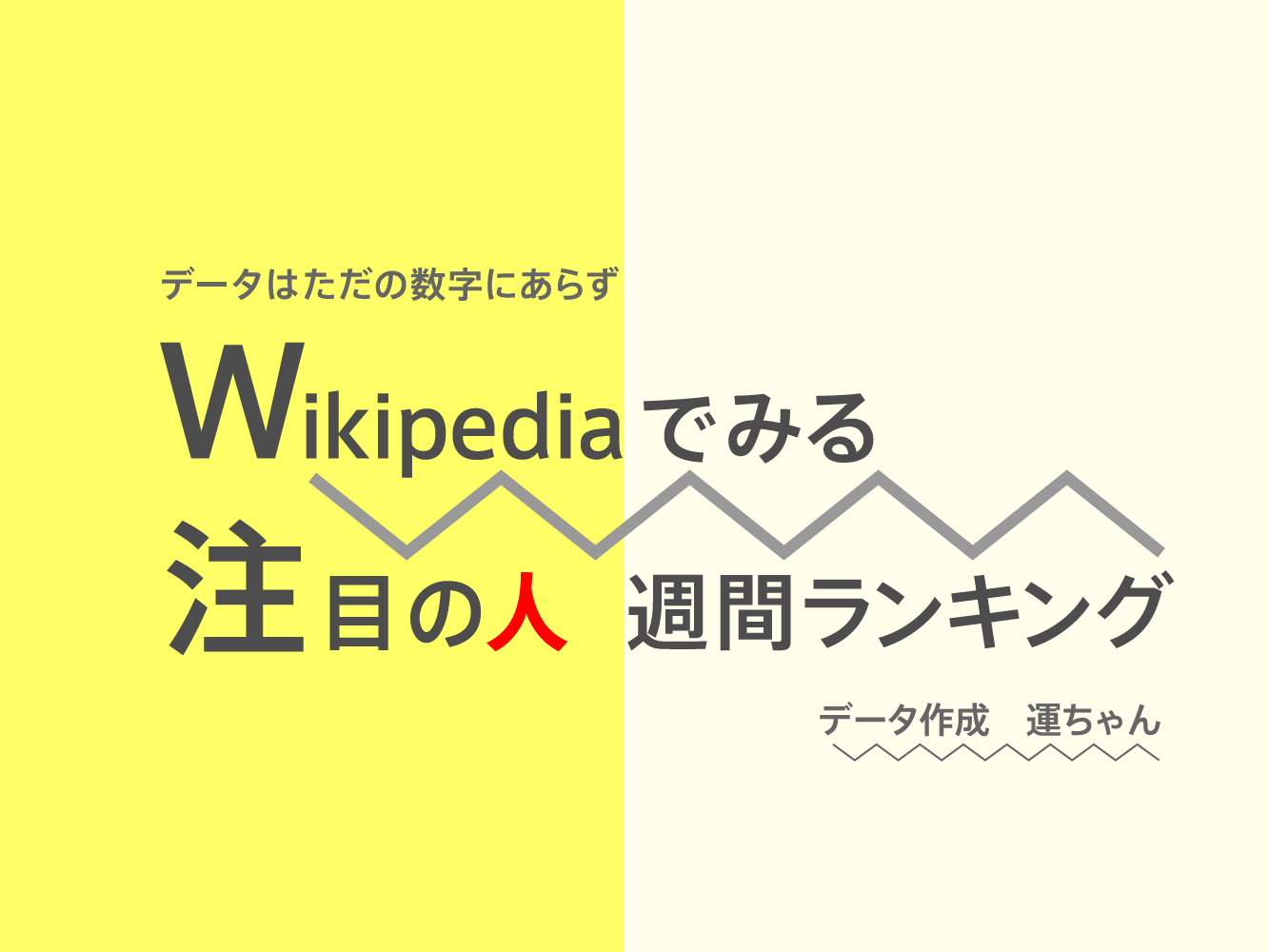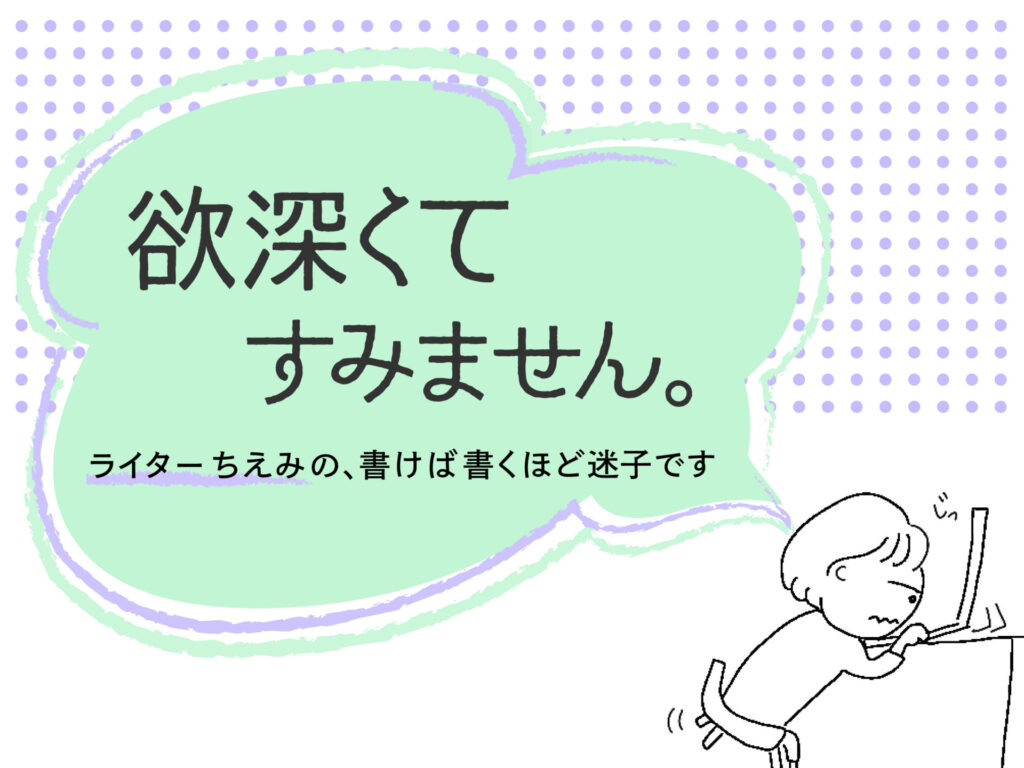
インタビューが空気の読み合いに? 意図や目的に縛られた不自由なインタビュー現場と、「場づくり」の技術【連載・欲深くてすみません。/第24回】
元編集者、独立して丸8年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日はインタビューの場づくりについて考えているようです。
インタビュー取材をしていて「知らない」「わからない」「それについては答えたくない」と返ってきたことが、ほとんどない。あるときから、その不自然さが気になり始めた。
事前に取材依頼書を送るので、相手方は取材の趣旨を理解したうえでインタビューに臨んでくれる。不機嫌だったり非協力的だったりするケースはほとんどなく、想定質問を読んで、答えを考えてきてくれる人もいる。
ただしインタビューが始まると、話の流れで事前に伝えた質問から外れていき、想定していなかった質問に及ぶことが多い。それでも、おおかたの人はすぐさま応じて何かしらの回答をくださるのだ。
私がどれだけあさっての方向にボールを投げても、必ずボールは返ってくる。投げた側としてはありがたい。でも、投げ返せない瞬間があるほうが自然ではないか。どれほどその道の専門家だとしても、何でも知っているわけではないはずだし、どれほどオープンな人でも、触れてほしくない領域を持っているはずなのに。
「そりゃあ、みんな大人だからね」
親しい編集者に私の違和感を打ち明けたところ、このように返ってきた。数年前のことだ。
「それ、正確には投げ返しているんじゃなくて、この質問の意図は何だろうとか、どういうことを答えたら記事が成立するのかとか、質問の外にある意図や目的を汲んでくれただけかもよ。インタビューをする側って、どうしても“意味がある”または“役に立つ”回答を求めてしまうでしょう。インタビューを受ける側も仕事だから、それに応えなきゃ、って頑張ってくれる」
そっか、あれは質問に答えたのではなく、“大人”として意図や目的を汲んでくれたのか。
聞く側も聞かれる側も、誰もが大人としての「立場」を背負ってインタビューの場にやってくる。聞く側の私は無意識のうちに「読者にとって何か意味のあること、役に立つことを答えてほしい」と圧をかける。聞かれる側は、言えないことをうまく避け、話の前提を少し傾け、にっこり微笑んで、質問に答えるのではなく相手の意図に応え始める……。
でも、それが行き過ぎたら、インタビュー取材なんてもう空気の読み合いになるのではないか。読んで読んで読まれて読んで。なんだか窮屈だ。これがもっと若い人たちなら、意図や目的、立場に縛られない純粋な対話ができるのかもしれないけれど……。
なーんて思ったら大間違いである。
私は中高生へのインタビュー経験が多いのだが、どんな大人よりも空気を読むのが、10代の人たちだと思う。特に高校生。現場に来た大人たちのわずかな会話、振る舞い、関係性をよく見ている。「クイズ★取材に来た大人たちをえらい人順にならべまSHOW」とかやったら、たぶんみんなけっこう正解する。
親切で賢く、周りの期待に応えて頑張ってきた高校生ほど、インタビュアーの意図を考えて“大人が求めていそうな答え”に寄せてくれる。その結果返ってくるのは、どこかで聞いたような「いい子ちゃん」な話ばかり。ああ本当はもっと「あなたの言葉」を聞きたいのに!
*
意図や目的、立場に縛られ、空気の読み合いが始まる「不自由で窮屈なインタビュー現場」から、どうすれば脱却できるのか。あるとき、そのヒントを得た。
高校生が集まる場に出向き取材をしていたところ、高校生同士の意見交流会が始まった。私も端の席に座り、見学させてもらうことに。
その場を仕切る先生が、開口一番こうおっしゃった。
「ルールはひとつ。『パスあり』です」
考え中、それについて今は答えたくない、よくわからない、興味がない。そういうときは「パス」と言ってよし。それがこの会のルールだという。
あとで話したくなったら、話題が次に行っていたとしても、手を挙げて意見を言っていい。考えが変わったら、話の途中でも「やっぱりやめた」と発言をやめてもいい。先生はそのように高校生たちに話した。
それ、いいの? と私はふしぎに思った。人前で自分の意見を言いたがらない高校生も多い。「パスあり」にしてしまったら、みんな「パス」の連続で、意見交流も何もできないのではないかと。
ところが、そんな凝り固まった私の頭をガコーンと殴るように、高校生は生き生きとした表情で、そして自分の言葉で、意見を交わし始めた。
あのとき先生の何でもないような言葉で、たしかに、その場の空気が変わった。何が起きたのだろうか。
私なりに先生の言葉がどういう効果をもたらしたのかを考えてみる。「パスあり」とはすなわち「すべてのことについて知っていたり、わかっていたりするフリをしなくていい」というメッセージだ。話したくない思いも許容した。
そして発言について「やっぱりやめた」を許すとは「絶対にこうだ、と言い切れることではなくても、考えたことは自由に言葉にしていい」と伝えることだ。言葉とは、一度発してしまったら元には戻らない、固めたセメントのようなものではない。こねながら形の変わっていく、柔らかい粘土のようなものだと先生は伝えた。
かくしてその場には、“知っている人”“わかっている人”を演じる必要がなくなった高校生たちが、自由に思考という粘土をこね合うようなゆるやかさがもたらされた。決まった枠に自分を当てはめるような「いい子ちゃん」的な答えは、もうどこにも見当たらない。
彼ら彼女らは、ただ自分の体験を語った。自分が見たもの、聞いたこと、経験したこと。そして数分後には変わるかもしれない暫定的な意見を、自由に話した。のびのび、ゆらゆら、ふわふわ、ぺたぺた。ここでは言葉が生きている、と思った。あまりに飾らない、魅力的な言葉がたくさん、たくさん。
そういう場だった。そういう場に「した」のだ。
*
立場や意図や目的を、むりやり人から剥がすことはできない。でもちょっとした言葉で、空気の読み合いがピタッと止まり、それぞれが自由に思考をこね合うような場になることはある。
予定調和から外れた、何が出てくるかわからない場だ。原稿に使える話がはたして出てくるか。意味もなく、役に立たない話ばかりかもしれない。そうした緊張のなか、生きたやわらかい言葉が飛び出してくるのを祈るようにして待つ。そういう瞬間が私は好きだ。
ちなみに安直な私はそれ以来、中高生へインタビューするときは冒頭に「パスありです」と言うようにしている。まっすぐなパクリである。
大人には「パスありです」とか言うとナメてんのかと怒られそうなので、ちょっと違う表現で工夫を、と、空気を読んでいる。
文/塚田 智恵美
CORECOLORの内部勉強会で、みんなが大絶賛した塚田智恵美さんのインタビューについてのセミナーに参加できるクラウドファンディングはこちらから!
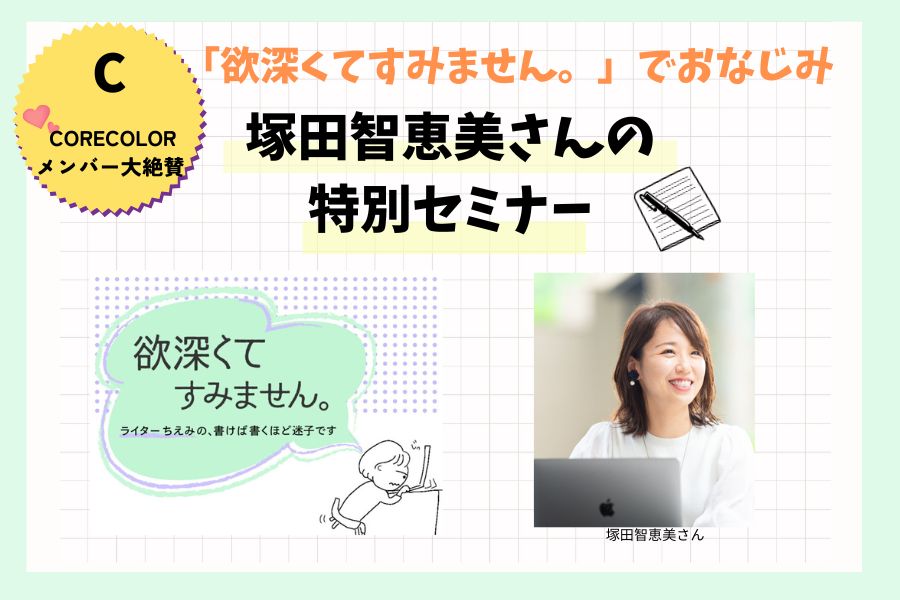
【この記事もおすすめ】