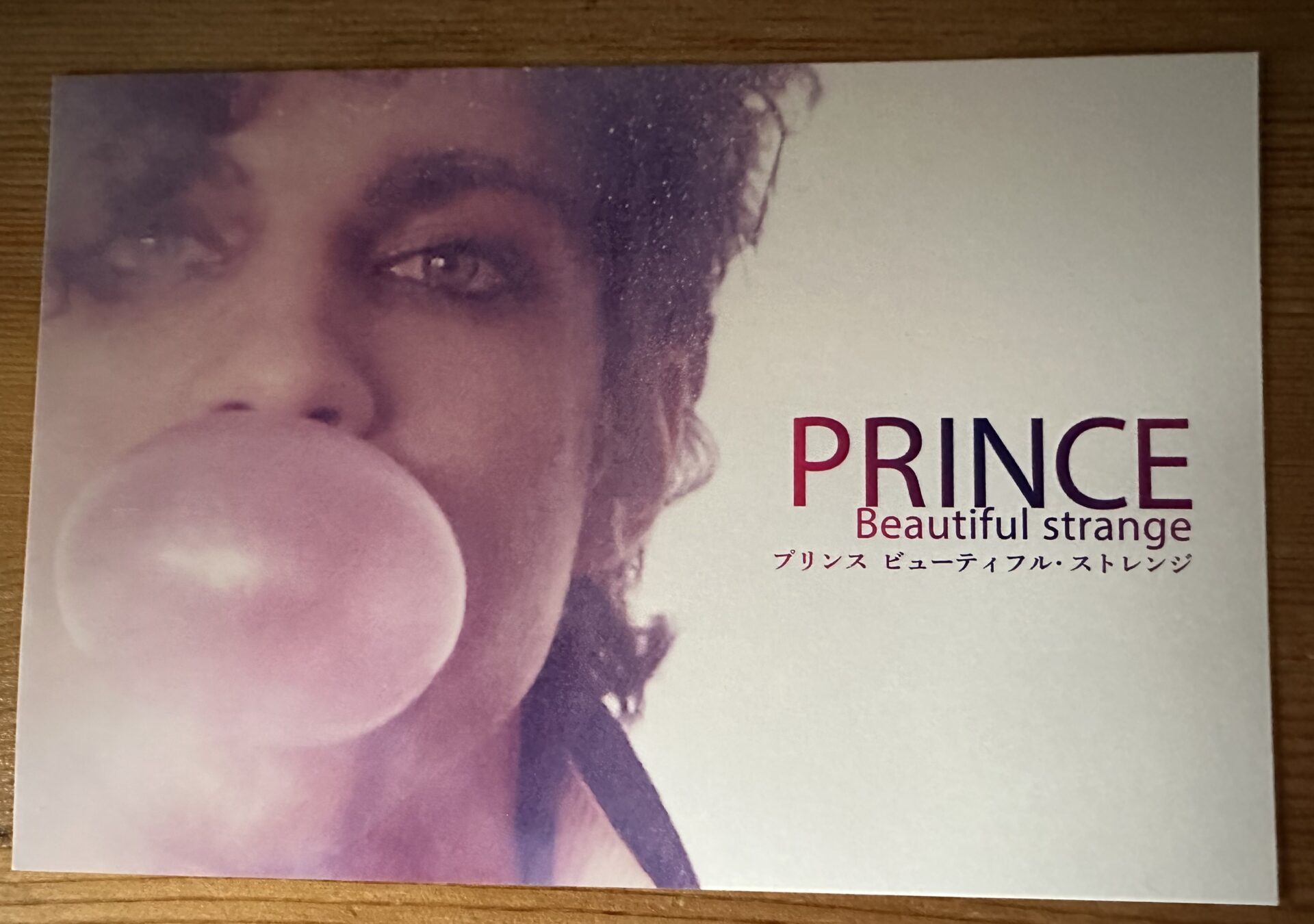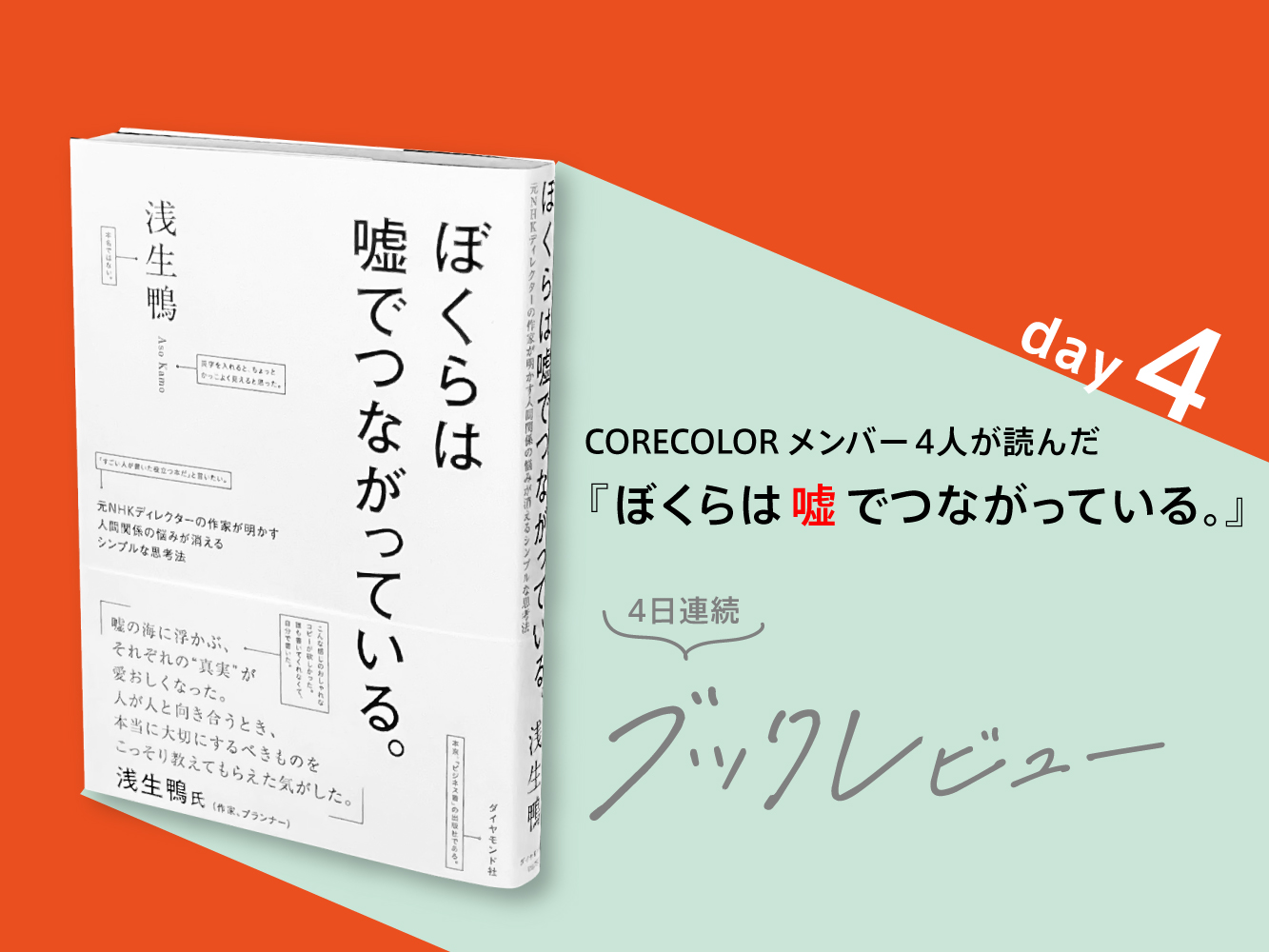しあわせの答えは1人で出さなくていい。『みんなでつくる未来の公園 ヘラルボニーと宮沢賢治』
宮沢賢治が残した短編童話に『虔十公園林(けんじゅうこうえんりん)』というお話がある。まだ鉄道も通っていなかった時代のこと。とある村に住んでいた虔十は、いつも腰縄の帯を締めて、森の中や畑を歩いていた。雨の日は青い薮を見ては喜び、晴れの日は空を飛ぶ鷹を見つけては跳ね上がる。そして、手を叩いて村の人たちに知らせるような人だった。
村の人は、そんな虔十を馬鹿にした。虔十を何度も笑い、からかった。そのうち、虔十は人前で笑うのをやめてしまった。
ある年のこと。
虔十は何を思ったのか、家の後ろにある野原に杉の苗を植えたいと言い出した。両親も、兄も、虔十のお願いを聞いたのは初めてだった。だから虔十の願いを叶えるために、杉の苗を700本買い、穴を掘り、等間隔で植えた。
やがて苗は木に成長し、杉林は村の子どもたちの遊び場になった。その後、虔十が亡くなり、鉄道が通り、村は町へと変化したが、虔十の杉林だけはそのまま残り、人々の心の拠り所として残り続けた。
この物語を通して、宮沢賢治は「本当の知性とは何か」という問いや、「価値を決めつけてはいないか」という気付きを与えてくれる。一方で、村の人から異質な存在として扱われた虔十が、家族以外の人と打ち解ける描写はなく、私はそこに引っ掛かりを覚えた。
後世になってから人々に認められたが、果たして虔十はしあわせだったのだろうか。亡くなる少し前、杉を植えたことをやっかんだ村人に「杉林を切れ」と言われ、「切らない」と反抗したら真っ青になるまで殴られるシーンもあった。虔十はその時、何を思ったのか。虔十が考えるしあわせと、私が考えるしあわせは、違うのだろうか。
そんな答えのない問いが、頭の中をかけめぐる。そもそもなぜ、私は『虔十公園林』を読んだのか。それは、へラルボニーが『虔十公園林』の世界観を軸にした展覧会を行うと知ったからだ。
ヘラルボニーは2018年に創立された、福祉を起点に新たな文化の創出を目指す企業だ。「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、知的障害のある作家とライセンス契約を結び、アートやプロダクトの制作・販売を行っている。昨年5月には、ルイ・ヴィトンやクリスチャン・ディオールなどを傘下に持つ世界的複合企業、LVMH主催の『LVMH Innovation Award 2024』に参加。日本企業として初めてファイナリストに選出され、カテゴリ賞を受賞した。今年の3月には、銀座や創業の地である岩手で常設店舗のオープンを控えており、国内外に事業を拡大し続けている。
今回の展覧会では『虔十公園林』の物語とともに、これまでのヘラルボニーの歩みと、これからの未来に向けた問いが、12個のブースに分かれて展示されていた。会場は2つあり、うち1つの会場には、知的障害のある方が生み出す日常音をメロディにした『ROUTINE RECORDS』が流れている。初めて聞くはずなのに、規則性のあるリズムが不思議と心地よく、しばらく滞在していたくなった。
展示を1つずつ、じっくり見ていく。6番目の展示で足が止まる。そこには、2024年に起きた能登半島地震の際、障害のある人たちのために防災情報サイトを公開したり、SNSで呼びかけたりした時のことが書かれていた。東日本大震災の時、知的障害のある方が避難所を追いやられるケースや、「周りに迷惑をかけたくない」という理由で避難所に行けないケースがみられ、その状況をくり返さないために行動を起こしたそうだ。その展示の下部に書かれた考察に、私は衝撃を受けた。
「虔十の『うれしくてひとりで笑へて仕方ない』様子を子どもたちが馬鹿にし、虔十は笑っていないふりをするようになりました。障害のある人が避難所を転々とした状況は、誰かが意図的につくったものではありません。でも、無自覚の意識から生まれる状況だからこそ問う必要があります。『大声を出す娘の口をガムテープでふさごうと思った』この言葉をどう受け止めますか?」
泣きそうになった。過去の自分と、重ね合わせたからだ。
*
私には、障害を持つ母がいる。
13年前に脳の病気を患い、後遺症が残り、現在も福祉の力を借りながら生活している。見た目は病気になる前とそこまで変わらない。けれど、記憶も、認知も、何もかもうまくいかなくなった。怒りと悲しみの閾値が極端に低くなり、まるで別人みたいに変わってしまった。
倒れてから1年ぐらい経った頃、母が暮らす施設を訪れた際に、ささいなことで口論になった。いつも母の罵声を黙って受け止めていたが、この日は我慢できなくて言い返してしまった。まさか娘に反論されるとは思っていなかったのだろう。母は驚いた顔をして、そのままうつむいた。そして「私、あのまま死んじゃえばよかったね」と言った。母がどんな顔で、その言葉を絞り出したのかはわからない。けれど、声のトーンが泣きそうだったのを覚えている。その後は何も言わず、私の言葉を静かに待っていた。
こんな時、「そんなことないよ」と言ってあげるのが筋だと思う。どうにもできない状況で1番苦しいのは母なのだ。「そんなことない、大丈夫だよ」と、すぐに言ってあげるべきだった。
でも、言えなかった。母の言葉に胸がつまり、声が出なかった。
母が望む言葉すらかけてあげられない。そんな自分が情けなくて、母と一緒に消えてしまいたかった。
現在、母の病状は安定している。親子で口論になることは滅多にない。それでも、あの日のことは一生忘れないと思う。
*
母との思い出に浸りながら、しばらく6番のブースの前で立ち尽くす。心を落ち着かせて、前に進もうと思い、左を向いた。そこには作家・輪島貫太さんが描いたアート作品が飾られていた。

輪島さんは、石川県金沢市に住む作家さんだ。1枚の絵の中に興味があるものを集合させて描くのが好きな方で、無数のオリジナルキャラクターを描くことが多いという。キャラクターは1人ひとり性格などが細かく設定されており、ご本人と妹さんもよく絵の中に登場するそうだ。今回の展覧会では、輪島さんの絵が4枚飾られていた。その中でも特に惹きつけられた作品がある。『sdgsが達成された未来』という作品だ。

この作品には、国や文化の違う人が数多く登場する。老若男女、なかには人ではないキャラクターもいて、見ているだけで楽しい。絵の中にいる誰もがいい顔をしていて、思い思いに自分の時間を楽しんでいるようだった。同じ教室で学んだり、手を取り合ったり、笑い合ったりもしている。こんな社会になればいいなと、思わされる作品だった。
もし自分がこの絵に入らせてもらえるとしたら、何をしようかと想像した。母のことを思い出した直後だったからか、母とともに出かけるシーンが頭に浮かんだ。
誰にも過去を変えることはできない。虔十をバカにした村の人も、母に寄り添ってあげられなかった自分も、みんな過去のできごとであり、変えることはできない。けれど、こんなふうに未来を描くことができたら……。嘲笑や罵声ではなく、一緒に笑い合えたらどんなにいいだろう。輪島さんのアートから、そんな風に思考を重ねた。これがアートの可能性なのかと、肌身で感じた瞬間であった。
*
今回の展覧会で、スタッフの方から「『虔十公園林』はヘラルボニーにとって大事で、身近な物語なんです」とお聞きした。代表取締役である松田崇弥さん・文登さんが同社を立ち上げる時、伯父であり、宮沢賢治研究者である牛崎敏哉氏から「こんな話があるよ」と紹介されたのが、『虔十公園林』だった。以来、毎週行われる全社会議でたびたび話題に上るほど、身近で大切にされてきたストーリーだという。今回の展覧会では、物語を一文一文深く掘り下げ、「このシーンはどういう意味だろうか」「こんな考え方もできるんじゃないか」と議論を重ねながら形にしてきたそうだ。スタッフの方は、続けて次のように語ってくれた。
「公園というのは比較的パブリックな空間で、本来なら誰もが来られる場所です。でも、なかには公園すら行けないという方もいらっしゃいます。今回の展示を通して、一部の人だけではなく、みんなにとっていい場所とは何か、どんな未来を創るのかを一緒に考える場にできればと思っています。知ってもらうことで価値観が変化していくと思うので、なるべく多くの方に来ていただき、話し合える空間にしていきたいですね」。
このお話を聞いた時、展覧会に行く前にあった「虔十は本当にしあわせだったのか」という問いの答えは、1人で考えることじゃないのかもしれないと思った。自分だけで答えを出すのではなく、人と人が話し合い、一緒に未来を創造する過程で見つかるような気がした。
いつか、母を展覧会に誘ってみようと思う。もし「いいよ」と言ってもらえたら、一緒に前を向いて、歩いていきたい。
文/小林 おすし
サムネイル画像撮影/橋本美花
【展覧会情報】

『みんなでつくる未来の公園 ヘラルボニーと宮沢賢治』
場所:BAG-Brillia Art Gallery-
期間:2025年2月21日(金)~3月20日(木)(月曜定休)
開館時間:11:00〜19:00
入場料:無料