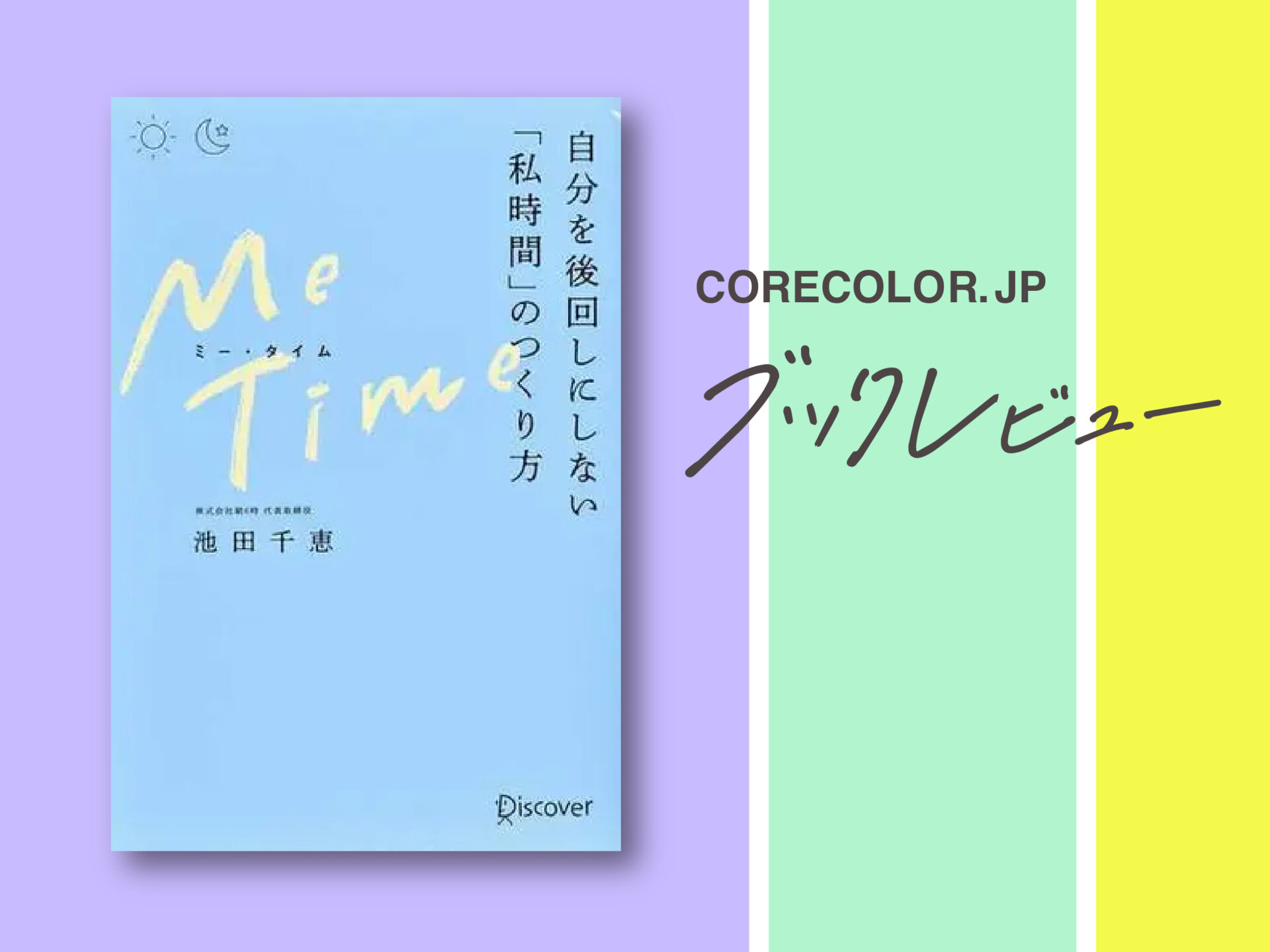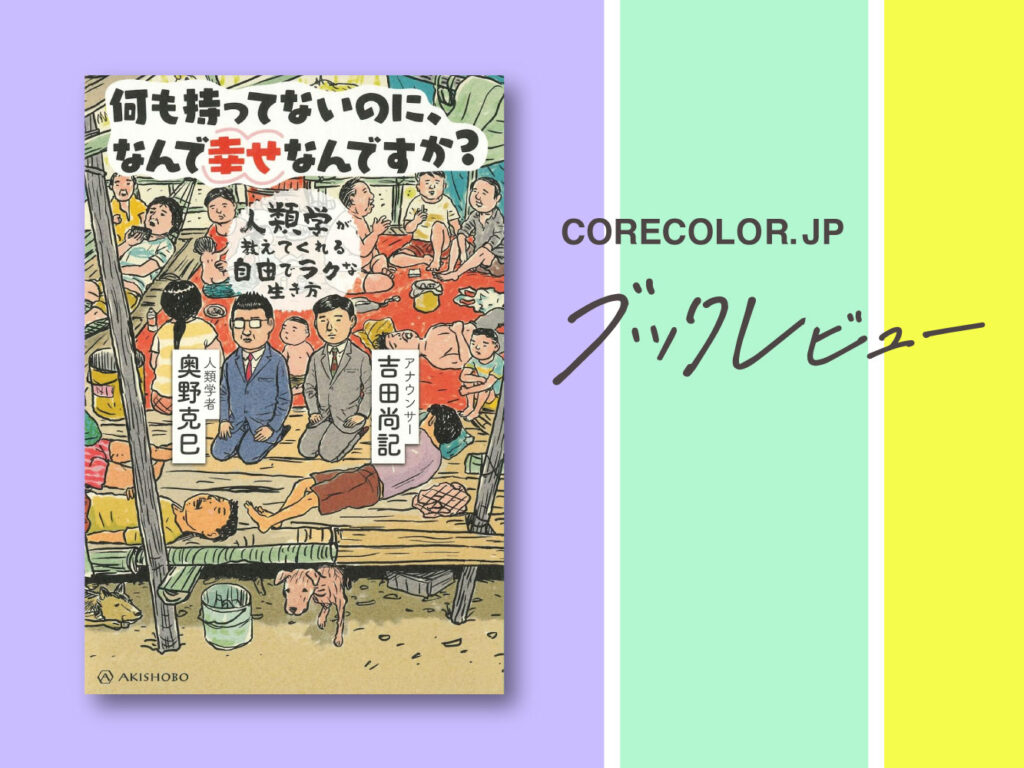
本物の「ありがとう」は年に0.1回しか言わない『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?』
最近、せっせと自分が持っている“もの”を減らしている。自ら集めたはずなのに、明らかに“もの”が多くて、モヤモヤする。先日、亡くなってしまった“世界で一番貧しい大統領”ホセ・ムヒカさんも、「貧しさとは少ししか持っていないことではなく、いくらあっても満足しないことだ」と言っていた。たくさんの“もの”に囲まれて、心のほうが貧しくなるって、元も子もないし恥ずかしい。
人類学者・奥野克巳さんとアナウンサー・吉田尚記さんの共著、『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?──人類学が教えてくれる自由でラクな生き方』は、“何も持っていない”のレベルが違いそうだから手に取った。この本に出てくるマレーシアに住む狩猟民「プナン」は、何を持っていなくてどう幸せなんだろう。
プナンの人たちが持っていないのは、“もの”ばかりではなかった。「ありがとう」を表す言葉がない。私は、お礼を伝えるメールで、「ありがとうございます」と3回くらい書きたくなる。くどい。親しい友人への感謝のLINEでは、アリの絵文字を10匹入れたくなる。気持ち悪い。
そのくらい私が多用している「ありがとう」がないとは、どういうわけか。プナンには、「所有」の概念が薄いので「ありがとう」がないらしい。あらゆる“もの”、服もスマホも、みんなで共有して使用する。お金が手に入っても、狩りで大きな獲物が獲れたとしても、全て公平に分ける。分配することで社会を保ってきた。資本主義社会を生きる私とは、根本的に違いすぎる。日本語の「ありがとう」は、「存在し難い・滅多にない」という意味の「有り難い」に由来している説が一般的だ。プナンは、あらゆる“もの”がほとんど「当たり前」に使えるから、特に「有り難くない」ということだろう。
しかし、「ありがとう」の言葉がないなんて、少し寂しい気がしてきた。人への優しさや思いやりを表現しない民族なのか? そんなことはなかった。プナンの人たちは、研究者である著者がジャングルでの移動中にはぐれていないか、お腹が空いていないかしばしば気にかけてくれるらしい。言葉で色々言われるよりも、優しさが伝わってくるし役に立つ。確かに、幸せな社会だ。
一方の私は、なぜ「ありがとう」と言い過ぎてしまうのか。本気で相手に感謝しているのだけれど、「こんなダメな私なんかに、優しくしてくれてありがとう」と、自分を低く見ている節がある。相手を立てて、うまく物事を進めたい下心も少なからずある。「ありがとう」の矢印が自分に向いていて、「ありがとう」が薄い。
「ありがとう」について反省していることもある。小学2年生の娘と出かけて買い物してからお店を出るとき、または病院に行って診察室を出るとき、親である私が「『ありがとう』って言った⁉︎」と、小声で子どもに感謝を促す。強制は良くないとわかっていても、お礼の言葉がない無礼への苦言を呈してしまう。感謝の気持ちを伝えられる子に育ってほしいし、社会で生きるうえで大切なマナーだ。でも、強制されたお礼には、言葉の重みはほとんどない。大人である自分の背中だけで手本を示せないのは、世間体を気にしている部分もあるのだろう。子どもだって大人だって、当の本人が言葉の必要性に強烈に気づいたら、言動は変わるはずだ。
また、友人を助手席に乗せて、私が車を運転していた時に気づいたこともある。混み合う幹線道路を走っていて、駐車場から合流しようとしている車がいた。進む先の道路が詰まっていたため、私は停車してその車を自分の前に入れた。しかし、入れた車から、「ありがとう」を意味するハザードがなかった。いつの間にか市民権を得た「サンキューハザード」という名のお礼の合図がないことに対して、「ちょっとイラッとする」と隣に座る友人はつぶやいた。穏やかな性格の友人なので、意外だった。私は、サンキューハザードは嬉しいが、どちらかといえば不要派だ。合流とサンキューハザードを同時に遂行しようとして、慌てふためいて車の軌道が変になるドライバーを、何度か目撃していたためだ。怖すぎる。お礼はいらないから安全に走ってほしい。交通ルールでは、サンキューハザードは禁止こそされていないが、ハザードの使用法としては間違っているらしい。超ベテランドライバーの私の親は、「譲るべきシーンでは譲るのが当たり前だから、ハザードはいらない」と言っている。プナンと近い考え方だ。「当たり前」に、むやみにお礼をつけると、物事が複雑になってしまう。あるはずのお礼が受け取れなくて、モヤモヤするのも損だ。「ありがとう」の出番も言葉の重みも、全て発する人に委ねられている。
この本は、普段私が乱用してしまう言葉の、用法・用量や意味を問いかけてくれた。本の前半で、自分の薄っぺらくなりがちな「ありがとう」に気づけたのでホクホクした温かい気持ちになりながら、後半を読み進めてみて唖然。後半は、ほぼ全て下ネタについて語られていた。なぜなら、プナンの人たちは、多くの“もの”を持っていないから、ほとんどの時間を下ネタトークで過ごすためだという。この本は、「下ネタの前では、肩書きや国境を超えて人類は平等」で、「幸福はくだらないものの中にある」といった話に行き着く。とはいえ、僭越ながら「このくだりは、必要か⁉︎」とツッコミを複数入れたくなるくらい、下ネタ満載。普段、コンプライアンスやジェンダーばかりを気にかけて、クリーン過ぎる社会で生きているせいか、かなり拒否感を持っている自分にも驚いた。「下ネタがめったに言えない世界は、下ネタが有り難い存在になるのだろうか?」などとグルグル考えながら、何とか読了。下ネタが良いとか悪いとかではなく、苦手な人は注意してほしい。
気を取り直して、「ありがとう」について。我が子に、「ありがとう」を強制していた今までの私の言動を反省していると伝えてみた。間髪入れず、「ほらね!」と凄みのある声で返された。「『ありがとう』は、『ありがとう』って感じたときだけ言うんだよ」。憤慨して続ける。「本当に『ありがとう』って思うときなんて、1年に0.1回くらいしかないし‼︎」。まだ習っていないはずの小数点を使って、「ありがとう」の出る幕の少なさを表現していた。「ありがとう」だけではなく、「ごめんなさい」も「お愛想」も「反省」も「男尊女卑」も「根気」もないプナンの世界は、自由で豊かな子どもの世界に近い。「ありがとう」を1年に0.1回しか言わないのは私には無理そうだが、たまには「ありがとう」禁止ゲームをしたら、幸せを問い直せるかもしれない。誰かを助けて、「当たり前でしょ」とすました顔で「礼はいらないよ」と言ったり、自分の「ありがとう」の重みを確かめる方法を開発したりしたい。「ありがとう」がない世界、有り難し。ここまで読んでくれて、ありがとう。
文/阿川 奈緒子
【この記事もおすすめ】