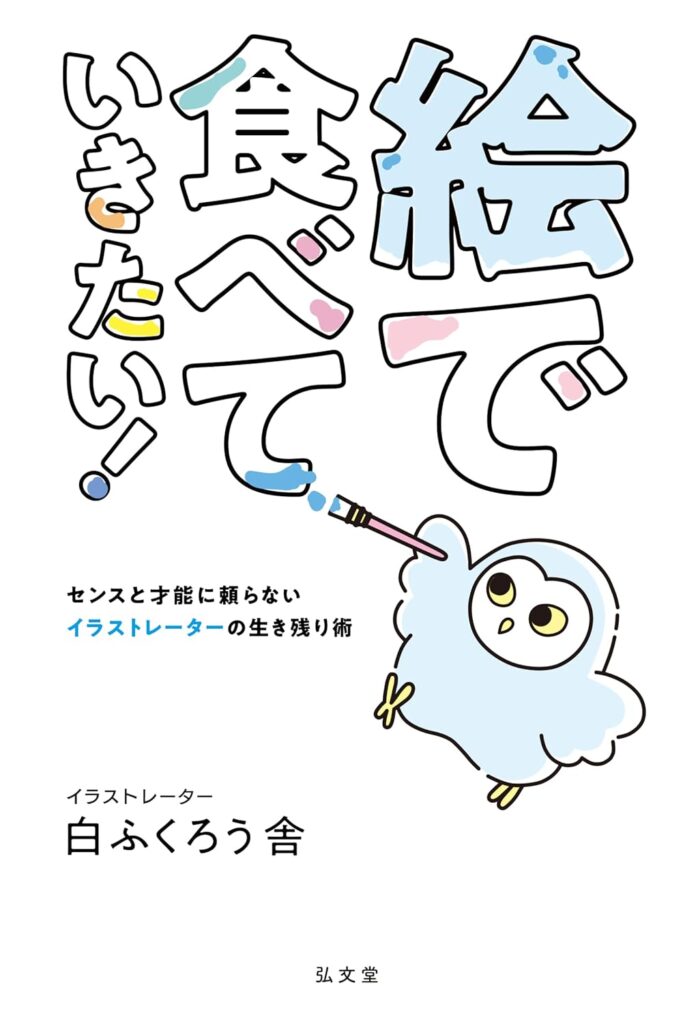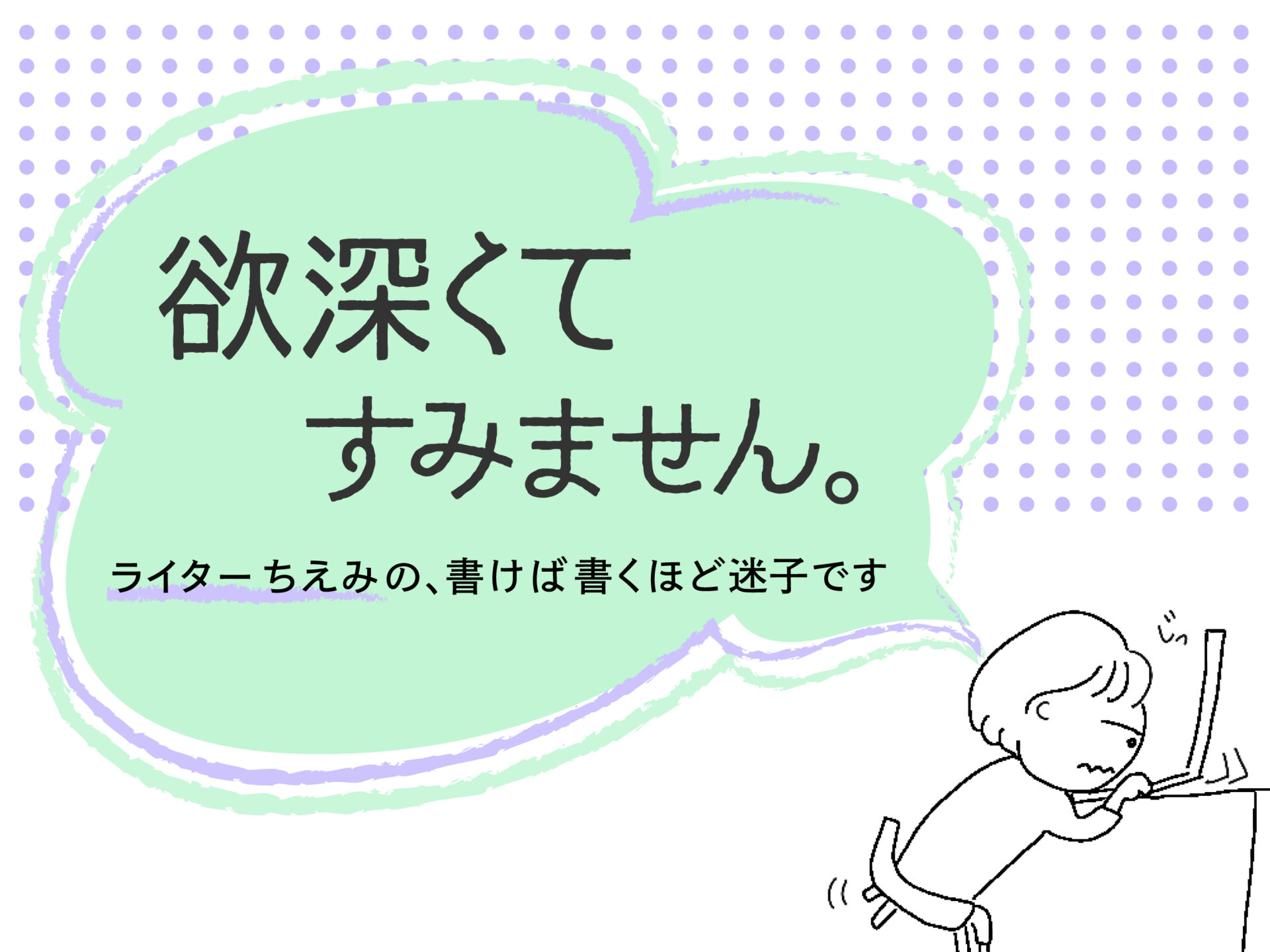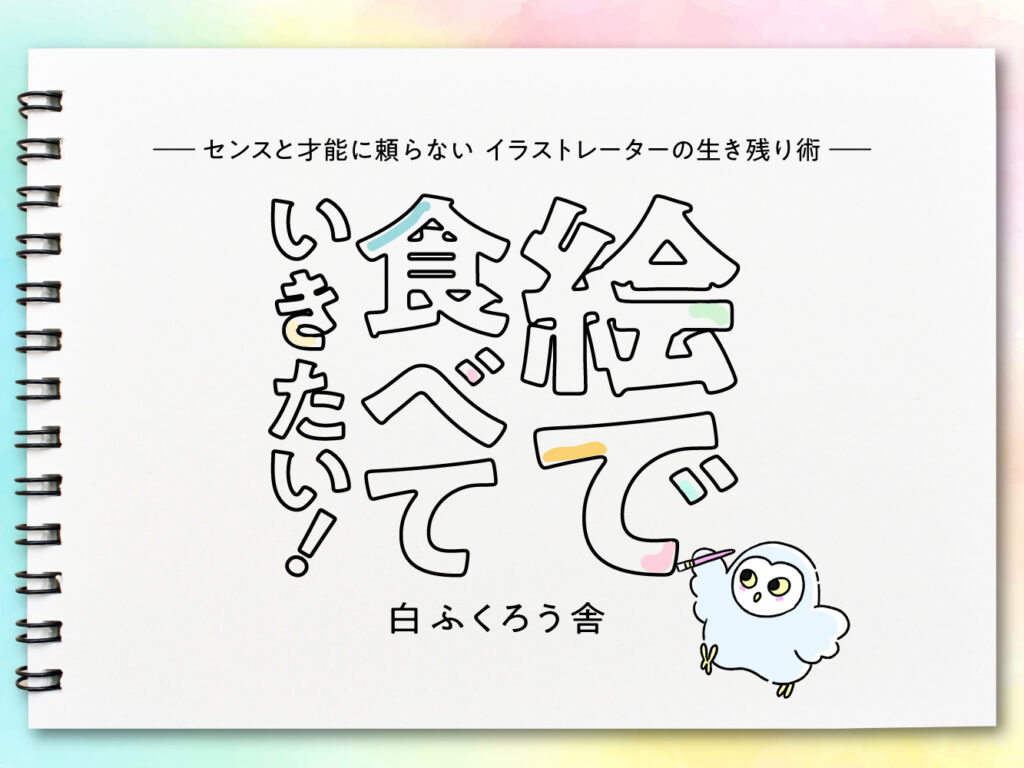
自分のイラストが「誰かのパクリ」だと言われたら? 著作権や契約について(その2)【絵で食べていきたい/第33回】
仕事で描いた絵や、発表したオリジナル作品が、思いがけず「〇〇のパクリ」「盗作では?」と言われたら──。SNSでの炎上騒ぎなどを目にして、不安になったことがある人も多いのではないでしょうか。今回は「パクリ」問題と著作権について考えます。
1:突然「パクリ」と言われたら
自分のイラストが思いがけず「パクリ、盗作」だと疑われたら、どうすればいいでしょうか。真似したつもりがない作品でも、似ていると言われることはあります。
そんなとき、著作権法の基本的な知識があれば、必要以上にあわてずにすみます。
(「パクリ」=「著作権侵害」とは限りませんが、ここでは著作権侵害にあたるかどうかを基準に考えてみます)
もちろん「これさえ知っていれば絶対安心」とは言えません。私は最近、資格取得のために著作権の勉強をしなおしました。そこで改めて感じたのは、著作権の侵害にあたるかどうかは、専門家でも簡単に判断できない事例が多数あるということです。しかし、落ち着いて適切な行動をとれば、深刻な問題に発展させずにすむことも多いはずです。
そもそも著作権法は、「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」(著作権法第1章第1節第1条)を目的としています。つまり、創作活動を守り発展させるための法律で、萎縮させるためのものではありません。まずこの大前提を心にとどめておきましょう。
2:著作権の基本 何が守られるのか
ここでは著作権法について、おおまかな基礎知識と事例をいくつかあげます。
著作権とは、著作物を独占的に使用できる権利のことです。この権利は著作物に「自動的に」付与されます。申請等の必要はなく、プロかアマかなども関係ありません。そして原則として、著作者の死後も70年間保護されます。
では、そもそも著作物とは何でしょうか。著作権法の規定では、以下のようになります。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条第1項第1号)。
この定義の中でも特に大事なのが、「創作的に表現したもの」という部分です。
たとえば、「設定」や「アイデア」「タッチ(作風)」など、目に見えない抽象的な要素には著作権は認められません。
「パクリ疑惑」が話題になるとき、まず確認したいのはこの点です。
「作風が似ていたら著作権侵害じゃないの?」と思うかもしれませんが、作風の定義はとても曖昧です。画材やモチーフが似ているだけで「〇〇さんの絵に似ているね」と言われることもあります。でも、そう言われるたびに作風を変えていたら、創作活動が続けられなくなってしまいます。著作権が問題になるのは、あくまで「表現された実体」が似ているかどうかです。
では、実際にイラストなどが著作権侵害にあたるかどうかは、どう判断されるのでしょうか。ポイントになるのは、「類似性」と「依拠性」という2つの要件です。
簡単に言うと、こうです。
・創作的な表現部分が同じか、または似ているか
・その作品に過去に接していたか(つまり、参考にした可能性があるか)
たとえば、誰が描いても似てしまうような「ありふれた表現」だと判断された場合は、著作権侵害にはなりません。また、創作性が認められる場合でも、偶然一致してしまっただけで、元の作品に触れていなかったのであれば、侵害とは言えません。
こうなると、「どこまでが似ているのか」「本当にその作品に触れていたのか」を判断するのは、とても難しいと思いませんか? 少なくとも、一個人が「これは著作権侵害だ!」と感覚だけで決めつけることはできません。
もう一つ大事なことがあります。
著作権侵害は、原則として権利者が訴えないと成立しない「親告罪」です。
つまり、関係のない第三者が「これは侵害だ」と思っても、実際に訴えることができるのは権利者だけなのです。
3:「パクリ」と言われたときの対応
では、実際に自分の作品Aが「Bのパクリだ」と指摘された際にできることを考えてみます。
まず、個人で作品を発表している場合でも、依頼された仕事でも、対応の基本は共通しています。
・まずは、権利関係について事実確認をする
・Bが著作物であり、Aと類似点がある場合、それが侵害にあたる可能性があるかを考える
あわてて作品を削除したり、反論したりする前に、本当に著作権侵害にあたるような要素があるかを確認します。Bの著作権が切れている、類似部分が実体でない「アイデアかぶり」であった、などであれば著作権上は問題になりません。また、Bが著作物だとして、類似部分があったとしても、明らかに誰が描いても似たような表現になる場合も多いです。また、指摘した人がたまたま後から見ただけで、自分の作品の制作時期のほうが早いかもしれません。
発注者がいる場合の対応も基本的には同じですが、この場合は特に一人で判断して行動しないことです。仕事を発注し、チェックして世に出している以上、制作物についての責任はクライアントが負うことになります。速やかに連絡し、対応を相談します。法律的に問題がなさそうでも、炎上リスクがあるならば、クライアントはイメージを優先して取り下げる判断をするかもしれません。イラスト制作者の名前が出る仕事では、描き手が批判の矢面に立つ可能性もあります。すぐに動きたくなるかもしれませんが、発注者と足並みを揃えるほうが安心です。
4: パクリと言われないために
「パクリじゃない?」といった言葉自体に何らかの効力があるわけではありません。しかしこの言葉は、描き手の心を萎縮させ、創作意欲を削ぐものです。極力その可能性を減らしたい場合、また著作権意識の低いクライアントが依頼主だった場合(残念ながらゼロではありません)にできることはあるでしょうか。
・自分の作品の「出典」や「参考元」を明記する
何かを参考にする場合、権利関係を確認するのは基本です。明らかに参考にしたとわかる作品が著作物の場合、最初からその作品名や作者を明示し、影響を受けたことを書いてしまう手があります。いわゆるファンアートの多くはこの方法で描かれています。応援や尊敬の意図が伝わればむしろ喜ばれるかもしれません。ただし、どう感じてどう対応するかは著作者の自由です。いわゆる2次創作については短くまとめられないのでここでは割愛します。
・参考資料やイメージ画を指定された場合、著作権の所在をクリアにし、どの部分を似せる必要があるか確認する。
イラスト受注の際に「この絵を参考に」と他者のイラストを提示される場合があります。その場合も、著作権の所在を確認します。
たとえば、こんなことがありました。依頼された仕事の絵コンテ(制作のための指示書)に、著名作家Cさんの作品が使われていました。企画を提案する際、既存のイラストで絵コンテを作り、クライアントの了承が出てから本制作を新たなイラストレーターに依頼する案件も多いのです。イラスト制作の依頼を受けた私は、絵コンテのイラストの著作者であるCさんの了承がなければ、この作品そっくりには描けないと伝えました。すると「クライアントにはこの絵コンテで通っているので極力似せてほしい」とのこと。ならばCさんに使用許可をもらってそのまま使ったほうが良いと提案したのですが、「それができないから頼んでいるんです」と言われたのです。
結局、私がアレンジして描いたイラストではクライアントのOKがでなかったらしく、その件は途中で立ち消えました。後日ふと思い出し、その案件を調べたところ、なんとコンテにあったCさんのイラストがそのまま使われていました。「できない」と決めつけていましたが、結果的に使用許可が取れたのかもしれません。ほっとしたと同時に、依頼者の対応には少し複雑な気持ちになりました。
でも、そっくりな絵を描かなくて本当に良かったと思っています。
この例は極端ですが、いくら依頼者に責任があるといっても、明らかに自分のリスクになる仕事を引き受けるのは避けるべきです。どこまでなら受けてよいかの線引きをするためにも、法律を知ることは大切です。逆に、法に触れない範囲なら何をやってもよい、ということでもないでしょう。最初に書いたように、著作権の目的は文化の発展に寄与することです。先人の創作をより発展させるために、ある程度の解釈を各人にゆだね、権利者が目こぼしする余地が残されているのです。誰かの表現にフリーライドするためではありません。自分の著作物を大切にするのと同様に、他者の著作物を大事にすることは創作の大前提です。
5: 創作は文化のバトン
法律的にどう解釈されるかはさておき、誰しも他者の作品から影響を受けて、似てしまうことはあります。それをどう扱うかが創作者の姿勢であり、また創作の楽しさ、素晴らしさだと思います。有名な作家の作品を並べてみると、初期は明らかに先人の影響を受けながら、時間と枚数を重ねて独自の表現を生み出していく様子がわかります。そして新たな創作者が、その表現に影響を受けて創作をはじめるのです。
真似される側になってはじめて自分がどれだけ先人たちの恩恵を受けていたか知ることもあるでしょう。これまで自分がのびのびと創作を楽しんでいた場所が、何によって守られてきたのかに気づくかもしれません。自分らしい表現を生み出したとき、誰かの創作を真似するだけでは決して見えない世界が広がっているはずです。託されたバトンを自分なりに次につなぐ、そんな意識で創作に向き合えたら──と、思います。
参考:文化庁「著作権サイト」著作権テキスト令和年版
文化庁 著作権侵害対策についての相談窓口
文/白ふくろう舎
【この記事もおすすめ】
【白ふくろう舎さんの書籍はこちら】