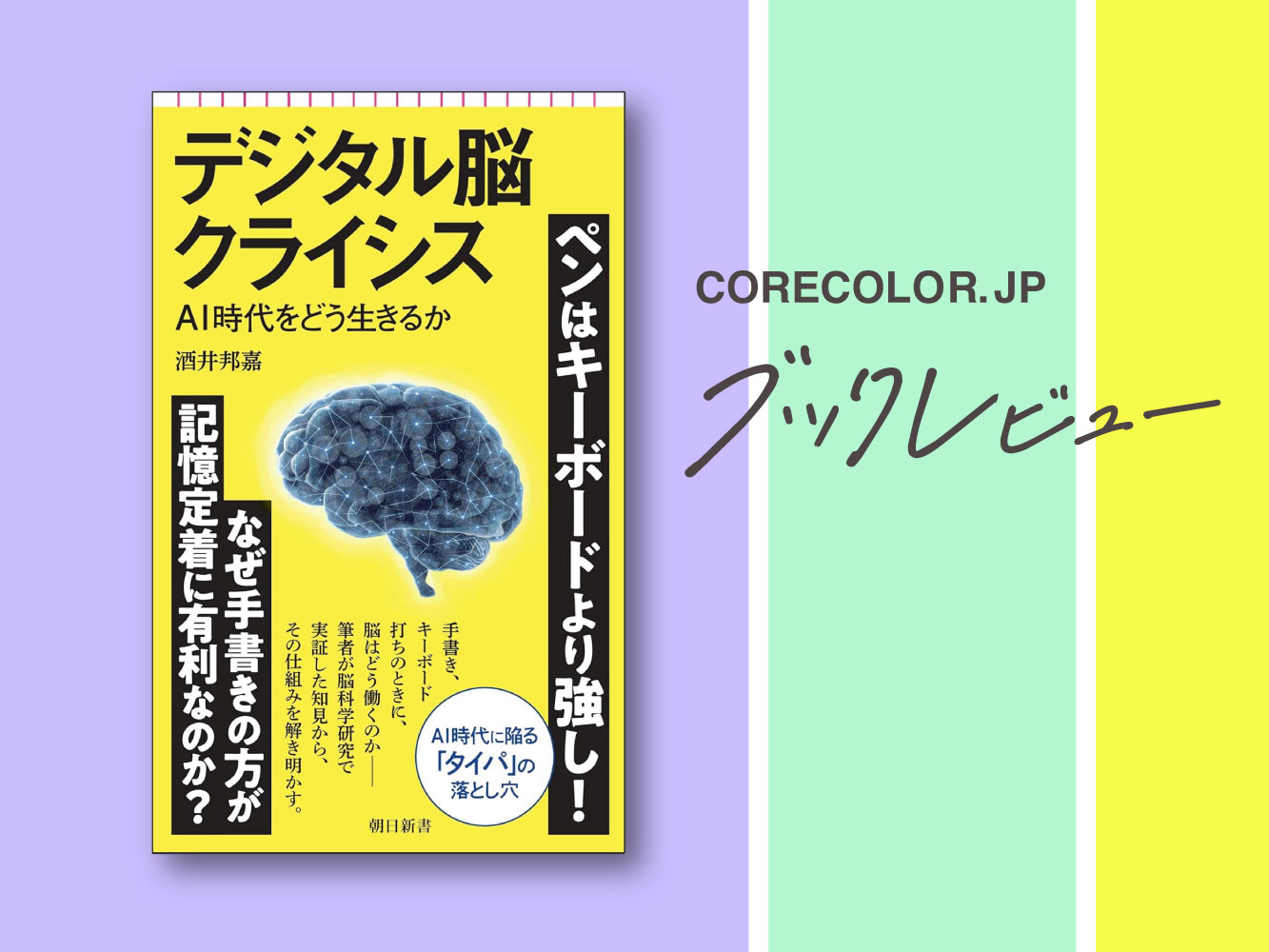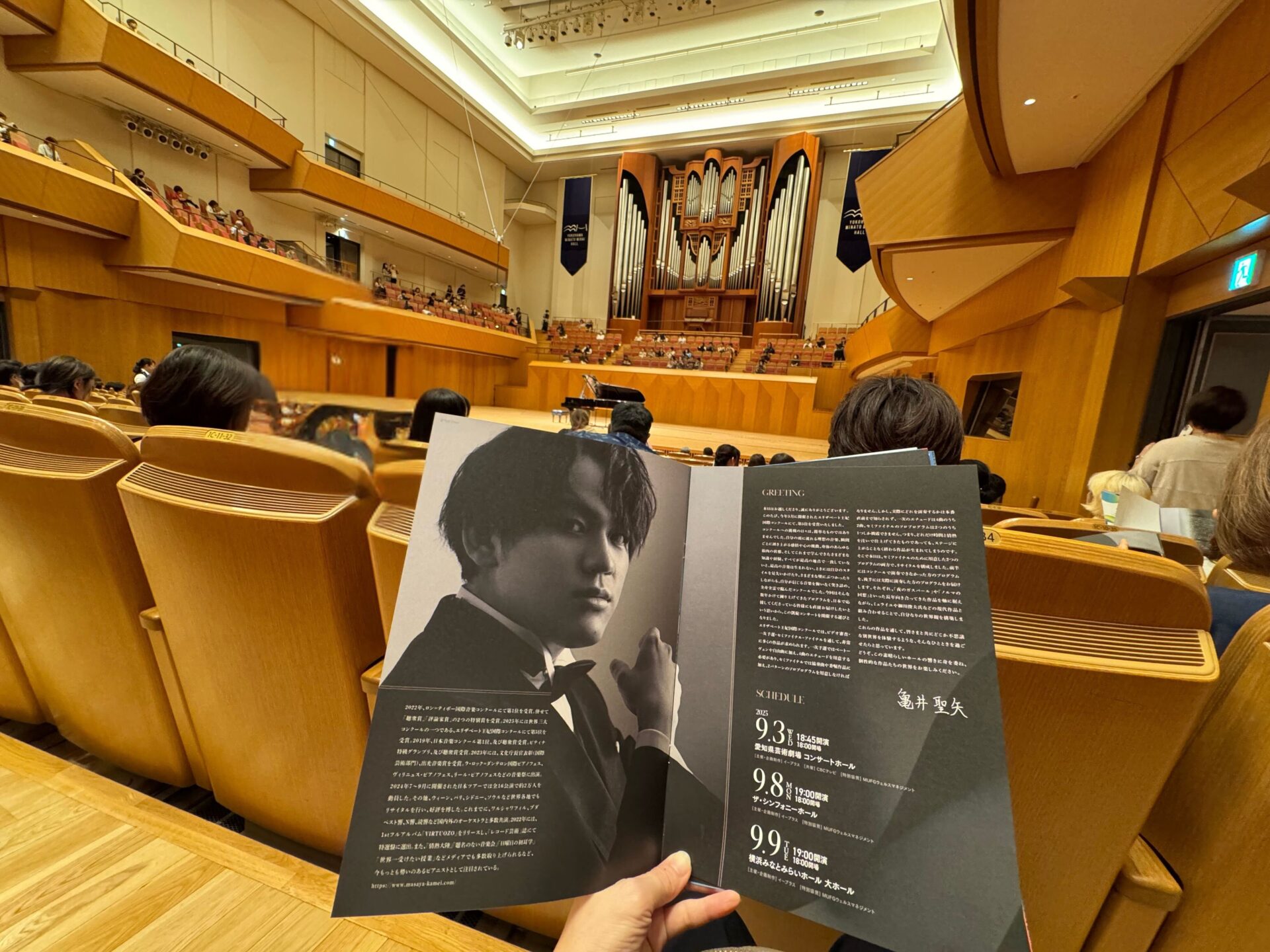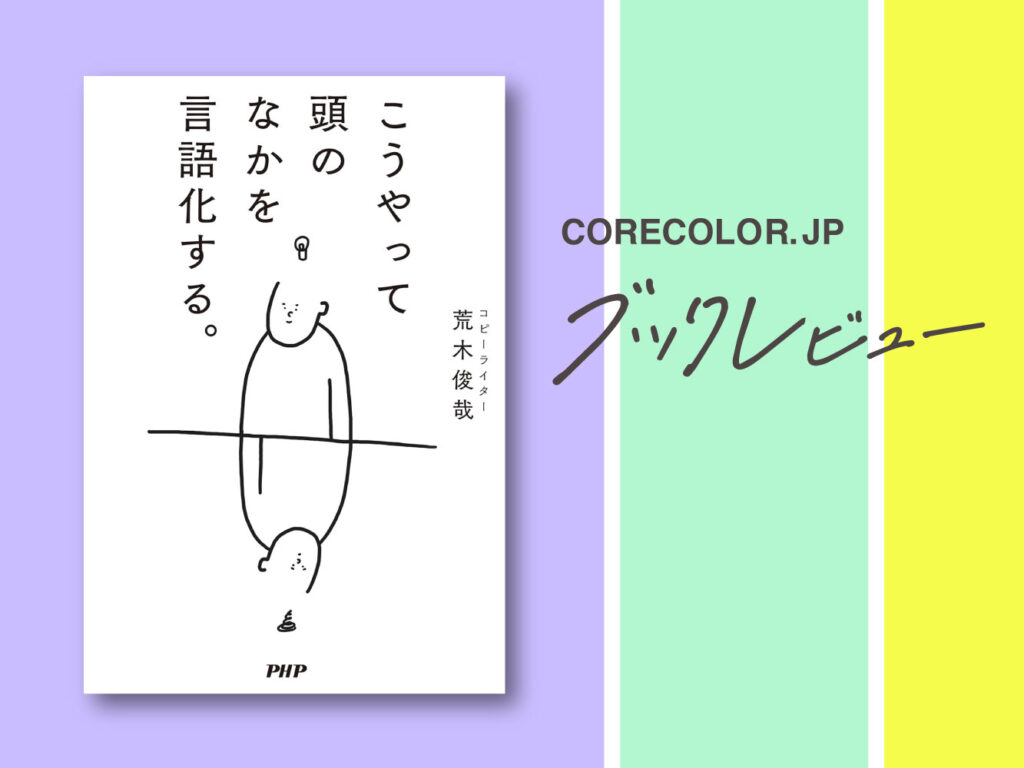
もやもやの正体を言葉にしたら、少し気持ちが軽くなった。『こうやって頭のなかを言語化する。』
子どもの習い事当番をしていたとき、乳児を育てる友人が「夫は休日もスマホばかりで、何もしない」とぼやいていた。同じように働きながら子育てしているのに、なぜ自分ばかりが家事を担うのだろうか。彼女の夫は「家事を手伝って」といえば動くけれど、そこには夫の「やってあげた」態度が透けてみえる。それがぼやきの原因だ。友人は、もはや毎週のように「手伝って」と頼むのに疲れ、自分の指示を待つ夫の姿勢にもやもやが募るばかりだという。
その話を聞いて、私の子どもが小さかった頃に似ていると思った。10年以上前の話だ。仕事と育児に追われる中、私はつい「自分で家事をやったほうが早い」と抱え込んでしまっていた。育児休暇を取得する夫が増えても、待機児童の数が減少しても、「指示を出しつづけることに疲れた妻」が、今も昔も一定数存在するような気がした。10年以上も夫婦間で同じような会話が繰り返されてきたのかと思うと、ちょっとめまいがするような感覚だ。
そんなとき、本屋で『こうやって頭のなかを言語化する。』を手に取った。コピーライター・荒木俊哉氏の著書だ。「妻のひと言に腹が立った」という30代男性のエピソードが目に入り、思わず読みすすめた。
本書では、言語化に悩む1,000人以上の人たちと一緒に作り上げたという、思考を言語化するためのメソッドが紹介されている。「言語化力のベースは『聞く力』にある」と述べられており、著者自身もコピーを作る時間の約9割を「聞く」工程に費やしている。
とくに印象に残ったのが、1日3分で実践できる「言語化ノート術」だ。ステップ1〜3に分かれていて、誰でも言語化ができるようシンプルにまとめられている。
ステップ1では、「日々の出来事」と「それに対して感じたこと」をメモする。
ステップ2では、「なぜそう感じたのか?」と問いを立てて、3分間で理由を一気に書き出す。
ステップ3では、その問いに対する「結論」を1行でまとめる。
という手法だ。この「言語化ノート術」では、感情の奥にある思考に気づけるよう、自分の声に耳を傾ける過程を大切にしている。自分の気持ちはわかっているようで、客観視することはなかなか難しい。この3ステップを踏めば、私にもできそうな気がした。
本書では、前述した「妻のひと言に腹が立った30代男性」が、実際にこの言語化ノートに取り組んだ様子が紹介されている。彼はステップ1で「ゴミ出しのことで妻に文句を言われて、腹が立った」と書いた。ステップ2では「腹が立った、のはなぜか?」と問いを立てた。問いの答えは、最初「気づいた人が自分でやればいい」「仕方ない」といった反発する理由が続いていたが、後半になると「わかっていて指摘されると、イラッとする」「反射的に言い訳してしまった」と、自分の中に原因を求める理由に変わっていた。
最終的にステップ3で彼が導き出した結論は、「やって当然と思われたとき」「自分でもわかっていることを指摘されたとき」の2つだった。著者はノートに記入した3分間で彼の反発する気持ちが収まり、内省が深まっていったと解説する。
ふいに10年前の自分を思い出した。職場でリーダーを任されていた私は、育休復帰した直後から出産前と同じペースで仕事ができると思い込んでいた。しかし、子どもの発熱や急な呼び出しが重なって思うようにいかず、とたんに壁にぶつかった。家庭でも、細かいいざこざが多くなり、山積みの家事はすべて週末に先送りされた。
夫は「疲れているんなら、休日くらい休んでいいよ」と気遣ってくれた。しかし、家事の多くを後回しにすると、翌週の生活がどうにも立ちゆかなくなることは目にも明らかだった。母に来てもらって一時的に状況を立て直すことができても、根本的な解決に至っていない。冒頭に述べた友人の「夫は休日もスマホばかりで、何もしない」状況と似ていると感じた。
もともと家事が嫌いではないのに、なぜ私はイライラしていたのだろうか? 子どもが生まれる前は、休日になると一日中キッチンに立ってごはん作りを楽しんでいた。なのに、自由気ままに作る料理と、時間に追われて義務感から作る料理は、まったくの別物だった。大好きだったはずの料理にストレスを感じていた。
そこで、10年前の出来事を振り返り、私もこのノート術を使って過去のもやもやを書き出してみた。
「なぜ、夫がスマホばかり見ていることに、私はイラッとしたのか?」と問いを立てた。出てきた理由は、「何度も同じことを言わせないでほしい」「私も休みたいのに、夫だけが休んでいてイライラする」「翌週に家事を先送りすると生活が回らないという危機感を感じてほしい」「夫は家事について自分ごとと思っていないのでは」といった本音だ。そこから導き出した結論は、「家事は妻の仕事だという暗黙の了解に対する反発」「家事を分担してほしい気持ちが夫に伝わっていない」の二つだった。
こうやって思考を整理してみると、家事に対する認識にズレが見えてきた。夫には「家事は妻がやったほうが良い、けれど大変そうなときは手伝う」という思い込みがあり、一方で私は「家事は協力していきたい」と考えていた。そのズレが、私のもやもやの原因だったのだ。
ノートに書き出すうちに、そんな日々をどうやりくりしていたのかを次第に思い出した。まず「夫と一緒に家事をする」ことで家事時間をスリム化しようとした。子どもが小さくてかわいらしい時期は本当に短い。その大切な時間を、夫へのもやもやで消耗するのは本末転倒ではないか、と思ったのは確かだ。
当時、家事の分担ルールを決めたことで私の気持ちは少し楽になった。「生活も子育ても一緒にとりくみたい」という目標に近づけたなら、それで十分だったと思う。分担を決めるにあたって、私は料理担当を手放さなかった。どんなに忙しくても「自分で作ったものを食べたい」「家族にも食べてもらいたい」という気持ちにずっと変わりなかった。
おいしい食事に元気づけられたり、満たされてほっとしたり。笑顔が見られて嬉しい瞬間がたくさんあった。「食を通じて体と心を整えたい」という思いこそが、自分の生きる原点だったと気づかされた。
もやもやを抱えたまま忙しい日々を送っていると、ちょっとしたことでイラッとしがちだ。「わかってもらえない」とぼやいていたのは、「察してほしい」思いの裏返しだったのかもしれない。夫婦間で話し合い、役割を分担し、自分にできることとやってほしいことを言葉にした。そうして少しずつ、新しい生活を築いていったことを思い出した。
こうしてあの頃の思考を言葉にしてみると、不思議と過去の自分も少し救われたような気がする。もやもやを放置せず、言葉に変えていくと気持ちが落ち着く。そのプロセスを大切にしていきたいと思った。今では、もやもやした日々もひっくるめて、かけがえのない子育て生活の一部だったと感じている。
文/石川 恵里紗
【この記事もおすすめ】