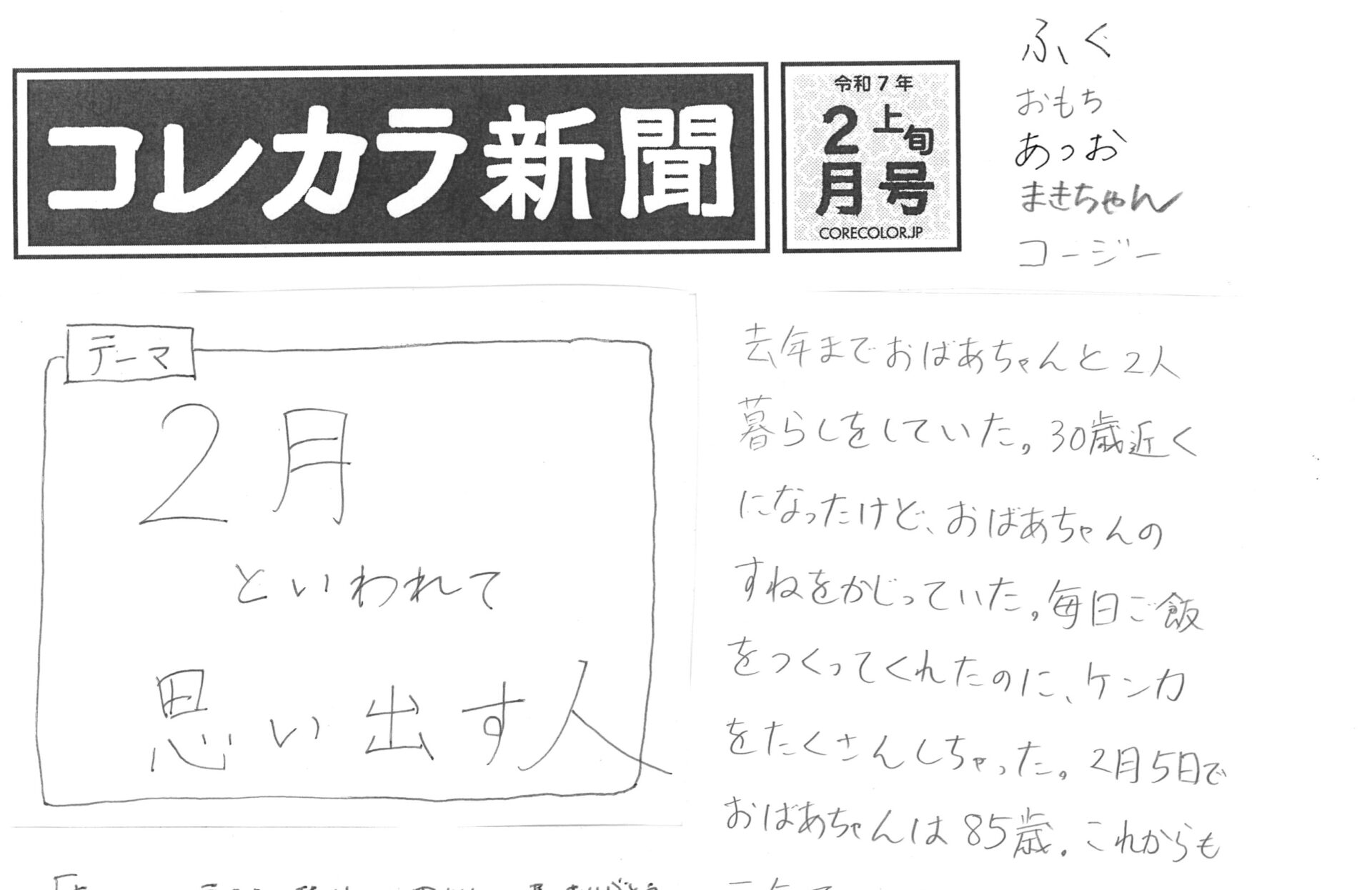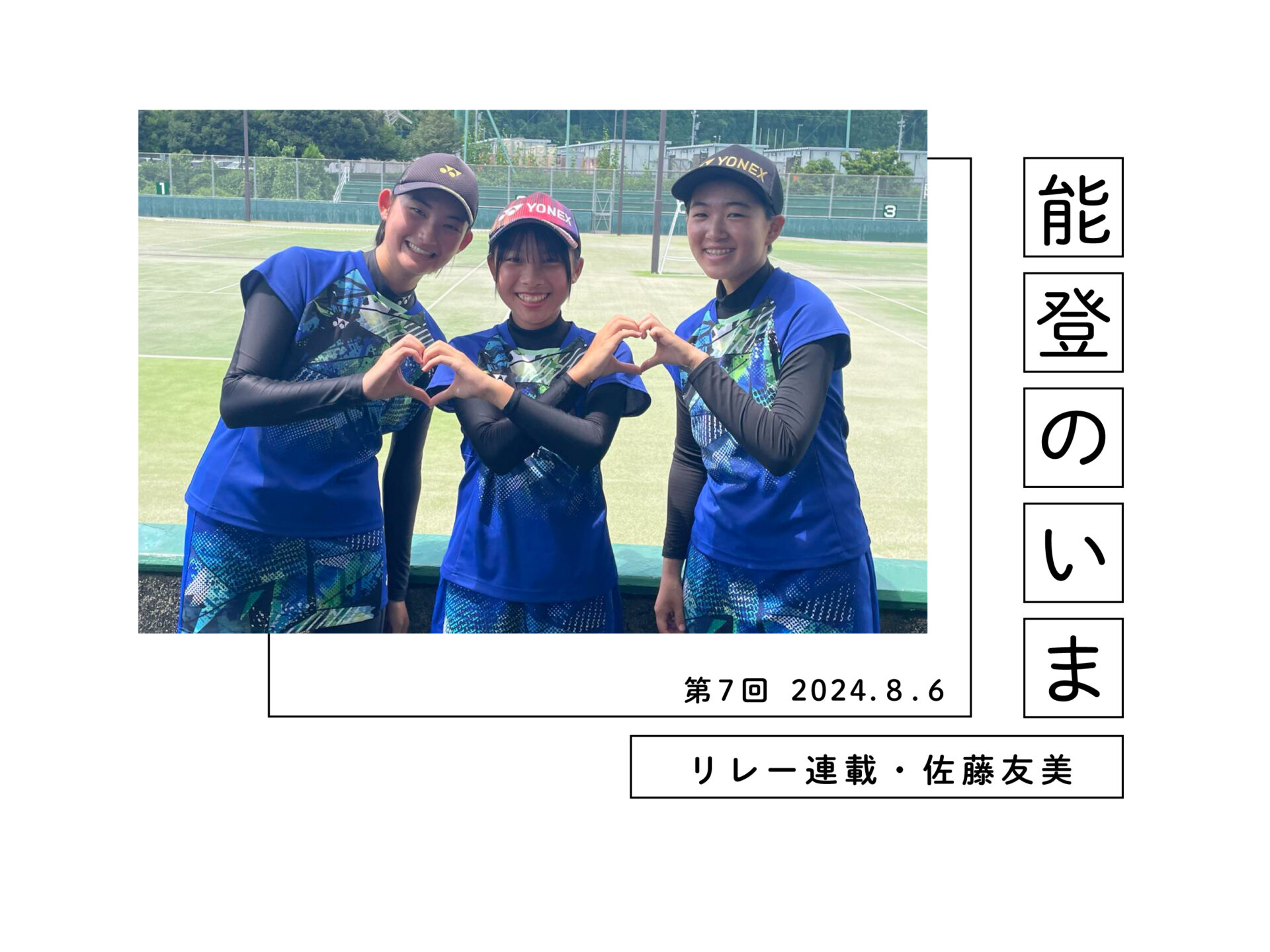骨董の器と現代の工芸作品が引き立てあう。プロデューサー・結城マミさん「新旧の美の競演」【リレー連載・あの人の話が聞きたい/第10回】
下町の面影残る家並みに、現代アートの美術館やカフェが点在する、東京・清澄白河。古き良き日本の姿を伝えながら新しさを受け入れるこの街に、2025年夏、築63年の古民家を改装したアートスペース「MUSUBI(結び)」が誕生した。結城マミさんは、ここで「骨董の器」と「現代の工芸作品」を組み合わせた展示会をプロデュースする傍ら、日本の伝統技術「金継ぎ」を教える。彼女のこだわりは「日常に美を取り入れること」。
20年間ツアーコンダクターとして世界を巡った彼女は、かつては旅先で人をつなぎ、今は街で美をつなぐ――その歩みの根には、幼い日の食卓に息づいていた日本の美があった。
(聞き手/青木 キクコ)
おしゃべりな金継ぎの時間
扉や床にのこる絵具がその歴史を物語る。かつて美術教室だった古民家の二階。すりガラスから柔らかな光が差し込み、窓辺には色鮮やかな陶器や骨董の器が並ぶ。色と光があふれる空間で、結城さんは定期的に「金継ぎのワークショップ」を開いている。
「飲み物を飲みながら、楽しくやりましょう!」結城さんの呼びかけに参加者の緊張も和らぐ。この日の参加者は5名、ほとんどが初心者だ。
金継ぎは、茶の湯文化が流行した室町時代から続く‶日本の伝統的な技術″。だからこそ、結城さんは、格式にとらわれない。目指すのは「敷居が低くて楽しい金継ぎ」だ。
やり方は、本漆を使った本格的な修復から、合成樹脂による体験型の簡易金継ぎまで、参加者が選択できる。結城さんの準備の手間は増えるが、参加者が気負いなく挑戦できる方を優先した。そして、作業に集中して静まりがちなワークショップ中には「ヒロさん、どう?」と、敢えて気安く声をかける。会話が生まれ、参加者同士も打ち解けていく。
「人と話すのは大事! どんな時も、人と話すとそこで新しい展開が生まれて、楽しくなることが多いでしょう?」そう力説する結城さん。人生の転機には、いつも誰かの言葉があった。

人が縁を結ぶ
もっとも思い出深いのは、高校3年生の時。手話とフランス語を学んでいた結城さんは、卒業後にどちらの道に進むか悩み、思いあまって区役所に電話を掛けた。「どうやったら手話通訳士になれるのか」という問い合わせから、話は膨らんだ。福祉課の男性は「手話通訳士は年齢を重ねてからでもなれる。若いうちに外国に行っときなさい!」と結城さんを激励した。顔も知らない人なのにと戸惑いながらも、その言葉に心が動いた。そして、高校卒業と同時にフランス南東部・アルプス山脈の麓にある小さな町に渡り、語学学校の門をたたいた。
その後も、結城さんは道に迷った時は人と話をして、心が動いた方を選んだ。心が動いた先には心躍るようなことが待っていた。人の勧めでフランスの山岳ツアーガイドになった時は「旅も人も好きな私には、この仕事が合っている!」と、そのままツアーコンダクターの道に進んだ。「私がたくさんの人にワクワクする世界につなげてもらったから、私も誰かをそんな世界につなぎたいと思ったのかもしれないですね」と結城さんは振り返る。
海外で思い出す、食卓に宿っていた「日本の美」
得意の語学と明るい性格で、結城さんはどこへ行っても人と打ち解けた。ツアーでは、ガイドブックに載っていない名所や現地の人の飾らない姿を引き出し、忘れがたい旅を提供した。お客さんの喜ぶ姿はやりがいになった。
一方で、ツアーコンダクターになって20年の間、結城さんは、旅先で美術品や工芸品に触れる機会に恵まれた。その度に、幼い頃の家での風景を思い出すようになっていた。
結城さんの家は、祖父の代から続く古美術商だった。家のいたるところに古い美術品が置かれ、食事時は、骨董の器が市販の食器と一緒に食卓に並んだ。母が古伊万里の器にかぼちゃの煮物を盛りつけ、父親が割れた器に金継ぎを施し、時折「お父さんの大事なお道具だよ」と風呂敷をほどいて由緒ある骨董の茶碗を見せてくれた――日常に、古くて美しい器があった。
「例えば、季節の移ろいを表す言葉が豊かだったりして、日本は生活に美が宿っているんだなと改めて気づいたんです」。結城さんにとって、そんな‶日常の美″の象徴が、骨董の器だった。世界を巡って日本の美を再認識し、骨董への憧憬が積み重なる。その思いが一気に弾けたのは、コロナ禍だった。感染症の流行でツアー旅行が激減。家族と過ごす時間が増えた結城さんは、父親の老いに気づく。「お父さんがいなくなったら、我が家の古美術商は途絶える」。焦る気持ちと共に心に浮かんだのは、幼い頃の食卓。骨董の器が食卓に彩を添え、豊かな時間が流れていた。「旅先へ人をつないだように、‶骨董の器がある豊かな日常″を、たくさんの人につなぎたい」そんな思いが、結城さんに芽生えた。
新旧の美をつなぐ
「思いを形にして!」――今度は姉の言葉に背中を押された。結城さんは、ツアーコンダクターを続けながら父から骨董の知識を学び、金継ぎの技術を身につけた。一方で、ツアーで訪れた先々で、現代の工芸作家の作品と出会った。ガラスや陶器など、作家の意匠を凝らした器は美しかった。骨董と新しい器がまぜこぜに並んだ生家の食卓を思い出し「あんな風に両方の器が身近にあってもいいのでは」と思った。ひとつのテーマに沿って骨董と現代の器を一緒に展示する企画を練り、意中の作家を訪ねては出品を依頼する日々が続いた。突然の出品依頼は取り合ってもらえないことも多かったが、諦めなかった。そんな折、結城さんは、足しげく通っていたギャラリーのオーナーに見初められる。作品をじっくり見ては質問をしてくる結城さんが、強く印象に残っていたのだ。結城さんの企画案に、オーナーは「ここでやってみませんか」と申し出る。
こうして、2022年夏、都内のギャラリーで、初の企画展が実現した。テーマは夏を表す季語「南風(みなみはえ)」。‶梅雨明けを告げる風″を、若いガラス作家の作品と伊万里焼の器で表現した。水のように澄んだ空色のガラスの皿に、父と選んだ伊万里焼の器を重ねた。ガラスの青に、伊万里焼の白と藍、金継ぎが映える。異質な組み合わせに、来場者からは「こんな組み合わせをしてもいいんですね!」と驚きの声が上がった。古い美と新しい美が響き合う瞬間、結城さんは自分の進む道を確かに感じ取った。

その後も、結城さんは企画展や金継ぎのワークショップを重ねていった。ある日、その様子をSNSで見た幼馴染から「清澄白河で一緒に何かやらない?」と声がかかった。聞けば、清澄白河の古民家を改装し、お店を立ち上げるところだった。下町の温もりと新しい文化が交わる清澄白河なら、自分の目指してきた「古い器と新しい器を提案する場」を実現できるかもしれない。これまで積み上げてきた活動に重なるような誘いに、結城さんは強い必然を感じた。
古民家を木の温もりを残すように改築し、一階は幼馴染の夢だったセレクト雑貨のお店に、二階は結城さんのアートスペースに決めた。物は違えど「魅力的で素敵なモノ・コトを発信していきたい」という気持ちは一緒だった。「楽しいことをしよう!」が、ふたりの合言葉になった。
「MUSUBI」に集う仲間たち
ワークショップがない時など、結城さんは一階の店頭に立ち、お客さんに「この2階で金継ぎやってるんですよ!」と気さくに声をかける。「え? ここで?」と会話が生まれ、金継ぎや器の美しさを楽しむ仲間が増えていく。8月だけでワークショップに参加したのは30人以上。リピーターもついた。人がつながるMUSUBIの姿に、かつて沖縄で金継ぎを施したシーサーが重なった。割れた破片をつなげた瞬間、シーサーの目に光が戻った。自分はつなぐことで新たな命を吹き込んでいるのだと確信した。

この秋には、陶器の破片を金継ぎでつなぎ合わせて箸置きをつくる新たなワークショップも開始した。「日本の伝統である金継ぎを広めたい」という趣旨に賛同した窯元が、材料の一部を提供してくれた。美を結ぶ仲間は、着実に増えている。「私は、チームMUSUBIを作っているのかもしれませんね」――結城さんの手から紡がれる一筋の金は、未来に向けて次の結び目を拓いていく。(了)
文/青木 キクコ

結城 マミ(ゆうき まみ)
東京生まれ。東京の古美術商の家に生まれ、幼少期より古美術品に囲まれて育つ。高校卒業後渡仏しフランス語を学んだ後、約20年フリーのツアーコンダクターとして活動。「人生は旅である」という思いのもと、国内外を巡り、伝統文化・芸能・アートを肌で体感。2025年春より、東京・清澄白河のアトリエギャラリー「MUSUBI結び」で、個展やアーティストとの企画展を手掛けるほか、金継ぎや苔玉のワークショップ講師として、伝統技術と現代のアートを結ぶ場を創り出している。
【この記事もおすすめ】