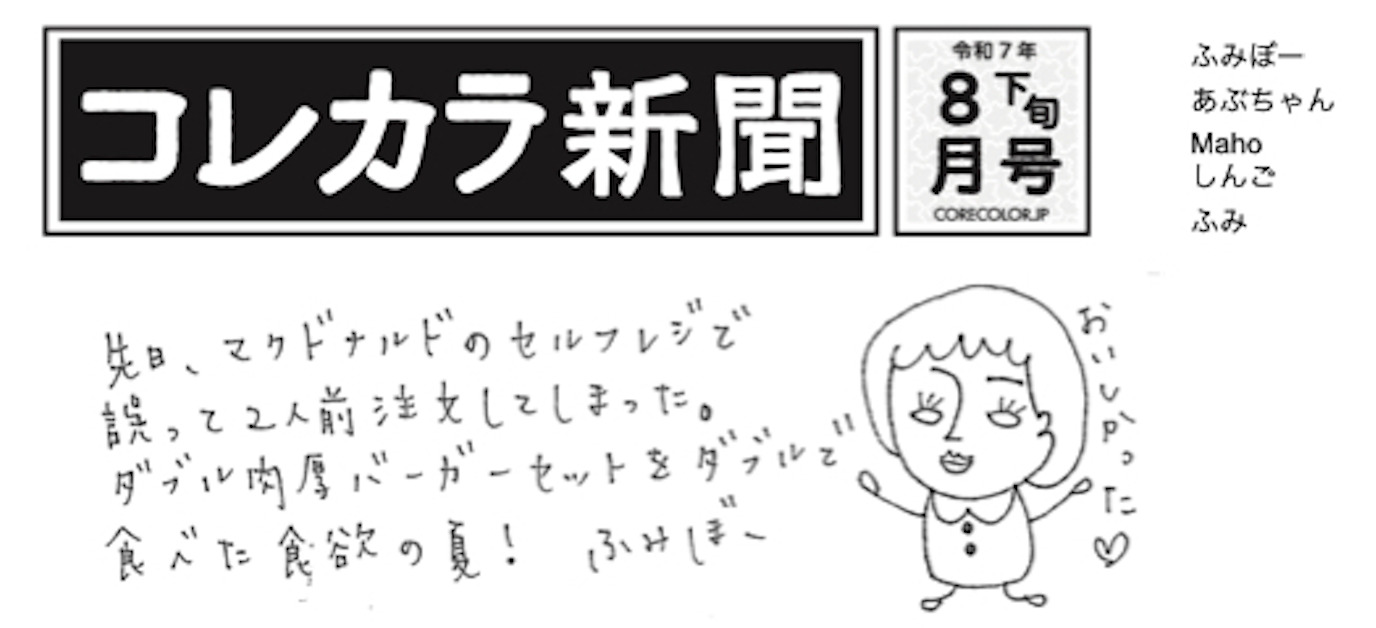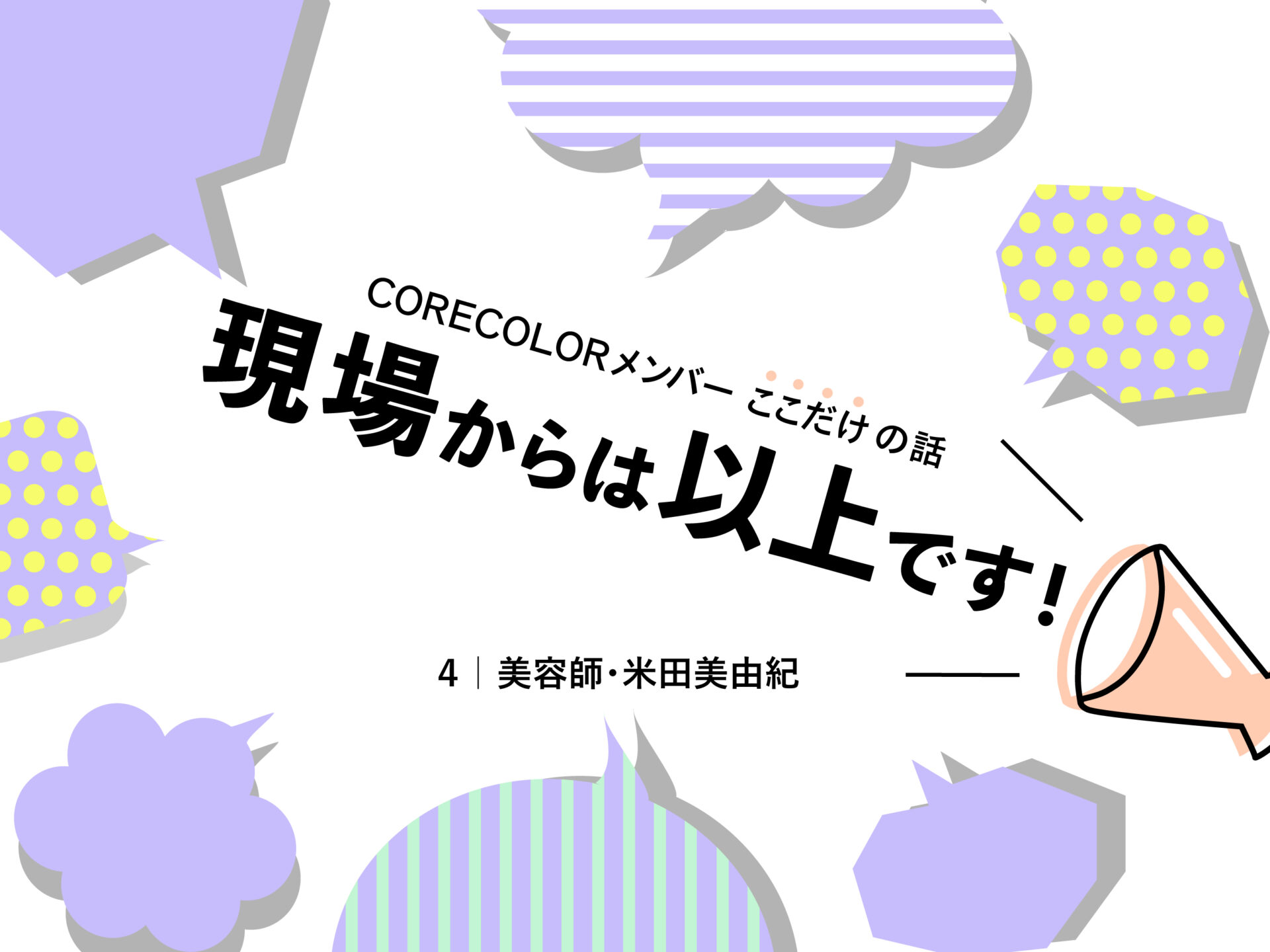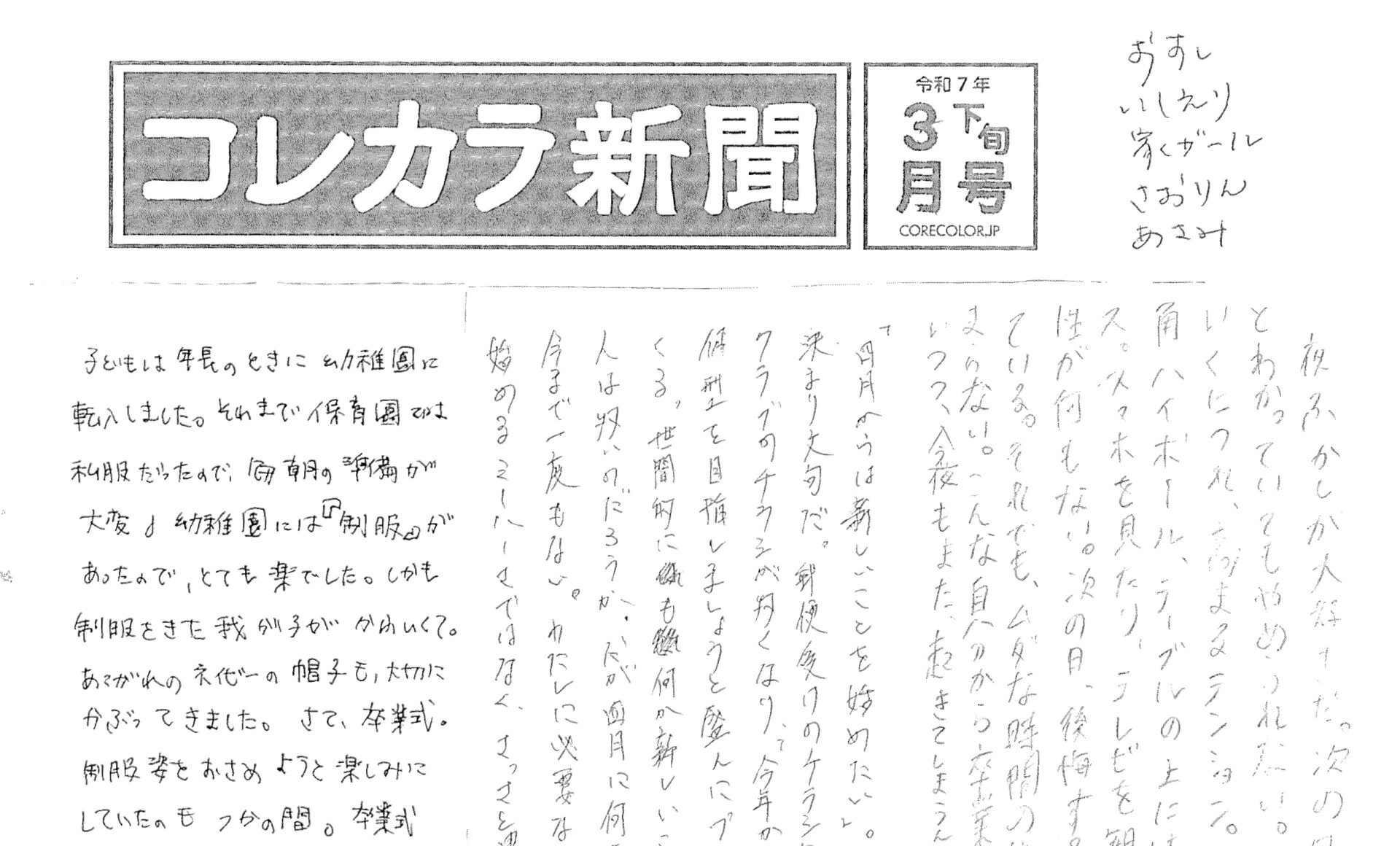過疎のまちが理想郷になる。中之条で拓いた「アーティストとして生きる道」山形敦子さん【リレー連載・あの人の話が聞きたい/第8回】
人口1万4千人の小さな山あいのまちのイベントに、国内外から48万人が訪れた――群馬県中之条町で 2007年から隔年で開かれている国際現代芸術祭「中之条ビエンナーレ」だ。前回の開催では初回の10倍に当たる48万人が来場、経済効果は4億4千万円に達した。先月はじまった第10回で、公式チラシのメインビジュアルのひとつに選ばれたのは、中之条町に暮らす美術作家・文化財専門委員の山形敦子さんの作品だ。「中之条だからこそ、アーティストがアーティストとして生きられる」と語る山形さんに話を聞いた。
聞き手/竹宮 周
過疎の町を変えたアートの祭典、その現場から
古民家の玄関先に無造作に置かれた袋には、採れたてのキュウリやナスが詰まっていた。「一度や二度ではないんです。本当にありがたくて」。そう頬を緩ませるのは、2021 年に群馬県中之条町に移住した山形敦子さんだ。美術作家として、顕微鏡で見る細胞のイメージや土地の記憶をテーマに、手漉き紙や接着剤・糸・布などの素材を使い絵画やインスタレーション作品を制作している。
山形さんが移住した中之条町は、群馬の北西部、新潟と長野の県境に位置する山里のまちだ。町の8割を森林が占め、かつては養蚕や温泉観光業で栄えたが、いまは少子高齢化に直面している。そんな過疎の町が、近年大きなにぎわいを見せている。その原動力は、2007年に始まった国際現代芸術祭「中之条ビエンナーレ」だ。会期中の週末は、カーナビに表示された山深い道路に渋滞を示す赤い矢印が並ぶほどの盛況ぶり。回を重ねるごとに、来場者数・経済効果ともに伸び続け、注目を集めている。

「アーティストとして生きていくのは、簡単なことではないんです」と、山形さんは言う。創作活動だけで食べていける人はごくわずか。経済的なハードルに加え、“アーティスト”という職業そのものが日本の社会では理解されにくい。
「自己紹介のときにアーティストと名乗ると、『普段は何をしているの?』と聞かれることもよくありました。でも、中之条なら、“作品をつくって生きること”と“アーティストとして暮らすこと”の両方が成り立つような気がしています」
中之条ビエンナーレの特徴のひとつに、国内最大規模のアーティスト・イン・レジデンスの取り組みがある。アーティストが完成した作品を外部から持ち込み、会場に設置する展示が多い芸術祭もあるが、中之条ビエンナーレはそれと一線を画する。募集要項に「10日以上、中之条町で滞在制作をすること」と明記されているのだ。アーティストたちは、町の使われなくなった宿に無料で宿泊し、中之条の土地や自然からインスピレーションを受け、町の人と交流しながら作品を制作する。この関わり方こそがアーティストと町の関係を築いてきた。はじめは「うちの町でアート?」「観に行ったけどよくわからなかった」のような声も多かったが、アーティストとの関わりを通して、町には徐々にアートの文化が浸透していった。2023年には、アーティストを含む227人が中之条町に居を移した。
札幌からフィリピンへ──山形さんが「アーティスト」になるまで
山形さんも、最初から職業・アーティストを名乗っていたわけではない。札幌に生まれ、幼い頃から父に連れられて美術館に通い、芸術に親しんで育った。嬉しいときもつらいときも、小さなスケッチブックに絵を描くことが心の支えだったと言う。東京での会社員・週末アーティスト時代を経て、家族の都合でフィリピンに渡り、美術作家としての活動を始めた。
「フィリピンでの最初の数年は、アイデンティティクライシスでした。私が入った現地のアートシーンは、日本人がほとんどいなかった。そこで“日本人代表”のように扱われるけれど、何をもって自分は日本人と言えるのか。自分のルーツとは何か、常に問い続けていました」
試行錯誤を重ねるうちに、パイナップルの繊維でできた和紙や、日本軍が戦時中に発行したカタカナが書かれた紙幣(軍票)と出会った。これらの素材を用いて、日本とフィリピンの文化を融合させた作品を発表すると、高い評価を受けるようになった。作品が売れ、ギャラリーから引き合いが増え、逆輸入のような形で日本や海外の展覧会に招待されるようになった。富裕層にアート作品を購入する文化が根付いているフィリピンで、山形さんは「アートで生計を立てる」実感を得ていった。
コロナ禍を経て中之条へ―見えないものを可視化するアートの力
2017年、2019年とフィリピンに拠点を置いたまま中之条ビエンナーレに参加したのち、山形さんはコロナ禍をフィリピンで経験した。日本以上に厳しいルールの外出・渡航制限で生活が揺らぐ日々、思い出したのは中之条での暮らしだった。そして、2021年に日本へ帰国、中之条町に移住することを決意する。
山形さんが中之条に住むことで生まれた作品が『消えゆく土地の記憶』だ。透明の立方体の中に、村内の場所の写真と地名の文字が浮かび上がる複数のオブジェで構成されたインスタレーション作品。暗闇の中に立ち現れる地域の古い地名と現在の写真は、観る者に現在と過去が行き来するような感覚を呼び起こす。

山形さんは、展示会場となった古民家「やませ」のことを調べるうちに、地域に口承でしか残っていない地名があることを知った。
「ここに住んだからこそ、より深く土地のことを知りたい。そう思ってリサーチを重ねました」
『伊参(いさま)の民俗』など、土地の名前が載った古い資料を集め、旧地名を知る 80代の住民から聞き取りを重ねた。歩くのも困難な場所もあったが、自分の足で現地を訪ねて写真を撮り、地名を記録して回った。
「今では数軒の家しか残っていないけれど、かつては子どもたちの声があふれ、村の暮らしはとてもにぎやかだった。この場所にたしかにあった日々を想像しながら、今の風景との対比で記憶を可視化したい──そんな気持ちで制作しました」
入念にリサーチを重ねた美しいインスタレーション作品は多くの反響を呼び、2023年の中之条ビエンナーレ図録の表紙を飾った。
細やかで情熱的なリサーチ姿勢が仲間に「民俗学者になったみたい」と評された山形さんは、郷土史家の高齢男性のみで構成されていた中之条町文化財専門委員に抜擢される。縄文時代の遺跡が残る中之条町で、文化財専門委員は町内にある無形・有形文化財の保存状態を定期的に調べ、広報誌に活動の紹介をする。40代・女性・移住アーティストの立場は異例だった。
中之条だから実現できるアーティストとして生きること
「私が住み始めたときから、すでに中之条にはビエンナーレの歴史がありました。農作業姿の 80 歳くらいのおじいちゃんから「ああ、ビエンナーレかい。アーティストかい」と当たり前のように言われたり、「湯の宿 山ばと」旅館の一室の内装を丸ごと依頼されたり。町の人にごく自然にアーティストに“仕事” をお願いする土壌があるんですよね。アーティストがお医者さんや学校の先生みたいに、社会を構成する一員として自然に受け入れられているように感じます」
地方の小さなコミュニティの人のつながりの中にこそ、想像もしない可能性が眠っているのかもしれない、と山形さんは語る。移住アーティストの友人と行なっている、中之条からアートの話を発信するポッドキャスト「こけラジオ」も人気だ。一軒家をまるまる布で飾った中之条ビエンナーレ2025年の参加作品『すべてはめでたき生のために』も話題を集めている。
「今はアルバイトをしなくてもアーティストとしての活動だけで生きていくことができています。美しい自然やおいしいご飯、温泉に囲まれて暮らせて、自分の作った作品がみんなに喜んでもらえて、循環していく。アーティストだからこそ、私のアンテナを使って町の人に見えない価値を提示することができる。なんだか奇跡みたいな日々です」
中之条を歩くアーティストの目は、かつてのように自分の内側だけでなく、町と未来を見つめていた。(了)
執筆/竹宮 周

山形 敦子(やまがた あつこ)
美術作家、中之条町文化財専門委員。
北海道札幌市出身。中之条ビエンナーレ出展をきっかけに、2021年に中之条町に移住。現在は、制作活動の傍ら築100年以上の古民家を改装した私設美術館「藝術中之条」や、「旅館山びこ」の別館7部屋に中之条町に拠点を置くアーティストが作品を展示する藝術空間「YAAP(ヤープ:Yamabiko Artist Apartment) 」の立ち上げに参加するなど、中之条町とアートを繋ぐ活動を精力的に行なっている。ポッドキャスト「アートのはなし こけラジオ」主催。東京外国語大卒。
中之条ビエンナーレ公式ホームページ
【この記事もおすすめ】