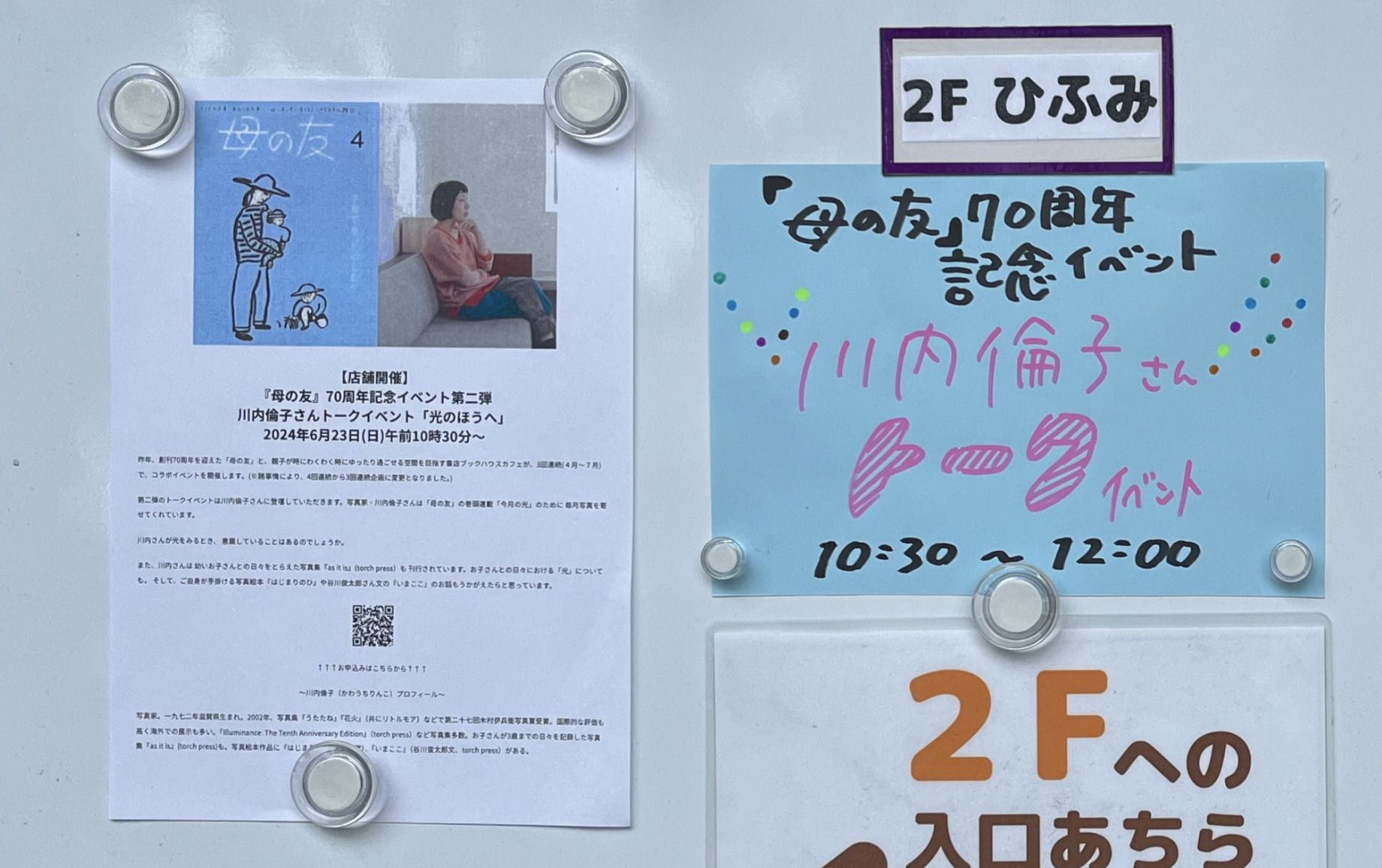私が目にした美しさと苦しみは何だったのか。舞台『三人姉妹』
重たい毛布をかけられたかのように、周りの空気がずっしりとのしかかり、私は椅子に沈み込んだ。既に幕は下り、拍手は鳴りやんでいる。立ち上がるのが難しい。悲劇を観た後には、ときどきそうなる。では、それが喜劇を観た後だったとしたら?
舞台『三人姉妹』。
ロシアの劇作家アントン・チェーホフが1900年に執筆した戯曲だ。『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『桜の園』とともに「チェーホフ四大戯曲」と呼ばれるうちの一作。日本でも様々な演出家、俳優により繰り返し上演されてきた。今回は、かつて蜷川幸雄さんの演出助手をされていた大河内直子さんの演出により、東京・浜松町の自由劇場で上演された。
実は、そんなことは全く知らずにチケットを取っていた。「主演に保坂知寿さん、場所が自由劇場」。それだけで、私にとってはチケットを取るに十分な条件だった。
保坂知寿さんといえば、かつて劇団四季の看板俳優として『キャッツ』『オペラ座の怪人』『ウェストサイドストーリー』等数々の作品でメインの役を演じていた方。2002年の『マンマ・ミーア!』日本初演のオリジナルキャストでもある。カーテンコールで立ち上がり、彼女が演じるドナと一緒に踊ったことを思い出してニヤついてしまう私のような人は少なくないと思う。2006年の退団以降も、ミュージカルやお芝居の舞台に立ち続けている舞台俳優だ。
自由劇場は劇団四季の専用劇場。大がかりなミュージカルではなく、お芝居を中心に上演する小規模劇場である。他の団体に貸し出すこともあり、今回のように劇団四季ではない公演も行われる。
30年ちかく劇団四季を見続け、退団された俳優さんも追いかけている私には、「あの保坂知寿さんが、あの自由劇場の舞台に再び立つ」だけで感動さえ覚える状況だった。
『三人姉妹』に話を戻す。
そんなモチベーションでチケットを取り楽しみにしていた公演前日、「一応」と思いウェブサイトを見てみた。内容や出演者について、さらっと見ておこうと思ったのだ。そして頭をかかえた。
チェーホフ? ロシアの戯曲??
演出家のコメントとして「チェーホフに挑むことを決めました」とある。「挑む」って、何?
長年演劇好きをやっているが、古典はシェークスピアを何本か観た程度。これはどう考えても、軽い気持ちで観られる内容ではない。鼻歌を歌いながら帰れるものではない。そんな覚悟だけは決めざるを得なかった。
時代は帝政ロシア末期。
三人姉妹の邸宅にたくさんの人が集まり、歌ったり踊ったりしながら未来を語り合う第一幕。明るい中でも各々が抱える不安や不満、理想通りにいかないもどかしさが語られる。
二幕目以降は、現在の生活の閉塞感に苦しむ姉妹が如実に描かれる。ある者は街を出、ある者は命を落とし、姉妹の周りから人々が去っていく。孤独や苦しみを抱えながらも、「それでも生きていく」と力強く前を見て、2時間半にわたる舞台は終演を迎える。
全体的に、台詞の量がとても多い。各人が、それはそれはよく話す。これは後から知ったことだが、自分の心理描写をとにかく言葉にするというのが、チェーホフの戯曲の特徴らしい。今自分がどんな気分で、何が嬉しくて何が嫌で何をしたくて……という心理の移り変わりやその理由を自分で説明する。観ているこちらからすれば、分かりやすいことは分かりやすい。けれど、言っていることがストレートすぎて、辛辣すぎて、少しずつ首をしめられているような気にもなってくる。
姉妹はこんな言葉を発する。(※実際の台詞とは異なると思います。)
「希望もないのに、なぜ生きるの」
「なぜ人生はあるのか、なぜ苦しみはあるのか」
「でき損ないの人生」
「みすぼらしい人生」
「地平線の向こうに、光はあるのか」
そんな言葉を受け止めるのは、正直しんどい。ああなんか分かる、そうだよね、と同意しつつも、すぐには受け入れがたい言葉が次々に飛んでくる。そんなにはっきり言わないで、と、舞台上の会話に自分も入っていくような感覚を覚える。使われる言葉が磨かれているだけに、その鋭さをかわすのは難しい。
三女が結婚前夜に婚約者を亡くし、姉妹が寄り添う最後のシーン。「働くんだ」「生きていくんだ」と支え合いながら決意するその様子とは裏腹に、晴れやかで軽快な音楽が流れ、朝日のような爽やかな光があたる。そのちぐはぐさが、理想と現実の乖離や、逃れることのできない辛さや苦しみを象徴するようで、苦しくなった。そして、幕が下りてもすぐに立ち上がる気になれなかった。
席数約500席の自由劇場は、作品に入り込みやすい空間だ。「”正統な新劇”を継承する運動を継続するための基点となるべく」建てられた(劇団四季ウェブサイトより)というだけあって、舞台と客席の距離が近く、濃密な空間を作り出す劇場だと感じる。劇場内外のシンプルな装飾も、お芝居に対する誠実さのようなものを感じさせる。舞台の奥行が深いのもいい。今回の演出もその奥行を活かした遠近で、人が集まるにぎやかさ、人々の心のすれ違い、去りゆく人が無言で語るメッセージなどが表現されていたように思う。
内容を少しでも知っていたら、その敷居の高さを敬遠して観に行かなかったであろう今回の舞台。「保坂さん×自由劇場」は、「私が働く理由」「私が生きる意味」に思いをめぐらせる機会になった。
正直、そういうテーマは得意ではない。答えが出ないから、常になんとなく避けている。さらに言えば、お芝居や映画、本で扱われるテーマを自分に当てはめて考えることは、めったにない。それなのに、というべきか、だからこそ、なのか、今回はこの姉妹から「あなたが生きる意味は?」と突きつけられて面食らった。そして、最近直面した身近な人との別れや、自分はどう生きたいのかという問いにも、目を逸らさずに乗り越えていけと発破をかけられた気がする。
自由劇場に帰ってきた保坂さんを楽しみたかっただけなのに、生きる苦しみや難しさに正面から向き合うことになるとは。それでも直視し続けたのは、姉妹の圧倒的な美しさと、俳優たちの技術から目が離せなかったから。彼らを支える舞台装置と照明、そして言葉の美しさにも、救われた気がした。
そして後日。
このレビューを書くにあたり作品について調べていたら、チェーホフ自身は『三人姉妹』を「喜劇と考えていた」という記述を見つけた。公式ウェブサイトでも、出演者のひとりがそう話している。
……ん?
笑えるシーンがあったのか。立ち上がれなかった私は喜劇を観たのか。そうであるならば、そもそも喜劇とは。
チェーホフ……? で始まり、喜劇……? で終わる、深い迷路に迷い込む観劇となった。
文/伊藤ゆり子
【この記事もおすすめ】