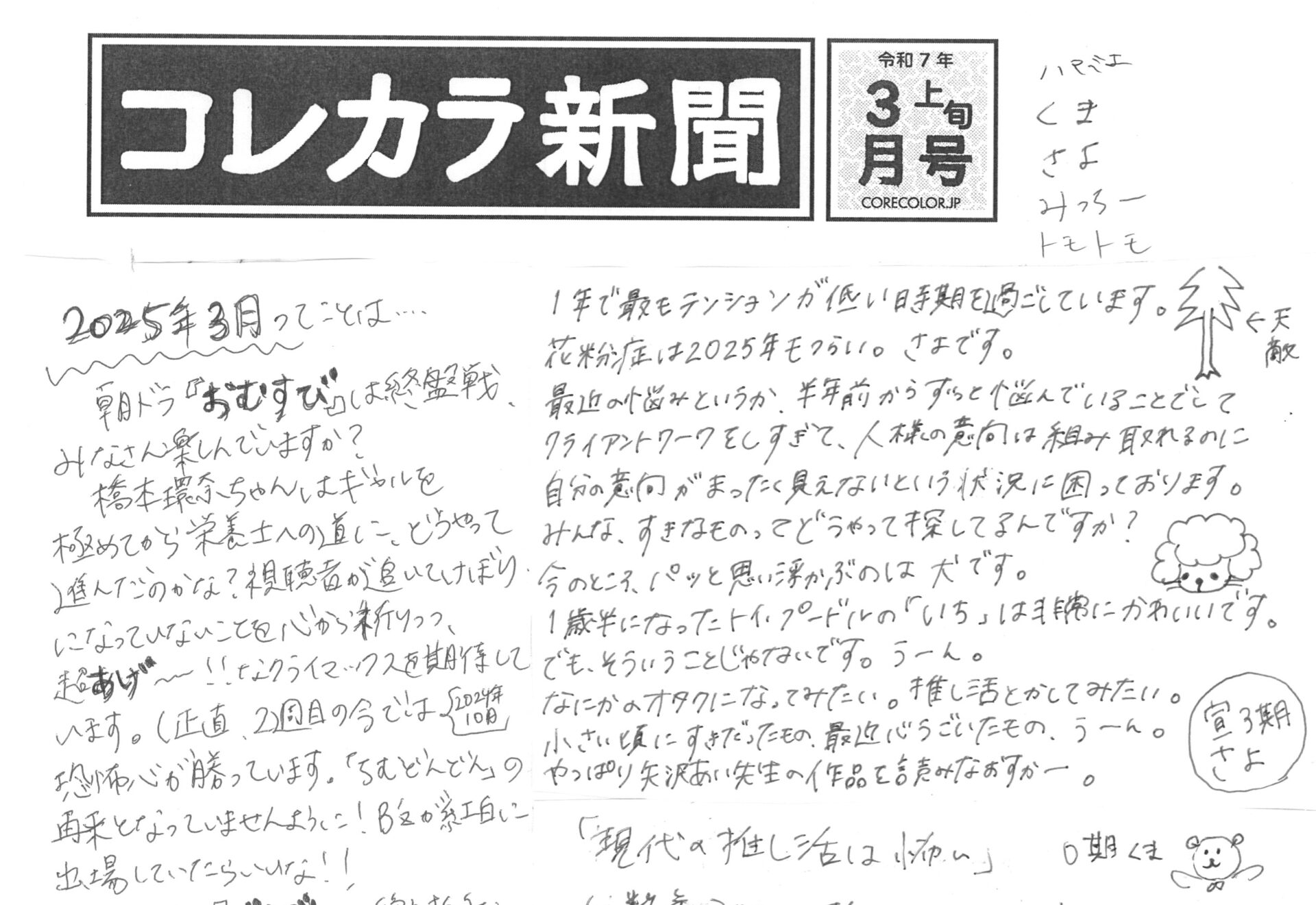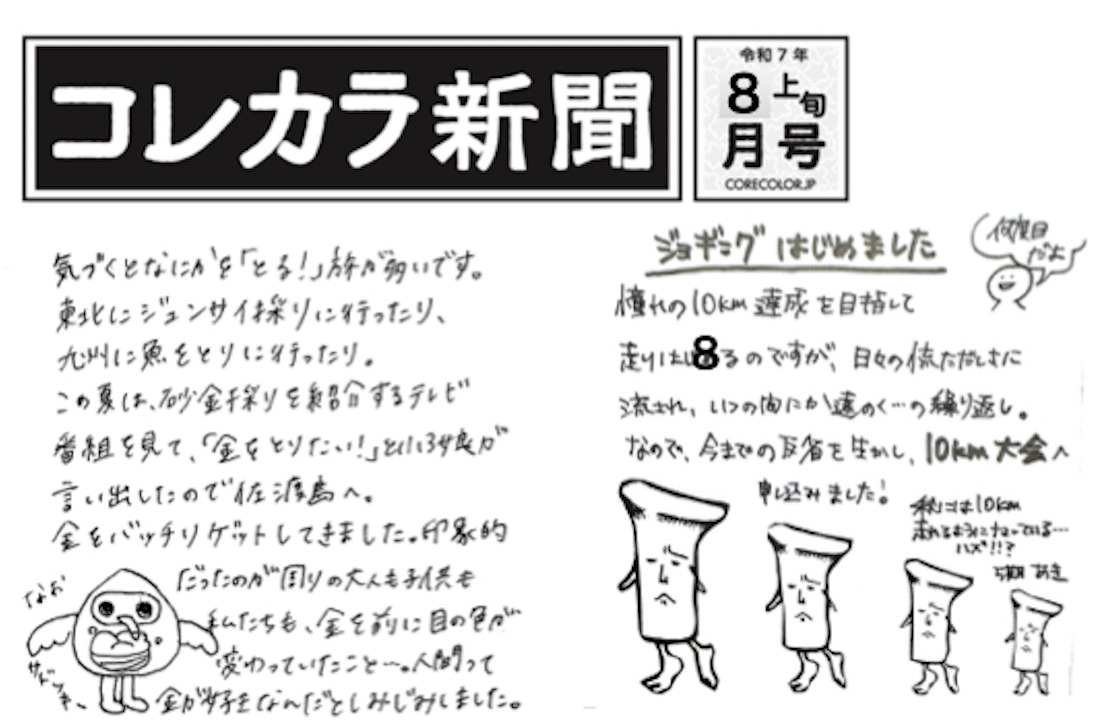避難先の落ち着かない日常【連載・能登のいま/第1回】
CORECOLOR編集長のさとゆみです。CORECOLORのライター仲間に、石川県輪島市に住む、二角(ふたかど)さんという男性がいます。今年1月1日の能登半島地震で被災し、いまは金沢市のアパートで避難生活を送っています。
輪島市はとくに被害の大きかった地域です。親戚のお一人は、今回の震災で痛ましくもお亡くなりになられたと聞きました。震災から5か月たったいまも、まだ家屋に上下水道が通らない場所が多く、二角さんも家に帰れないまま、2人の子どもを抱え単身避難生活を続けています。
久しぶりに連絡をとったとき、Zoomの向こうから「このまま復興が終わったと思われるのが怖い」「能登を忘れないでほしい」という切実な二角さんの言葉を受け取りました。
私たちに、何ができるだろうと考えました。まずは現地を知る二角さんから、リアルな「能登のいま」を伝えてもらおうとこの連載をスタートします。
ここからは、二角さんの文章をお届けします。
始まりは2024年1月1日午後4時すぎに起きた2度の地震でした。
1回目はまだ余裕がありました。地震が頻発していた奥能登の輪島市の住民としては、いつもより少し揺れが大きいなと感じる程度。ところが2回目は激しい縦揺れ。横にいた小学5年生の息子に毛布をかぶせて覆い被さり、揺れが収まるのを待ちました。
あれから、5か月。私はいま能登から100km以上離れた金沢市にあるアパートにいます。1月の発災後数週間は避難所近くの親戚の家に居ましたが、しばらく水道が使える見込みが立たなかったので1月下旬には2次避難として金沢市内のホテルに移りました。4月からは現在のアパートに住んでいます。
私はフリーのライターをしていましたが、震災後には精神的に書けなくなり、取引先にはお詫びの連絡をしました。その後、インフルエンザや1か月以上続く腰痛に悩まされ、ほぼ寝たきりの生活を送っていて、ほんとうに笑うしかない。人は追い詰められると、感情をシャットアウトして笑うのですね。書けないので仕事はなくなりました。
地震後まずは、生活できる環境を確保することを優先しました。
私にはふたりの子どもがいます。中学生の娘はもともと耳に障害があり避難先近くの金沢のろう学校に通っています。平日は寄宿舎からの通学です。息子は私とアパートに住み、避難先で特別支援学校に通っています。もともと特別支援学校に通っていたので同じ種類の学校に通えて安心しています。妻は被災地の自治体職員なので、被害が比較的少なかった祖母の家に寝泊まりして、復興のために働いています。
被災した当初、上の子は家族と離れたがらず、学校に行かないと言い張りました。弟が通っていた被災地の学校は、自宅から距離が離れているので、通学するには道路事情が悪く、水も出ない劣悪な環境のため学校再開の目処はたっていません。大人の生活は何とかなるとしても、子どもの教育は守らなくてはいけない。私たちは、家族が別れ別れになったとしても、離れた地に暮らすことにしたのです。
目が覚めると、朝食のパンを焼き子どもの通学準備を慌ただしく行う。NHKの朝の連続テレビ小説がはじまる時間には、子どもを学校に送るために一緒に家を出ます。見知らぬ土地での生活にも慣れ、子ども中心の生活を送る毎日です。あれほど悩まされた余震もなく、水が何不自由なく使える。電気代や水道料金ってこんなにかかったのか、と平和だった日常を思い出したりしています。
しかし、遠く離れた地で子ども中心の生活を確立すると、被災地の自宅にはなかなか行けません。余震などの不安からは離れられても、自宅の修理やこれからの生活の問題などでいつも不安がつきまといます。平日は学校に通い土日も行事があることも多く、被災地の自宅にもなかなか行けません。
現地の情報はネットニュースやSNSで入手します。それだけでも、被災者支援の情報や現地での困りごと、飲食店の再開など様々雑多な情報が入ってきます。
自宅は修理すれば住める状態ですが、まずは散らかった家財の片付けをしなければなりません。2度の揺れで家具は倒れ、あちこちにものが散乱しています。遠くに住んでいてはなかなか手がつけられず、腰痛もあって長距離の運転もままなりません。
6月現在、道路はようやく自動車専用道路の「のと里山海道」を片側だけ通行できるようになりました。が、道は凸凹で、卵を買って帰ったらすべて割れていたという嘘のような笑い話も。地震前は1時間半くらいで行けたのが、震災後は倍くらいかかります。金沢から輪島へは全線で走行できますが、帰りの輪島から金沢へは一部一般道も使わないと避難先までたどり着けません。自動車専用道路の対面通行は今年の7月以降に実現するそうですが、相変わらず速度は出せそうにないので不便な生活が続きそうです。また、市内のガレキは全然片付いておらず、いまにも倒れそうな家屋が道をふさぐこともあります。
能登の外から見ると、発災から5か月も経てば復興が進んだだろうと思うかもしれません。テレビやネットで取り上げられるニュースもめっきり少なくなりました。発災当初、被災地への道路が一本しかなく大渋滞が起こったため、緊急車両以外は被災地には来ないでほしいと自治体が呼びかけました。そのためか、その後も被災地を訪れる人は少なく、十分な情報も発信されていません。現在は、地域で医療が再開しており、緊急患者を100km以上の医療機関へ運ぶ必要がないため、自粛は不要です。ボランティアに来てくださる方も増えてきているのですが、そのような状況はあまり伝わっていないようです。
震災直後のニュースでは、Yahoo! JAPANならトップページにトピックスが並び、NHK総合の放送では必ずトップニュースで報じられていました。2か月ほど過ぎたあたりから、震災の話題はトップニュースの座から転落し、報じられない日もあります。それでも、NHKのテレビニュースは、少なくても1日1回は被災地のニュースを扱うようにしてくれているようで、何かに絡めてでも言及してくれています。NHKの全国ニュースはWebの公式サイトで記事化されます。サイトでは全国の主要なトピックスに続いて、個別のまとまった話題を紹介するコーナーがあります。スマホで見ると縦長のサイトなので、重要度の高い話題が上から順番に並びます。1月や2月は、全国ニュース枠のすぐ下に能登半島地震関連のバナーがありましたが、いつのまにか10個くらい下にランクダウン。全国での注目度が下がると、能登は忘れられたのではないか、もう復興したと勘違いされるのではないかと、とても不安になります。
現地ではいまだ避難所に暮らす人がおり、避難所を出ても上下水道が使えない危険な倒壊家屋に住んでいる人もいます。仮設住宅が少しずつ提供されていますが、運良く入居できても、食費や水道光熱費は自己負担。避難所にいる頃とは環境が激変します。
息子は新しい学校に馴染んでおり、最近、輪島市で通っていた学校より避難先の学校の方が良いと口にするようになりました。尋ねたわけではないのですが、いつか帰らないといけないのは気付いているようです。避難先のアパートの入居期限は6か月となっているようですが、自宅の水道を直すのは設備業者の順番待ち。漏水箇所を特定して修理するのにどのくらい時間がかかるか、地下の水道管を掘り返してみないと分かりません。
住宅の被害には、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」と6つの区分がありますが、行政から手厚く支援が受けられるのは半壊以上です。準半壊の我が家は住めるだけマシと思われるかもしれませんが、片付けたり手直ししたりしなければなりません。柱の割れやクロスのひびがあっても住めますが、きちんと直せば相当なお金がかかります。
避難生活は、現地に比べれば一見平和そうですが、時間はあっという間に過ぎていきます。私は腰を痛めて1か月以上を棒に振ったので尚更焦っているのかもしれません。能登半島地震は風化してほしくないと願い、自分とつながりのある人にだけでもとSNSで毎日情報を発信しています。私の知りたい情報が被災地で求められている生の情報だと信じて、続けています。私は輪島市に自宅があるので、他の被災地のことは詳しく分かりません。被災地には、さらに被害の甚大な地域から、生業を再開できるまで復旧した地域まで幅があります。それでも、元のように経済が戻っているわけではありません。
被災者のひとりが感じたことを徒然に伝えていければと思います。よろしければ、どうぞお付き合いください。
文/二角 貴博