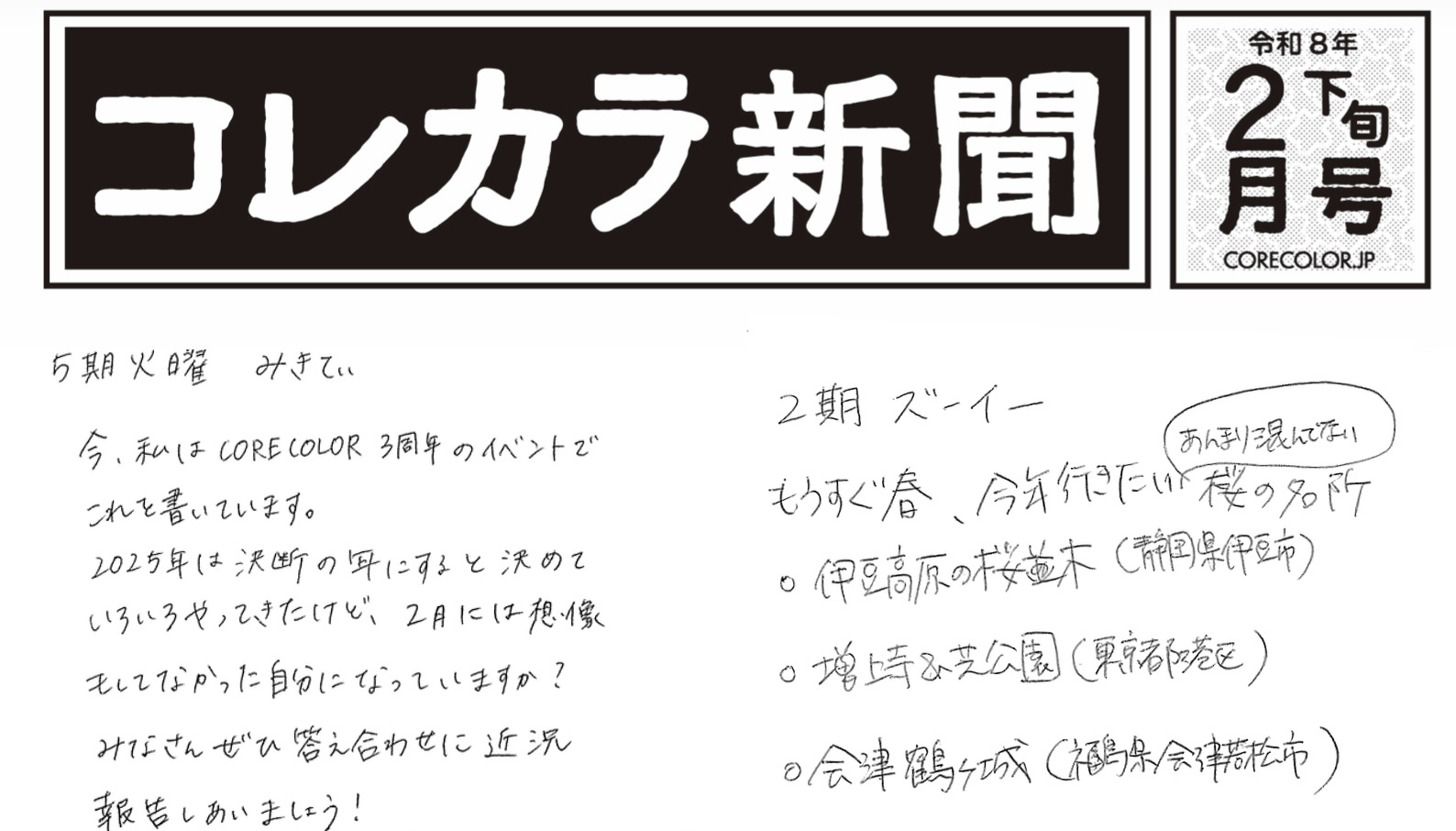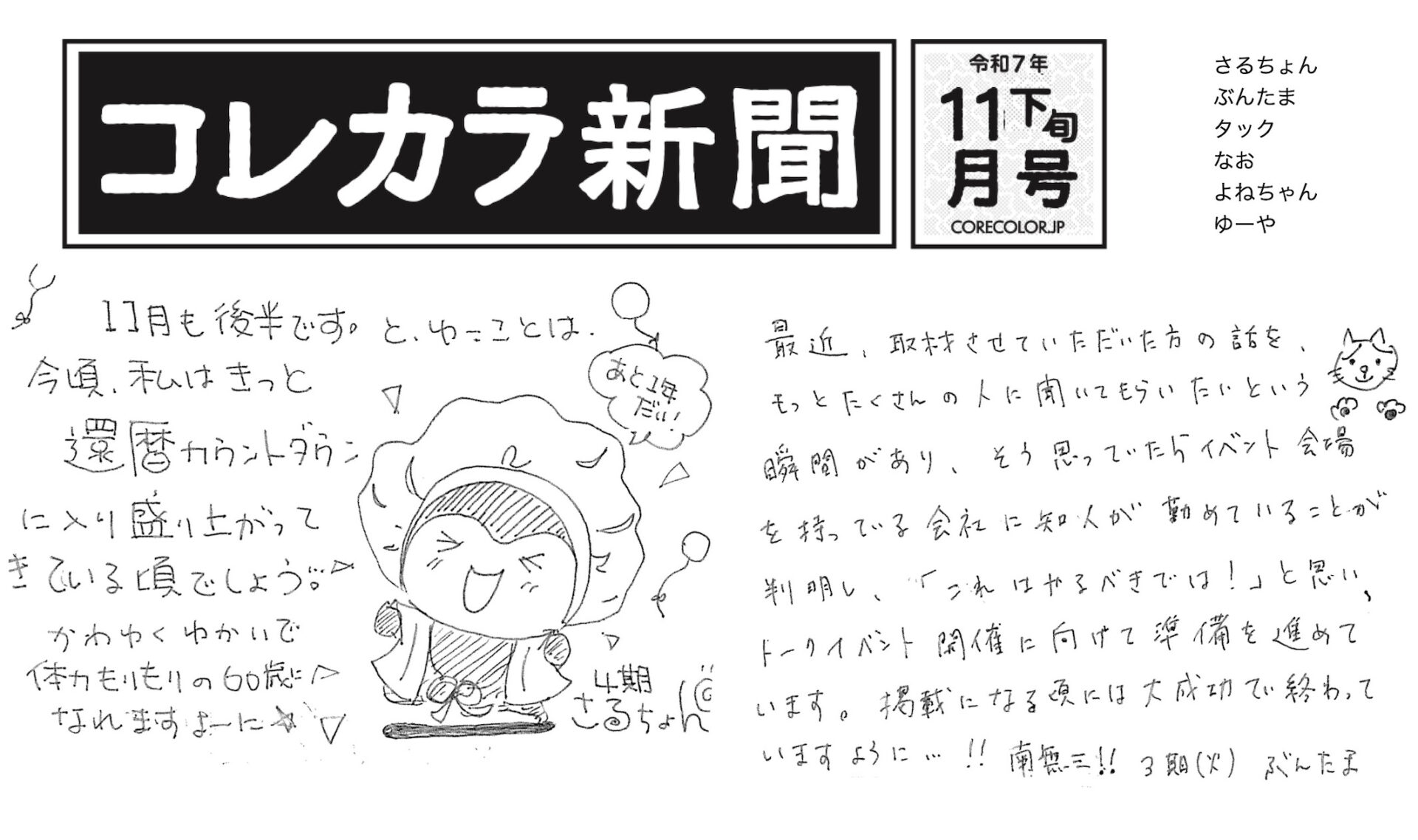被災体験をひとくくりにしない。一人一人の物語と向き合う輪島のドクター【能登のいま/第6回】
CORECOLORメンバーが能登を訪問し、そこで感じたことを書くリレー連載「能登のいま」。今回は、普段ドクターや病院への取材をしている、私、ライターの安藤梢が、輪島市にある「ごちゃまるクリニック」を訪問し、院長の小浦友行先生にお話を伺いました。
私が小浦先生に会いに行きたいと思ったのは、先生がもともと地元への強い愛情を持ち、地域に根差した医療を実践されているという報道記事を見たからです。ご自身も被災したにもかかわらず、1月1日の発災直後から、刻々と変わる現地の状況をSNSでも発信されていました。震災から半年以上が経ち、今、先生の目に街の風景や人々の姿はどう映っているのか。現地からのルポをお届けします。(執筆/安藤 梢)
震災から半年を経た、“非日常の中の日常”
7月20日。輪島市河井町の住宅地にある「ごちゃまるクリニック」を訪問した。院長の小浦友行先生は輪島市の出身で、地元に帰って恩返しをしたいという思いから2022年にクリニックを開業。「ごちゃまる」の名前は、「ごちゃまぜ」と「まるごと」を合わせたオリジナルの言葉だ。医師と看護師、助産師、保健師、作業療法士とさまざまな専門分野のスタッフが「ごちゃまぜ」になり、病気を診るだけでなく患者さんの家族や地域も含めて「まるごと」応援したいという思いが込められている。小浦先生は、小児科医である妻の詩先生とともに、子どもから高齢者まで外来診療を行い、自宅で暮らす高齢者のもとへ往診もしている。
能登半島地震が起きたのは、開業からわずか1年後のこと。クリニックにも被害があり、ようやく診療を再開できたのは5月に入ってからだった。

震災から半年が経ち、今の輪島市の状況はどうなっているのだろうか。
「発災直後は“非日常”だったのが、今はいやおうなしに“日常”が始まっている。“非日常の中の日常”を過ごしています」
毎日、朝起きて、ご飯を食べて、掃除、洗濯をして、仕事に行き、お風呂に入って、眠る――。震災前と同じことをしているようで、これまでとは全く違う日常の中を生きている。何気なく手にしていたものや、出会う人、見ている街並みは「今までとは全然違う」と小浦先生は話す。
非日常の中の日常。この言葉を聞いたとき、私の頭にはつい数時間ほど前に立ち寄った本町通り、通称「朝市通り」の光景が浮かんだ。朝市通りは、震災直後に発生した火災によって、街がまるごと焼けてしまった場所だ。もともとは露店が建ち並んでいたところに、今は焼け残った建物の骨組みと、土台のコンクリートがあるだけだ。その中で、大きな音を立てながら重機が動き、地面を均している。
倒壊した建物が道路にまでせり出し、歩道はあちこち陥没している。瓦屋根に押しつぶされた建物のすぐそばで、商いを再開している飲食店もあった。

小浦先生が両親と祖母、それに妻と子どもたちと一緒に住んでいる自宅は、朝市通りにある。家のすぐそばまで火の手が迫ったが、ほんの数軒のところで焼け残ったのだという。
「震災が起きてから3月頃まで、街はシーーンとしていたんです。街で人に会っても、みんなほとんど話せなかった」
止まっていた空気がようやく動き出したのは、春が来て、暖かくなってきてから。小浦先生はその変化を感じながら、今もこの街で暮らし、診療を続けている。
医療を超えて、今、できることをこの場所で
今、ごちゃまるクリニックがある輪島市には、倒壊を免れた家に住んでいる人もいれば、半倒壊の自宅や仮設住宅で暮らす人もいる。小浦先生はクリニックでの診療だけでなく、そうした場所へも患者さんを診るために出かけて行く。
子どもから高齢者まで、患者さんにとってのよろず相談所。それがクリニックのコンセプトでもある。小浦先生は、総合診療医として「これはうちでは診られない」とは言いたくないという。どんな訴えでもいったんは受け止めて、できることはクリニックで対応し、もしできないときには専門機関へと適切につなぐ。
震災を経て、ますます「よろず」の役割は増えている。避難所となっている公民館で住民たちの話を聞く、出張保健室もその一つだ。クリニックのスタッフがお茶とお菓子をふるまい、のんびりと話をしながら相談に乗る。
「かしこまった場所で、何か心配なことはありますかと聞いても、なかなか話は出てきません。でも、一緒にお茶を飲んでいるうちに、『実は、最近膝が痛くて…』『お腹の調子が悪くて…』とぽろっと悩みを打ち明けてくれることがあるんです」
小浦先生が公民館を訪れるようになったのは、1人の男性患者さんがきっかけだった。朝市通りに住んでいた80代のAさん。自宅が火事で焼けてしまい、地域のコミュニティから離れて、知り合いが誰もいない仮設住宅で一人暮らしをしていた。「外来でお会いしたときに、なんだか寂しそうだったんですよね」と振り返る。時々、会いに行って、Aさんを元気づけられたら。そんな思いで何度か公民館に通ううちに、館長から「健康講話をしてもらえませんか」と声をかけられた。

取材に行った日の午後、ちょうど河原田公民館で小浦先生の健康講話があった。この日は、敷地内の仮設住宅に暮らす人たちが30人ほど集まった。「今日はどんな話をしましょうか」。冒頭で集まった人たちに問いかけると、「ストレスと上手に付き合うにはどうしたらいいですか」と質問が挙がった。
具体的なストレス解消法を紹介しながら、日々を楽しむちょっとしたコツを伝える。時々、冗談を交えながらの健康トークに、会場は和やかな雰囲気になった。
輪島で診療をしていて、震災のことに全く触れずにいることはできない。だからこそ、つらいことばかりではなく、震災を通して改めて気付いた日常の喜びや人の温かさにも目を向けていきたい。そう小浦先生は考えている。
「だから、ちょっとでも笑ってもらえたら嬉しいんです」
これはもう医療だけの話ではないかもしれない。人として、目の前の人とどう向き合うか。少しでも心が軽くなってほしい、癒されてほしいという思い。その思いは、きっと集まった人々にも伝わっているのではないだろうか。
復興までの道のりには一人一人の物語がある
震災直後から新聞やテレビなど、メディアの取材をたびたび受けてきた小浦先生。発災直後、1カ月、3カ月後、半年後と、「節目」のたびに話を聞かれることについて、少しずつ違和感を覚えるようになったという。その理由は「被災地の今はこうです」と大きくまとめて語ることを求められているように感じたからだ。
「ここにはたくさんの人がいて、被災の状況も、震災の受け止め方も一人一人違う。それを十把一絡げにして語ることはできません」
そう言われて、私自身「能登は」「被災地は」と、大きなくくりでとらえようとしていたことに気が付いた。乱暴なまとめ方で、「被災地の今」を分かった気になろうとしていなかっただろうか。
震災後はトラウマによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)の話ばかりが語られるが、「実はそのトラウマを乗り越えて、強くしなやかに成長する人もいるんです」と小浦先生は教えてくれた。5月にクリニックでの診療を再開したとき、震災前と比べてたくましくなった患者さんがいて驚いたという。災害心理学では、傷付いた体験をきっかけに心が成長することを「ポスト・トラウマティック・グロース」と呼ぶそうだ。
1月から時が止まり、亡くなった人たちに対する思いを抱えきれずにいる人もいれば、「何となくつらい」と不調を感じ始める人や、周囲の人たちと同調できずに怒りが湧いている人、地域興しに団結する人、新たな生活へと前向きに動き出そうとしている人たちもいる。

震災直後のような、とにかく命を助けるという段階が過ぎ、今はそれぞれの心のケアをしながら、一人一人が抱える思いや、背景をくみ取っていかなければならない段階になっている、と小浦先生は話す。
「復興は目指すものではなく、振り返ったら『できていた』と思うものではないでしょうか。それまでの道のりには、決してひとくくりにはできない、一人一人の物語があると思います」
小浦先生が診療を通してやっていることは、その一人一人の物語と向き合っていくことだ。それは、この地で被災した小浦先生自身が、自分の物語と向き合っていくことでもあるのだろう。自らも同じ地域に住む一員として、被災した人たちの生の声を聞き、受け止めようとしている。私が輪島で見たのは、そんなドクターの姿だった。
文/安藤 梢
【この記事もおすすめ】