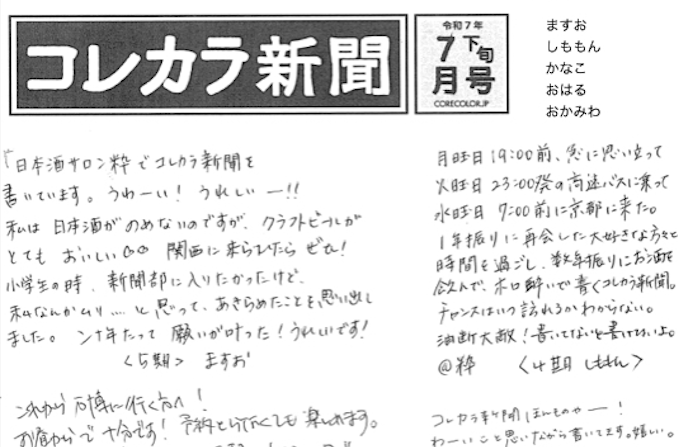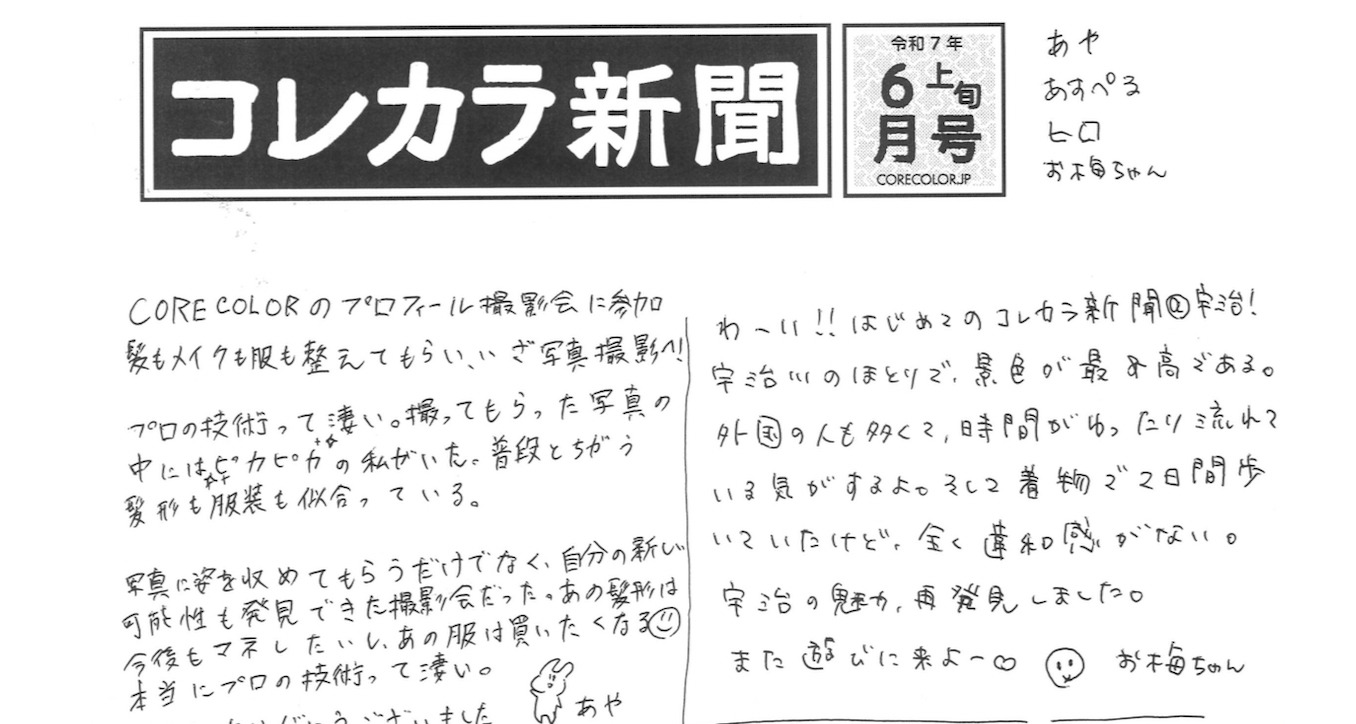被災した故郷で暮らす人々の日常。輪島のまちで起こっていたこと【能登のいま/第19回】
今年7月、『能登のいま』執筆者の二角さんに案内していただき、輪島のまちを車で巡りました。発災から半年以上が経過したにもかかわらず、火災で焼け野原になってしまった朝市など、その被害はいまも目に見えるかたちで残されています。
私は東京に暮らしていますが、能登半島地震のときには家族で新潟の旅館に宿泊していました。古民家をリノベーションした建物は、このまま潰れてしまうのではないかと思うほど揺れ、正月からとんでもないことが起こってしまったと、余震に怯えながら過ごしたことをよく覚えています。
二角さんの記事を読み、より大きな揺れを経験した仲間の助けになれることが何か一つでもあればと思い、今回初めて輪島の地を訪れました。当日は、地元放送局で報道カメラマンとして活動し、現地でボランティア団体の運営も手掛ける小田原寛さんにお話を伺うことができました。被災した故郷で現地の方々は、どのような時間を過ごしているのか。復興に邁進する小田原さんの言葉から見えた、その実態をお伝えしたいと思います(執筆/Yuni)。
(この原稿は、7月時点で伺ったお話をもとに執筆しています。9月末に発生した奥能登豪雨の影響で、取材先の皆さまの無事は確認できたものの、まちには水害まで加わり、現地の状況は更に変化してしまったとのことでした。能登半島地震が輪島の人々の生活にどのような影響を及ぼしたのか。その被災状況をお伝えするとともに、皆さまの暮らしが、一日も早く不安のない状態に戻ることを心から願っております。)
能登のまち並みと道路状況
のと里山空港に到着すると、輪島方面へは能越自動車道が通っている。この道は、能登半島北部地域へのアクセスを向上させるルートとして、観光振興の大きな期待を背負って昨年9月に開通されたばかりだった。そしてたった数ヶ月後―。
地元の方々がやっとできたと喜んでいた矢先に、それは観光地ごとさま変わりしてしまった。
現在では道路は復旧しており、確かに車は走れる状態だった。しかし、私はその道中で車酔いをした。油断していたら一度、天井に頭をガツンとぶつけてしまうこともあった。道には体を揺らし続ける凸凹が、人が跳ね上がるほど大きなものも含めて数多く存在していたのだ。
窓から外の景色を眺めると、全壊していたり、形を留めていても不自然に傾いていたりする家屋が、そのまま残されていた。電柱・標識はなんとか立っていても、そのすべてが少しずつ、歪んでいる。復旧したとはいえ、運転してみれば、ここが本来の自動車道に戻れていないことは明らかだった。
今回取材させていただいた、地元放送局で報道カメラマンとして働く小田原さんも、日常的に車を運転するため「道」に関する悩みは尽きないそうだ。最近は、運転中に石を踏んだタイヤが裂けてしまい、次々とパンクしてしまう事象が発生しているとのことだった。
道中に大きな段差があればブレーキを踏まなければならず、凸凹続きでどこに溝があるか分からない状態では、終始、神経を使い続けてしまう。「もう、道の悪さに疲れてしまったよ」と語る方を前に、道路が復旧して良かったですね、とはとても言えなかった。
家族の心理的安全を確保する
被災地での生活において、高齢者とその家族は様々な問題に直面している。
小田原さんの場合は、お父様の認知症の症状が、震災による環境の激変によって一気に進行してしまったそうだ。発災後に近くの小学校で避難生活を送っていると、次第に徘徊行為も見られるようになった。輪島のまちは瓦礫や凹凸だらけで、一人で出歩けばどんな怪我をしてくるか分からない状態。安全な場所で暮らしてほしい一心で、小田原さんは施設探しに奔走されたという。
介護施設も震災の影響で態勢が整っていないところが多く、かなり難航したそうだが、ご友人のフォローもあって、無事に預け入れ先が決まった。新しい暮らしの中で、今では少しずつお父様の表情も和らぎ、やっと安心できる環境に落ち着けた、とのことだった。
輪島から他の地域に避難した高齢者の中には、輪島に戻ることを希望する方も多くいらっしゃる。しかし今は、仮設住宅で暮らす選択をする方が多く、「高齢者が安心して過ごせる生活拠点づくり」が、地元の方々の要望だという。
家を建て直すのは難しいおじいちゃん・おばあちゃんたちが、それでも故郷で最後を迎えたいと望んでいる。家族は叶えてあげたいと思う反面、震災の影響が残る場所に高齢の父・母が居続けることには大きな不安がつきまとう。輪島での安全な暮らしは、きっと子ども・孫世代の強い願いとしても必要とされているのだ。
自宅の解体を見守る
傾いた大木や、壊れかけた家屋などは、そのまま放置しておくと近隣の建物に倒れかかるリスクが高くなってしまう。木を安全な方向に倒す作業や、家屋の解体作業が、復旧の一環として急がれている。
小田原さんの知人の方も最近、公費解体(行政による解体作業)で自宅の取り壊しが始まったそうだ。しかし、早期の解体を希望していたものの、いざ壊されるとなると、どうにも心にぽっかり穴が開くような、やるせなさに襲われてしまう。これでやっとお隣さんに迷惑をかけなくて済む、と安心しながらも、体に全然力が入らなくなってしまったと話していたそうだ。
震災以降ずっと家に立ち入ることができず、やっと帰ってこられたときには解体。知人の方は、取り壊しの現場からひとときも離れられず、崩れていく我が家をずっと見守っていた。そんなとき、作業場から一つの絵が拾い上げられた。それは、知人の方が生まれたときにご両親が買ってくれた記念の絵で、汚れてはいたものの形はきちんと残っていた。奇跡が起こった、これなら元に戻せると、感激されたそうだ。
公費解体は前提として、低コスト・最速スケジュールを優先して進んでいく。そのため、思い出の品を一つ一つ取り出すような対応を望んでも、基本的には叶えられないとのことだった。
取り壊しは復旧の第一歩ではあるが、そこで暮らしていた家族にとっては、はかり知れない心理的負荷を伴う。どんなに傾いていようが、やっと我が家も解体できたと手放しに喜ぶことなんて、できるはずがないのだ。
「会いにきて」が伝えること
今回小田原さんからお聞きしたことは、決して発災当初のことばかりではない。凸凹のある道路も公費解体も、半年以上が経った時点での話だ。
輪島のまちを巡ってみると、震災の記憶を思い起こさせる光景はそこかしこに残されていた。輪島は特に土砂崩れによる被害が甚大で、整地が追いついていない場所では、「あの土砂が溜まっているところに、まだ見つかっていない方が1人いるんです」という説明も受けた。
“生活ができるようになること”と、“元通りに生活すること”はまるでちがう。小田原さんのお話を反芻しながら、まちの復旧だけでは決して、失ったものは取り返せないことを思い知った。一瞬にして暮らしは激変したのに、目が覚めたらすべてが元通り、とはならない。復旧が進む被災地で、現地の方々は少しずつしか変化を遂げられない日常に、多様なストレスを抱えながら向き合い続けている。
今回の訪問は、二角さんの連載『能登のいま』の中にあった、「ボランティアでなくても良いので、被災地で暮らしている人たちに会いに来てください」というメッセージをきっかけに参加を決めた。実際に現地へ行ってみると、「遠方の方が足を運んで来てくれるのは嬉しい」と、行く先々で歓迎していただいた。
これはあくまで、現地の方のやりとりを見たうえでの私の印象になってしまうが、被災者同士では、被害の程度・作業進行の個人差も大きいので、復旧に関する話をするには気を遣う場面も多いのではないかと想像した。お会いした方々の話し方には、とにかく能登の現状を知ってほしい・聞いてほしいという想いを強く感じた。
離れた場所に暮らす第三者と話すことが、小さいながらも一つの救いになっていたらと思う。
文/中谷 柚香
【この記事もおすすめ】