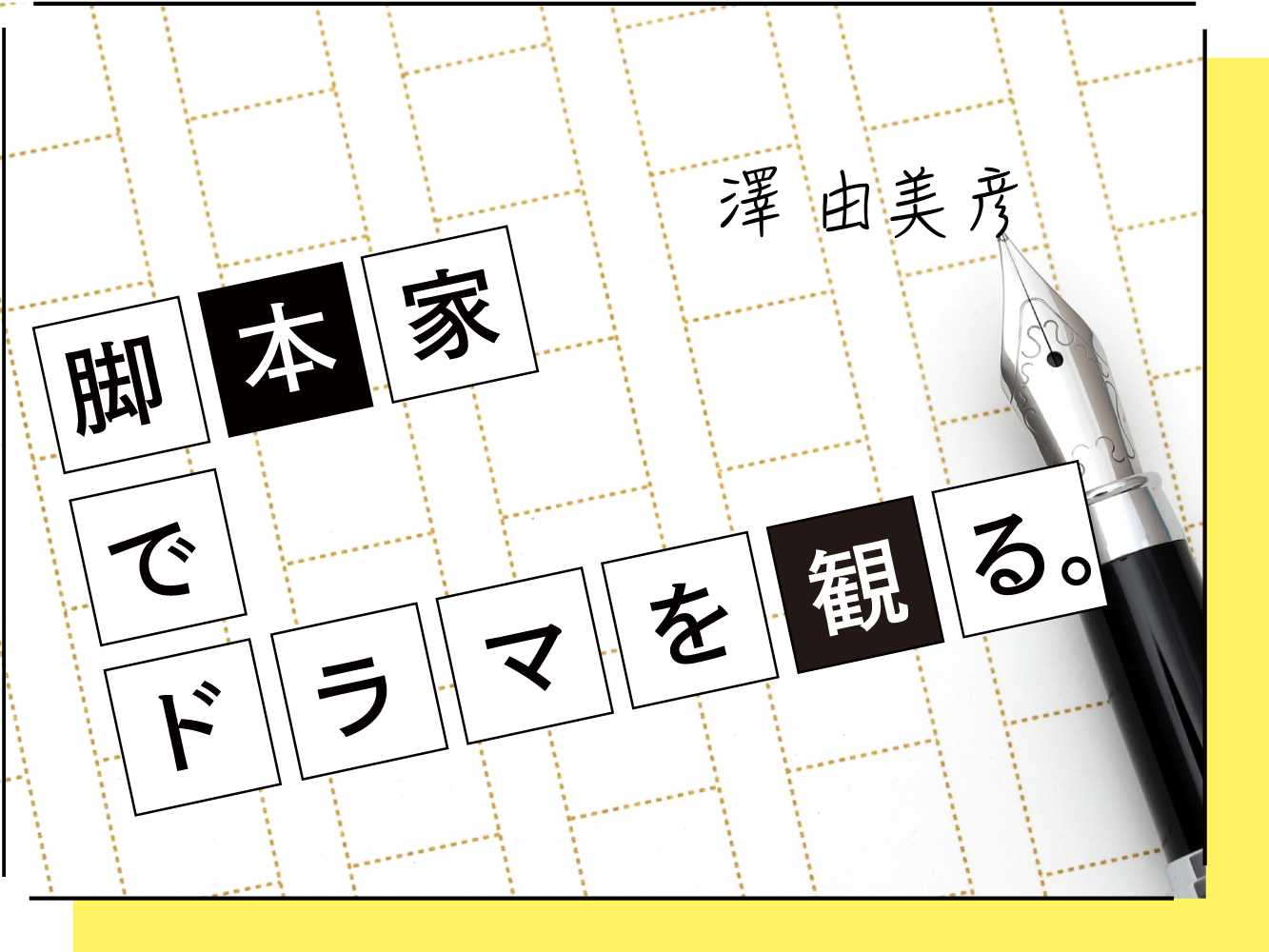私の“ホラー観”は鬼の手によって培われた『地獄先生ぬ〜べ〜』【連載・あちらのお客さまからマンガです/第27回】
「行きつけの飲み屋でマンガを熱読し、声をかけてきた人にはもれなく激アツでマンガを勧めてしまう」という、ちゃんめい。そんなちゃんめいが、今一番読んでほしい! と激推しするマンガをお届け。今回は、今月再アニメ化され、令和の時代に再び蘇ったホラーバトル漫画の金字塔『地獄先生ぬ〜べ〜』について語ります。
私の大好きな季節がやってきた、夏! とはいえ、夏そのものが特別好きというわけではない。日焼けはするし、酷暑のせいでずっと体調が優れないし、正直なところ1年でいちばん絶好調とは言い難いシーズンだ。それでもやっぱり、夏が好きと言いたくなる理由がある。それは、この時期になるとまるで風物詩のように次々登場するホラーイベントやコンテンツの数々が、たまらなく楽しいからだ。
例えば今年なら、連続ドラマ系ではTXQ FICTION第3弾『魔法少女山田』や、沖縄ホラープロジェクト『疫(えやみ)』。映画では8月公開の『近畿地方のある場所について』が注目作。体験型ホラー展示も充実していて「恐怖心展」や「1999展 ―存在しないあの日の記憶―」など……。すべては書ききれないけれど、まさにホラー豊作の夏! 今年もありがとう! 夏!
そんなわけで私はホラーが大好きなのだが、実はこの連載でも過去に、伊藤潤二先生の『死びとの恋わずらい』や、田島列島先生の『みちかとまり』を紹介してきた。いずれも、私をホラーやオカルトの世界へと誘ってくれた大切な作品たちだ。……でも、最近ふと思ったのだ。そうした入り口以前にもっと根っこの部分。言うなれば私の“ホラー観”の土台を作ってくれた作品があるのではないか、と。それが今回語りたい『地獄先生ぬ〜べ〜』である。
子どもの頃、夢中になったオカルトヒーローたち
『ぬ〜べ〜』こと『地獄先生ぬ〜べ〜』をご存じない方は少ないと思うが、念のため紹介しておこう。本作は1993年〜1999年に「週刊少年ジャンプ」で連載されていた、オカルト・ホラー系のバトルアクション作品だ。主人公は、霊能力を持つ小学校教師・鵺野鳴介(ぬえの・めいすけ)。通称ぬ〜べ〜。普段は優しくてちょっとドジな先生だが、左手には鬼を封印した「鬼の手」を宿し、悪霊や妖怪から生徒たちを守るために戦う。
1996年にはアニメ化もされ、その当時私は幼稚園児だった。運動会で主題歌「バリバリ最強No.1」が流れていたのを覚えているし「鬼の手パワー!」なんて叫んでいた男児がクラスにいたことも、なんとなく記憶に残っている。実はその頃、「ポンキッキーズ」という子ども向け番組の中で『学校のコワイうわさ 花子さんがきた!!』というホラーアニメも放送されていた。今では考えられないが、あの時代は子ども向けのホラーが妙に充実していた気がする。
そしてこの『ぬ〜べ〜』と『花子さんがきた!!』に共通していたのは、どちらも幽霊などの“怖い”存在が出てくる一方で、最終的にはぬ〜べ〜や花子さんがそれらを退治してくれるという構造であった。
“怖い”という感情は、幼いころだと両親や姉に叱られたとき以外、そう簡単に味わえるものではない。いや、あれとはまた別種の心臓が嫌にドクンドクンするあの感覚が、これらの作品に触れている時には常にあった。でも、物語のなかでは、必ず“強い誰か”が登場して助けてくれる。その安心感ごとセットになっていたからこそ、私は夢中になっていたのだと思う。あれは、幼少期の私にとっては唯一無二の体験だった。
ちなみに余談だが、「ぬ〜べ〜のトラウマ回は?」という話題で盛り上がれるのは、同世代の証かもしれない。例えば「金田一少年の“はじめちゃん”といえば誰?」という問いに近い、サブカル的な世代確認クエスチョンだ。ちなみに私にとってのトラウマ回は「妖怪・枕返し」のエピソード。ぬ〜べ〜の教え子・郷子が、ある夜妖怪・枕返しに枕をひっくり返されてしまったことで、ここではないパラレルワールドに迷い込んでしまうのだ。目が覚めると、彼女は小5から一転してOLになっていて、大人になった世界にはぬ〜べ〜がいない……。それまで側にいた絶対的な存在が突然消えてしまうという、不在の恐怖が妙にリアルで今でもふと思い出してはゾッとする。
ただ“祓う”だけじゃない、大人になって気づいたぬ〜べ〜のすごさ
実はこの『ぬ〜べ〜』だが、2025年7月から再びテレビアニメ化されている。ぬ〜べ〜がスマホを使っていたり、授業ではタブレットを活用していたりと、ところどころ令和ナイズが施されているが、何より嬉しいのは、ぬ〜べ〜役の声優・置鮎龍太郎さんが続投していること。その声を耳にした瞬間、当時の記憶が一気に蘇ってくる。
そんな『ぬ〜べ〜』再アニメ化をきっかけに、原作マンガ全20巻を大人になった今改めて一気読みしてみたのだが、やはりこの作品はすごい! 学校の七不思議に始まり、妖怪、都市伝説、UMAまで網羅していて、まるで一つのオカルト事典だ。さらに、怪談、民間信仰、呪術、心霊写真といった題材も扱われており、まさに“子ども向けオカルトの基礎教科書”と呼ぶにふさわしい、知識と想像力の宝庫である。
だが、そんな『ぬ〜べ〜』の魅力は「怖さ」だけではない。特筆すべきは、怪異たちのビジュアルとその解釈のセンスが、天才的なまでに独創的なことだ。例えば、雪女・ゆきめ。本来なら、白装束に長髪の儚げな存在として描かれがちな雪女が、本作では水色のショートカットにミニ丈の着物という斬新な姿で登場する。可愛くて快活で、初見のインパクトはいまだに鮮明に覚えている。霊媒師・いずなも然り。通常なら竹筒に入れるはずの“管狐”を、まさかのリップケースに収納しているというセンス! プリティで軽やかに霊力を操るその姿に、思わず心を掴まれた読者も少なくないはずだ。
そんななかでも特に心に残るのは、ぬ〜べ〜が単に“怪異を倒す”存在ではないということだ。心霊写真や口裂け女のエピソードでは、人々が恐怖し、排除しようとする存在の内側にある理由や想いにぬ〜べ〜自身が耳を傾け、生徒たちに共生の道を問いかけていく。そんな、ただ怖いだけではなく、ふと胸が温かくなるというか、怪異の存在を尊重するような話も多い。そしてこれこそが、私の“ホラー観”の土台と密接にリンクしているように思うのだ。
敬意と畏れを胸に、恐怖と向き合うということ
実はこんなにホラー好きを公言しながらも、私はいわゆる心霊スポットという場所には行ったことがない。学生時代に「肝試しに廃トンネル行かない?」と誘われても、いつも丁重に断ってきたし、不思議と同じように断るタイプのホラー好きの友人と、自然と仲良くなっていた気がする。
「ビビってるだけだろ」と言われれば、それはまぁ否定はしない。けれど私は、“ホラー好き”にも2種類いると思っている。それは“畏れ”を持つ者と、持たない者だ。後者は例えば廃トンネルを「おもしろそうだから行ってみようぜ!」というノリで訪れる人たちであり、私は心の底から「マジでやめとけ」と思う。正直に言えば、そういったタイプの人はかなり苦手で、自分は完全に前者のタイプだと思う。
物語として作られたホラーコンテンツは大好きだし、架空の恐怖にワクワクしながらページをめくることも多い。けれど、実在の心霊スポットや曰くつきの場所のように、「この世のものではない何かが存在するとされている場所」には、むやみに足を踏み入れたり、土足で踏み荒らすようなことは絶対にしたくない。そこには、触れてはならない何かが、確かに“ある”気がするからだ。
ちょっと気取った言い方になるけれど、私は好きだからこそ、怪異に対して一種の敬意を持っている。近づいてはならないもの。触れてはいけないもの。そうした感覚を、『ぬ〜べ〜』は子どもの頃の私に教えてくれていたのだと思う。
怖いものを、ただ乱暴に消費するのではなく、畏れながら向き合うこと。そして、その背後にある想いや理由に、静かに想像力を巡らせてみること。あの頃、ジャンプの最前線で、そんなホラーとの向き合い方を提示してくれた『ぬ〜べ〜』は、やっぱりすごい。
令和になった今も、彼の授業は続いている。これからもきっと、ホラーに興味を抱く子どもたちがいる限り、恐怖の裏にある敬意や畏れの感覚を、静かに教え続けてくれるだろう。
文/ちゃんめい
【この記事もおすすめ】