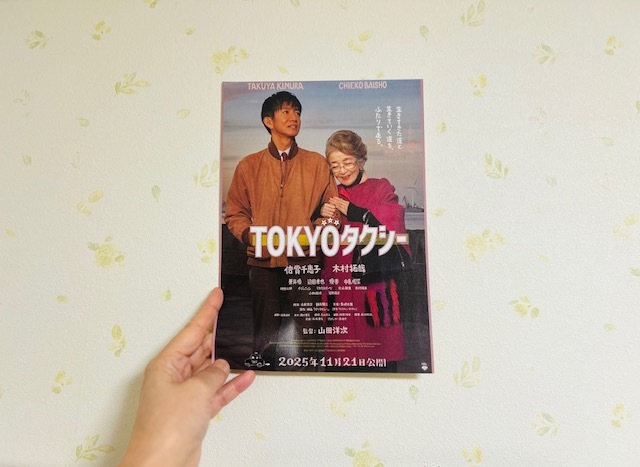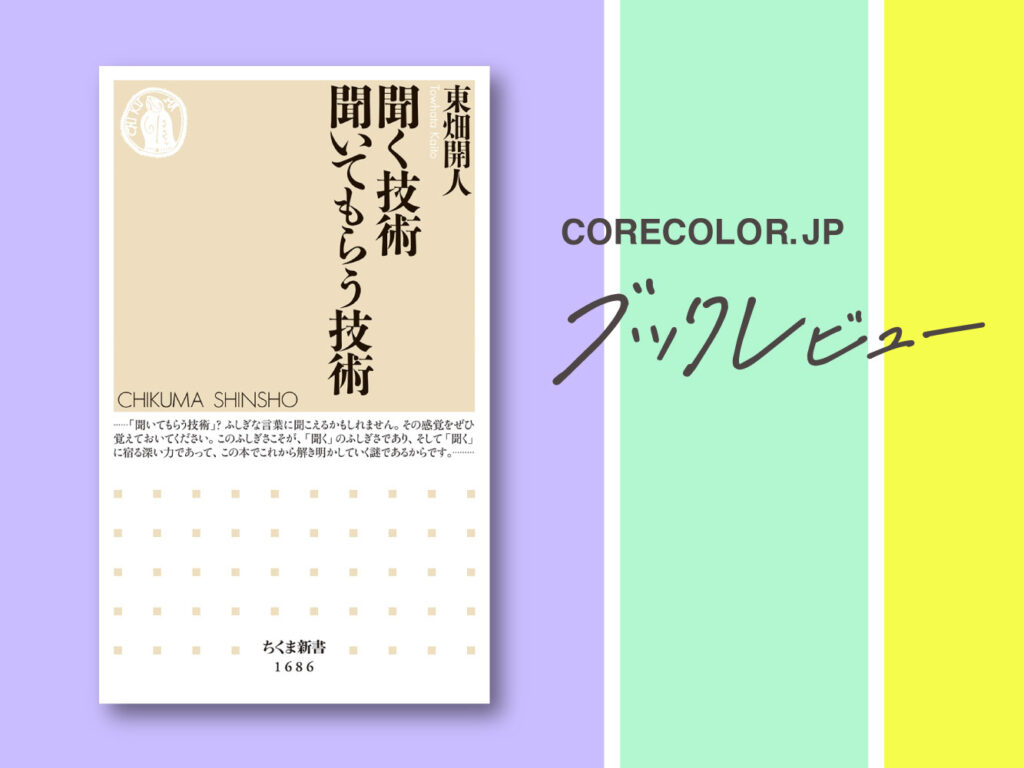
「何かあった?」「ちょっと聞いて」の循環で孤立から救われた。『聞く技術 聞いてもらう技術』
「来週はいつが空いている? 素子に合わせるからとにかく会おう」と友達からLINEが届いた。私はスマホを見ながらちょっとだけ考えたあと、「火曜日」と打って送った。「わかった、火曜日ね。ランチしよう。会わないとダメだ」と一言。そのメッセージにはスタンプも絵文字も、笑いもないとてもシンプルなものだった。そこには気迫すら感じられて、ちょっぴり私は怖かった。
この友達がなぜ会おうと言ってきたのかはわかっていた。私は先日、一時的に血圧が下がり意識を失い倒れた。そのことをSNSにアップした投稿を読んで、すぐにこのLINEが届いた。救急搬送はされたが、おかげさまで頭も内臓も異常なし。たぶんストレスだろうというのが医師の見解。そして友達からのメッセージを受け取った時点ではすでにピンピンしていた。だからわざわざ時間を作ってもらうのは申し訳なかった。彼女の貴重な時間を私のために使えない……と言う思いもあり返信をためらったが、違う私が出てきて、勝手に「火曜日」と文字を打って送信していた。
約束は13時。そして別れたのは20時。その間、とにかく話した、話した、話した。ランチを食べたあとは場所をかえ、お茶をしてまた話した。いつもは友達と会っても2,3時間だから、「元気?」と聞かれて、あとはよもやま話で終わる。でも今日の彼女は違う。私の話を聞く気満々の態勢で来ている。最初はなんとなくお茶を濁して当たり障りのない話をしていたがそれでは彼女が許さない。「今日はあなたの話を聞くから」の圧がバンバンかかってくるのだ。すると不思議なもので、私のバリアはアッというまに崩壊。私の口から、いつもはあまり出ない本音が次から次へと飛び出した。「ダメだ、ダメだ」と抵抗しても無駄。封印していた心の闇のフタが“パカっ”と勢いよく開いて、硬い、堅い、固い黒いマグマが私の中から勢いよく噴き出す。「もういいや」と思うと同時に、「でもこんな話を聞かせてしまってゴメン」と心の中で友達に謝りながらも、私の口は機関銃となり、黒いドロドロしたものを吐き出していた。
彼女と別れたあと、私は彼女が心配だった。なんせ私が抱えている問題や、心の闇は重くて暗くてドロドロしている代物だ。このマグマが彼女に伝染していたらどうしようと心配でたまらなかったが、その後の彼女のSNSには、元気にテニスを楽しんでいる様子や、家族で焼鳥屋に行きおいしそうにご飯を食べている写真がアップされていた。
よかったと思うと同時に、なぜ? なぜなんだ? と疑問がわいた。今まで、このマグマは人に伝染すると思い込み、うつった人は私と同じようにウツウツとなってしまうと信じていたのに、なぜ彼女は平気なのか?
そんなことを思いながら暮らしていたら出合ったのが『聞く技術 聞いてもらう技術』(著者・東畑開人)。この本のなかで東畑先生は、私にこっそりその謎の答えを教えてくれた。
どうやら聞く技術と聞いてもらう技術は、双方向の関係で成り立っている。自分の話を聞いてくれる人がいる人は、他の人の話を聞く姿勢が整っている。彼女が家族や友達に支えられた日常を送っているのは、SNSを見てもわかる。だからどんなに私がドロドロした物体を投げつけても感染しない。それどころかはねのけるパワーがあるのだ。ああ、先生が言うところの他の人の話を聞く体勢が整っている健全な人とは、彼女のような人のことを言うのだと納得した。
彼女は周囲に話を聞いてくれる人がいっぱいいて、すごい防衛力の持ち主だってことは理解した。でも話を聞いてもらう私側の問題はどうだろう? 自分の悩みや不安を話したところで、問題は解決しない。そんな不毛なやり取りは無駄ではないのかと思って生きてきた。
東畑先生は、私の心を見透かしたようにさらにささやきかける。解決に至らなくて当然。でも話したことでかわると先生は断言する。うーん、確かに。いわれてみれば、私はあれから少しかわった気がする。友達と7時間話したあと、劇的に何かがかわったということではないけれど、少しだけ何かが楽になった気がする。とても軽やかになったように思う。
そしてこの本で先生はさらに私を諭す。孤独はいいのだけれど、孤立はダメだと。孤独も孤立もポツリと一人でいる状態は一緒なのだけれど、心の中の世界がまるで違う。孤独は、鍵のかかる個室に心がいることを指す。そしてその個室にいる時の状態は、
“安定した仕事がある、心を許せる友人がいる、お金がある、しばらくは住んでいられる家がある“
そんな安心した環境が揃った上での孤独は、問題ない。
しかし孤立は心が相部屋にいて、「私さえいなければ」とか、「私が悪いからこんなことになっている」などと、想像上の悪しき他者が同居して自分を責める声が吹き荒れてくる状態だ。孤立はヤバイらしい。
ここで少し私の話をすると、私には7歳年下の妹がいた。ちょうど1年半前に彼女は乳がんで亡くなってしまった。私たち姉妹は、妹が高校を卒業してからずうっと一緒に暮らしていた。部屋は狭い1DKに2人暮らし。もちろんそれぞれの部屋はなく、布団を2つ並べて寝ていた、何十年もの間。そして夜、布団を敷くと始まる「今日の反省会」。どちらからともなくビールをもってきて「今日、こんなことあってさ」とか、「〇〇さんがむかつく」とか、愚痴や憂さ晴らしが始まる。
しかし彼女がいなくなり、私はそういうことを誰とも話さなくなった。だからといって「話したい」とか、「話を聞いて」なんて思ったことはない。でも私はこの「反省会」がなくなり、気が付けば人の話が聞けない、そして人と話をしたくない状態になっていた。それが積もり積もって黒いマグマがフツフツと沸騰し、とうとう噴火した。
東畑先生は孤立を回避するには、とりあえず話を聞いてもらうことが大切だという。友達に7時間話を聞いてもらい、私のマグマは外に飛び出していった。その後に、この本が私の積読からひょっこり顔を出した。手にとってみると、私の最近の一連の出来事をわかりやすく紐解いてくれている。もしかして、私って孤立する寸前だったの?
この本のあとがきで東畑先生はとりあえず、聞く技術と、聞いてもらう技術は「何かあった?」と、「ちょっと聞いて」というところからはじめれば良いという。
友達が別れ際、「素子、ご飯食べていないでしょう」と、保冷剤がいっぱい詰まった保冷ボトルの中から、ジップロックを取り出し手渡してくれた。その中には彼女お手製のミートソースがギューギューに詰まっていた。ジップロックは7時間経っても冷え冷えで、冷たいまま。家に帰り、パスタを茹で、早速ミートソースをかけてパクリと食べてみる。彼女のミートソースは妹も大好きで、「おいしい、おいしい」と笑って食べていた。今ではすっかり広くなった部屋で、一人パスタを食べていると、涙があふれてきた。
文/谷口 素子
【この記事もおすすめ】