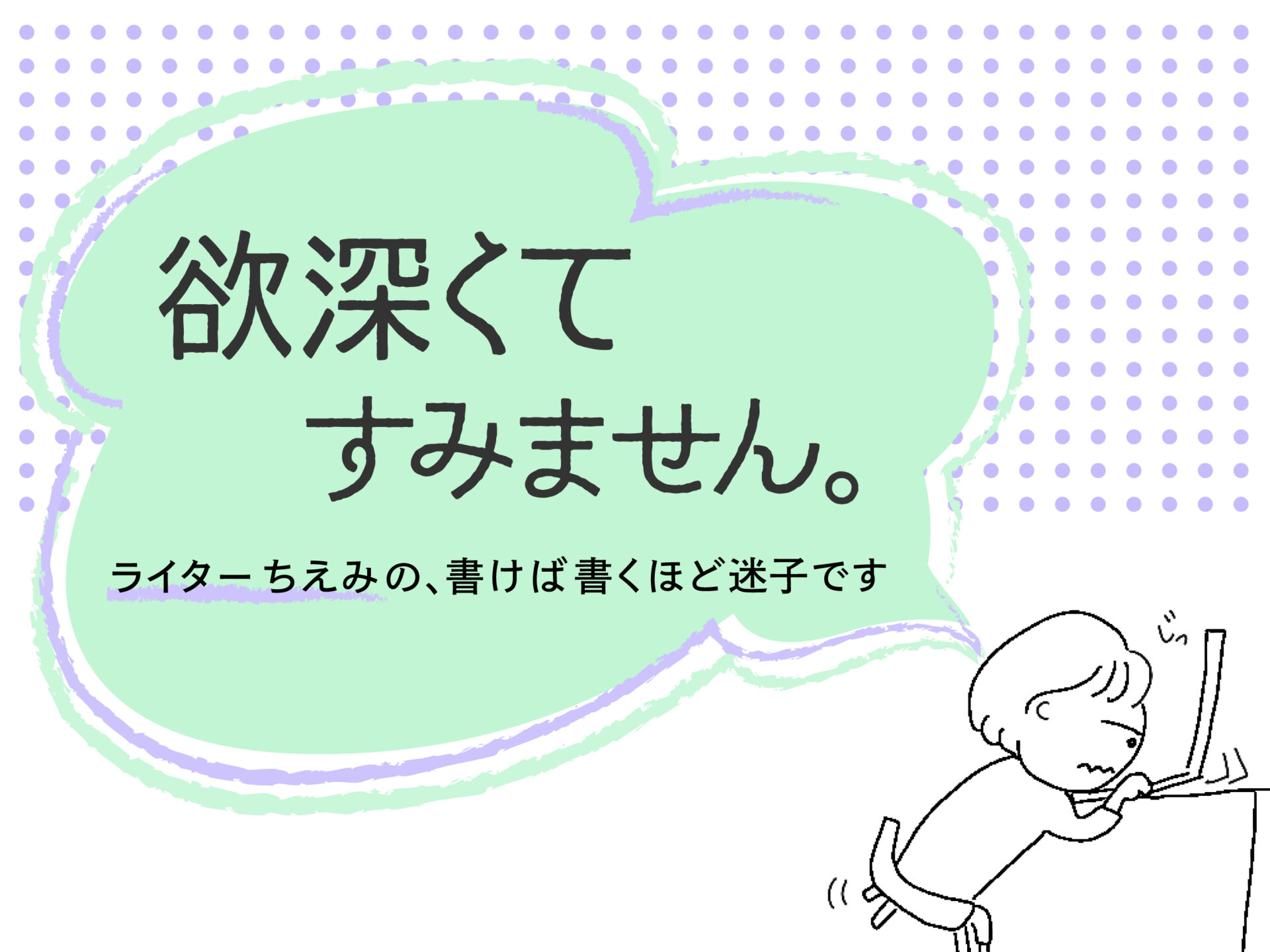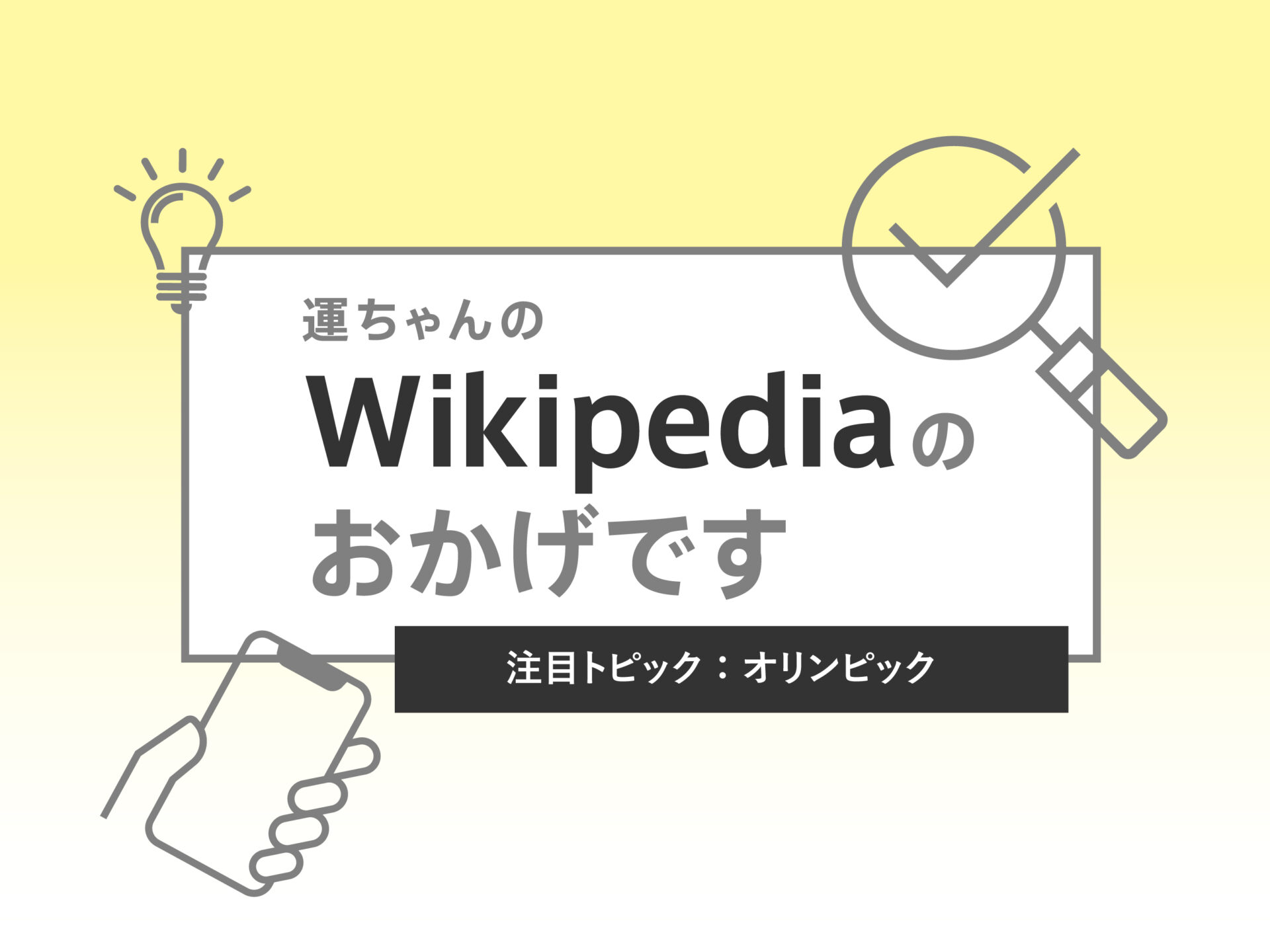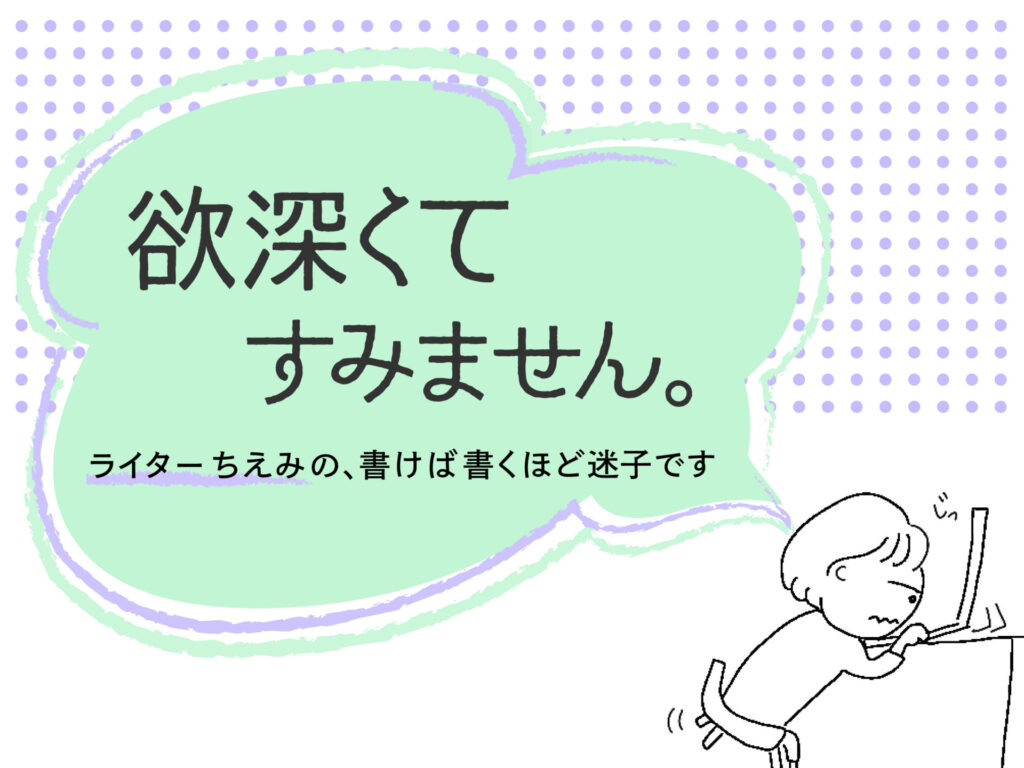
なぜインタビューですれ違いが起きたのか。抽象と具体の往来で話を聞くこと【連載・欲深くてすみません。/第32回】
元編集者、独立して丸9年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日は、過去のインタビューでの失敗事例について思い出しています。
重大な事故につながりかねない“ヒヤリ”な瞬間は、当人にとっては唐突だが、客観的に見ればしかるべき時に訪れるものだ。
ずいぶん前だが、インタビューをした相手を危うく怒らせそうになったことがある。どのような状況だったか。ここでは、若い読者を抱えるビジネス系の媒体で、酸いも甘いも知るベテラン経営者A氏に「20代のうちにしておくべきこと」について聞く、と仮のシチュエーションに置き換えて書いてみたい。
インタビュー経験の少ない当時の私は、テーマそのままの質問をいきなり投げかけた。さて、そこからどのようにヒヤリが訪れるか。
私「20代の読者に、これだけはしておくといいと思うことはありますか?」
A氏「エネルギーと体力のある20代のうちに、自分の限界を広げておくことが大切なんです。だから読者のみなさんには、身の丈に合わない挑戦をしてほしいですね」
私「ははあ、では20代の頃のAさんにとって『身の丈に合わない挑戦』とは、たとえばどんなことでしたか?」
A氏「? ……いや、今、私は読者のみなさんへのメッセージを話しているんです。私が20代の頃の話はしていません」
……あれ、何かおかしなことを聞いたかな? 答えてもらえなかったことを不思議に思いながらも、そこまで深く考えずに私は質問を続けた。
私「……えーと、では、Aさんがそう考えるに至ったご経験があれば、伺いたいなと思って」
A氏「意思決定に必要な能力は3つあり……(A氏の考える、経営者にとって大切な力の話が続く)これらが身につくのは、20代の頃の無謀な経験からなんですね」
私「ははあ、ではAさんにとって、それらの能力を養った『無謀な経験』とは、たとえばどういうことですか」
また同じようなことを聞いた。ここで、A氏の顔色が変わる。
A氏「あのね、話、伝わってるかな(苦笑)。私は20代の読者に伝えたいことを聞かれたので、汎用的な教訓を答えているの。無謀な経験の“中身”は、何だっていいんですよっ」
はい、ヒヤリ。実際はヒヤリどころか、ビンタされたのかなと思ったほど、冷たい空気が頬を打った。すぐさま謝罪し、取材の方向性を変えなければと思ったが、そのとき私は冷静になった。そもそも、なぜ、こんなにも会話が噛み合わないのだろうか。
さて、何が起きていたのでしょう? みなさま、おわかりになりましたでしょうか。
A氏の側からすると、「20代の読者に」と広く問われているので、できる限り多くの読者に当てはまるような表現で、誰にでも通じるような話をしようと心がけている。つまり話はどんどん抽象化する。そして、この「抽象的な考え」について、インタビュアーに、より詳しく聞いてほしいと思っている。
しかし、してほしい質問がいっこうに来ず、挑戦の「具体例」ばかり聞かれるので、なぜそんな瑣末なことにこだわるのだろう、とイライラしている。
私の側からすると、A氏の「伝えたいこと・抽象的バージョン」を聞いたものの、社会人経験の少ない読者からすると、A氏の言いたいことが頭では理解できるが、いまいちイメージできないなと思っている。地球の裏側でヒッチハイクしてみろ、と言われるのと、降りたことのない駅で一度降りてみろ、と言われるのとでは、受け取り方が変わる。だから「伝えたいこと・具体的バージョン」を聞く方向で、話を掘り下げようとしている。
さらに、率直に言えば「若いうちは身の丈に合わない挑戦をしよう」は、誰でも言える話なので、大した見出しにはならない。A氏は数々のユニークな挑戦で知られる人だ。その無謀な挑戦の具体例がひとつでも聞ければ見出しができる、と腹の中で編集している。
抽象の世界で歩きたいA氏と、一度具体的な世界に降りたい私。どちらに向かって歩くかの意思疎通ができていないから、話が噛み合わなかったのである。
*
このヒヤリは「インタビュアーが話の編集に夢中になっており、取材相手の話したい文脈にまったく沿おうとしていない(自分の中で、足りないピースを補うような質問の仕方をしていて、その意図が相手に伝わっていない)」ところに最大の問題があるが、他にも大切な教訓を秘めているように思う。
往々にして伝わる話とは、抽象的なだけではなく、具体的なだけでもなく、どちらをも行き来して観察を深めた結果、普遍性を獲得した話なのではないか。
だとしたら、優れたインタビュアーは、その往来の同行者もしているのかもしれない。
いきなりあさっての方向に走り出したり、予告なく土の中に潜り出したりすることなく、相手とあゆみのペースを揃えながら、双方を行ったり来たりして、何かに気づいていく。そんなインタビューがしたいなあと思う。
ところでヒヤリのその後はどうなったか。頭が真っ白になった私が「すみませんんん、ここの具体的な話がないと、読者に伝わらないと思ったんですううう」と腹の中を隠さず伝えたところ、A氏が「うむ、なるほど、それは大切な読者視点だね」とすんなり納得され、取材は軌道修正された。怒られるどころか、最後には「あなたのおかげで、いい話ができました」と褒めてもらえて、何事もどう終わらせるかが大事なのだなと学んだのであった。はーあ、ヒヤリ。
文/塚田 智恵美
【この記事もおすすめ】