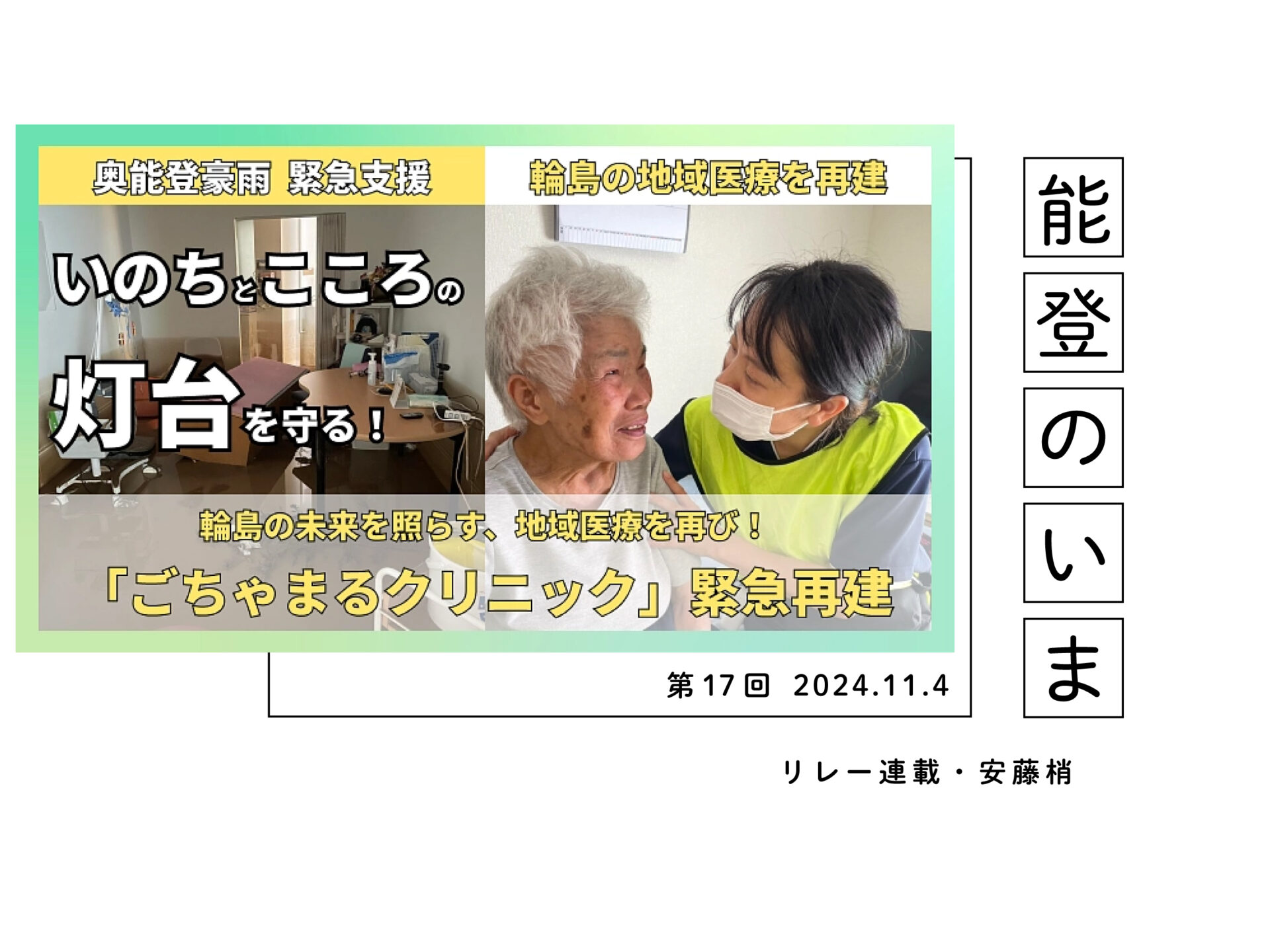「頑張らない」でつながるコミュニティは、不登校の子の居場所づくりから始まった【リレー連載・あの人の話が聞きたい/第5回】
不登校の子どもの居場所をつくるために始まった「いばしょかふぇ」。5年目の現在、小学生から50代まで、多様な人たちが集うコミュニティへと変化している。いばしょかふぇの道のりと、コミュニティを継続する秘訣について代表の宅間和美さん(48)に聞いた。
聞き手/村上 いろは
京都の町家にある「頑張らなくていい場所」
「おめでとうございます!」
2025年2月、京都・二条城にほど近い町家。小学生とその両親、大学生、画材屋の社長たちが訪ねてきては、お祝いの言葉をかけた。笑顔で対応していたのが、いばしょかふぇ代表の宅間さん。この日は、いばしょかふぇ5周年記念のオープンデーだった。
「12時過ぎから17時頃まで、たくさんの方が来てくださったんです。ハンドマッサージをプレゼントしてもらったり、いちごやフラワーアレンジメントを渡してもらったり。みなさん、無理のない範囲で祝ってくれて、とても嬉しかったです」

いばしょかふぇは、7歳から18歳までの不登校の子、大学生、会社員、自営業者、在留外国人など、幅広い層の人たちが参加するコミュニティだ。開催は月3〜5回。12時〜17時までのいばしょかふぇと、15時〜20時までのいばしょかふぇnightがある。宅間さんは、初めて参加する人に「何もしなくても大丈夫です。そのままのあなたでいてください。ここで過ごすあいだは、頑張らないでください」と伝える。このコンセプトは、いばしょかふぇを始めたときから変わらないという。
不登校の子どもの居場所をつくりたい
宅間さんがいばしょかふぇを立ち上げたのは、2020年2月。15歳の娘さんと、11歳の息子さんが不登校になったのがきっかけだった。
「不登校の子たちは、少しずつ少しずつ気力を取り戻し、再び社会とつながろうとします。学校に戻る子もいれば、自宅から外に出るのが精一杯で、スモールステップが必要な子もいます。私の子どもは後者でした。フリースクールはあったものの、ICTによる学習などのカリキュラムが用意されていました。『ただ、その場に行くだけでいい』場所は、見つからなかったんです」
「自分でつくるしかないかな」。そう思った宅間さんが、よく足を運んでいたKYOTO LAUNDRY CAFEのオーナーに話したところ、「じゃあ、うちの定休日にやってみたら?」と提案された。実現に向け、宅間さんが娘さんの意見を聞くと、その場で何かをしなければいけないのはハードルが高い。滞在時間を指定されるのもしんどい、と言われた。
カフェは、営業時間内なら出入り自由で、その場で何をするのか自分で決めることができる。カフェにそんなイメージを持っていた宅間さんは、自分がつくる場をいばしょかふぇと名付けた。開催は第3月曜日。開催時間内は出入り自由。コンセプトは「何もしなくていい、ただいるだけでいい」。宅間さんは、友人、知人にいばしょかふぇをオープンすると話し、SNSで告知をした。
口コミとSNSで交流の輪が広がった
初回には、不登校の親子や、宅間さんの活動に共感した教育関係者たちが遊びにきた。回を重ねるごとに、帽子を目深にかぶりヘッドホンをつけて座っている子、Nintendo Switchで遊ぶ子、隅のほうで本を読む子など、子どもが自分のペースで過ごす様子を見守るのが自然な場となった。付き添う親は、学校への対応や、フリースクールの感想といった本音の情報交換ができる。いばしょかふぇは、体験した人たちの口コミ、宅間さんのSNSでの告知によって広まり、参加者が増えていった。
オープンから半年が過ぎると、「他の日にも開催してもらえませんか」との声が多数寄せられるようになった。宅間さんは、いばしょかふぇの活動で知り合った、不登校支援をしている人たちに相談した。その一人が、現在いばしょかふぇを開催している町家のオーナー・駒井さん。「不登校の親の会やイベントを開催していない日は、自由に使っていいよ」。駒井さんの一言で、いばしょかふぇの移転が決まった。
「とんとん拍子に話が進んで、とてもありがたかったです。いばしょかふぇを立ち上げたときも同じでしたが、一人で悩まず、誰かに話してみるのが大事ですね」
「心地よさ」から見つけた課題解決法
2020年12月に、町家で再スタートした、いばしょかふぇ。月日が経つにつれて、3つの課題が浮き彫りになった。一つは運営費。大人1000円、子ども500円の参加費を設定し、京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金も申請している。とはいえ、賃貸料の支払いやお茶菓子の用意が必要で、毎月赤字寸前の状態だった。次が、参加者から寄せられる「ごはんを一緒に食べたい」などの要望にどう応えるか。最後がSNSの運用。告知が義務のように思えてきて、負担になっていた。
「すべてを解決する方法が、私がやりたいと思ったイベントを開催することでした」
ヨガや気功、古武術を取り入れたエクササイズなど、身体を整えるイベントを企画。メディアリテラシー、アクティブリスニングの講座も行った。イベントの収益をいばしょかふぇの運営費に充て、運営費に少し余裕が出たタイミングで晩ごはんを共にするいばしょかふぇnightを開始。SNSの運用は、自分が楽しみにしているイベントだから苦にならず、熱量の高い告知文を書けた。

多様な大人との出会いが子どもを変えた
予想外だったのは、イベントに参加した大学生や大人たちが、いばしょかふぇにも来るようになったこと。「何もしなくていい、ただいるだけでいい」が前提の場のためか、それぞれが自分のペースで過ごし、相手を否定する発言もない。いばしょかふぇ常連の翻訳家は、「さまざまな立場の人が、雑談をしていたり、本を読んでいたり、タブレットを触っていたりして面白い。ここなら、日本語をあまり話せない人でも受け入れてくれそう」と言い、日本語を学ぶフランス人やアメリカ人を連れてきた。3ヶ月にわたって一緒に過ごすうち、不登校の子たちがフランス文化に興味を持ったり、片言の英語で話しかけたりするようになった。
「いろんな背景を持った大人がいると知って、いい影響を受けているのではないかな、と思っています。他にも、ゆっくりと変わっていった子がいます。帽子を深くかぶり、ヘッドホンをつけて周りの音を遮断していた中学生は、2年経った今では何もつけずに話すのが日常になって、大好きな麻雀の大会を主催してみたいと伝えてくれました。私も、自分のやりたいことが明確になり、違和感をスルーしてまで頑張るのをやめました」
コミュニティを継続する秘訣は自分のケア
「いばしょかふぇを心地いい場にしてくれたのは、参加者のみなさんです」という宅間さん。それでも、参加回数が一番多いのは代表を務める本人だ。心理的安全性が保たれた場を継続する秘訣は何だろうか。
「自分の心と身体のケアを大切にしています。私がすこやかでいたら、いばしょかふぇを長く続けられますよね」
運営に伴う悩みを相談できる存在にも助けられた。宅間さんは、町家のオーナー・駒井さんとともに、京都市内で子どもの支援活動をしている人たちが集う団体「京都・子どものミライ作り ポレポレ」(以下、ポレポレ)を立ち上げている。
「京都市内で支援活動をしている人たちとつながって、子どものニーズにあった場所をマッチングしています。運営で悩んだら、同じ立場の人に相談できるのもよかったです」
ポレポレの活動を通じて、京都市中京区の社会福祉協議会とも連携するようになった。次は、町家の近隣の人たちと交流できたらと考えている。今年11月には、町家の向かいにある佛現寺と、小さなマルシェを共催する予定だ。
「オープンデーの際、地域の方々に『何をしている場所なん?』と聞かれたんです。活動内容を知ってもらって、悩んだり、孤独を感じたりしたとき、いばしょかふぇに足を運んでくれるようになったら嬉しいですね」(了)
執筆・サムネイル撮影/村上 いろは

宅間 和美(たくま かずみ)
京都市右京区在住。「いばしょかふぇ」「京都・子どものミライ作り ポレポレ」代表。2020年に不登校の子どもの居場所「いばしょかふぇ」を立ち上げる。京都市内で子どもの支援活動を行う団体を紹介する「居場所フェス」を主催し、認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会の研究集会に登壇。京都市中京区社会福祉協議会とも連携し、さまざまな活動をしている。