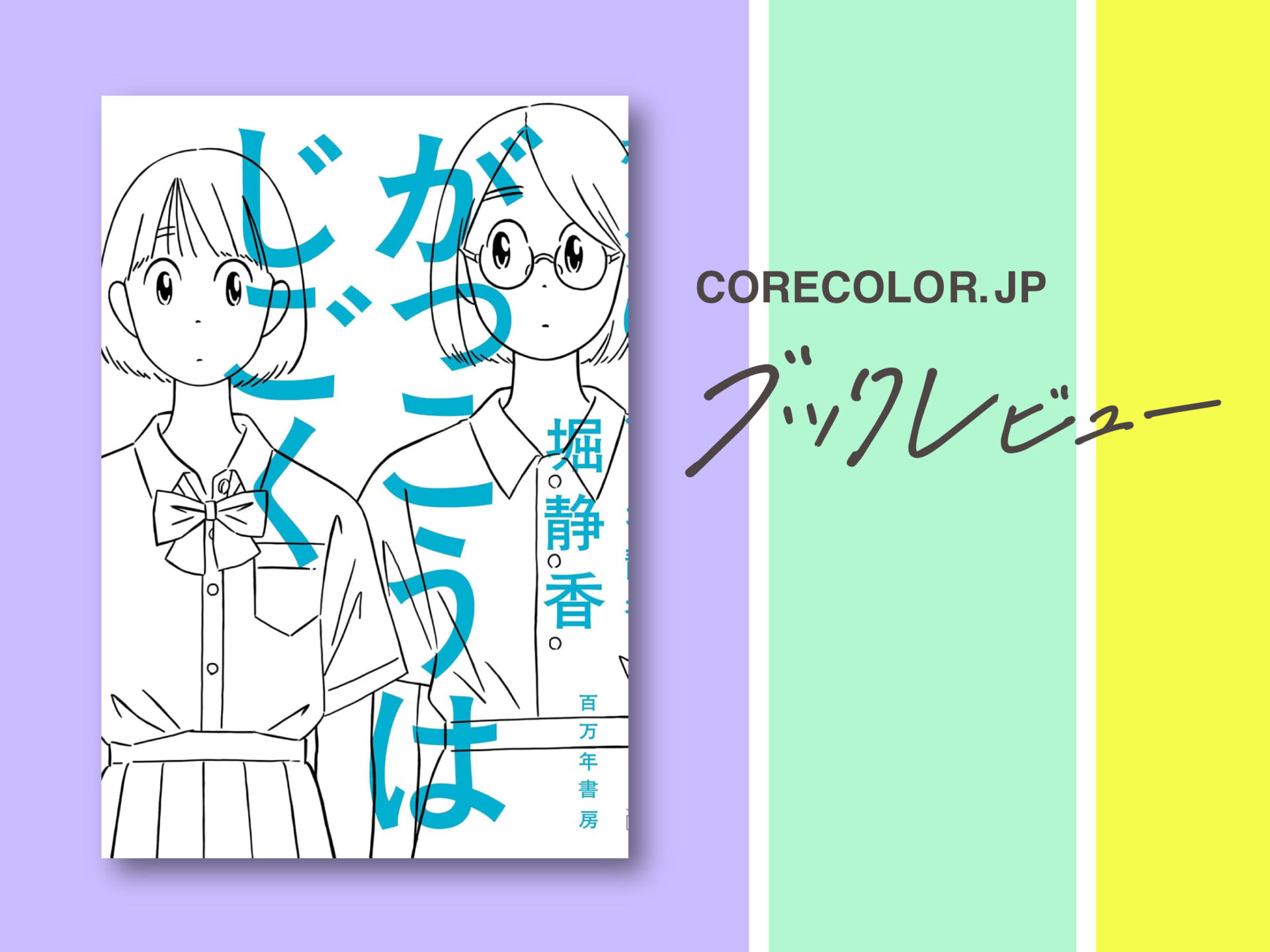頼まれてもいないのに、私は誰かに勝手に寄り添ってはいなかったか。KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ライカムで待っとく』
2022年はたくさんの舞台を観た。この12月だって、シチュエーション・コメディ、壮絶な二人芝居、シェイクスピア劇にかつて演劇賞を総なめにした某劇団の代表作など、さまざまな演劇に触れた。
だけど観劇後、何度書こうとしても上手く言語化できない芝居があった。今書き始めた原稿は、既に5回目の書き直し。その作品では次のようなセリフが放たれる。
「娘さんいなくなったら悲しいですか? 寄り添いますよ? あなたが悲しいうちは、悲しそうに見えるうちは、寄り添いますよ? あなた方も、いつもそうしてきたでしょう?」
(2022年、「沖縄の人の痛みに寄り添いたい」と語る内地の雑誌記者の言葉を受けた沖縄のタクシー運転手)
「……不幸だと思ってるんでしょ、沖縄の人のこと」
「でも決めたわけ。私は自分が不幸だって認めようって。そうしたら、人を差別しなくて済む」
(1964年、内地から来た雑誌記者に対して、米軍兵士相手に1回5ドルで売春をする沖縄の20代女性)
この作品のタイトルは『ライカムで待っとく』。神奈川芸術劇場 中スタジオで11月30日(水)〜12月4日(日)の非常に短い期間のみ上演された。関係者にコロナ感染者が出たことで一部日程が中止となり、前売券は完売。私が観た日は当日券も出なかったので、ごく少数の人だけが目撃した舞台となった。ちなみにライカムとは、アメリカ占領下の沖縄本島中部に存在した琉球米軍司令部(Ryukyu Command Headquarters)の略称で、現在は地名として知られている。
150人キャパの小さな会場に入ると、客層が普段観る演劇と違っていた。沖縄の過去と現在と未来が交錯する戯曲になるからか、ドキュメンタリーの映画祭で見る客層に近かったと思う。政治や歴史に興味がありそうな50〜60代の男女が多い。かと思うと、生足が寒そうな10〜20代女性の姿もあった。
この舞台は、現代日本に生きる私たちへ答えの出ない問題を突きつけるドキュメンタリーなんだろうと身構えていた。しかし蓋を開けてみると、舞台の手触りは藤子不二雄(A)の『笑ゥせぇるすまん』を彷彿とさせるダークファンタジーだった。内容は、アメリカ占領下の沖縄で1964年に起きた「米兵殺傷事件」の手記をもとに、現地取材を持ちかけられる雑誌記者・浅野の話だ。1964年の沖縄と2022年の沖縄が時空を超えて行き来する。
やがて浅野は自身が書いた原稿の世界に飲み込まれてしまう。米軍によって裁かれる「米兵殺傷事件」の裁判。そして事件の当日、何が起こったのか。話が核心に進むと、次のようなセリフが観客の身体に絡みつく。
「ここは、沖縄は、日本のバックヤードだからね」
「(内地に住む)あなたの生活が平和であるためには、どこかに犠牲が必要なんです」
(1964年、普天間で暮らす写真館経営者)
「バックヤードで起きたことは、表からは見えない。この島で起こっていることは、内地からは見えない」
「(犠牲になる人は誰でもよかった説明として)たまたまそこにいたらレイプされた。たまたまそこにいたら飛行機が落ちてきた。たまたまそこにたら殴り殺された」
(1964年、普天間の写真館で働く従業員)
基地周辺で育ち、今も沖縄市に住む劇作家・兼島拓也のセリフは、軽妙でコミカルでありながら観客の心に塞ごうにも塞ぎきれない穴を開けてしまう。本土復帰50年を迎えた2022年、個人的に沖縄に関するさまざまな作品を目にしたが、えぐり出した内臓のような沖縄人の本音に素手で触れた感覚はこの舞台が初めてだった。
冒頭にあったセリフ、「寄り添う」の白々しさ、狡猾さ。今まで何も考えずに「寄り添う」だなんて、原稿に書いてはいなかったか。頼まれてもいないのに、私は誰かに勝手に寄り添ってはいなかったか。
今年、一番書きたくて書けなかった原稿が今、終わろうとしている。劇場に放たれた兼島拓也のセリフが、今、読んでいるあなたの身体にもいつの間にか絡みついていたのだとしたら、とても嬉しい。そして、作品の背景をわかりやすく綴った劇場のページを見て、もう1ミリ先まで沖縄を知ってもらえたのだとしたら、私はもっともっと嬉しい。