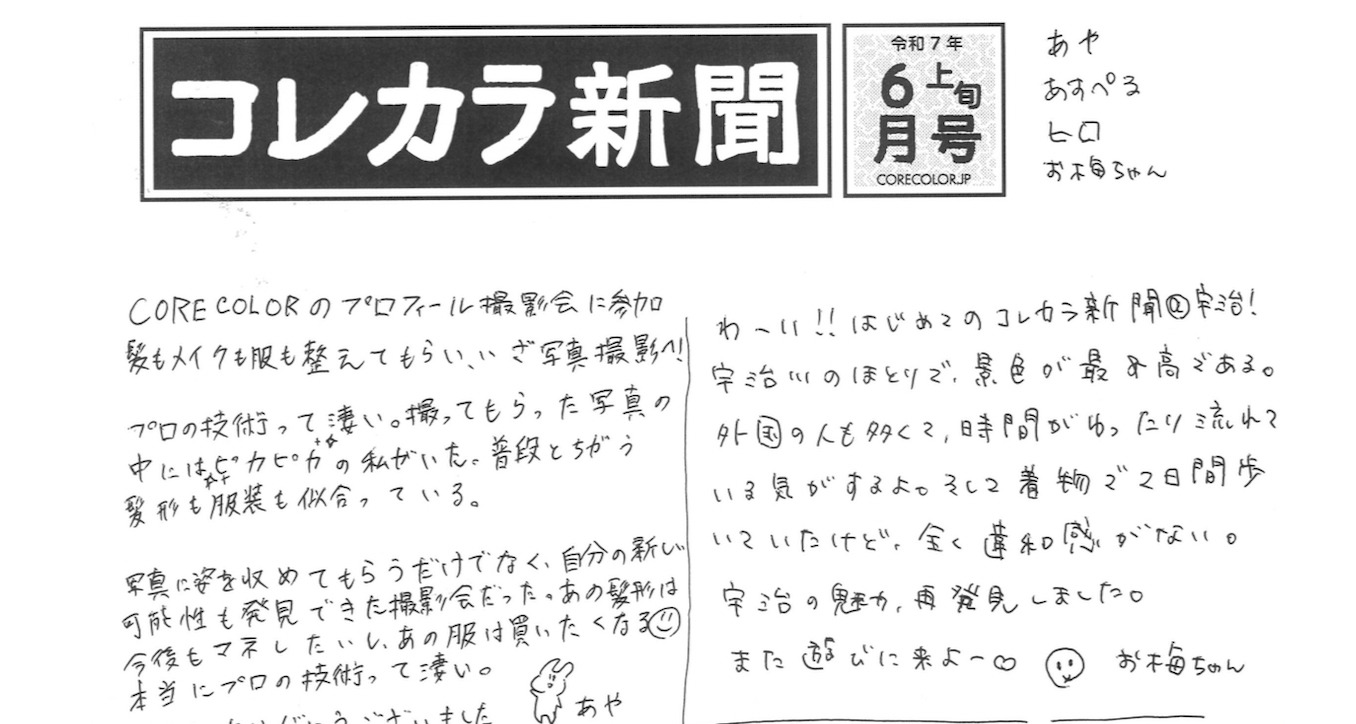「本を売れないのは編集者の責任感の欠如」。社員6人、本社は明石。一人当たりの売上単価は業界トップクラス。ライツ社/大塚 啓志郎さん【編集者の時代 第2回】
CORECOLOR編集長、佐藤友美(さとゆみ)が、編集者に話を聞くシリーズ「編集者の時代」。
『リュウジ式悪魔のレシピ』(22万部)、『売上を、減らそう。』(5万部)、『認知症世界の歩き方』(16万部)などベストセラーを連発するのは、ライツ社。2016年に兵庫県明石市に創業した社員6人の小さな出版社だ。年間に発行する冊数はたった4〜5冊。しかし、その本がひとたび書店に並べば、たちまち話題になる。どんな本作りをし、どう売っているのか。見えてきたのは、「1冊の本に対する責任」をどこまでも取ろうとする姿勢だった。
聞き手/佐藤 友美(さとゆみ) 構成/市橋 かほる
構成に2カ月。文字は1文字でも減らし、4行に1回は感動させる
――ライツ社さんの書籍、すごく売れていますよね。どんなことを意識して本作りをされているのでしょう。
大塚 ビジネス書で言えば、読者に著者のストーリーを届けることです。よく、「たった〇分で」とか「すぐにできる」といった本が何十万部ものヒットになります。でも、僕自身、そういったハウツー本をあまり信じていないところがあって、読んだことはほとんどありません。それより、「私はこんな風に生きてきました。こんなことを考えてやりました。あなたならどうしますか」という風にストーリーで語られた本の方がスッと身体に入ってくる。だから、ライツ社ではどのビジネス書もハウツーではなく、ストーリーとして読んでもらえる本にしています。

心掛けていることって言われるとすごく難しいんですけど……編集のニオイを限りなく消すことですかね。わかりやすくいうと、『売上を、減らそう。』も『マイノリティデザイン』も、ページには装飾的なデザインを入れていません。罫線も太字もなし。そういうものを入れた時点で、読者に編集者やデザイナーの存在が見えてしまう。読者は著者のストーリーを読みたくて本を開いているのに、そこに僕らが割り込みたくないんです。だから、著者と読者の接点をいかに邪魔せずに作るかを意識しています。
――「ここ、重要だから読んで」と押し付けないということですね。具体的にはどんなプロセスで本を作っていくのですか。
大塚 ビジネス書の場合は、取材前にまず、著者に関するあらゆる情報を集めます。ウェブ記事や雑誌記事、講演会の記録など。足りないときは、ミーティングや商談の様子を録音してもらってテキスト化することもあります。それらを1つのWordにまとめる。だいたい70万文字を超えるデータになります。
次にそれを項目ごとに整理していく。たとえば、『売上を、減らそう。』では、「飲食店に絶対にあるはずのものがない」という項目がありました。著者の中村朱美さんはこのテーマについていろんな媒体で話されているので、関連するすべての記事をこの項目に集約させます。こういった項目をいくつも作って、順番を並べ替えて構成を考えていきます。

――膨大な量の素材を集めるんですね。この構成を作るまでにどれくらいの時間をかけますか。
大塚 朝の9時から夕方18時まで丸々この作業にあてたとして、多少ほかの仕事もしながらですけど2カ月くらいは使っているでしょうか。大量の情報に目を通して整理して構成を考える。もう一度、すべて読み直して構成を練り直す。こういうことを何回かやるので。ここまでできて、やっと取材開始です。
――そこまで下準備をしたうえで、取材ではどんなことを聞くのでしょう?
大塚 景色です。ウェブ記事や雑誌記事は文章が短いので、どうしても景色の部分が抜け落ちる。そこを補っていきます。
――「その出来事は朝だったか、夕方だったか?」といった景色?
大塚 そういった本当の景色の場合もあるし、心の変遷の場合もあります。ウェブ記事で時系列に並べられていた事実関係も、「それ、本当にその時点で気づきましたか? もうちょっと後では?」「これとこれの間に、何かあったんじゃないんですか?」といった質問で、当時の情景や心境を一緒に思い出してもらうんです。そういう景色まで書かれたものが本として読み応えがあって、読者の心を動かすと思っています。
――書くのはライターさん?
大塚 骨格となる最初の文章をライターに作ってもらって、僕が不要なものをそぎ落としていきます。たとえば、この部分。書き出しが「気づかせてもらったことがあります。」ですよね。通常、こういった文は冒頭に「この仕事を通して、」といった一文が入りがちです。でも、それはなくても通じる。その結果、最初の文章の3分の1くらいになることもあります。
――文が短い方が伝わる?
大塚 前提として、ビジネス書の場合、同じ内容を伝えるのであれば、1文字でも少ない本の方が、読者が多くなると考えています。実は、本で伝えたいことって非常にシンプルで、『マイノリティデザイン』だと、「人の弱さって生かせるんだよ」ということだけが伝えられたらいいんです。だから僕は、伝えたいことに対して不要な文は1文字でも削りたい。
逆に、読んだ後にそれがしっかり読者に残っていなかったらダメ。そうやって削り切った後、今度は、文章を数値化していきます。これは、前に勤めていた出版社の社長から教わった方法ですが、読むときに生まれるであろう感情を数字に置き換えてチェックするんです。ここは楽しさ「8」、悲しさ「10」みたいに。
――数字が大きければ大きいほど良いということですか。
大塚 というより、たとえば感情の数字が0とか1の文章ばかりが続いていたら、アウトといった感じですね。発見や共感のない文章が4行続いただけで、読者は飽きてしまう。だから、4行に1回は、「楽しさ」や「悲しさ」といった心が動くポイントを作るようにしています。
見たことがない。だけど見た瞬間に「それだ」と通じる企画
――売れる企画には何が必要でしょう?
大塚 見たことがない企画にすることです。「日本初」や「類書がない」ことにこだわっています。実は、起業1年目に、出せば必ず売れるような大ベストセラー作家の方たちの本を作らせてもらうことができたんです。きっとその作家さんにしてみれば、「出版社設立おめでとう」のご祝儀のような気持ちでOKしてくれたのだと思います。でも、他の売れている本を見よう見まねで作った結果、どこかで見たことがあるような本になってしまった。そのベストセラー作家の方たちの代表作品を超えるようなヒットにはならなかった。で、結局、ライツ社の1期目も赤字。尊敬している出版社の営業部長からは、「そんな本を作りたくて、わざわざ独立したの?」と言われてしまいました。作家の方にも本当に申し訳なくて。
それ以来です。絶対、誰も見たことがない企画を作ると決めたのは。自分だから、ライツ社だから作れるものでないと、僕らが出版社をやっている意味がないって。

――見たことがなければ、売れる? 逆に、売れないから見たことがないということもありませんか?
大塚 見たことはないけど、見た瞬間、「そうだよな」って思うもの、ですね。『マイノリティデザイン』の著者の澤田智洋さんが、本の中で、「キャッチ概念」と呼んでいるものなんですが、まさにそれで。
「この世の中に物事や事象としてすでに存在しているけど、だれにも言語化されないでいる。それを忘れがたい言葉で表現したもの」
(該当ページより抜粋)
これですね。
『リュウジ式悪魔のレシピ』は22万部売れました。これは、みんなが「リュウジさんの料理って美味しくて食べ過ぎてしまうから危険だよね」と思っていたのを、「悪魔のレシピ」というキャッチ概念で言語化できたからだと思っています。
――企画は会議で練るのですか?
大塚 ライツ社では企画会議はありません。社員が6人というのもあって机も1つしかないような距離感なので、みんなが思いついた言葉や、いいなと思った記事をLINEで共有して反応が良いものを本にしています。
たとえば先日、僕が登壇したあるイベントで、参加者の方に企画作りの課題を出したんです。その中に、「こわいものいじめ」という企画を出してきた人がいました。それを見たとき、森元総理が女性蔑視発言をして、一斉にバッシングされたことを思い出しました。もちろん、発言自体が問題のあるものでしたけど、ひょっとしたら、これまで「よわいものいじめ」と言っていたのは、実は「こわいものいじめ」なんじゃないかな、と思ったんです。僕らは、実は自分より強い者やこわい者に対して攻撃しているんじゃないかって。それをLINEで共有したら、みんなすごく盛り上がって。

この間は、ある著者さんが未来のロボットについて書いた原稿の中で、この本は「むかし、むかし」ならぬ、「みらい、みらい」の話だと紹介していました。それを見た瞬間、「日本、みらいみらい話」という企画を思いつきました。昔話形式で、未来のちょっと難しい研究者の話や医学・科学の話を伝えられたらおもしろいんじゃないかと。その話をLINEで送ったら、また、みんなが「わぉー」ってなった。
――盛り上がったらどうなるんですか? そこからは?
大塚 そうなれば、「本、作ります!」となって、著者を探しにいくんです。みんなの反応が良かったら、本にしようと思えるし、売れると思う。本当にそれだけなんです。でも逆に、この盛り上がりがないものは作らないし、たぶん売れないと思っています。そうなると、年に何冊も企画って出てこないんですよ。だから、結果的に昨年は年4冊の出版になりました。これは出版社の中でも極端に少ない発行数。でも、発行数を絞る方が、結果的に売れると思うんです。
――業界の重版率の平均は2割あればいい方ですが、ライツ社では7割以上重版になっていると聞きました。それはなぜでしょう。
大塚 通常、出版社の営業が書店員さんに新刊を紹介できる時間は15分程度です。発行点数が多ければ1冊あたりにかけられる時間が少なくなりますが、僕らはその時間を1冊についてまるまる使える。すると、伝わり方が全然違います。本の企画について深く語れるし、面出しといって、その本の表紙を見せて10冊陳列してもらう話をしにいける。棚の中でいい場所がたくさん取れたら、読者との接点が増えるわけで、確実に実売につながっていきます。そうすると、発売2週間で返品されるといったことも起きません。
――確かに最近は発行が少ない出版社の書籍ほど売れていると感じます。たとえば、ダイヤモンド社さんなども、編集者に年間の発行数のノルマを設けていないそうですよね。一冊入魂の書籍が、読者に選ばれる時代になっているのかもしれません。
大塚 あとは単純に、編集が1冊の本作りにかける時間も増えるし、広報に当てる時間も増えますよね。編集も営業も広報も、質が全部上がれば、必然的に売れる確率が上がるのかなと思います。
本を売れないのは編集者の責任感の欠如
――売り方についても教えてください。何を意識していますか。

大塚 僕らの本は企画が特徴的です。だからあとは、読者との接点さえ作れれば売れると考えています。その方法はいくつかあるのですが、ひとつは、先ほども話した書店の同じジャンルの棚で一番面出しされること。そのためには、書店員さんにこの本は世の中に1冊しかない特別な本だとわかってもらうことが必要になってきます。
タイトルで言えば、たとえば数字を効果的に使います。たとえば『全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ』は、「世界のレシピ」だけだと、どこかで見たことがある料理本になってしまいますが、「196ヵ国」という数字があることで、急に「他にはないもの」感が出ます。料理本の棚にはたくさんの似たような本が並んでいます。そういう場所でどう売るかを考えると、デザイン面でも「悪魔のレシピ」みたいな、料理書ではそれまであり得なかった真っ黒な表紙だったり、『リュウジ式至高のレシピ』のように、表紙にあえて料理の写真を出さずに目を引くといった戦略も考えられるといった感じです。
――『認知症世界の歩き方』も、病気関連の棚ではまず見ない表紙です。

大塚 その分、認知症の本だと認知してもらえるように、タイトルの文字をかなり大きくしているのも特徴です。背景色は薄い黄色で。実はこの色は、最初はもっと濃い色だったのですが、ある本の経験を生かして認知症に悩んでいる本人やご家族の気持ちに寄り添う優しい黄色を選ぶことができました。
――ある本の経験というと?
大塚 岸田奈美さんの『もうあかんわ日記』です。

2万部以上売れたのですが、岸田さんの文章の持つ力を考えたら、もっと部数が伸びてもおかしくなかった。なぜだろうと考えたときに、表紙の色が明るすぎたんじゃないかと。この本は、「もうあかんわ」というタイトルですが、読み終わった後は元気が出る本なんです。僕は読んだ後のゴールを知っていたから、色を明るくしました。でも、読者が本を手に取るときは、そんなことまでわかっていません。ここで読者とズレが生じたのかな、と今となってはめちゃくちゃ反省しています。これはもう、編集の責任です。ご家族が入院して大変な状況だった岸田さんを少しでも応援したくて作った本だっただけに、岸田さんには本当に申し訳なかったと。
――著者のことをとても大切にされているんですね。
大塚:著者になってほしい方々はみなさん、素晴らしい経験や才能、世界感を持っています。それなのに、出版した本がもし売れなかったら、その本は返本され、営業もされなくなる。しかもその実績を見られて、次作は出せないと評価されてしまうこともあります。それを考えると、決して安易に出版できないんです。
だから、僕は著者に企画の話を持っていく時点で、多くの場合、タイトルや表紙の方向性も決めていますし、販売部数目標も、販売促進のプランまでお伝えするようにしています。編集者が売り方まで考えることによって、1冊の本のクオリティは変わります。1冊に対する編集者の責任の重みが違ってくるんです。
僕は本を売れないのは、作り手の責任感の欠如だと思っています。編集者って、きっと本作りの力はみんなそれほど変わらないと思うんです。だけど、どこまで売ることを考えられているかが行動の差になる。だから著者やライターの方は、編集者にどうやって売るつもりか、逆に聞いたらいいと思います。
――販売部数の目標を伝えるとのことですが、その約束はどれくらい達成されているのでしょう?
大塚 目標部数をお伝えするようになってからは、今のところ100%です。『リュウジ式悪魔のレシピ』は、10万部を超えると約束して今は22万部に。『認知症世界の歩き方』は2万部と伝えていましたが、16万部まできました。
――プロモーションではどんなことを?
大塚 小さい出版社なので、お金をかけずにPRする方法を常に考えています。たとえば、テレビなどのメディアに取り上げられると、売上部数は跳ね上がります。だから、「はじめに」のページは、ある意味メディア向けにもかなり作りこんでいます。ここを読めば、誰がどんな思いで誰に向けて書いた本なのかが一目でわかるようにしています。その本の企画書を入れているイメージですかね。書店では、はじめにのページがそのままPOPとして使われることもありました。前に編集のニオイをできるだけ消すと話しましたが、唯一このページは、作り手の姿勢を見せるんです。

そして、やっぱりSNSで話題にすることです。僕は、書評を書いているようなライターさん一人ひとりに連絡をとり、本を送らせていただいて、「こんな本を出したから読んでほしい、この著者をぜひ取材してほしい」とお願いしています。
――大塚さんは私にも『マイノリティデザイン』を送ってくださいましたよね。私は普段は献本を受け取らないのですが、大塚さんの力のこもったメッセージに圧倒されて、思わず受け取ってしまいました。
さとゆみが『マイノリティデザイン』について書いた記事はこちら
https://telling.asahi.com/article/14342341
大塚 そうやって書いてもらった記事が、ヤフーやスマートニュースなどに転載されたり、ツイッターで拡散されたりすると、アマゾンランキングで一桁台にラインクインすることもあります。なのにやらないというのは、ちょっと意味がわからないです。
大反対の中起業。2000万円の赤字が出た1年目
――ベストセラー連発のライツ社さんですが、最初から順調なスタートだったのでしょうか。
大塚 いえ。前の職場で同僚だった営業の高野と一緒に独立したんですが、周りからは「こんな出版不況の時代に、無謀すぎる」としきりに止められました。起業しようと思ったのは、前の会社で「給与カット」を言い渡されたのがきっかけでした。でも当時、僕たち2人で回していた出版部門は黒字だったのです。それなのに、ほかの部門が赤字続きで結局、還元されなかった。それに、役職がマネージャー、事業部長と上がるにつれて、マネジメントや会議にかかる時間ばかりが増えて、本を作るための時間がどんどん削られていったんです。自分の子どもも生まれたばかりで、でも家に帰るのは日をまたいでからで。もっと本を作る時間を増やしたい、もっと家族との時間を増やしたい、転職……でも関西に出版社なんてほとんどない。そう考えると、起業するしかないと思いました。

大塚 とはいうものの、退職時には、貯金がほとんどない状況で。地元に帰って、親に独立しようと思っていると報告すると、「祖父が持っていた古いビルが空いている」と教えてもらって。そのビルの1階に事務所を構えて、その上の階に僕も高野も安い賃料で家族で住まわせてもらえることになって、明石に引っ越してきました。そして、地元のつながりもあって、幸いなことに銀行と国庫から合計3000万円を借りることができて、なんとかライツ社を立ち上げることができました。出版業界は収支のサイクルが遅くて、出版してから売上が入金されるまでに半年はかかるんです。3000万円という数字は、そういった期間やもし本作りに失敗しても、当時の社員4人が生きていけるだろうという額でした。
でも、1年目はヒットが全然出ず、予想を上回る2000万円の赤字。みるみるお金は減り、預金額は1000万円を切るまでなりました。倒産するかもしれない……。崖っぷちのときに、世界中の少数民族を撮っているヨシダナギさんの写真集『HEROES』を出す話が決まりました。定価12000円の写真集で、初版4000部を刷ると、原価だけでざっと1000万円かかる。ので、またここで1000万円の借金をしました。この『HEROES』が9500部も売れて、1億円以上の売上を出してくれたんです。

――売りにくいと言われている写真集が1万部近くも売れること自体が異例です。社運を賭けたのだと思いますが、勝算があった?
大塚 売れる根拠はなかったんですよね。ただ奮い立ったというか。当時、ナギさんはテレビにもたくさん出演しだした頃で、何社も大手の出版社から声を掛けられていたんです。でも、ナギさんの最初の写真集は僕が前職にいたときに作らせてもらったという縁があって、「1冊目を大塚さんに出してもらったから、次も大塚さんに話をしてから」と、言ってくれたんです。そんなことを言われたら、もうやるしかないだろうって。
出版業界が不況だとは言わせない。明石のライツ社が希望になる日
――これから会社の規模は大きくされる予定ですか。
大塚 僕は、みんながまだ見たことがない本を作りたいだけで、会社を大きくすることには興味はないです。ただ、前からやりたかった絵本の出版もスタートしたし、いずれは小説にもチャレンジしたいと思っているので、人数的にはあと2人くらいは増えるかもしれませんが。それぐらいの人数が、僕の器量で仲良くやっていける範囲だと思っています。

大塚 ただ、出版業界自体はもっと大きくなったらいいな、明るくしたいなとは思っています。よく出版業界は不況と言われますよね。でも、僕自身はそんな風に思ったことはなくて、むしろドリームを感じられる場所です。6期のライツ社の売上は4億円ちょっとだったんですが、それを社員6人で割ると1人当たりの売上は、約7000万円。これはトップクラスの大手出版社の1人当たりの売上単価と並ぶ数字です。
これだけ売れたのは、全国の書店に本を配本してもらえる取次というすばらしいシステムがあるからできたことです。そういう出版業界のしくみももっと評価されるべきだし、出版業界をもっと明るい目で見てほしい。そのためにも、僕らが本の世界を目指す人にとって希望になれるような出版社でありたいと思っています。だからnoteでも、『明るい出版業界紙』というマガジンをやっていて、おもしろい活動をしている書店や出版社の情報を発信しています。
――『明るい出版業界紙』、素敵な取り組みですよね。私も出版業界がオワコンだとは思っていなくて、夢があると感じています。
大塚 これは本を作りながらわかってきたことなんですが、著者、編集者、ライター、デザイナー、営業、広告、広報、印刷会社、書店。これら、すべての人が今持っているポテンシャルを発揮できたら、良い本ができて売れるんです。だから、僕はできるだけみんなにお金とか時間とか判断でストレスを感じさせないようにさせたいと思うんです。
――どういうことでしょう。
大塚 お金に関して言えば、みんなにちゃんとした対価を払いたい。たとえば、ライツ社の本は、若い人向けの本が多いので、新聞広告は向きません。だから、その分のお金はすべて書店の報奨金にしたいというのが基本的な考え方です。報奨金というのは、書店が1冊売るごとに定額をお支払いする制度です。できるだけ、みんなが儲かる方法を選びたいんです。
発行点数が少ないというのも、良いことだけではないです。年々、トラックに積む物量が減ってきたせいで、取次でも輸送運賃の問題が課題になっています。そこに関してはもちろんできるだけ協力したいし、そもそも売れる本を作れば物量は増えるわけですから、それもがんばりたい。社員に対しても、もう二度とないかもしれないけど、今年は24カ月分のボーナスを出しました。10万部を超えたら、デザイナーやカメラマンにたくさん図書カードをプレゼントしたりもします。1人ひとりにしっかり還元することで、本に関わる1人ひとりを大切にしたいんです。それは僕自身も大切にされたいからなんですけど。

――お金はわかりました。「時間」と「判断」とは?
大塚 時間については、絶対的な締め切りを設けないこと。気持ちが乗らないと、いい文章は上がってきません。いいデザインも、いい写真も同じです。だから、気持ちが乗るまで待ちます。刊行時期もきっちり決めていないんですよ。その分、流行りすたりに関係なく、3年遅れても大丈夫な企画を作るように意識しています。
「判断」というのは、僕がしっかり「これがいい」「これはいらない」と決めることです。撮影現場などで、カメラマンに「念のために、あれもこれも撮って」ということは、僕はしません。良いものを撮ることに集中してもらえるようにしています。
――それって、イチ編集者ではできない改革ですよね。そうやってみなさんがポテンシャルを発揮しやすい環境を作れるのも、大塚さんが覚悟を決めて独立して決裁権を持ったからこそでしょうね。今後も明石で続けていかれるおつもりですか?
大塚 もともと、お金がなくて明石でスタートしましたが、今は明石にいることのメリットの方が多いと感じています。東京は、情報量が多くて刺激的ですよね。それに比べると、明石は何もない。毎日平和で、特に刺激もなく同じことの繰り返し。でも、だからこそ、それでも感じる世の中への違和感や課題みたいなものは、本質的な課題だと感じます。
明石の環境は、日本の大部分を占める地方の姿であって、日本に暮らす多くの人と同じ体験をしている。そういうところに住んでいる僕らが出す本だから、多くの人に共感してもらいやすいのかなと思っています。(了)

大塚 啓志郎
ライツ社 代表取締役 編集長。1986年兵庫県生まれ。2008年京都の出版社に入社し、編集長を務めた後に30歳で独立。2016年9月、兵庫県明石市でライツ社を創業。
撮影/吉田 義和
執筆/市橋 かほる
編集/佐藤 友美
シリーズ「編集者の時代」バックナンバーはこちら