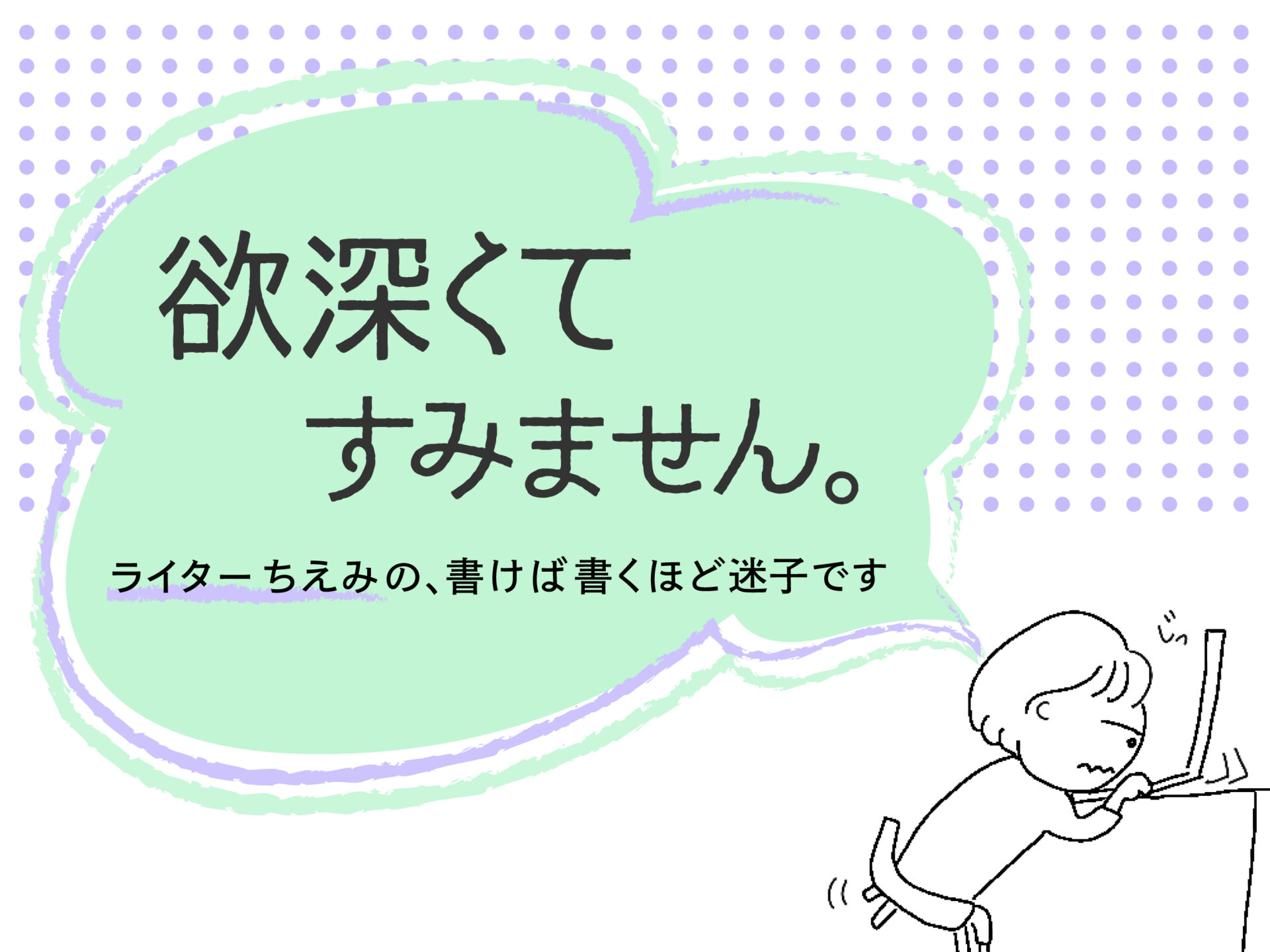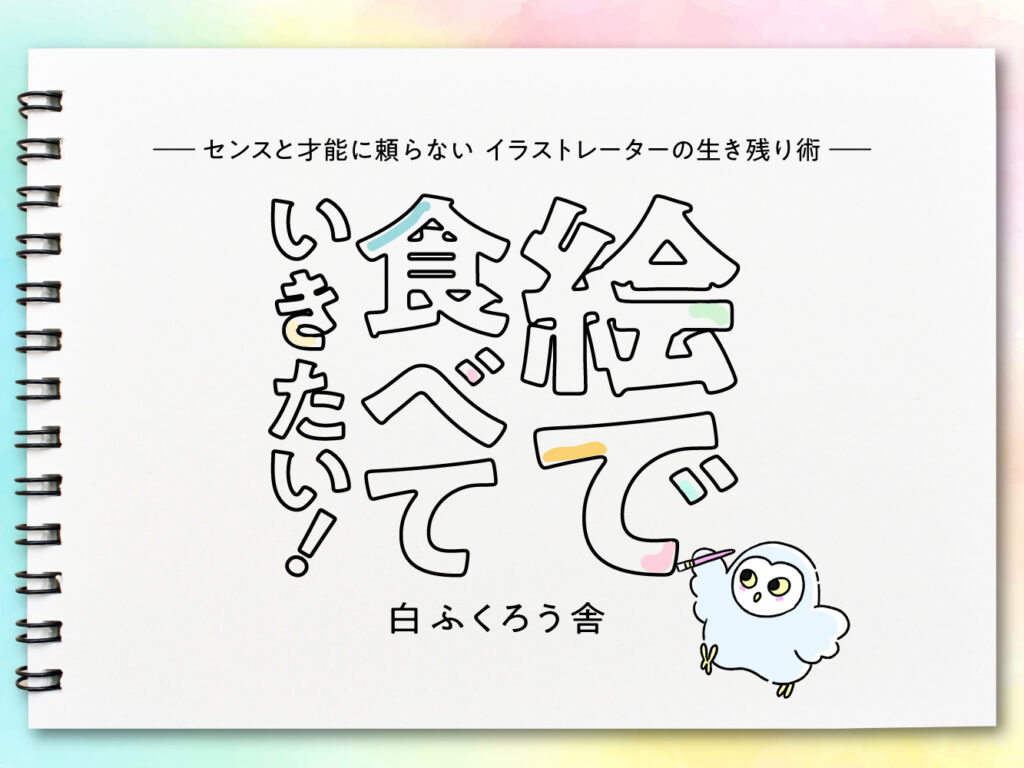
絵の仕事に「個性」は必要? 自分らしさはどう作るか【絵で食べていきたい/第29回】
絵を仕事にする際、個性は必要でしょうか? という質問を受けました。このテーマはよく話題にのぼります。なぜ個性が必要といわれるのか、実際に仕事をする上ではどうなのか、考えてみます。
これからは個性的な絵でないと生き残れない?
絵を仕事にするなら、一見してその人の絵だとわかるような個性が必要だという言葉はよくききます。特に、デジタルソフトや素材イラスト、最近では生成AI画像の登場を受けて、個性的な絵の重要性はより多く説かれているようです。
個性が大事だといわれる最も大きな理由は、他と差別化できることでしょう。誰が見ても作者がわかる絵は、描き手の替えがききません。逆に、どこかで見たような、誰が描いたかわからないタイプの絵は、より安く、よりはやく描ける人が現れたら、簡単に仕事を奪われてしまうかもしれません。
しかし、個性的なら絶対に有利かというと、そうとも言い切れないのです。特にクライアントワークでは、クライアントの意向に沿った表現が求められます。その場合、作家の個性が必ずしも優先されるわけではありません。実際、依頼を受けたのに、描き手の個性である表現部分を変えるように指示が入ることもあります。「ここを変えるなら、なんで私に依頼したの?」という描き手のボヤきは、絵の仕事をしていたら時々きくものです。
また、個性のある絵は、使い所を選ぶ場合があります。個性派俳優にその他大勢の役を与えたら浮いてしまうようなイメージです。実際の仕事では、その他大勢の役をそつなくこなせるような、誰にも嫌われない、安心感のある絵が好まれることも多いのです。
さらに、「はやっているタイプの絵」の需要も多いです。その絵を生み出したのは一握りの個性的な描き手でも、人気が高まるにつれてその影響は他の描き手にも広がり、「今どきの絵」になります。メディアで使用されるイラストは時代感が大事なので、「最近よく見るタイプの絵」の仕事は増えます。
つまり、個性的な絵は替えがきかない分、淘汰されにくい。
一方、汎用性が低い分、仕事のチャンスが限定されやすい。
このように一長一短があるので、結論は出しにくいのです。
個性的な絵が必要かどうかを論じる前に考えたいこと
また、絵の仕事に個性が必要かどうかを結論づける前に、確認すべきことがあります。
ひとつは、「個性がある絵」「個性のない絵」を、描き手は選んで描けるのかということです。
何を描いても独特の表現になる、はじめから強い個性のある絵を描ける人もいます。一方で色々な絵を描き分けられるけれど、自分らしい絵が描けないと悩んでいる人も多いでしょう。そういう自覚があるならば、わざわざ自分が苦手なほうを選ぶ必要はないと思います。
私がイラストレーターをはじめたときは、色々なスタイルの絵が描けることをアピールして仕事を得ました。とにかく最初の実績が欲しかったので、求められそうなイラストを研究してポートフォリオを作り、それが重宝されて順調に依頼を受けることができました。
その後、このままではより若くて体力もある人たちと同じポジションを取り合うことになるかもしれないという危惧と、描き続けるうちに自分の得意分野が見えてきたことで、画風を絞る方向に変えたのです。
このように、最初の方針を途中で変更することは可能なのです。自分の描きたい・描けるものと需要のバランスを見て、より仕事がしやすいやりかたでスタートする。もともとの自分のタイプを活かす仕事をしながら、必要に応じて幅を広げていけば、選択肢が増えてシフトチェンジもできるようになります。
もうひとつ確認しておきたいのは、個性のある絵とない絵を、誰が判断するのかということです。極端な話、自分の絵には個性がないと思っていても、全く違うスタイルの絵を見慣れた人たちから、とても個性的だといわれることもあるのです。
私の現在の画風は、レトロな少女漫画スタイルです。なんでも描いていた頃よりは個性的だといえるかもしれません。しかしこれも、同じような絵を描く人が少ないだけで、多くの人にとって、レトロな少女漫画風の絵であれば、誰が描いたものかはあまり区別がつかないのです。
ですから、差別化という部分だけに着目するなら、突き抜けた個性ではなくても、自分のスタイルが希少になる場所を探すだけで食べていける可能性があります。
「絵の個性の有無」で悩む以上に大切なこと
さらに、絵の個性が必要だと思う理由が「淘汰されないため」ならば、それ以上に目指したほうがいいことがあります。それは「この人に頼みたい、一緒に仕事をしたい」と思われることです。
絵の仕事で評価されるのは、画力だけではありません。画力も含めた、すべての力を合わせた「総合力」です。「個性=自分にしか描けない絵」ととらえて、絵だけで差別化しようと考えると心理的ハードルは上がります。しかし、もっと視野を広げて「自分に絵を頼みたい/買いたいと思ってもらえる理由は何か?」を考えてみるのです。
たとえば、描くモチーフにこだわりや知識がある場合。「世界中のお菓子に詳しいので、リアルやポップなど様々なスタイルで、わかりやすくおいしそうに描けます」としっかり伝えることができたら、仕事をする上で十分な強みになると思います。
この人に頼みたいと思われる理由は、スタイルやモチーフなど、絵そのものに限定しなくてもいいのです。「描くのがはやいので急ぎの仕事はお任せください。現場で描くのも得意です」と、依頼者にとって魅力になる部分をアピールすることもできます。ほとんどの仕事では、どうしてもこのスタイルの絵が欲しいという場合でもない限り、手のはやさは間違いなく強みになります。
SNSで絵だけではなく、思いや信念を投稿して、その考え方に共感した人から声をかけられることもあります。同じような絵を描ける人が他にいても、描き手自身に興味をもたせ、「この人と仕事をしたい」と思ってもらうことができれば、強力な差別化になります。絵そのものの魅力に加え、描き手の生き方や考え方も含めて発信することでブランド化する、ファンを作るという方法もあります。
そもそも個性的な絵は、付け焼き刃では成立しません。ちょっと珍しい表現の作品をいくつか描いてみた程度では、その描き手の個性とは認められないでしょう。多くの描き手は、色々なスタイルの影響を受け、模倣を重ねて描き続けるうちに自分らしい画風や表現方法が定まります。それが周囲に認知されてはじめてその人の個性と認められるのです。
同様に、生き方、姿勢というものもいきなり出来上がったりはしません。戦略的に自分のキャラクターをたてるという方法はあります。しかしその場合も、そのキャラクターが認知されるまでにはある程度の時間と労力がかかります。
まずは自分に描ける絵をたくさん描き、それを求めている人を探す。そうして仕事を得ながら、自分らしい表現や仕事のやりかたを磨いていく。地道なことですが、それを続けていけば、より仕事の選択肢を広げながら、「あなたでなければ」という強みも身について来るのだと思います。
文/白ふくろう舎
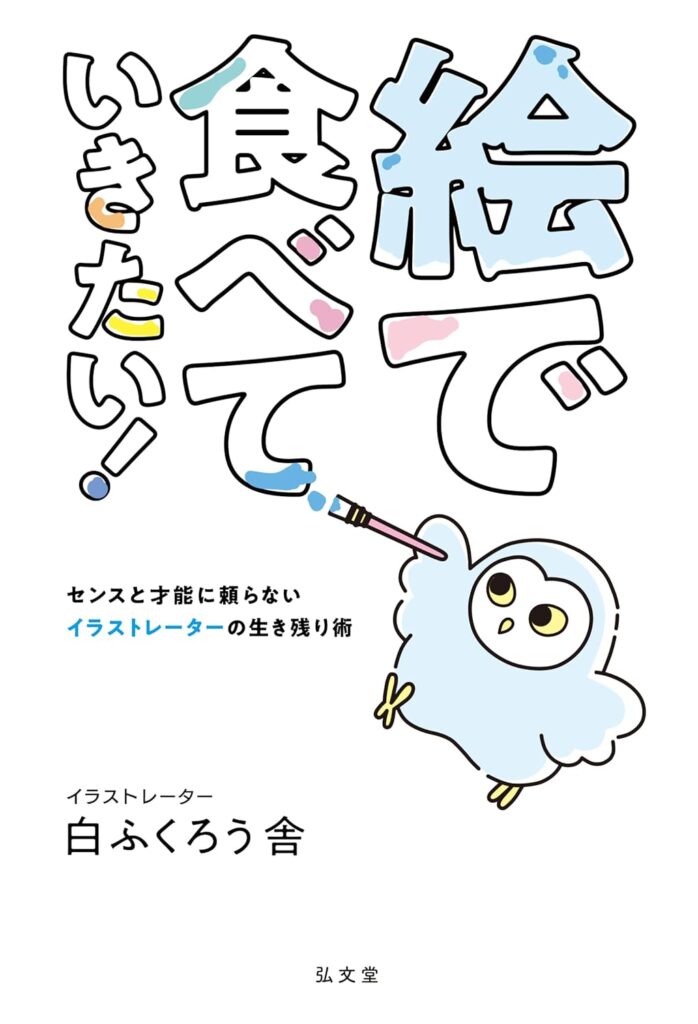
【この記事もおすすめ】