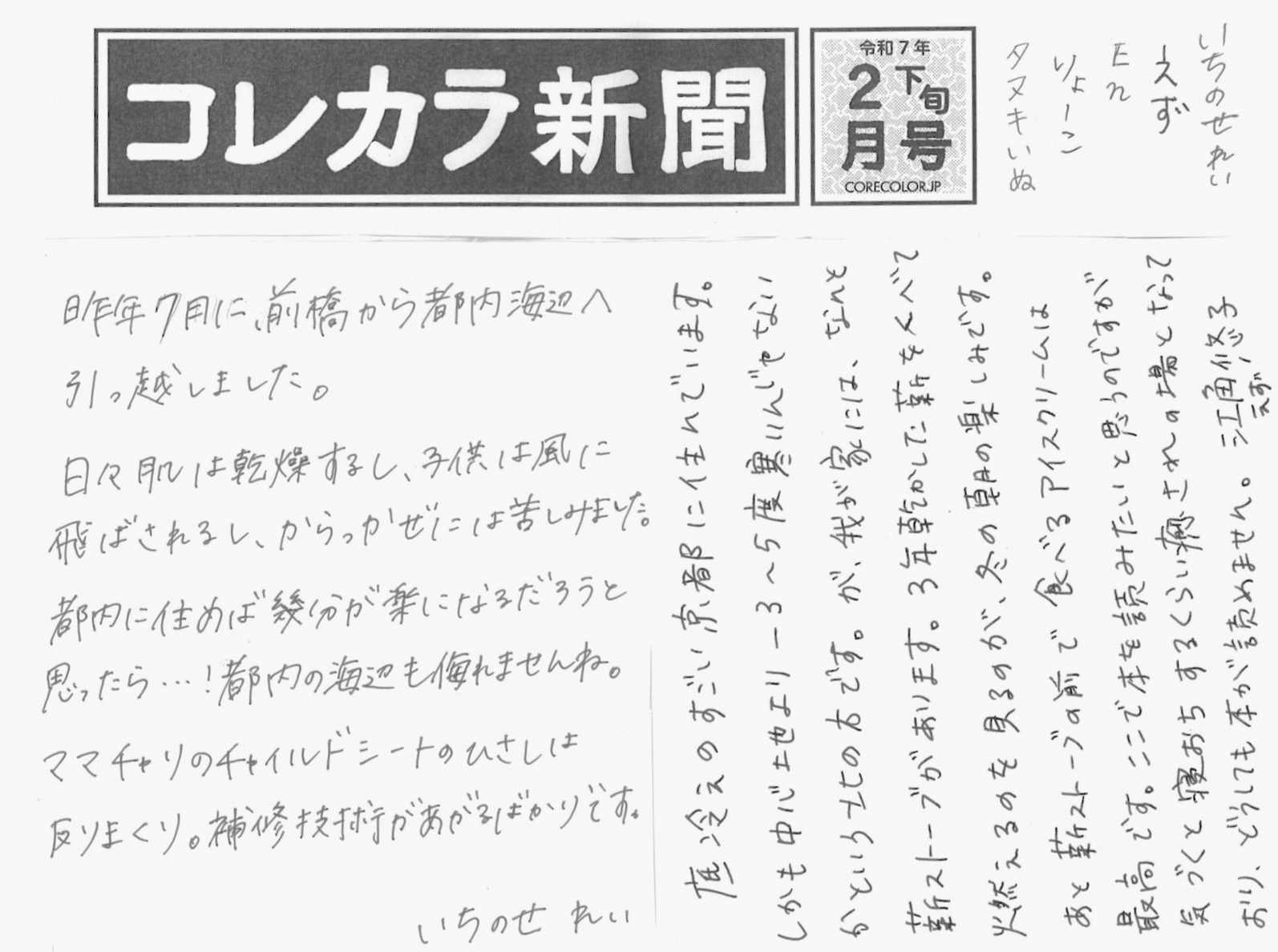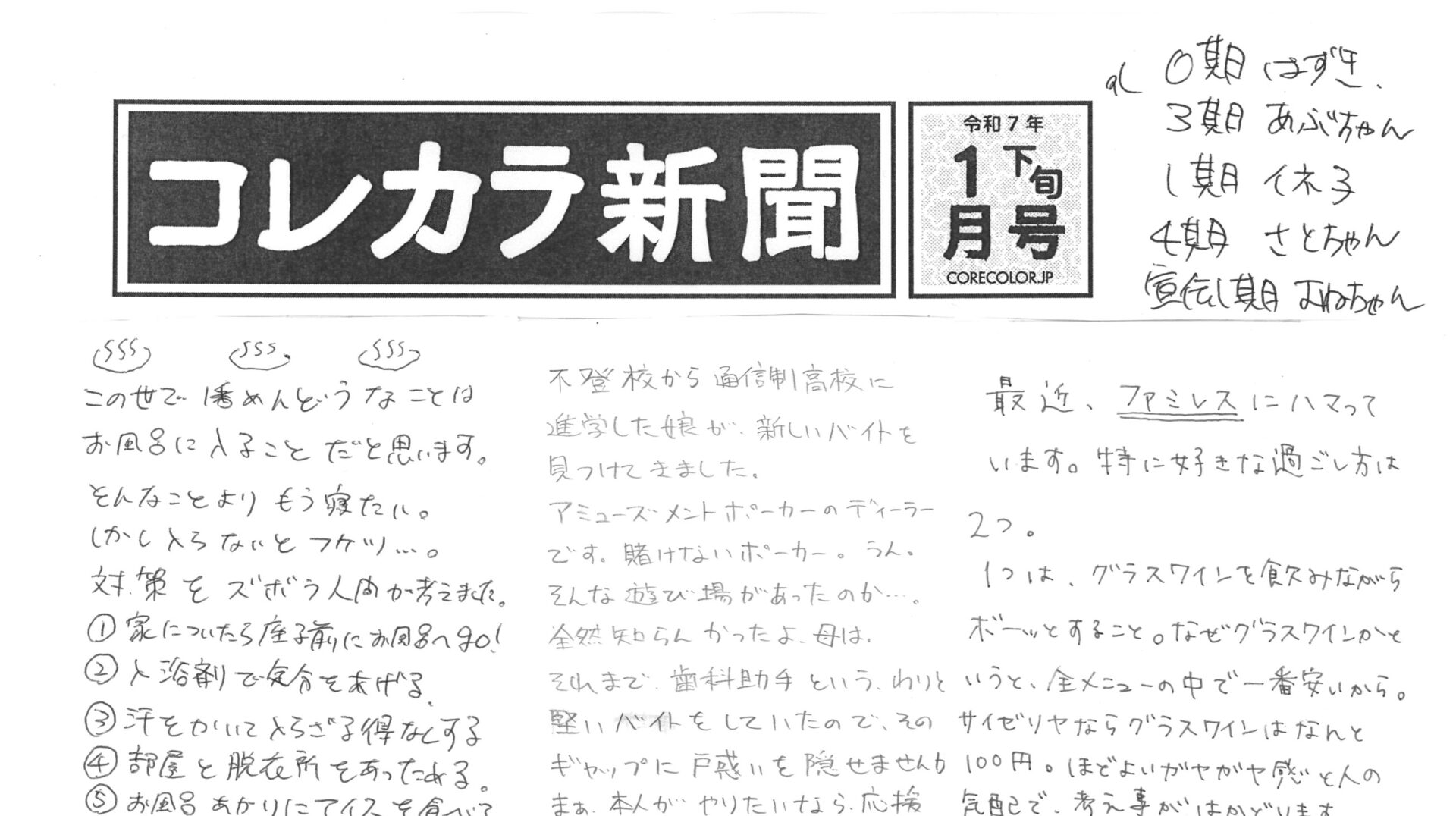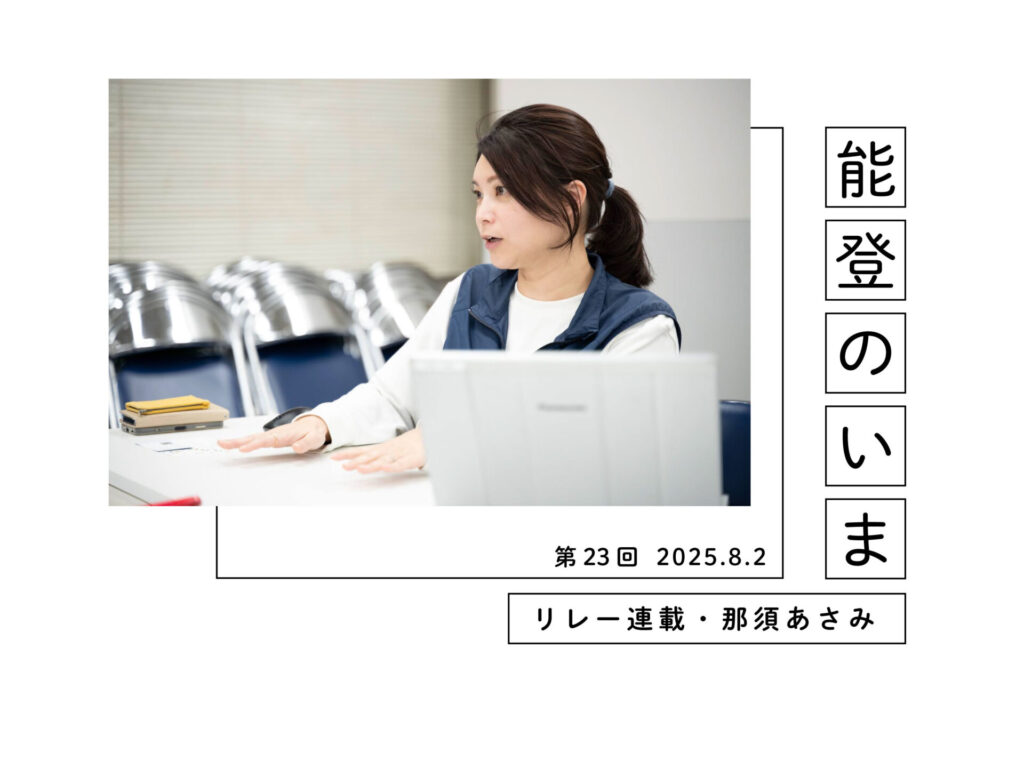
行政に伴走して被災地支援を行うNPO。「能登の震災と豪雨で、今まで以上に官民連携の重要性を感じた」ピースボート災害支援センター・辛嶋友香里さん【能登のいま/第23回】
能登半島での震災から9ヶ月後に起きた豪雨災害では、官民が連携して災害対応に当たった事例が多くあった。その結果、より被災地のニーズを汲んだ支援や制度運用が実現したという。県や市町(しまち)と連携する民間団体に、災害支援に特化したNPOがある。災害対応の知見と実績が豊富なNPOは、時に被災者の支援にとどまらず行政の支援も担う。公益社団法人ピースボート災害支援センター(PBV)も、能登半島地震では複数の市から協力要請を受けた。国内外で支援を行なってきたPBVによる行政支援とは。そして官民連携の重要性が明らかになった今、本当の連携のために必要なことは何なのか。能登の震災と豪雨対応で、官民連携の加速を感じたと話すPBV・コーディネーターの辛嶋友香里さんに聞いた。(執筆/那須 あさみ)
災害支援で存在感を増すNPOと、社協、行政が「朝会」で連携
日本国内のNPO法人の数は49,381法人(2025年5月現在)。その活動内容はさまざまで、災害支援に特化したNPOも存在する。そのうちのひとつ、ピースボート災害支援センター(以下、PBV)は2011年の設立以降、国内外100以上の国と地域で災害支援を行なってきた。能登半島地震の際も、発災当日から情報収集を行い、翌日には現地で先遣チームによる支援活動を開始。現在も珠洲市、輪島市で活動を継続している。

能登半島地震においては、震災後から内閣府や県といった行政と、民間団体双方が参加する会議が実施された。PBVの一員として会議に参加してきた辛嶋友香里さんは、「国、県レベルでの方向性・方針を知った上で、現地のニーズを直接伝えることができました」と話す。
さらに豪雨水害後は、浅野大介・石川県副知事が新たに「官民連携会議(通称・朝会)」を主導したことによって、スピード感を持って課題や情報を共有し整理することが可能となった。「副知事が自ら声をあげ、プライベートな早朝の時間を活用して横の連携が取れる場を作ってくれたのは、すごく協力的な形だと感じました」と、辛嶋さんは朝会の意義を振り返る。
特に能登の場合は二重被災という過去に例の少ないケースだったため、地震と豪雨一体で被害を認定する新たな支援が必要となった。その制度設計をする際に、現場の意見を伝えられたことは大きかったという。
「被災者の不利益になることがないよう、制度が運用される前に懸念点の再検討を提案できたことがいちばんの成果でした」
災害対応の方針や制度を決定する県や国に上がってくる情報は、確実性の高い情報が優先されるので、どうしても取捨選択されてしまいがちだ。そのため県や国が示す決定や制度が、現場の課題とは噛み合わないことも多く、「ボタンをかけ違えてしまう」こともあると辛嶋さんはいう。その点、今回は「朝会」で県側と直接話し合えたことで、被災者が混乱するような制度になるのを未然に防ぐことができたという。
被災地支援の専門性と実績を生かして行政に伴走
PBVの活動内容は、物資調達から避難所の運営、支援情報の一元化と調整、さらには行政支援など多岐にわたる。その専門性と実績から、行政から支援の要請を直接受ける機会も多く、能登半島地震においても珠洲市と輪島市からはPBVへ直に協力要請があった。
今回のケースに限らず、PBVは役場の各課が持つ課題をヒアリングし、行政に対して伴走型の支援を実施している。
「官民での連携以前に、県や市町の中での情報連携がすごく難しいんです。だから私たちが現地の課題や要望を伝えても、行政内で全体に共有されず、本来届くべきところまで情報が届かないのが現状です」
まず各課のキーパーソンを見つけ、それぞれが抱える課題を聞き出す。次にそれを解決できるPBVのリソースを伝え、一緒に支援を行う。伴走するうちに、現場や各課の情報が集まってくるので、それらの情報をまた係部署に伝えていく。これが、PBVが行政に対して行なっていることのひとつだ。
「もちろん第三者だからこそ連携を促せる側面もあります。でも本来は行政内で連携が取れていれば、現地からの情報をもっと迅速に共有し、適切な被災者支援が行えるはずです」と、辛嶋さんは指摘する。【見出し】
震災後に築いた関係性が連携の取れた支援へ繋がる
2024年9月21日に発生した豪雨後もPBVの活動内容に大きな違いはなかったが、被災地では再び被害状況の把握を行わなければならなかった。
「地震災害の復旧作業がやっと少し落ち着いてきたタイミングで豪雨災害が起きて、0というよりマイナスからのスタートになってしまったというのが、正直な感想でした」
地震と比較して、水害はマンパワー、スピード感がより必要とされる。というのも、流入した土砂を放置していると、家屋の腐食やカビなどが発生するからだ。また水害の場合、できるだけ早く適切な処置を行なうことで解体せずに住める住宅も多い。安易に解体を選ばずに、地元にとどまる住民を増やすためにも住まいの再建に注力する必要性があった。
このような状況下で、震災後に数カ月かけて積み重ねてきた関係性が生かされた。行政、社会福祉協議会(以下、社協)、各支援団体が連携し、それぞれが役割を持って支援を進められたという。

また豪雨以前ではあるが、2月5日には内閣府防災担当から県に対してNPOとの連携を促す通知が出るなど、被災地でのNPO、NGOの必要性が理解されてきたことも大きい。「被災地全体を把握しコーディネーションができる団体と、どう連携するのが被災地や被災者にとって最善かという知見を持つ自治体が増えてきた」と辛嶋さんは感じているそうだ。
その証拠に、輪島市からの協力要請のきっかけは、対口支援(たいこうしえん)の総括支援員(※)からの「避難生活の支援に長けている団体はいないか」との呼びかけだった。
また内閣府の通知でNPOの名称を個別に記載したことで、自治体にとっても民間団体を頼りやすくなったのではないかという。
「団体名を挙げたことで、何万とあるNPOの中から信頼のおける団体が明確になったと思います。資源が限られる市町村にとっては、何をどこに頼めばいいかの判断材料にもなったのではないでしょうか」
※:被災自治体へ他自治体から応援職員を派遣する仕組みを対口支援と呼び、特に被害の大きい自治体には、災害対応経験のある職員による総括支援チームが派遣される。チームを取りまとめる職員は災害マネジメント総括支援員(GADM)と呼ばれる
相互理解の先に本当の官民連携がある
官民連携において、特に災害対策本部会議、保健医療福祉調整会議などの重要な会議にNPOが呼ばれるようになったことは大きな前進だ。ただしこれはあくまでPBVとしての経験で、他の団体をそのような場で見ることはまだまだ少ないという。
「もっと多くのNPO、NGOが専門職として参画できる仕組み作りの必要性を感じています。加えて、災害後のまちづくりや防災に関する検討会等にも、同じことが言えます。専門家として呼ばれるのは研究者やコンサルタントがほとんどで、住民の声が反映されているとは言えません」
こうした現状から、どこの被災地でも復興ビジョンを考える際に「誰の声を聞いているのか?」との疑問がたびたび投げかけられるそうだ。被災経験のある住民か、あるいは住民の声を整理して代弁できるNPOか、「生の声」を届けられる人が参画できる仕組みが求められている。
一方で災害時には自治体に対して批判的になりがちな団体もあり、対立構図が生まれやすい。それを避けるためには、「お互いが支援できる範囲や文化を理解し、協力して被災地支援にあたっていく必要がある」と辛嶋さんはいう。
「NPO側と行政側の相互理解が進めば、自治体がカバーできない部分に対して、NPOが支援メニューを充実させられます。そうすればより効率よく漏れのない支援ができるのではないでしょうか」
制度や法律の範囲内でしか動けない自治体の苦悩や葛藤は、住民やNPOからは見えづらい。民間団体でありながら、伴走型の支援をしてきたPBVだからこそ知っている行政の姿もある。それゆえ民間団体と自治体、双方がお互いの事情を理解した上で連携することが、より被災者に寄り添った支援への近道だと辛嶋さんは考えている。

同時に官民連携の促進のためには、NPO、NGOに対する認知度と信頼性の向上も求められる。
「海外のように、災害支援におけるNPOの活動や連携の必要性を認知してもらうためにも、専門職として共通の名称がほしいと切に願っています」
海外では災害や紛争の発生時に人道支援活動に従事する人は「エイドワーカー」と呼ばれ、一般的にも広く知られている。一方、辛嶋さんの役職名は「コーディネーター」。何をしている人なのか伝わりづらく、NPO関係者には「現地コーディネーター」、自治体には「現地責任者」と名乗るなど、相手によって呼び方を変えることも多い。
またNPO育成のためのガイドラインの設定も、官民連携のために有効ではないかという。NPOにとっては、信頼性向上のために目指すべき方向性が定まり、団体の育成も促進される。自治体にとっては、指標を設定することで信頼性の高い団体との連携が可能になる。
専門職としての呼称も、参画の仕組み作りも、辛嶋さんがPBVの活動に携わるようになった14年前から変わらず感じている課題だという。東日本大震災の発生時に海外にいた辛嶋さんは、テレビで津波の映像を目にし、「これはすぐに帰らなくては」と帰国を決意。日本に戻って数日のうちにボランティアとして宮城県石巻市へ向かったという。そこでちょうどPBV設立の動きがあることを知り、当時たまたまフリーだった辛嶋さんも運営側として参画。
「1ヶ月ぐらいなら手伝えるよ、と参加したはずが、振り返るひまもなく気づいたら10年以上経っていました」
災害支援に携わっていると、「活動のきっかけは?」とか「モチベーションは?」と聞かれることも多いそう。「でも本当にたまたま飛び込んで、いまに至るんです」と辛嶋さんは笑う。災害の現場でひたむきに活動してきたからこそ、NPOの参画がなかなか進まないことへの課題感は切実だ。
現在、全国で実施されている内閣府による避難生活の支援員養成の研修に、PBVは監修・講師として参加している。研修では、「国と県と市町村自治体、NPO、市民が同じ目的を持った取り組みを行い、それぞれがどういう考えのもとどう動くのかを初めて知った。だからこそ、災害時に各関係者がそれぞれ尽力していることを実感・体感できた」との声が多数聞かれたという。
この経験からも、情報が錯綜する災害時ではなく、平時から顔の見える関係性を作り同じ目的を持った取り組みをすることの意義を辛嶋さんは感じている。
「それぞれの事情がわかっていればお互い譲歩できるところも見えてくる。その上で協力して支援を行う。それが本当の連携、協働だと思っています」
※本インタビューは、一般社団法人RCFが公開している「「奥能登豪雨災害 官民連携の効果と課題」レポート」作成を目的として実施されました。本インタビューおよびその他関係者へのインタビューを踏まえた内容については、レポートにて掲載されています。(公開先:PR TIMES)
【この記事もおすすめ】