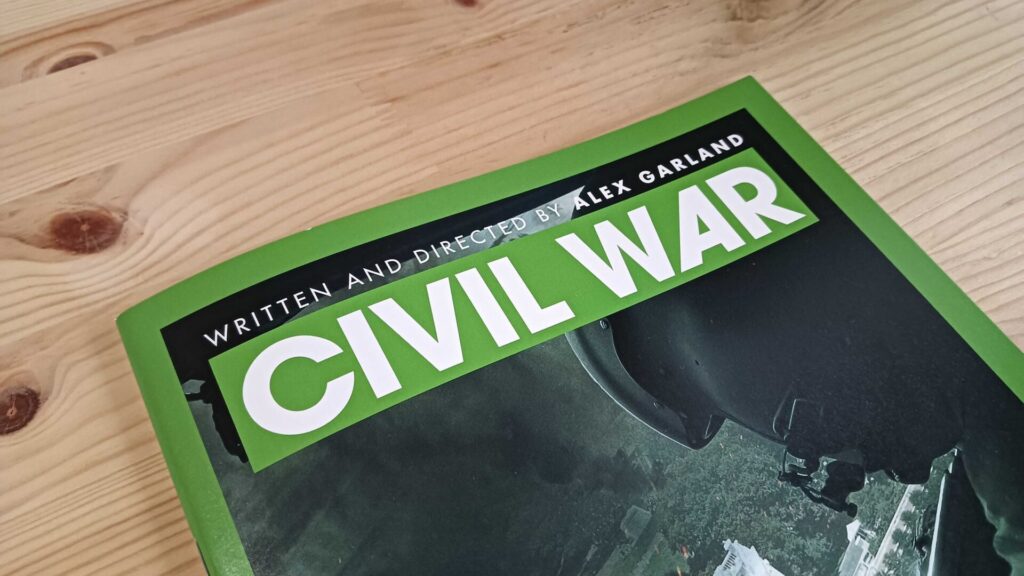
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」は現実にも見るアメリカ分断のその先
3日間のうちに2度、この映画を観に行った。こんなことは初めてだ。
トランプ大統領が誕生した時ほど、米国人の意見が極端に割れた状況を僕は見たことがなかった。露骨に批判的な歌を歌う音楽アーティストがいた。一方で、彼が大統領でなければ生きていけないという人もいた。人の意見とはこんなにも両極端に割れるものかと思った。
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、去年アカデミー作品賞を受賞した「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(略称:エブエブ)」などで知られる映画制作会社A24が作った最新作だ。戦争ものが大好きな僕は特にあらすじなどを確認せずに、トレーラーを見てすぐに観ようと決めた。作中のアメリカでは、アメリカ50州のうち19州が政府から離脱し、政府軍 対 反政府軍で内戦が起きている。南北戦争の再来だ。映画を観て、この状況は今のアメリカであれば全く可能性がないわけではないと思った。というか、映像として観るまで、この状況が想像の範囲になかった自分の感覚を恥じた。平和ボケしているぞ、自分。
この映画の視点が新鮮だ。戦場カメラマンの主観的な角度で戦場を見ていくのだ。すでに歴史に残る写真も撮っているベテラン・カメラマンのリーと、その馴染みの記者であるジョエル、それに加えリーの恩師であるサミーと、若手カメラマンのジェシー。この4人が1台の車に乗り込んで、転覆間近の大統領側の陣営のワシントンDCを目指しながら1,379km、戦場を渡り歩く物語だ。
ロードムービーの形で様々な場所に辿り着き、時には4人の命も危険にさらされながら物語は展開していく。その1つ1つのイベントがショッキングで、いちいち再生を止めてうーんと考えたくなるほど胸をえぐっていくのだが、残念ながら映画館なので一時停止はできない。心の整理がついていなくても、旅は次の場所へと続いていく。
観ていくうちに、現実の状況から考えてもこれは決して絵空事ではないということが徐々にわかっていく。この実感が深まっていく感覚が、この映画で最も注視すべきポイントだ。自分が住んでいる地域内でミサイルが飛び交う光景は、想像を超える恐怖ではあるが、現在のアメリカを見ていると、起こらないとも限らないギャップ。「アメリカがこうなってしまう状況に、王手をかけてしまっていませんか?」というメッセージが、そこにはある。
兵士にぴったり身を寄せてついていき、震える手でカメラを握りしめ、銃弾や炎、建物の破片が飛び交う中、弾が飛んでくる方向を正面にカメラを構え、物陰からひょいひょいと飛び出すリーとジェシー。どんな気持ちだろう。でも段々と、恐さよりも使命感の方が上回ってきてしまう感覚が伝わってくる。これは、観客である自分の脳内でもドーパミンが分泌されているのでは? と思うような体験だ。(僕は映画館から深夜に帰ってきても目が冴えてしまって、この原稿をそのまま朝方の5時までかけて書いた)
リー演じるキルステン・ダンストさんは、2002年〜2007年の「スパイダーマン」シリーズでヒロインをつとめた。当時は美しく爽やかな印象が強かった。今作で演じるリーは過去に自分が通り過ぎてきた戦場の悲惨さ、惨状を脳裏に焼き付けたままファインダーをのぞく。ときどき1人でたたずむ姿は、自分がそれらを”撮る”ということについて、いまだに折り合いをつけられないでいるようだ。無言で正面を見つめるという表情だけで、自分のこれまでの写真が母国の争いを防ぐことはできなかったという無念さや悲しみを見事に感じさせる。
戦場でカメラを抱えている時は、瞳孔を開いたままでずんずんと前に進み、時には兵士に首元を掴まれて引っ張り戻されるほど積極的な若手カメラマンのジェシー。戦場から戻ると、隅っこで小さくなりボーっと1点を見つめるようなシーンが多かった。初めて戦場で仕事をしたら、きっと皆あんな風になってしまうのではないだろうか。観ているこちらは、あどけない彼女が銃弾に倒れるシーンだけは見たくないという思いが映画の最後までずっと続く。さて、結末やいかに。
ちなみにジェシーを演じるケイリー・スピーニーさんは、上映中の「エイリアン:ロムルス」では主演をつとめている。僕はこちらの作品も鑑賞したのだが、その時は、本人のパーソナリティが気になるほどのインパクトはなかった。しかし本作では主演が彼女だったとしても違和感がないくらいに存在感が強い。僕は映画館を出たあとにすぐに検索して彼女のインスタグラムをフォローした。
1つの車で何日もかけて移動していたら、4人はとても仲良くなっていくことが想像されるだろう。実際に、20代のジェシーを他の3人はどんな状況でも気にかける。しかし、リラックスしたシーンでも、誰かが誰かに身を寄せて眠ったり、包容して頭を撫でたりするシーンは一切出てこない。1人1人が独立した人間、いち仕事人として互いと関わり、あくまで自己責任で旅をする。それはそのまま仕事に対しての愛情であり、4人が互いを愛するということともイコールなのだ。この潔さがなかったら、僕は短期間に2度も鑑賞できなかったと思う。
ベテランカメラマンのリーは、最終的には自分を犠牲にしてある行動に出る。少しでもそそうをしたら自分の体に穴が開いてしまうかもしれない状況で、彼女は行動に出る。撮ることによって起こっていた彼女の葛藤は、ここで結実する。人間のしわざとは思えない光景の中にいても、彼女は人間の心を失わなかった。
選挙で意見が極端に割れているアメリカという国を見て、正義とはなんだろうと思う。そんなモヤモヤした気持ちが続くここ数年、私たちは何を感じ、何をすべきなんだろう。確固たる存在の国家というものも当たり前にあるわけではないということを、この映画は自分の頬を至近距離で銃弾が通り過ぎていくかのようなリアリティとともに考えさせてくれる。
【この記事もおすすめ】







































































































































