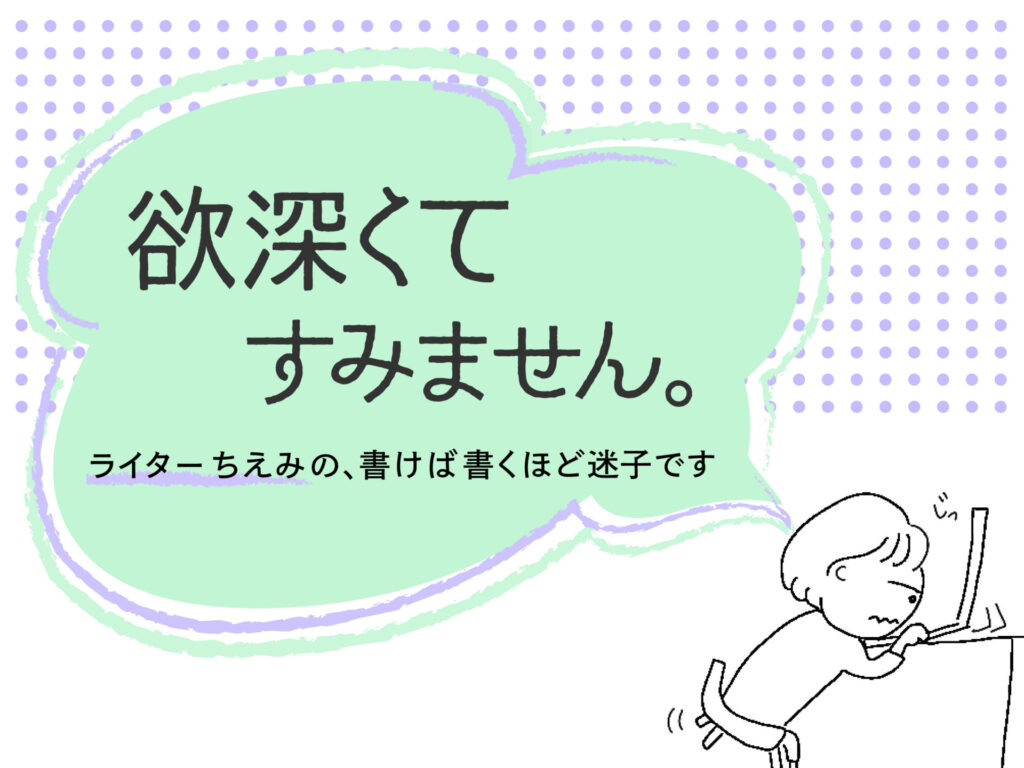
「わからない」は恥ですか。罪ですか。取材に行く前の準備ですべきことは【連載・欲深くてすみません。/第27回】
元編集者、独立して丸8年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日は、取材前の下調べや質問の準備をすることについて考えているようです。
なるべく賢そうに見られるように、これまで全力で自分を装い、取り繕ってきた。学のなさを隠すのが、癖になっているのだ。部活や趣味に没頭してきたことが言い訳になるかわからないが、机に向かって勉強するのをできる限り避けてきた結果、あらゆる学問の前提となるような一般教養や、時事用語にめっぽう弱い。
勉強不足で、これまで幾度となく恥をかいた。大学1年生のとき、先輩たちの会話から伝説的なオーディション番組の名前が聞こえてきたので「それ、私も観てました! ゴマキの初登場は衝撃的でしたよね!」と割って入ったところ、彼らが話していたのはASAYAN(アサヤン=モーニング娘。らを輩出したオーディション番組)ではなく、ASEAN(アセアン=東南アジア諸国連合)についてだった、という悲しい思い出がある。憐れみの混じった眼差しを注がれて、アセアンってなんですか、とは、とても質問できなかった。
しかし30代後半になった今、かつて生徒や学生だった頃とは比べ物にならないほど、みずからすすんで机に向かい、勉強している。ふしぎだ。10代の私が気づかなかった、学ぶことの楽しさを、今になって感じている。
取材準備の話です。
*
ここ数年で仕事の幅が広がり、もともと専門にしていた領域だけでなく、さまざまな分野でインタビューとライティングの依頼をいただくようになった。
「東南アジアの政治経済について、専門家に取材してもらえませんか?」
とは、まだ依頼を受けたことがないが、万が一お声をかけていただいたとしたら、「今のところアセアンが何かよくわからないレベルですが、大丈夫でしょうか?」と正直に聞く。ただ、このような依頼の場合、その分野の専門ライターではない私に声をかける時点で、編集者さんの狙いはほぼひとつである。
「よくわからない、知らない読者にぜひ届けたい企画なので、その視点から取材してほしいんです」
知らない私には、知らない読者の「わからない」がわかる、という強みがある。政治経済の専門誌なら、私にお呼びはかからない。知らない人の目線を求められている。
しかし、とはいえ、です。
相手はその道の専門家。質問するのも話を聞くのも、一定ラインの知識がなければお話にならない。「アセアンってなんですか?」と質問しても、決まった時間内に、原稿が書けるだけの話を聞くことはできない。
だから取材当日までに、素人なりに必死で勉強することになる。最近では取材後の執筆よりも取材準備のほうが、時間がかかることもざらである。
ただし、取材準備のための勉強は、10代の頃の“勉強”とは根本から質が違う。
なにせ「わかる」必要はないのである。これから、その道のプロフェッショナルに教えを請うのだから。むしろ中途半端にわかったふりをするよりも「この部分がよくわからなかったのですが、くわしく教えていただけますか?」とまっすぐ聞けるほうが、意義があるはずだ。
ということは、自分の「わからない」の解像度を高めることが、取材準備の勉強の目的となる。
だから私は取材の依頼をいただくと、その分野の入門本や雑誌記事などを山ほどかき集めてくる。まずはざっと目を通し、「おそらくこのあたりが、この分野の前提知識だ」「たぶん、このできごとが、エポックメイキング的なやつだ」と、ざっとあたりをつける。
そして「なんかよくわからない」の「何」が「どう」わからないのかを言語化していく。「わかるようでわからない」ところを素直に白状し続ける。自白に次ぐ自白。
取材者としては、簡単にわかったふりをすると、価値がなくなってしまう。曖昧な「わからない」を、たしかな「わからない」にしていく。
この作業は、ふしぎな高揚感を伴う。
「わからない」ことをまるで“罪”のように思っていたのが、そうじゃない、とわかっていく。「わからない」は可能性だ。まだ見ぬ世界への扉だ。
自分の無知が、恥ではなくなっていく。
*
かつての私は、“勉強”とは「答えを知る」ものだと思い込んでいた。しかし、今の私にとっての勉強は「ふしぎを前に立ち止まる」もしくは「ツッコミを入れる」ようなものだ。
本や雑誌の、さも「これはこういうものです。ジョーシキです。当たり前です」と書かれている文章をスルーせずに「何それ、なんで? ふっしぎ〜!」と立ち止まる。
「当たり前です、って顔してるんじゃないよ! わかんないよ!」とツッコミを入れる。
「わからない」でもいい。
「わからない」が、いい。
あ〜、アセアン、アセアンっすね〜、アセアンいいですよね〜、と先輩の前でわかったふりをしている大学1年生の頃の自分に「わからない、って言っていいんだよ」と教えてあげたい。
【この記事もおすすめ】
文/塚田 智恵美





































































































































