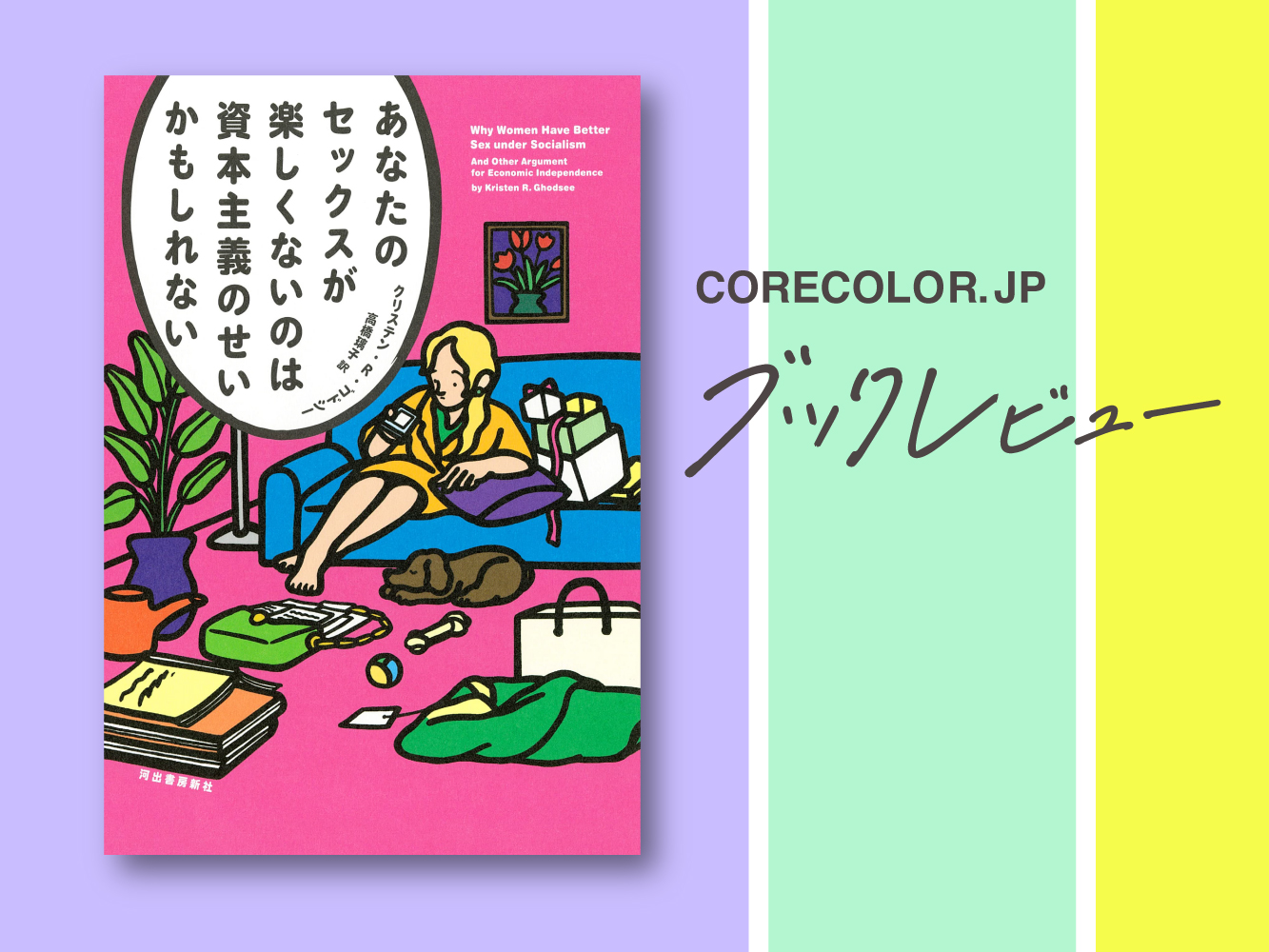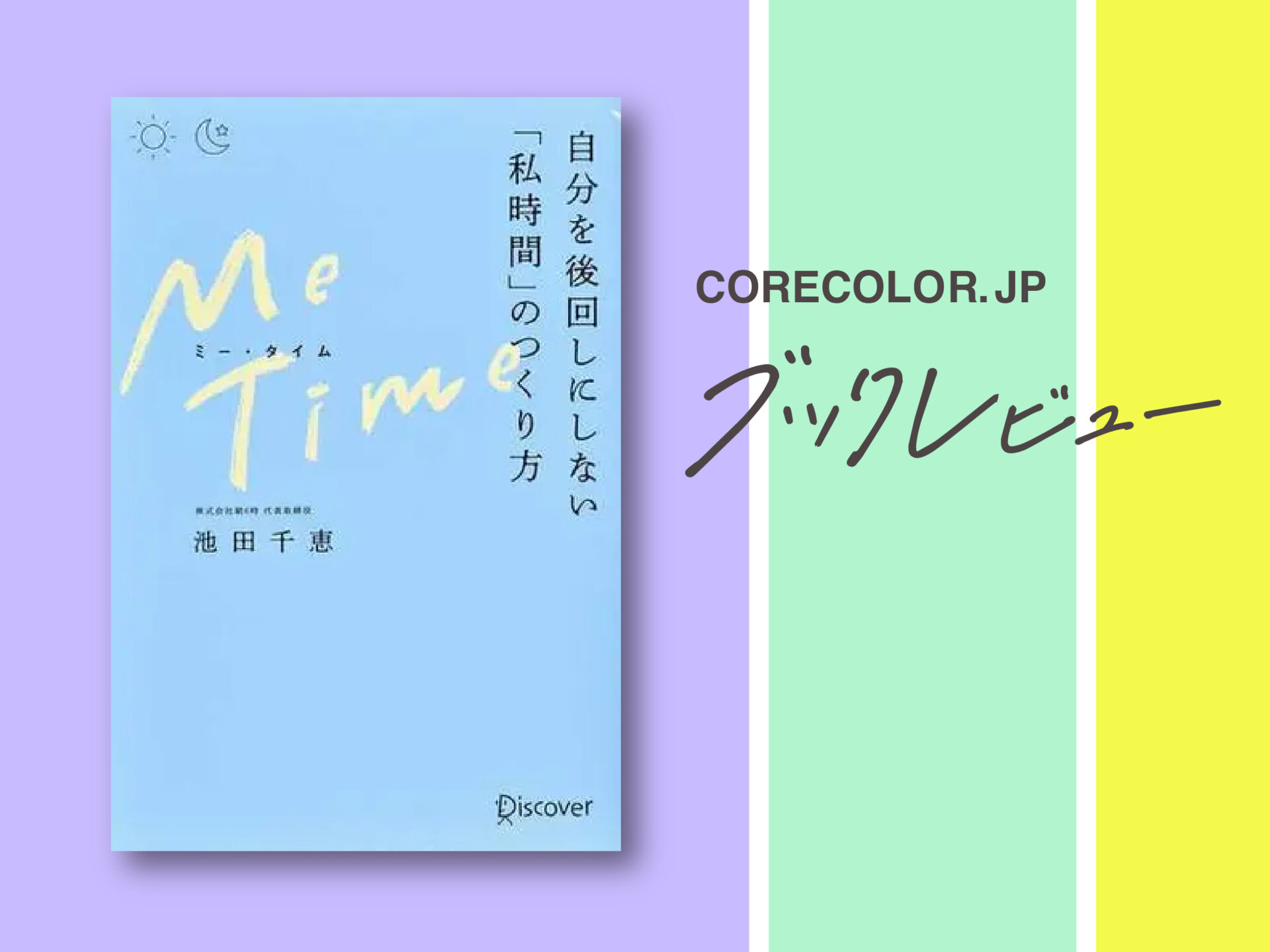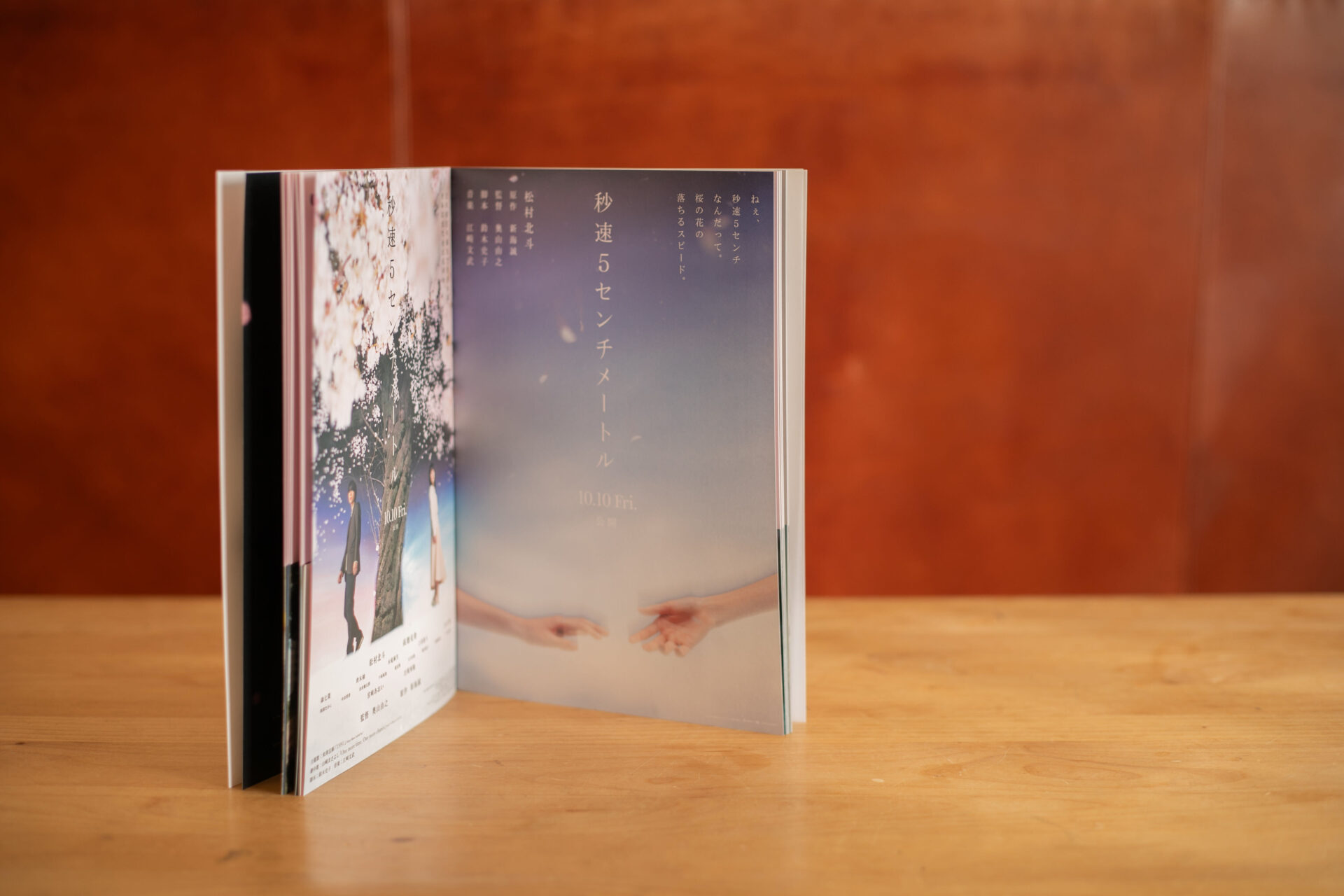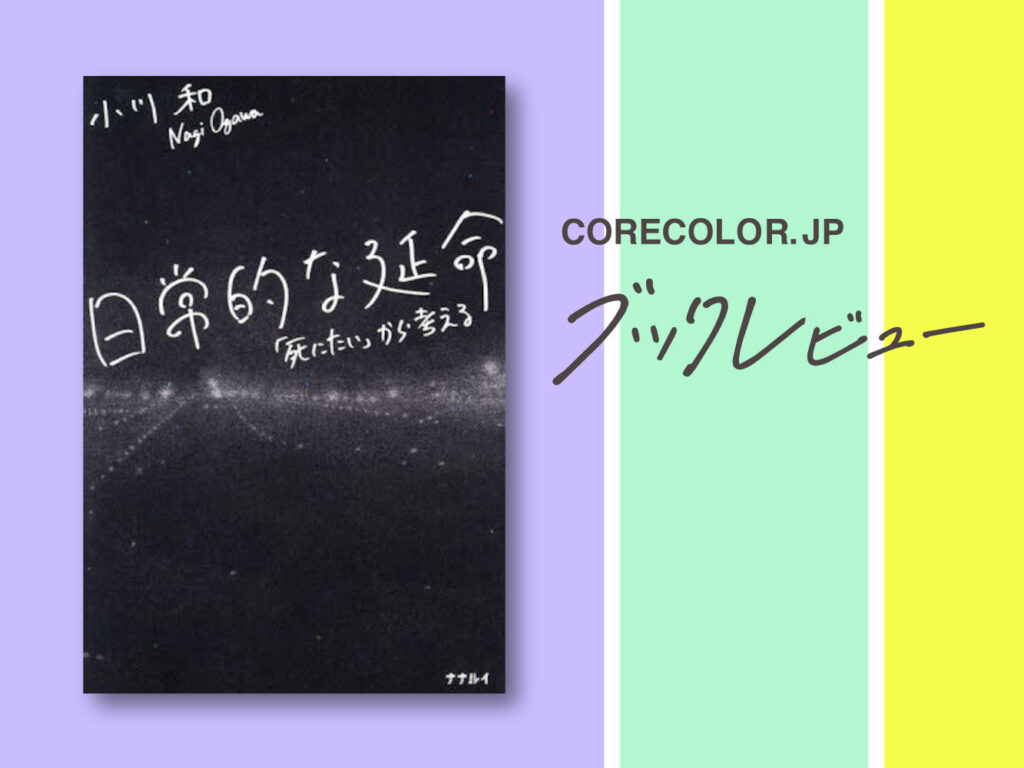
承認欲求に隠れた“安心”欲求『日常的な延命「死にたい」から考える』
「このまま消えてしまいたい――」
朝5時45分。目は覚めたけれど、体を起こすにはまだ少し早い時間だ。
布団の中でぼーっとしていると突然、消えたい感情に飲み込まれる。ずーんと重く、ざわざわと落ち着かない心とは裏腹に体は軽快だ。体を起こしてシャワーを浴びに行く。熱いお湯で全身を流した後、濡れた体をタオルで拭きながら、どうして消えたいなんて思ってしまうのかを考えてみた。
しかし、答えはまったくわからなかった。そして、シャワーを浴びてすっきりしたら、その黒い感情もどこかに流れていってしまったようだった。
消えたいと思うのは、私にはよくあることだ。たとえば、出先で仕事を終えて1人で家まで帰る道中や家で大切にしている植物を1人でじっと眺めているとき。そんないつもの生活の、どうってことのない瞬間に消えたい気持ちが降って湧いてくる。
ところが最近、あまりにも頻繁にその感情が顔をのぞかせてくるので、何か根本的な対策が必要なのではと考えた。しかし、どうすればいいのかわからない。
そんなとき、本書と出会った。サブタイトルの『「死にたい」から考える』というフレーズに惹かれ、読んでみることにした。
『日常的な延命』は「死にたい」について様々な角度から分析、考察している本だ。その内容はセンシティブではあるものの、誰もが少なからず興味のあることではないかと思う。なぜなら、人間は誰もが陰と陽の部分を持ちあわせているからだ。「陰」のコアな部分にまっすぐと向き合っている本だと感じた。
実際に本書を読んで、消えたいと思ってしまう理由を明らかにできた。消えたくなるのは、自分の抱えている「安心欲求」に気づいていなかったからだと思う。
著者の小川和(おがわなぎ)さんによれば、SNSで見かける「死にたい」発信には、承認欲求と安心欲求の2つの願いが込められているという。承認欲求は認められたい願望、安心欲求は安心したい願望のことだ。そして実は、それら2つの意味合いが「承認欲求」という言葉に混在しているのではないかと、小川さんは仮説を立てている。
若手批評家である彼が問題視しているのは、承認欲求という強い言葉に安心欲求が隠れてしまうために、死にたい気持ちを抱えている人が本当は安心を求めていることに誰も気づかず、適切なアプローチがなされないことだ。
この考えに触れて、私は学生の頃を思い出した。
高校生だった私は、他人とうまく打ち解けられない悩みを抱えていた。同じグループに所属して毎日のように顔を合わせるメンバーにさえ、どう振る舞っていいのかわからなかったのだ。たとえば、グループ3人組で歩いていると無意識に歩みを遅めてしまい、2:1の構図(私が1人)にしてしまう。
その癖は「自分はここにいたらいけないんじゃないか」という不安からきていたように思う。私はそういった何気ないシーンで「ここにいてもいい」と安心できず、孤独な時間を過ごすことが多かった。
ただ、不安は私の原動力にもなっていた。
大学2年生の頃だったと思う。学生たちから敬遠されていた辛口で評判の教授のところへ行き、勉学について教えてほしいと掛けあったことがある。卒業後の進路が不安だったからだ。教授はうれしそうだったけれど、同じ学部の学生に「意識高い系だね」と皮肉を言われてしまった。
私は他の誰もがしないような行動をして悪目立ちしてしまう自分のことを、承認欲求が強い人間だと感じていた。そして、そのことを自虐的に思うことしかできず、どうすることもできなかった。
そのため、いつか自分が誰からも必要とされるような立派な人間になったときに、初めて承認欲求が満たされて、周りと打ち解けられるのだろうと考えていた。だから、いつも無理をしていたと思う。厳しい環境に身を置いて、早く成長しなければいけないと自分に鞭を打っていた。
ところが本書を読んだ後、その考えが180°変わった。読み終えてからも、半年ほど頭の片隅で考え続けてわかったことがある。
承認欲求が満たされていない状態でも、自分の抱える安心欲求に気づくことで、自分も他人も思いやれるようになるのではないか。自分を安心させられるようになると、周りの人のことも同じように大切にできるのかもしれない。そういう考えに落ち着いた。
以前の私は認められたいがために、特定の人の教えや要求に120%応えようと気負ってしまう傾向があった。相手が望んだとおりに自分が動かないのは許されないことであり、認められるために必要な課題をすべて1人で完璧にこなさなければいけないと思い込んでいたのだ。
そのため、周りの人を気にかける余裕がなかったように思う。身近にいるのがどういう人かわからず、余計に不安を感じていた。よって、人の輪の中で「ここにいてもいい」と安心できなかったのだろう。
結局は独りよがりになってしまい、かえって悪い結果になることが本当によくあった。成長どころか、幼稚な自分を感じて承認欲求は強まるばかりだった。
しかし、安心欲求に気づき、自分の感情の機微に敏感になったことで、人から要求されたことでも自分が無理だと思えば避けられるようになった。評価してくれる人がいなくても地道に努力できるようになった。助けてほしいときに身近な人を頼れるようになった。
そして、人を頼れるようになったら、身近にいてくれる人たちのことが大好きになった。
本書では、安心欲求へのアプローチについても論じられている。そのうちのひとつに「自分の好きなことを続ける」とある。好きなことを無目的に続けていると、承認欲求が強く作用しない範囲で他者との関わりも広げられるのだそうだ。
私は今「文章を書くこと」が自分の好きなことになればいいなと願っている。書くのが好きだと確信したことはまだないのだけれど、書く過程で自分と向き合うのが楽しかったり、前より少しでもうまく書けるとうれしかったりする。
そして、書く仕事をしている仲間とのつながりが、今とてもありがたい。1人では乗り越えられない不安があるとき、仲間に相談することがある。その際、今まで感じたことのない「心の底からの感謝」を相手に感じた。
また、他人とコミュニケーションを取ると気負って疲れてしまうことがあるため、少し前まで必要最低限にとどめていた。けれど、今はただ癒やしとして他人と関わってみるという選択肢も増えた。相手とちょっと通じ合えたらうれしい。そういう肩の力が抜けたやり取りが少しずつできるようになっていると思う。
そういう変化があった結果、消えたい感情が薄れてきた。
その感情が完全になくなることはないのだけれど、顔をのぞかせてくる頻度は確かに減った。
たまにその感情と出くわしたときには、まず自問自答して不安要素を明らかにする。そして回避するなり、周りに助けを求めるなり、些細な不安でも対処するようにしている。ちなみに今は、自分の実力不足で気持ちが不安定になることが多いため、安心したい願望を抱えたまま日々勉強中だ。今日できたことをカレンダーに記録して「私は大丈夫」と思える工夫をしている。
私は『日常的な延命』に出会えたことで、見えていなかった安心欲求に気づき、だいぶ生きやすくなった。「自分の弱さを受け入れるって、こういうことかもしれないな」とも思う。これからも自分の弱さに寄り添いながら、私にとってちょうどいい生き方を模索していきたい。
文/尾崎 ゆき
【この記事もおすすめ】