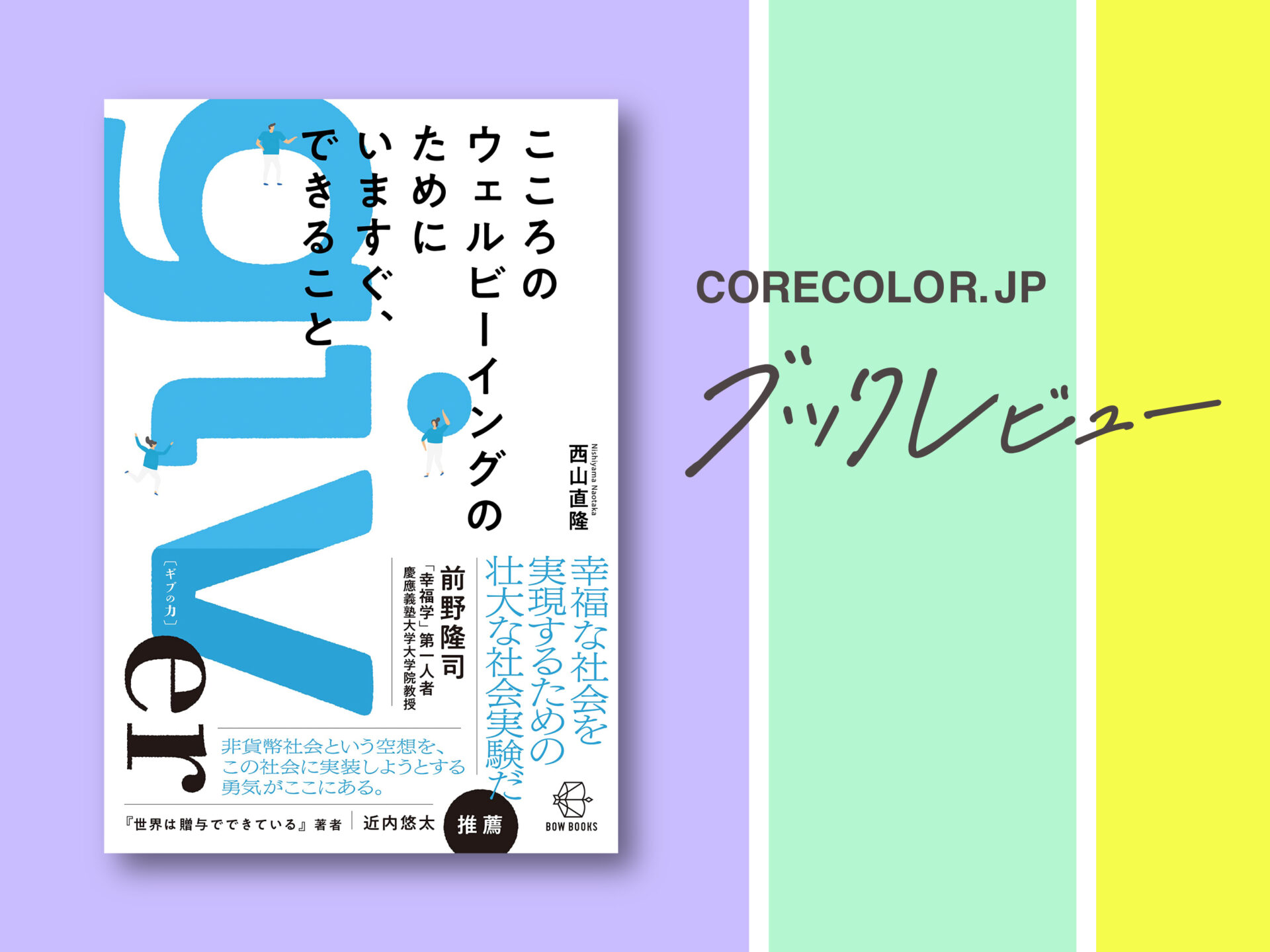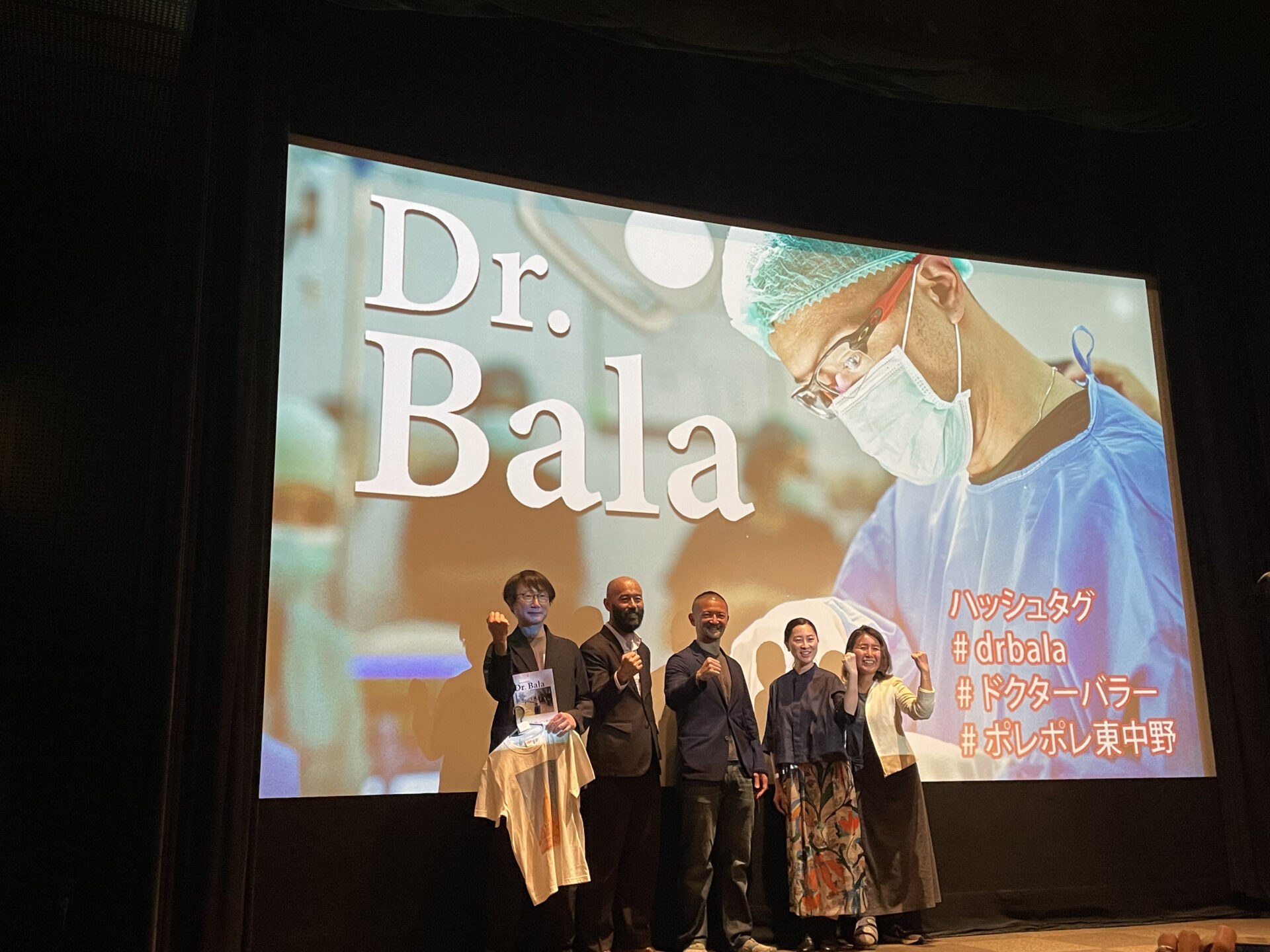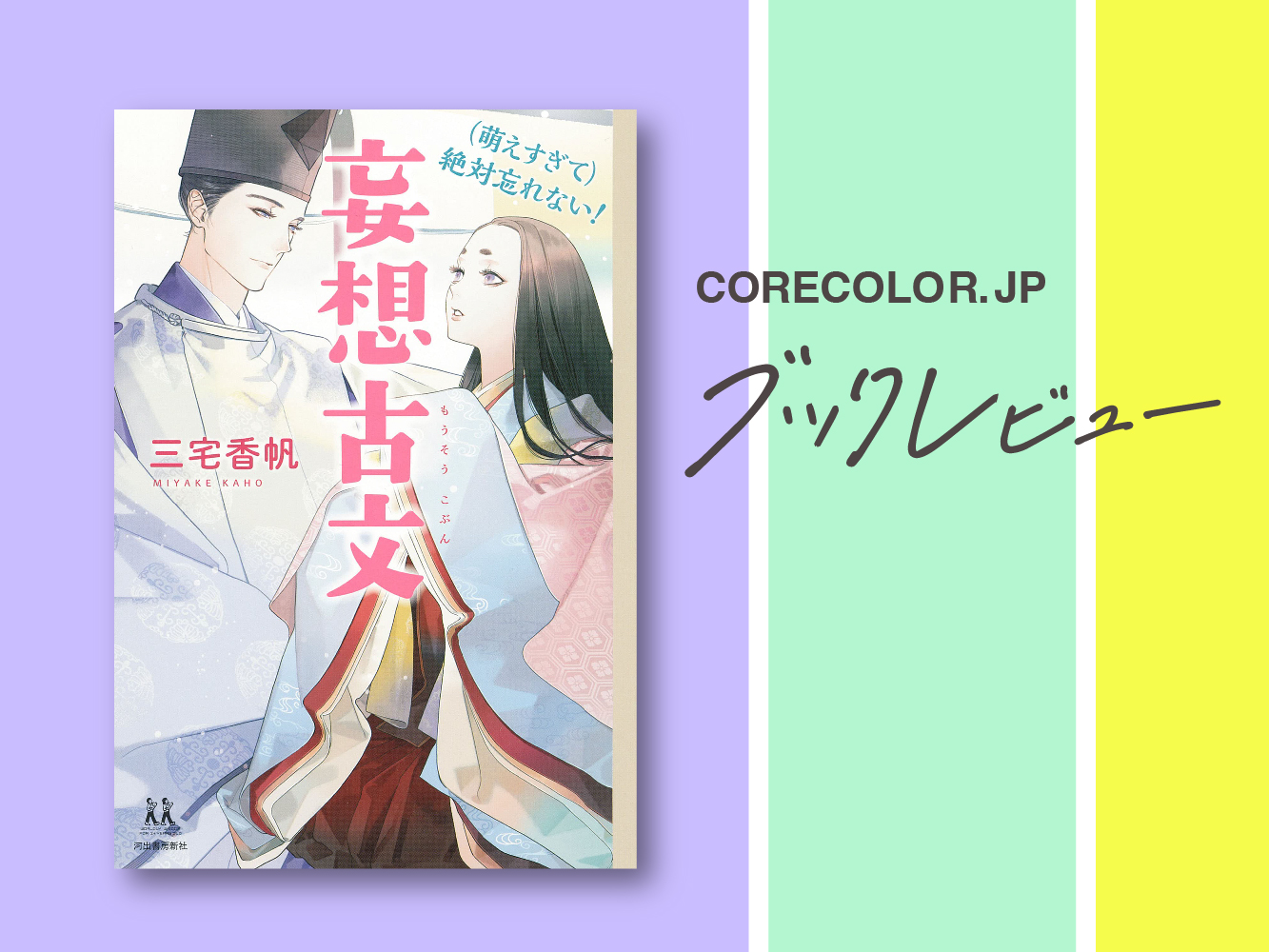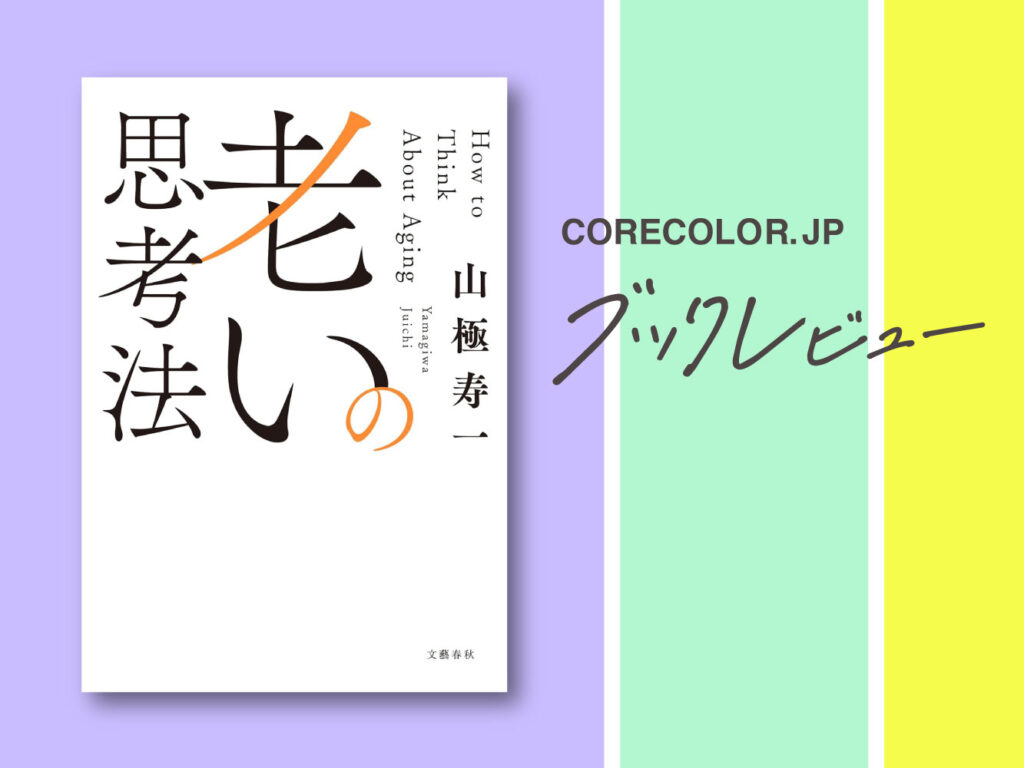
人生後半戦が待ち遠しくなる『老いの思考法』
よちよち歩きを始めた1歳3ヶ月の我が子。暖かい春のポカポカ陽気に誘われて、庭の芝生にちょこんと座らせる。庭仕事を随分サボっていたので、芝生はぼうぼう。まだ花が咲いていないシロツメクサは芝生を覆い尽くすように生い茂っている。柔らかい草の上に座った娘は、小さな手で葉っぱを触り、拾った草を「はい」と渡してくる。娘から手渡される草のやり取りの合間をぬって、四つ葉のクローバーを真剣に探す私。娘は座ったままで、十分満足そうに過ごしている。これまでの経験上、歩き回るようになったら、更に目が離せなくなると重々わかっている。こんなにじっくりと植物を観察できない。だからこそ、この時間が愛おしいのだ。日々できることが目に見えて増えていく我が子を見て、嬉しいような、名残惜しいような気持ちが滲む。子育ては一瞬なのかもしれないと感じている。
一瞬の子育てと感じているとはいえ、私自身は人生の後半戦に突入している自覚は随分とある。20代・30代・40代と出産を経験してきて、明らかに身体の衰えを感じているのだ。傷や風邪の治りも遅くなったし、授乳中を考慮しても、朝までぐっすり眠れたことがほぼない。年齢を重ねた分、じわじわと老いているのは否めない。自分の老いをひしひしと実感していた時、目に飛び込んできたのが『老いの思考法』だ。著者は、霊長類学者・人類学者で、総合地球環境学研究所所長の山極寿一さん。年を重ねて豊かで健やかになっていくロールモデルを探しているものの、身近ではなかなか巡り会えていない。だからこそこの本は「どのように老いていきたいか」を考えるきっかけをくれた。
第3章の「老年のタイタスとの再会」で、著者がゴリラのタイタスと過ごした日々から26年ぶりに感動的な再会を果たすシーンがある。タイタスが著者と再会をし、タイタスの幼少期の記憶が蘇るというもの。五感と結びついた身体の記憶は原初的なもので、記憶の深い部分と結びついているそうだ。著者は、「老年期の大きな楽しみの一つは、身体に眠っていた過去の記憶との再会なのではないかと思うのです」と語っている。タイタスが、著者の前で見せた幼少期に一瞬だけ戻った姿に、私は、心を動かされた。著者と共に過ごした記憶がしっかりとタイタスの身体に残っていたのかと思うとウルッとして涙を堪えた。タイタスにとっては著者との時間がかけがえのない日々だったとわかる場面だ。
かけがえのない日々を「人生のなかでの幸福な出会い」と呼ぶのなら、私にとってそれは、子育てのすべてだ。シロツメクサを触り、暖かい春の風を感じている娘の情景を思い浮かべてみる。これが彼女の記憶になり得るのかと思うと、胸がキュウッと熱くなる。いつか彼女が老いる時、この何気ない日々の記憶と再会できるかもしれない。子どもたちの記憶に、私と過ごした幾多の日々が、豊かな幼少期の思い出として残ることを幸せと呼ぶほかになんと表現すれば良いだろうか。私も老いる時、子育てをしていた日々をみずみずしく思い出したい。新生児を抱っこしていた腕の重さや、おんぶをしていた腰の痛みや、小さい手を繋いだ感覚を。鮮明に、ありありと。
私は、6人の子どもを授かり、気づけば自分の人生の半分を子育てに費やしている。数年ごとに妊娠・出産を繰り返しているので、赤ちゃんと子どもの存在が日常に溶け込んで久しい。常に子どもがいる状態なので、自分の時間と一般的に呼べるものは、ほぼ皆無だ。第1章の「人はなぜ “人生後半戦” が長いのか?」の中で「いまや核家族の少子高齢化社会において、子育ては『コスト』になってしまいました。ストレスフルな日々において、自分の時間を削られていると思ってしまう保護者も多い」という見解に、私も思わず唸る。
夫婦で協力して子育てをしていても、自分の時間が欲しい! と切実に思ったことは何度もある。助けてほしいけれど、助けてもらえる人がいない。夫や友人はどんどん社会に出て経験を積んでいるのに、私は社会から取り残されている気がする。子育てメインの人生を選んだのは自分なので、孤立していることを吐露できない。そんな苦い気持ちを抱えながら子育てをしてきたけれど、私の視野が狭くなっていたのだなと今なら思う。私は幼児期に母親と離別したせいか、母親という存在に対する理想や葛藤が入り混じり、随分と長い間、母親はこうあるべきという幻想に縛られていたのだ。「本来の子育ては『ともに在る』楽しい時間です」と著者は語る。自分〝だけ〟の時間と切り分けずに、「あなたの時間は私の時間、私の時間はあなたの時間—だから私たちの時間」として心ゆくまで、「ともに在る」時間をめいっぱい楽しもうではないか。そう思うと、心がフッと軽くなった。
文/青山 書子
【この記事もおすすめ】