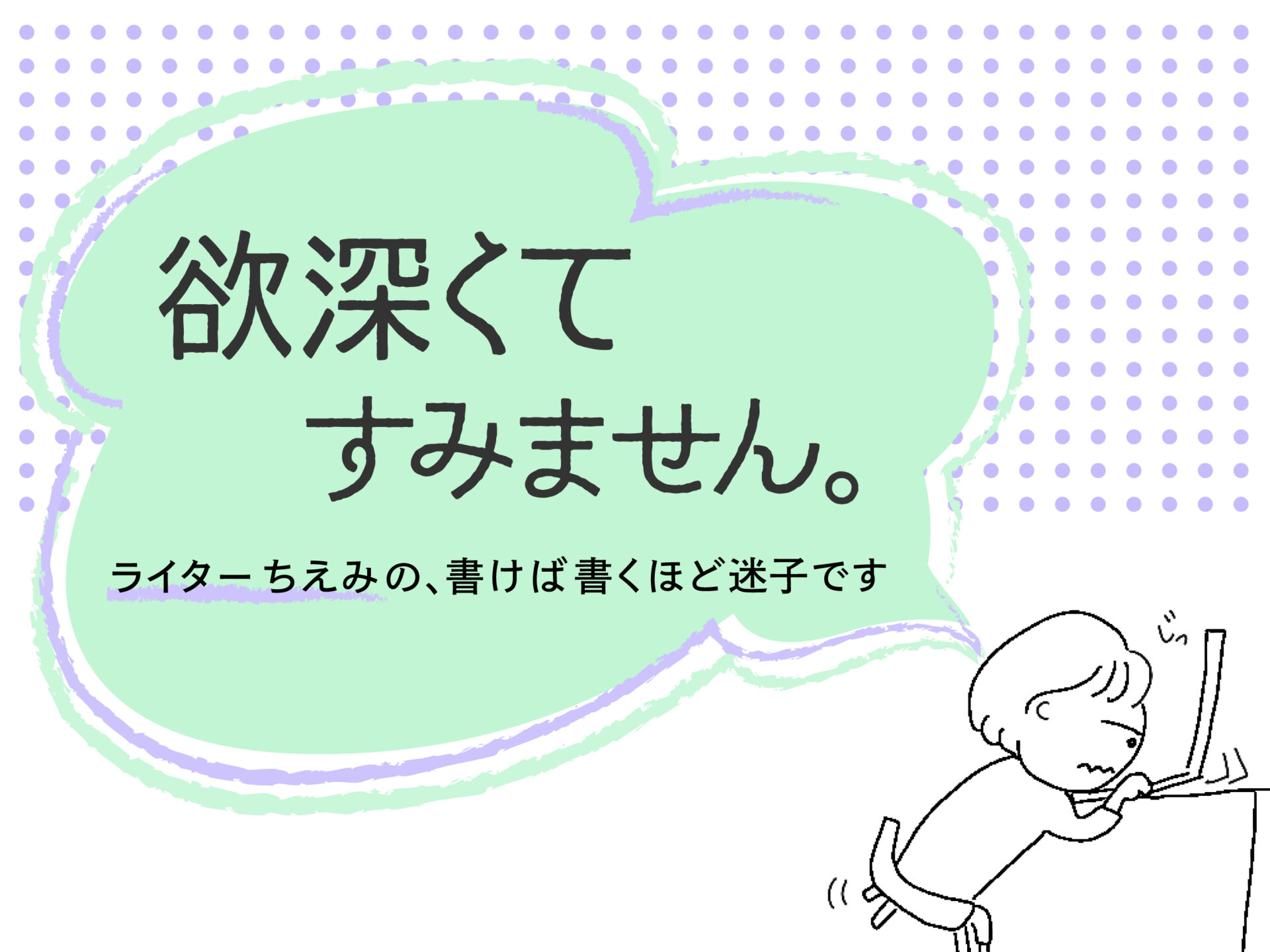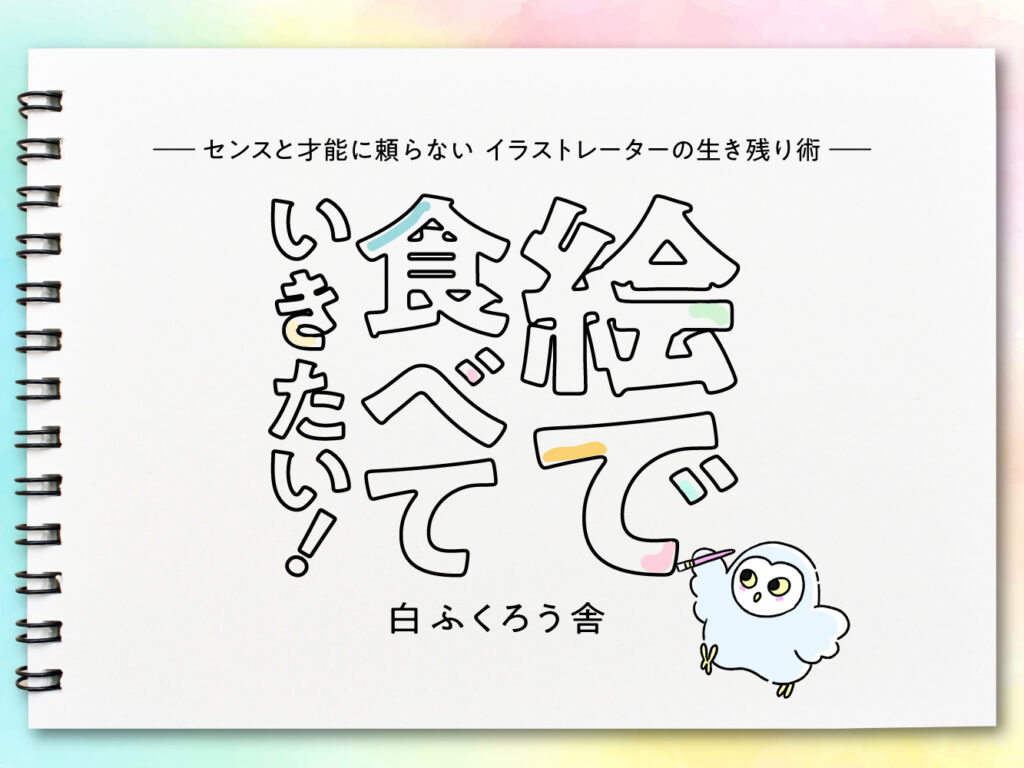
個人からのイラスト依頼を受けるときに気をつけたいこと【絵で食べていきたい/第30回】
SNSの普及により、イラストレーターに直接仕事を依頼することが以前よりずっと簡単になりました。スキルマーケットなどを活用し、主に個人からの依頼で描くイラストレーターも増えています。今後この市場はますます広がると思われますので、「個人からの依頼を受けるときに気をつけたいこと」を、自分の経験をもとにまとめておきます。
個人依頼にありがちなトラブル
絵の仕事には企業からの依頼を受ける他、個人からの依頼を受けての制作もあります。と言いつつも、現在、私は事業主を除く個人からの発注は基本的に受けていません。理由は、個人からのご依頼を受けたときに特有の困りごとが多く、それらに対応するのが大変だったからです。困りごとを大まかにまとめると、以下の3点です。
1)イラストの完成イメージが曖昧で、ゴールがわかりにくい
2)納品したイラストの使用範囲を誤解されやすい
3)料金の回収トラブルが起きやすい
ひとつずつ説明します。
1)イラストの完成イメージが曖昧で、ゴールがわかりにくい
企業案件では、編集者やアートディレクターなど「発注のプロ」が間に入り、初めての依頼でも基本的な要件は押さえてくれます。しかし個人の依頼主には発注の知識がないのが普通です。「こんな感じのイラストを描いてほしい」という漠然とした希望はあっても、最終的なゴールが明確でないことが多いのです。
発注側がゴールを明確にできていないことは、イラストレーター側にとって「満足される納品物の基準がはっきりしない」というリスクになります。
企業案件の場合、「この誌面にこのサイズで、こういった内容を描いてください。タッチはこのサンプルのイメージで」といった具体的な指示があり、それに沿って制作すれば基本的には問題ないことがほとんどです。修正が入る場合も、最初のオーダーの範囲内で済みます。もし欲しいイラストの内容そのものが変わったら、先方理由の変更なので、追加料金の請求も可能です。
しかし個人依頼では、ラフスケッチにOKを出したにもかかわらず、完成品を見て「思っていたのと違う」「もっとこうしてほしい」といった反応が返ってくることも珍しくありません。これは事前に明確なゴールをイメージできない、イラストの発注に不慣れな人にはよくあることです。
この場合に、「ラフスケッチでOKをもらっている」「オーダーの内容とずれていない」と説明しても、相手に納得してもらうことが難しいのです。
2)納品したイラストの使用範囲を誤解されやすい
こちらが想定した使用範囲を超えてイラストをつかわれてしまうケースです。たとえば「名刺用に似顔絵を描いてほしい」とオーダーがあった場合、制作者はそのイラストが名刺につかわれるだけという想定で納品します。しかし、購入者が著作権に詳しいとは限りません。納品されたイラストが気に入ったのでSNSのアイコンにしよう、シールにして配ろう、グッズを作って販売しようと考えるかもしれません。悪意がなくとも、意図しないつかわれ方をされると、対応に労力をさかれることになります。結果として活動に支障をきたすので注意が必要です。
ちなみに、この問題は受注制作の場合に限らず起こり得ます。近年では、イラストの原画やデータをウェブショップやハンドメイドサイトなどで販売する人も増えています。原画を購入した場合、特に取り決めがなければ買い手に移るのは所有権のみです。しかしそれを知らなければ、原画を買ったのだからどう利用しても大丈夫、スキャンしてポストカードやカレンダーにしてみんなに配ろう、などと思う人がいるかもしれません。
3)料金の回収トラブルが起きやすい
これは文字通り、イラストを納品したものの支払いを渋られたり、納品そのものを拒否されたりして料金が回収できないというトラブルです。たとえば、顔見知りの人との口約束で絵を描いたものの、なかなかお金を払ってもらえないケースなど(ちなみに口頭でも双方合意であれば契約は成立します)。私も以前、友人に紹介された人からイラストを頼まれ、納品したのになかなか料金を支払ってもらえず困ったことがあります。そのときは友人から催促してもらい、料金を回収できました。しかし、SNSのメッセージで注文を受けてしまい、相手の住所などが確かめられない場合などは、連絡がつかなくなったらそれきり、ということもありえます。
個人からの依頼も、注文しやすい「仕組み」でトラブルを減らす
上記のようなトラブルが法人や事業主相手に比べて起こりやすいとなると、個人からの依頼は怖い、受けるべきではないと感じるかもしれません。しかしこうした問題に対する工夫や解決策もあります。個人からの依頼を多く受けているイラストレーターたちは、工夫を凝らしたオーダーシステムを整えていますし、受注者がつかいやすいスキルマーケットやコミッション用サイトも増えてきました。これらのシステムから、具体的な解決方法を学ぶことができます。たとえば以下のような工夫です。
1)イメージを明確にするために、オーダー方法を工夫する
2)イラストの使用範囲を事前に明記する
3)不払いをしにくいシステムにする
ひとつずつ説明します。
1)イメージを明確にするために、オーダー方法を工夫する
「ご希望のものを何でも描きますよ!」というスタイルは一見親切ですが、依頼内容がはっきりイメージできていない人にとってはかえって負担になることもあります。
それを解決するために、たとえば用途やサイズごとに受注ページを分けます。人物イラストならば、構図を「顔だけ」「バストアップ」「全身」など、希望に近いものを選べるようにするのです。各々の構図はそれぞれ同じタッチで描けば、完成がイメージしやすくなります。さらに、背景や小物など描き込む量が変わる場合はオプション料金を設定します。ヘアカタログから希望のスタイルを選び、それをもとに美容師さんに細かいオーダーをしていくようなものです。
また、ラフの修正回数にも制限を設けるなど、作業におけるルールもわかりやすく明確にし、受注前に双方の意識のずれができるだけないようにしておきます。
2)イラストの使用範囲を事前に明記する
使用範囲の条件や禁止事項も事前に明記しておけば、納得した上で依頼してもらえるので、後のトラブルを避けやすくなり、毎回質問に答える労力も削減できます。使用範囲ごとに料金を設定しておけばなお親切でしょう。
これは金額の問題だけではなく、「ウェブだけでなく印刷にもつかいたい」という場合に、はじめから印刷用の解像度に合わせて制作するなど、制作側もやりやすくなります。
3)不払いをしにくいシステムにする
料金の回収方法でもっとも確実なのは、依頼内容と金額で双方の同意がとれた時点で前払いをしてもらうことです。しかし、こちらが料金を回収できない不安があるのと同様に、相手も「絵を納品してもらえず雲隠れされたらどうしよう」と不安に思っていることも忘れてはいけません。自分の情報や実績をしっかり伝えて安心してもらうことも必要です。前払いや着手金をもらうことに抵抗があるならば、支払い保証をしてくれるスキルマーケットやコミッションサービスを利用する手もあります。利用料はかかりますが、やりとりの手間などを考えたらかえってお得かもしれません。
自分に合った受注スタイルを考える
こういった受注システムは、個人だけでなくイラスト発注に慣れていない企業クライアントにとってもわかりやすいはずです。
「それなら、注文しやすいサイトと料金表を作ればすべてうまくいくのでは?」と思うかもしれません。でも、それが最適かどうかは「自分がどんな仕事をしたいか」によります。
たとえば私自身、印刷会社に発注する際、安さや納期を最重視するなら、ウェブで自動見積もりができ、発注方法もパッケージ化されている会社を選びます。一方で、作品集のように仕上がりに強くこだわりたい案件では、対面で一から相談できる会社に依頼したいと思うでしょう。つまり、どういう発注スタイルが自分に合うかは、扱いたい仕事の内容によって変わってきます。
わかりやすいオーダーシステムを整えることで入口を広げ、その後、より自由度の高い仕事へと発展させることも可能です。飲食店がランチで新規客を呼び、ディナー利用へとつなげていくような流れです。
必要としてくれる人に、届ける準備を
大事なのは、「自分のイラストを必要としてくれるのはどんな人か」「その人はどうすれば発注しやすくなるか」を考えて自分のスタイルを選び、それに合った仕組みを整えることです。
その仕組みが適切ならば、依頼主が個人であれ企業であれ、安心して仕事を受けられるようになるはずです。個人受注の問題をクリアできそうな環境が整ってきたので、私自身も今後は個人受注を受けていくかもしれません。
やり方を固定せず、自分の希望や現在の状況に合わせて常に依頼されやすい環境を整えていけば、イラストを仕事にしていくことは十分に現実的な選択肢になります。
文/白ふくろう舎
【この記事もおすすめ】