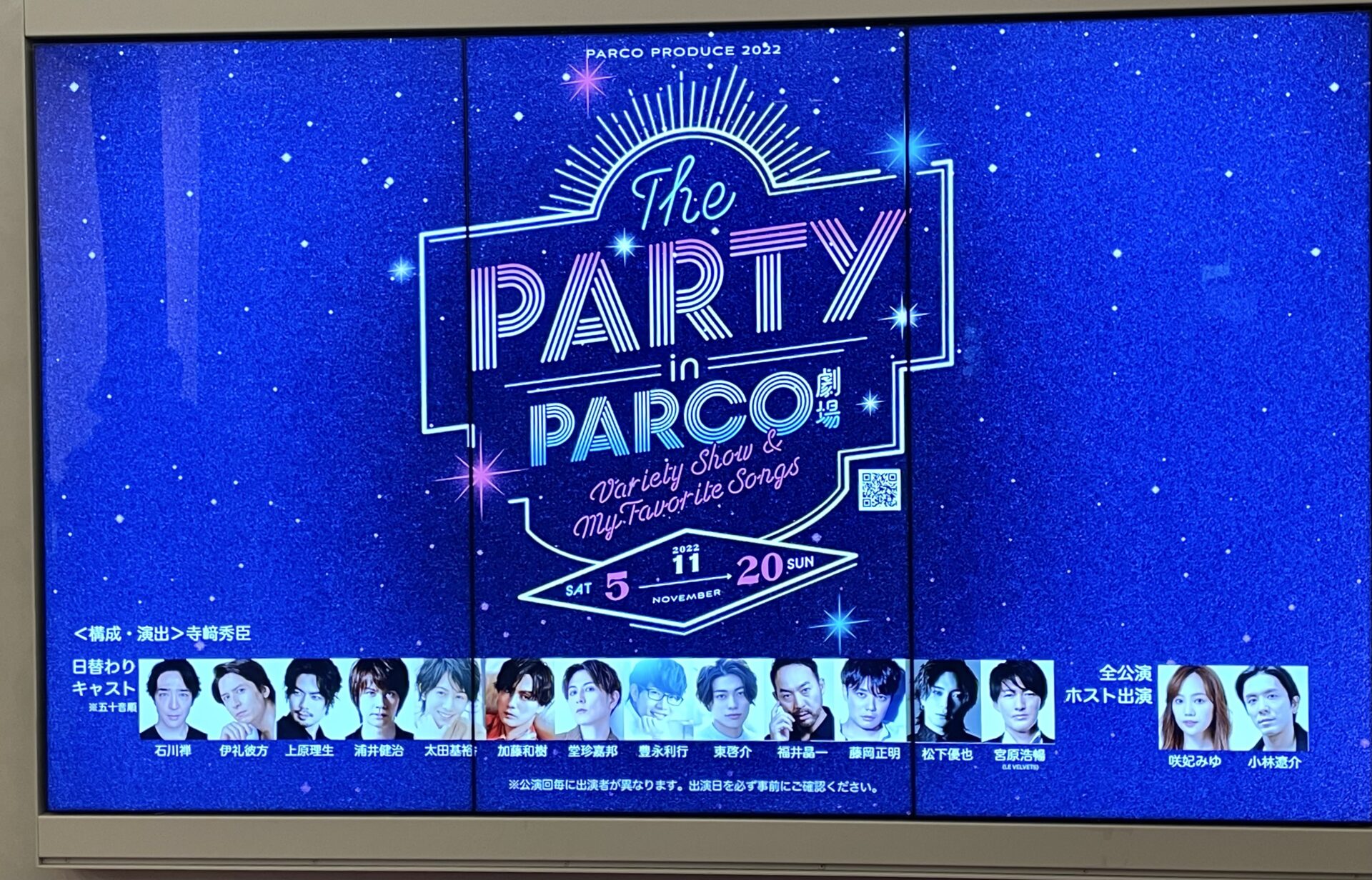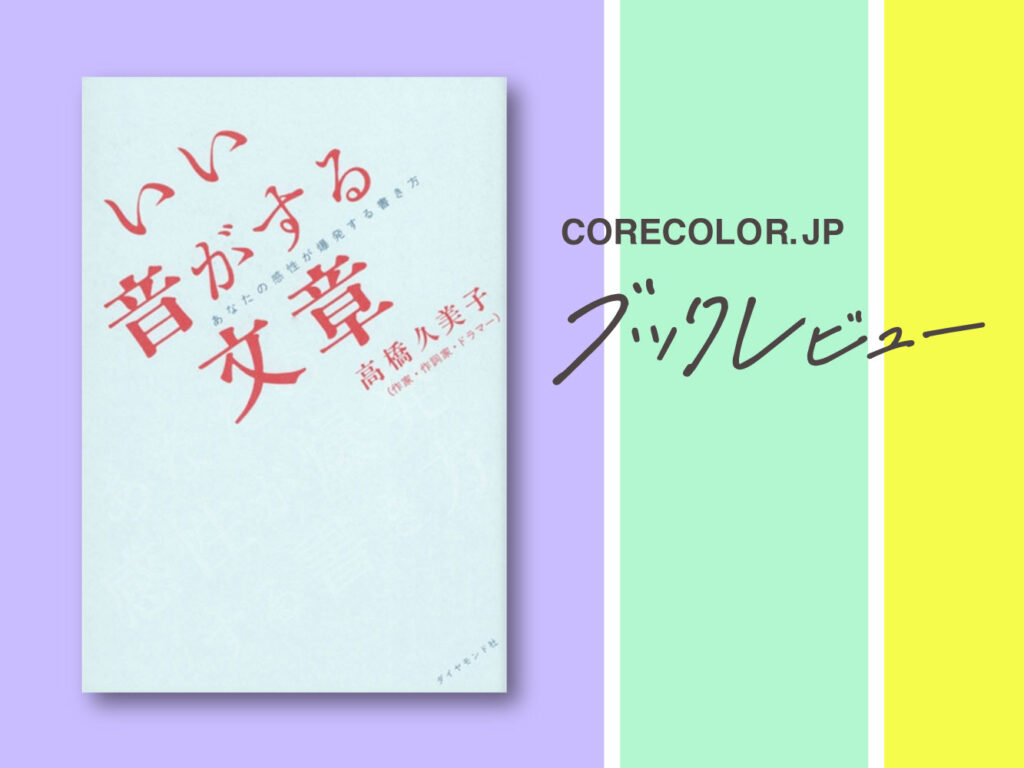
『いい音がする文章』が示してくれた「自分の音」の掘り起こし方
人生で2度、歌詞を書いたことがある。
1度目は中学生の時。もう何を書いたのかは覚えていないけど、ピアノが得意な友だちが曲をつけてくれると言ったので書いた。たぶん普段言葉では言えないような少し恥ずかしい歌詞だったと思う。そして、2度目はほんの2年前。5年間住んだ街を離れる時に、その街への思いを歌詞に託して、街で出会った音楽家の方に渡した。
どちらも結局歌になってはいないけれど、音をつけたらどんな曲になっていたのだろうか?
そんなすっかり忘れたふりをして実は記憶の片隅に引っかかっている過去を思い出させてくれたのは、元チャットモンチーのドラマーで今は作家・作詞家・ドラマーの高橋久美子さんの著書『いい音がする文章』だ。
インドネシアに住んでいるので紙の本はすぐには手に入らないから、一時帰国まで待とうと思っていたけれど、ライター仲間が次々に読んでいるのが気になって、待ちきれずに電子書籍で買ってしまった。
著者は「はじめに」の最後にこう記した。「さあ、そろそろ一曲目が始まりそうですね。あ、言葉より音楽好きのあなたは第5章から読むといいですよ。」
そっかぁー。音楽好きな人かぁ。どうしよっかなぁ。と、5秒間考えて、えいっと第5章に飛んだ。
そこからは初めての読書体験が待っていた。
片手に電子書籍、隣にはYouTube。本を読んではYouTubeで歌を検索し、音を味わったらまた本に戻る。しまいには閉鎖された室内ではなく、青空の下で著書内に出てくる歌を大音量で聴いたり歌ったりしたくなって、スマホを2台持って屋外のベンチに出た。
元々音楽を歌詞で聴く派の私は、歌詞を聴きながらその世界観が脳内で映像化される時間がたまらなく好きだ。この歌詞を絵や写真にしたらどんな描写になるだろうと妄想することもあった(画力に自信がなくて実際にやったことはないんだけど)。
だからこそ歌詞にストーリー性のある、DREAMS COME TRUEやコブクロ、Mr.Childrenなどの歌を好んで聴くし、歌詞の意味が取りきれない洋楽はあまり心に残っていない。最近ではインドネシアの歌が流れている時に、知っている単語が耳に入ってくると、無意識に脳内翻訳をしている。cinta kamu(あなたを愛してる)、hatiku(私の心)。あぁ、これはラブソングか。hilang(消える)、rindu kamu(あなたがいなくて悲しい)。あら、別れの歌かしら? そんな妄想が広がっていく。
ところが、「歌詞」は音楽の一部でしかないと著者はいう。
第5章にはバンド時代に歌を作ってきた方法や、作詞家やドラマーとしてたくさんの音楽家とセッションしてきた実体験がちりばめられていた。
中でも、いきものがかりの水野良樹さんがメロディを作り、著者が歌詞を書き、編曲に亀田誠治さんが入られた『星屑のバトン』という歌の制作過程の話は最高にエキサイティングだった。水野さんがイントロとサビのメロディを作り、著者がそこに歌詞を載せる。そこからさらにAメロとBメロは歌詞を先に書き、そこにメロディを作る。お互いが言葉とメロディを贈り合い、それぞれのイメージに導かれながらひとつの作品が生まれていた。初めて知った歌だけれど、何度もリピートして聴いてしまったぐらいいい曲だった。
この本は、歌だけでなく文章にも「自分の音」を鳴らす楽しさを教えてくれる。それが自分らしい文章になるのだと。
私は、「CORECOLOR」の編集長さとゆみさんに、一度だけ、文章が「跳ねている」と言ってもらったことがある。 その瞬間、びっくりして何も言えなかったけれど、私の鼓動は跳ねた。私にとっては最高の褒め言葉だった。
今思えば、この「跳ねる」というのが「自分の音」が出せている文章だったんじゃないだろうか。書く時に筆が乗っている文章はたいてい「自分の音」も乗っている。
しかし最近の私は、「自分の音」の出し方が少しわからなくなっている。インドネシアでの貴重な経験を文章にしたいと頭では思っていても筆は一向に進まない。noteに書くのか、SNSに書くのかもわからなくなって、結局書かずに日々過ぎていくことが沢山ある。アウトプットしきれていない経験が体内にたまって、もう便秘状態だよ。そりゃカラダが重たくなるはず。
そんなカラダが重い私へのアドバイスはこれだった。「もし、あなたが、自分らしい文章を書けないなと思っているならば、自分のルーツになった場所の音を確かめに行くのもいいかもしれない」。
もうすぐ、年に一度の日本一時帰国だ。日本語に触れて、日本の街に触れて、日本の人たちに触れて、自分のルーツになった音をたくさん掘り起こしてこようと思う。
文/岡山 美和
【この記事もおすすめ】