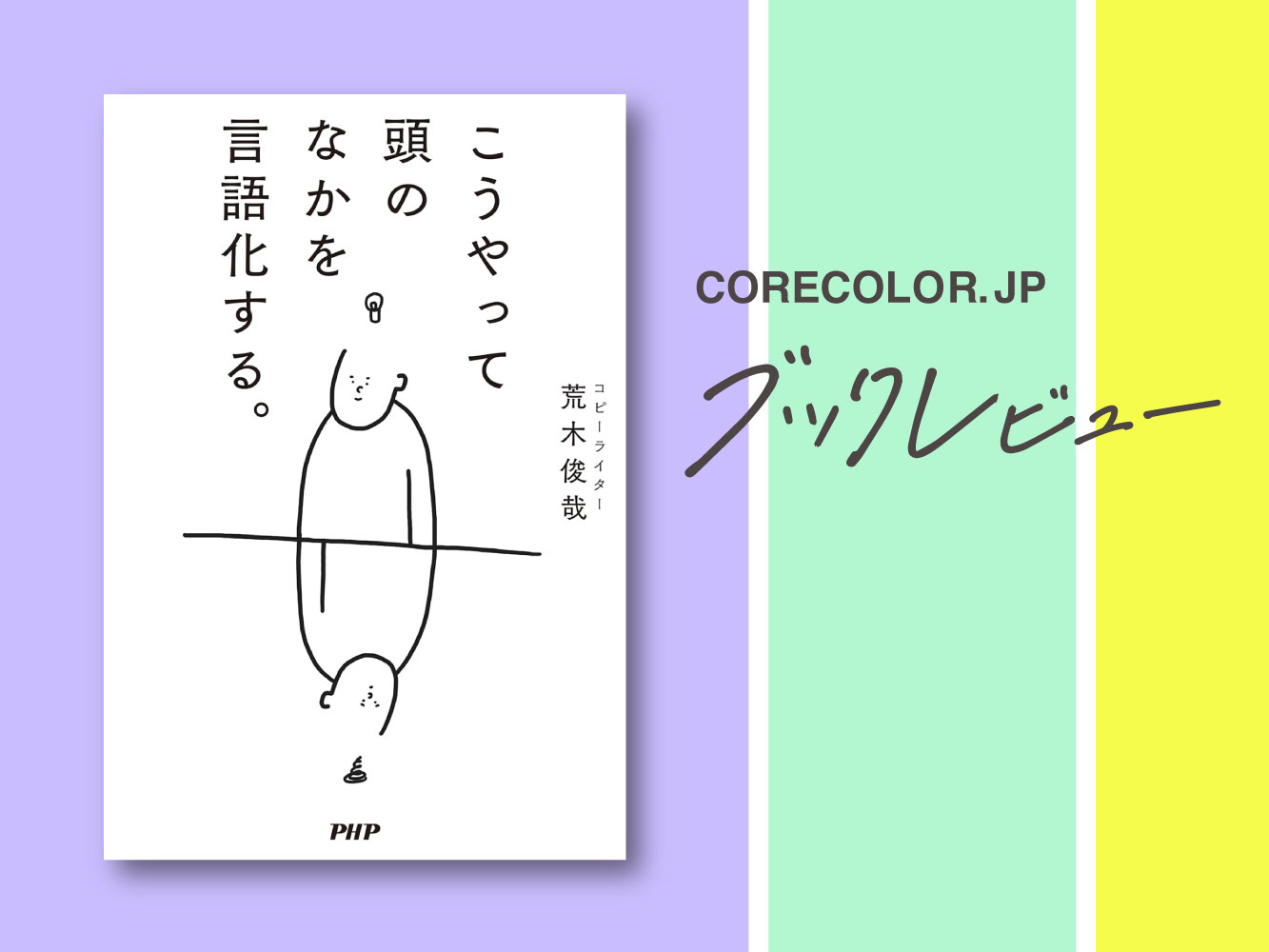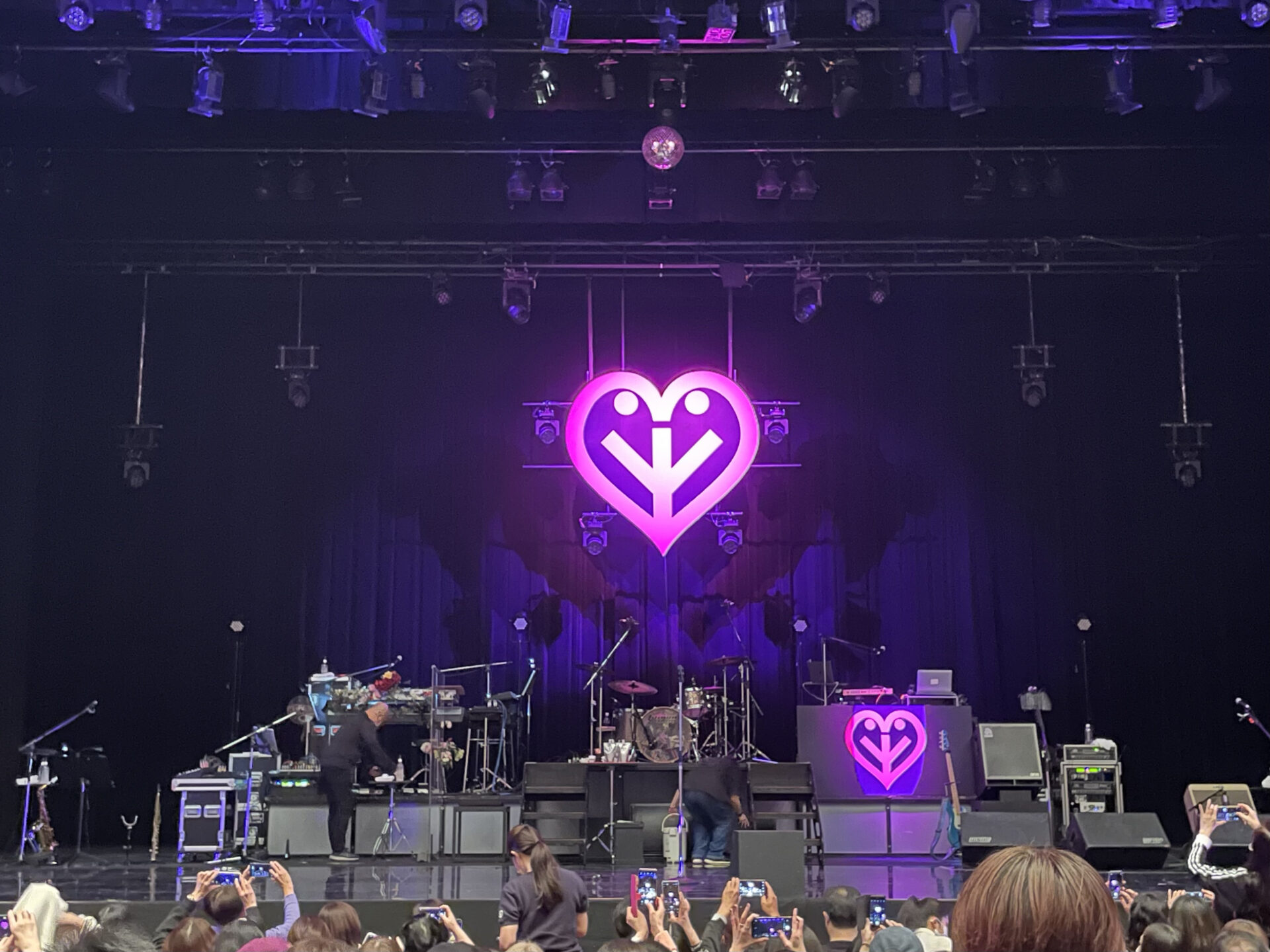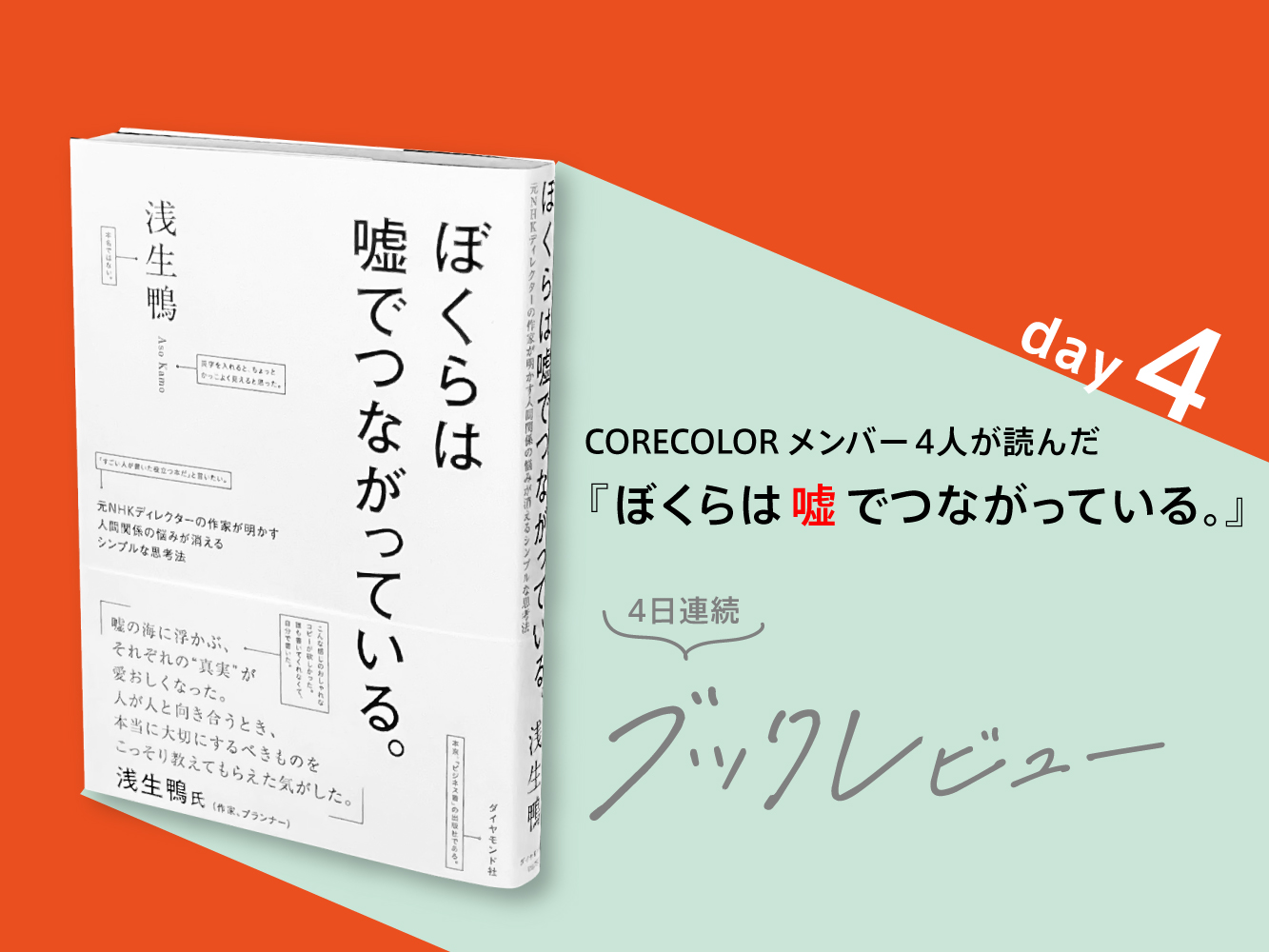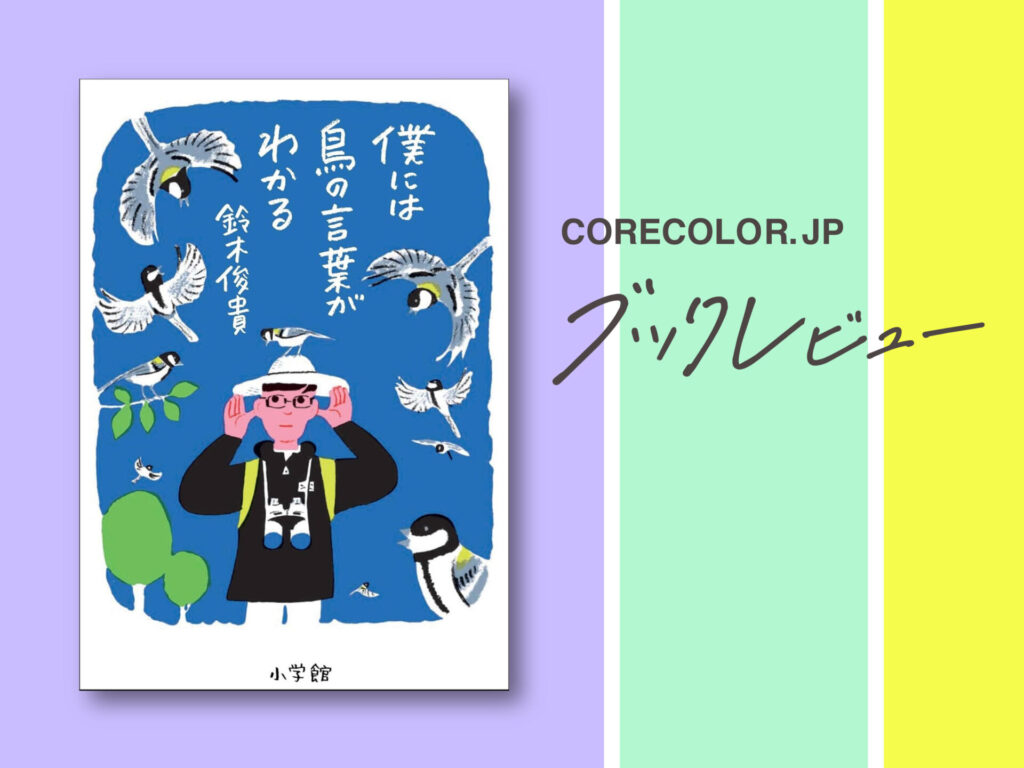
シジュウカラ語を知ったら、見える景色が変わった。『僕には鳥の言葉がわかる』
普段から、下を向いて歩くクセがある。
足元にいるかもしれない、生き物を見つけるためだ。
たとえば、早朝に近所を散歩していると、アスファルトの道路を足早に横断するコガネムシを見かける。ちょっとした草むらを覗けば、小さなカマキリやバッタと目が合う。自然豊かな土地だからか、運が良ければヘビやトカゲに会える日もある。なかなかお目にかかれない存在なので、朝の占いで1位になったぐらい、嬉しくなる。
生き物さがしは、宝さがし。
一期一会の出会いを逃したくなくて、足元ばかり見ながら歩く自分は、はたから見ると変な人かもしれない。
そんな自分だが、数ヶ月前からは足元だけでなく、空にも目を向けるようになった。動物言語学者・鈴木俊貴さんの著書『僕には鳥の言葉がわかる』を読んでから、外を歩く時の視点が変わったのだ。
*
『僕には鳥の言葉がわかる』の著者・鈴木さんは、幼い頃から生き物が好きで、虫やカエルなどを捕まえて飼育する少年だった。高校生の時、双眼鏡を購入したことがきっかけでバードウォッチングにハマり、飼育下とは異なる生き物の世界に魅せられていく。鳥の研究ができる大学に進学すると、野鳥の観察に明け暮れる日々を送った。
そして、大学3年生の冬。鈴木さんの人生を変える出会いが訪れる。
国内有数の探鳥地・軽井沢の森を訪れた時に、鳴き声で餌の場所や天敵の存在を知らせ合う鳥たちに遭遇したのだ。なかでも、シジュウカラは「ヂヂヂヂ」「ヒヒヒ」など、多彩な声で鳴いていた。それらを聞くうちに、「ひょっとしたら、鳥たちの鳴き声にはいろいろな意味があるのかもしれない」と考え、鳥語の研究を始めることにした。
まるで自由研究かのごとく、鳥の言葉を解き明かす15年以上の日々の記録。動物言語学という新たな学問の創設に至るまで、本書には鈴木さんの研究人生がギュッと詰め込まれている。専門的でありながらわかりやすく、ユーモアあふれる内容が話題を呼び、刊行から8ヶ月で15万部を突破した。
巻末には、特別付録として7種類のシジュウカラの鳴き声が聞けるQRコードが付いているのだが、これがまた、とてもいい。「あれ? この鳴き声、聞いたことあるかも!」「え、こんな鳴き方もするの?」という発見が1つ、また1つと生まれて、ワクワクが止まらない。鳴き声を聞くだけで、シジュウカラをさがしに出かけたくなってしまうのだ。
*
実は、本書を読み始める前は「鳥の言葉を理解することなんて、本当にできるのかな?」と、少し懐疑的だった。これは、私自身の経験が関係している。
私がまだ小学生だった頃、犬の鳴き声を分析し、人間の言葉に翻訳してくれるコミュニケーションツールが流行っていた。当時、わが家には犬が4匹いたので、私も愛犬と話してみたくて、親に「買って!」とねだった。しかし、「高いからダメ!」と、あえなく撃沈。それがもう悔しくて、担任の先生に思わずぼやいたことがあった。
先生は私をなだめつつ、「でも、犬は話せないと思うよ。だって、言葉を話せるのは人間だけだから。ここまで文明や文化が発展してきたのも、人間が言葉を持つ生き物だったからなのよ」と諭すように言った。その教えが、当時の私には妙に響いて、そういうものなのかと納得してしまった。それから、親にねだることも、誰かに「犬と話してみたい」と話すことも、しなくなったように思う。
しかし、本書の「井の中の蛙」という章を読んだ時、幼い頃からの常識が一気に覆された。この章の一節を読んでほしい。
「シジュウカラにも言葉がある。これは僕にとっては当たり前の話であった。そんなある日、大学の図書館である本を読んでいて驚いた。そこには、『言語を持つのは人間だけだ』と明記されていたのである!」。
鈴木さんは「言語を持つのは人間だけだ」という通説に驚き、そんな人間を「井の中の蛙」と表現していたが、私はむしろ、鈴木さんの驚きっぷりに驚いた。ご本人が目の前にいたら、「え、違うんですか?」と言ってしまっただろう。
そもそも、人間だけが言語を持つという説は、2,000年以上前から信じられてきた常識だ。鈴木さんによれば、かの有名な哲学者・アリストテレスは「動物の鳴き声は、人間の言葉のように意味を持つものではない」と主張し、進化論の提唱者・ダーウィンでさえ、「言葉は人間固有の性質である」と著書に記したという。
これだけ高名な歴史上の人物が「言語を持つのは人間だけだ」と、言っているのだ。疑う余地なんて、あるだろうか。けれども、鈴木さんは違った。
毎年6ヶ月以上1人で森にこもり、朝から晩まで鳥たちと暮らし、実験をくり返し、鳥には鳥の言葉があることを証明した。それはつまり、2,000年以上前からある常識ではなく、目の前にいる鳥たちを信じ続けたことになる。
鳥の言語能力を論文にまとめて発表した時、(人間の)言語学者から意見論文があがってきたこともあったそうだ。その大半が「人間が最も高度で、動物は単純である」という前提を感じるものだったという。
「人間の言語も動物の言語の一つにすぎないのだが、まだこれに気づいていない人が本当にたくさんいるのである」と言い切る鈴木さんに、思わずうなる。「人間」という枠で物事を考えていないのだ。それが面白くて、何度も、何度も反芻する自分がいた。
本書には、人間だけが特別じゃないという話がたびたび出てくる。不思議なことに、その言葉に突き放すようなニュアンスは感じない。むしろ「特別じゃないから、わかり合えるかもしれない」といった可能性を感じて、ニンマリしてしまう。こんなに希望にあふれた話が、あるだろうか。
*
『僕には鳥の言葉がわかる』を読み終えた初夏の頃、家の目の前にある桜の木から「ヂヂヂヂ……」という鳴き声が聞こえてきた。
あれ、この声、もしかしてシジュウカラ……? なんて考えていると、隣にいたわが子が「お母さん、シジュウカラ鳴いている! シジュウカラ!」と嬉しそうに教えてくれた。巻末付録のシジュウカラの鳴き声を一緒に聞いていたからか、反応が早い。
「ヂヂヂヂ」は、シジュウカラ語で「集まれ!」を意味する。もしかすると、ここで待っていたらシジュウカラたちが集まってくるかもしれない。そう考え、少し離れた場所から桜の木を見守ることにした。すると、数分も経たず、1匹、また1匹と鳥たちがやってきて、気づけば、桜の木はシジュウカラたちであふれかえっていた。
この前、本を読み終えたばかりなのに。引き寄せの法則って、こういうこと? いや違うな。きっと、シジュウカラたちはずっと前から、この場所に来ていたのだろう。私が、シジュウカラのことを知ったから、この景色を見ることができた。知ることで、世界の見え方が変わったんだ。
一緒に鳥たちを観察していたわが子と「来たね、本当に来たね!」と言いながらハイタッチをする。こんな瞬間を、これからも重ねていこう。
さて、次はどんな生き物に会いに行こうかな。
ワクワクしながら、今日も私は生き物さがしに出かける。
文/小林 おすし
【この記事もおすすめ】