
見たことがないものを見たくて撮る。『夜明けのすべて』『ケイコ 目を澄ませて』三宅唱監督
2022年に公開された『ケイコ 目を澄ませて』が、第72回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に正式出品され、第77回毎日映画コンクールで日本映画大賞・監督賞など5冠を達成し、いま最も注目を浴びている映画監督の1人である三宅唱。
創作のスタート地点は中学3年生の学校祭で発表した短編映画『1999』。3人の男が学校の中を延々と走り続ける作品だ。寄って、引いて、俯瞰して。工夫されたアングルと編集でループして見える短編はなんとも言えない吸引力があり、完成度が高かった。
幸運にも三宅監督の第1作の発表に同じ学校の生徒として立ち合い、「何でこんな表現ができるのだろう」と衝撃を受けたライターがインタビューを申し込んだ。すると、「正直照れくさいけど、同級生であることは忘れて喋る」と応じた三宅監督。25年前の映像作品を出発点に、どんな道を辿り、映画監督になったのか。中学生の頃の話や創作への思い、最新作『夜明けのすべて』について聞く。
聞き手/石川 仁美
映画との出会い。「すげえ大人がいっぱいいるじゃん」
━━今回のインタビューを企画したきっかけは、中学の学校祭で三宅監督が作った短編映画『1999』がずっと私の記憶に印象深く残っていたからでした。三宅監督が男2人に追いかけられるシンプルな内容なのにアングルが工夫されていて編集もメリハリがあって、一瞬で引き込まれました。中学生でこんな作品を作るなんてと驚いたことを覚えています。
三宅:自分にとっては、すごく大きな経験だったけど、覚えてくれている人がいたことは驚きだし、うれしいことですね。当時の自分は、同級生がどう見るかなんて気にもしないぐらい、学校祭の準備中は映画を撮ることに夢中だった。

━━映画を作ることになった経緯は?
三宅:実は僕、学校祭では当初、演劇のチームに入っていたの。本当は演劇をめちゃくちゃやりたかったんだけど、先生がすごく張り切っているから中学生なりの反発心もあって一緒にはやりたくなかった。そこで、好き勝手やる方法はないかなって考えて、「自分たちは映画を作ろうと思う。演劇チームから抜けていいか」と先生に非常に生意気な打診をしたのがきっかけ。自由な校風の中学だったこともあって、先生が映画制作を歓迎してくれたのはありがたかった。
学校祭準備期間の1週間ぐらいは、学校に行っては朝から晩まで、今日は何を撮ろうって試行錯誤する時間がすごく面白かった。脳みそを使えるし、体も動かせるし。撮っていくうちに、映画は美術や運動や音楽の要素も含まれるし、ありとあらゆるものを総動員した総合芸術が映画なんだなと気づいたんだよね。もともと美術の授業も好きだったし、作文が得意だったのも映画に惹かれた理由のひとつだと思います。
━━実は中学生の時に入賞した作文のコピーを持ってきました。
三宅:まじか。また、すごいものを。ありがとうございます。この中学1年生のエッセイのタイトル「と思う。」だなんて生意気だよね。幸運にも作文がコンクールで認められたから、自分は作ったり書いたりする仕事に向いているんだろうなと思うようになりました。新聞とか雑誌とか超面白そうだし、テレビ局という選択肢もある。考えがコロコロ変わっていく中で、あ、もしかして映画だったらいろんな表現が全部できるんじゃないかというのが、中学校3年生の時の体感だった。
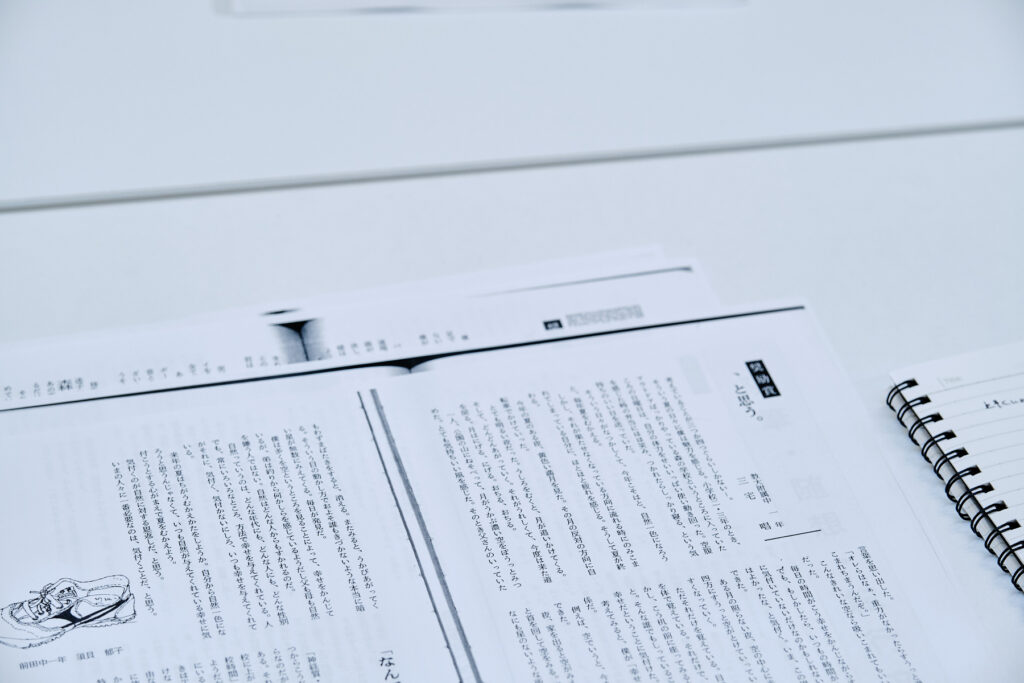
━━映画を見たり、小説を読んだりすることは好きでしたか?
三宅:本を読むのは好きでしたね。2、30年前に読んだ本の名前を出すのは恥ずかしいけれど、ひとつは宇宙飛行士に憧れていた時に読んだ、立花隆さんのアポロ11号を題材にした本、『宇宙からの帰還』。物ごとを調べて1冊の大きい本を書くなんて、とんでもなく頭のいい人がいるんだな、かっこいいなと思った。小説だと村上龍さんの『希望の国のエクソダス』。自分の住んでいる北海道を舞台に、同じ中学生の主人公が日本から独立した国を作ろうとしている話で、超面白いって、自分を重ねて読んでいました。そこから、村上龍って人もかっこいい人なんだな、頭が良くてすごい面白い人だと思って、彼の他の小説を読んだり。
そして彼の対談集を読んで、「すげえ大人が他にもいっぱいいるじゃん」と気づくわけです。中でも映画評論家の蓮實重彦さんがバキバキに面白い。「踊り出す瞬間をどう撮るか」みたいな話をされていて、もう興奮しちゃって、「やっぱ映画ってすげえんだな」と、自分の中での映画の価値がどんどん高まっていきました。「早く東京に行って、もっと映画見たり作ったりしてみたい」と考えるようになって、大学は東京に行くことに。

━━中学以降、映画を撮り始めたのは大学に入ってから?
三宅:うん、高校時代は思春期真っ盛りだったのか、恥ずかしさもあって映画は撮ろうとも思わなかった。でも、大学生になってサークルに入ったんですが、すぐ作ればいいものの、遠回りもしたんです。というのも、学生映画は、学ランとセーラー服を着て恋愛ごっこしているようなものばかりで、この仲間には入りたくないと思ってしまった。だから、一旦自主制作とは距離をおいて、大学1年生の冬に商業映画の現場を紹介してもらって見習いとして参加してみたんです。有名な俳優が出ているショートフィルムの現場で、たった1日だったんだけれど、自分が使えなさすぎて心がズタボロに折れました。カチンコを打つのが役割だったのだけど、午前中の間に僕のカチンコは照明部の人が持って代わりに打っていたし、夕方に登場する小道具のパフェを午後イチからずっと持って、カーテンに隠れているようなひどい状態。自分の無能さに気づくのも恥ずかしいし、怒られるのも嫌だし、こんなことするために東京出てきたわけじゃないとプライドだけ高くて、挫折したわけです。
それならやっぱり自分で映画を作らなきゃと思ったのが21歳の時でした。本当に不真面目な学生で、朝起きたら今日は映画館で何を見ようかなって、毎日、映画のことしか考えていなかった。色々と映画を見ていくうちに、「自分だったらもっとこうしたいな」なんて生意気なことも思うようになっていましたね。
でも、やってみると当然うまくいかなくて。次はもっとうまくいくはずと思って撮るけど、やっぱりうまくいかない。だからまた撮る。そうやっているうちに、あっという間に今になっちゃった。

━━うまくいかないというのは?
三宅:撮る前は「これは傑作ができる」というのが頭の中にある気がするんですね。でも、いざカメラ向けると、「あれ? なんか違う」の連続で。ぴあフィルムフェスティバルのような若手登竜門のコンテストでも、箸にも棒にもかからなかった。
自分にとって大きかったのは「思っていた通りにならんな、これは一体なんなんだ」っていう悔しさです。でも、映画を見たり撮ったりするうちに「あれ? 何か分かったかも」と感じたり。悔しさと面白さの両輪で「まだ続けたい」と思ったので、周りが就職活動をし出す大学3年生の秋から1年間、僕は映画美学校にダブルスクールの形で通い始めました。
━━不安はなかったですか。
三宅:それがなかったんだよね。課題を与えられて、それを撮ってという繰り返しで、1年間はずっと映画のことを考えていたから、将来を気にしている暇もなかった。びっくりするぐらいお金はなかったけど。
大学は6年目に突入する気満々だったのに、ある日、掲示板見たら、卒業が決定した学生一覧の中に自分の学籍番号があって。「あ、やっべ、出ることになっちゃった」っていう焦りは一瞬、あったかな。でも「やっべ、無職じゃん」と思ったのはほんの数日で、もうしょうがないかって感じ。卒業後は、いちおうフリーランスを名乗った上で、テレビ番組のアシスタントディレクターをしたり、企業用の映像を作ったりしながらギリギリ食い繋いで映画を作ろうとしていました。

映画は自己表現ではない。最初にメッセージがあるわけでもない
━━最初に作品を認められたと感じたのはいつでしょう?
三宅:大きいのは、劇場公開1本目の『Playback』をロカルノ国際映画祭コンペティション部門の正式出品作品に選んでもらったことですかね。その映画祭は新人コンペと巨匠も参加するようなメインコンペの2つ部門があるのだけれど、僕の映画はメインコンペで選んでもらったんですね。当時28歳でしたけれど「うわ、思ってもいなかったところに引きずり出されたな」という驚きがありました。うれしいと思うよりも「あ、この仕事続けていかなきゃだな」と自覚するきっかけになったと思います。
━━誰かに認められたいという思いはあった。
三宅:いや、そんなにないかなあ。なんだろうな、映画は自己表現じゃないと思っているから続けられているのかもしれない。
━━自己表現じゃないんだ。
三宅:もちろん、結果、自分は表現されちゃうのだけれど、スタート地点が自己表現じゃないと思っています。たとえば、見たことない海の風景に出会ったら、好きな人にも見てもらいたくなるし、一緒に感動してほしいと思う感じ。こんな悪いやつがいた、こんな面白い話があったと伝えたい感じで、「僕は、こういう風に受け止めたんですけど、どう思いますか」と提案する感覚といえばいいですかね。
感情の吐露とか、自分の考えとか、論理的な考えを表現したいなら、僕は音楽やるか、論文を書いた方がいいと思う。映画は、俳優たちと一緒に別の世界を作っていく作業だし、外からやってくるものを捉える仕事だと思っています。

━━別の世界を作るというのは、何かを再現したいという感じでしょうか。
三宅:再現とは違う気がしますかね。少し話はそれるかもしれないけれど、カメラに映らないけど確かに存在するものがあると思うんです。たとえば、一目惚れする瞬間の心の中の大きな動きは、どれだけカメラを向けても映らないわけです。人が亡くなった場合もいろんな感情が生まれますが、それはカメラに映らないし、そんな瞬間にカメラ向けるなんてそもそも失礼だし。だからこの世界にあるものを再現するというよりは、カメラに映らないものや撮れないものを、俳優たちの演技やストーリーテリングの技術を通じて、フィクションとして表現するという感じですかね。
━━何かメッセージを伝えることが、そもそもの目的ではないということ?
三宅:そうですね。作っていく過程のあるタイミングで作品のメッセージに気づくことはあるけれど、初めから具体的に、文章化できるようなメッセージがあるわけではないです。
━━それ、面白いですね。伝えたいメッセージがあるから映画を撮るわけじゃないんですね。
三宅:見たことないものが見れそうだなという期待からたいていスタートしますよね。映画は100年ちょっとの歴史があって、本当にいろんな作品があるけれど、でも「あれ、こんな映画ないかもしれないぞ」「あ、すっげえいい方法を思いついた」と気づきがあると、わくわくする。

━━自分が見たいものを作る感じですか?
三宅:自分が見たいもの、と言っても、未知のものなんで、どうですかね。見たことがないものを見たい、見たこともないものを探しにいくような感覚かしら。見たことがないものを見たいから映画館に行くことと同じです。「宇宙人が襲ってくるのを見たことない」とか、「誰と誰が恋に落ちるか見てみたい」とかで映画館に行きますよね。すでに見たことがあるものにお金は払いたくないはずだし。
見たことのないものというのは、風景や物語に限らなくて、たとえば、人の顔をまじまじと見ることは、映画だからこそできる経験かなという気がしています。特に日本人は、そう相手をじろじろと見ずに、適度に目を外す。だけど、映画館のスクリーンなら、じーっと人の顔を見られる。それは単に美しい顔だけでなく、そうじゃない顔もまた等しく興味深く見ていられる。
さらに、その人が口で言っていることと心の中で思っていることが違うことにも気づいたりすることもある。実生活で2人がお喋りしている場面があったら、我々はつい喋っている人を見ると思うけど、映画の中だったら、聞いている人の顔の変化をじーっと見ることもできるわけですよね。物を言わなくても「あ、この人、話を楽しんでいるな」「いや、相当ムカついているな」とか、「全く別のこと考えているな」とか、俳優の演技を通して、見えないものを顔から感じ取ることができる。
映画で喋っていない人をじーっと見る経験ができれば、実生活に戻った時にも喋っている人だけじゃなくて、聞き役に回った人にも目を向けられたりするんじゃないかなと思っています。視点が増える、ものの見え方が変わるという感じですかね。自分が映画監督をやっていて面白いなと思う経験のひとつです。

━━具体的なシーンを挙げるとしたら?
三宅:『きみの鳥はうたえる』では、喋る人よりも聞いている人の顔を印象深く撮ったつもりでした。『ケイコ 目を澄ませて』のケイコさんは、手話話者としてもお喋りな人ではないし、だからこそ彼女が一体何を感じて考えていたかということに、99分かけて彼女の全身を見ながら想像する映画だったと思います。新作の『夜明けのすべて』で言えば、基本、メインの2人は比較的お喋りなキャラクターで、2人を捉えるのが重要なんですが、でも同じくらい、2人が勤務する会社の社長や脇を固める人も2人と同じ画面の中でどう捉えるかも、すごく重要な仕事だったなと思います。
映画を観ていて「いいなあ」と思うのは、生き生きしている人を見た時なんです。でも、カメラの前で生き生きするのって難しいですよね? 不安だし、緊張するし。俳優たちは、ただでさえ「好き」とか超照れくさいセリフを、目の前にカメラも照明機材もあるような異常な状態で言わなきゃいけない。
でも、「こんな世界がある」と信じてもらうためには、悩んでいる時だろうが明るい時だろうが、俳優には生き生きしてもらいたい。だから、登場人物が生きている環境をちゃんと設定したいと思っています。すると演技にリアリティが生まれるし、最終的には俳優が生き生きする。そして、本当にその世界が動いているように見える。そこが「面白い」に繋がってくのかなと思っています。火星に行く話とか、古代ローマにタイムスリップする話とか、素面で考えたらリアリティなんて一切ないはずなのに、ちゃんと世界観ができていて俳優たちの体がそこで嘘なく動けていると、リアルを感じることってありますよね。
━━なるほど。『ケイコ 目を澄ませて』を見た時にドキュメンタリーを見せられているような気分になったことがありました。それは私が映画にリアリティを感じていたということなのかなと話を聞いていて思いました。
三宅:そういう風に見てもらえると、「よし、まんまと騙せたな」と(笑)。ボクシングのパンチを実際には相手に当てずに、でも「うわ、痛い!」って思わせられるのが映画の面白さです。東京の河川敷にケイコはいないわけですが、でも、もしかしたら街のどこかにケイコがいるかもしれないなって感じてもらえたらいいなと思います。

━━今までの作品を見ていると、あえて言葉にしてない場面が結構あると感じています。
三宅:そうですね、あえてということでもないけれど、映画で何でもかんでもできるわけじゃなくて、映画にできないこともたくさんある。映画は金がかかるわ、大勢を巻き込むわ、その割に作ってから発表するまで時間かかるわ、非常にどんくさい芸術ですよね。もしかしたら、文章書いた方が早かったり、写真の方がいいかもしれない。場合によっては歌を作った方が感情的に伝えられるかもしれない。じゃあ、そこで映画は何ができるかと考えた時に、人の動きや表情だとかでこそ一発で分かりそうなもので表現した方が伝わることもあると思っています。
━━映画監督として何か目標はありますか。
三宅:夢とか野心はないです。持たなきゃいけないなとは思っているんですけど、ない。お金のかかるような趣味もないし、別に普通に生活できる程度でいいと思っています。綺麗事に聞こえるかもしれないけれど、なるようになるとしか思ってないというか。単に1本、1本、いい映画を作りたい。
━━認められたいという欲求もない?
三宅:欲求が出ると、うまくいかないことの方が多いし、傷つきたくないじゃん。だから、期待しない。今までのキャリアは本当にラッキーだったと思います。でも、もしかしたら野心を持たないことによって、自分が傷つくことを避けていただけなのかなとも思うんで、わからないですね。その欲求があっていい映画が撮れるなら、持ちたいけれど。

40歳手前だから撮れた『夜明けのすべて』
━━ここからは2月9日に公開される映画『夜明けのすべて』について聞いていきたいと思います。今回の作品は瀬尾まいこさん原作の小説と設定が違う部分がありますよね。その辺りは何か意図があったのでしょうか。
三宅:小説を映像に起こすと、必ずしも同じように伝わるとは限らないと思うんですよ。文字を読んで頭の中で想像する自由を、映像はたった1つに制限してしまうこともあるし。大枠として、小説の印象や読後感はキープしたいという思いはあります。細部や具体は変わっているけど、トータルの印象としては変わってないように、とは思っています。
━━同じものではなく、原作にプラスアルファする。
三宅:文字で読むとめちゃくちゃ面白いことでも、実際に映像にすると途端につまらなくなっちゃうこともあるわけです。美味しい食事の説明で、1枚の写真が見事な文字のレポートに負けることは往々にしてあると思うんですよね。小説の魅力を削いでしまうこともあるから、あえてやらないこともあるし。あと、小説ならばセリフ以外にも、心の動きを地の文で表現できるけれど、映像には、役者が頭の中でどれだけ「美味しい」と思ってもそれは映らない。そこで、心の動きをどうしても目に見えるアクションに変えざるを得ないこともある。小説での数行の葛藤を、瞬きや手の震えというアクションに置き換えるということですね。

━━有名な作家さんだとファンも多いですし、原作の内容を変えることに怖さを感じることもあるのでは。
三宅:ええ、怖いです。今回は恋愛するかしないかというところに大きな改変をしないことが最重要だと思っていました。映画化の例で、小説の中では恋愛をしないのに、映画になったとたんに恋愛ものになるケースもあるわけです。それは『夜明けのすべて』ではあり得ない。「主人公2人に恋愛をさせる場合は降ります」と伝えたうえで監督を引き受けました。プロデューサーさんたちも同じ思いだったようで、「いや、この作品は恋愛しないからいいんですよ」と言ってくれたのでうまくいきました。
━━主人公の藤沢さんと山添くんの関係性は心地よいものでした。
三宅:映画で若い男女が出てきたら「そりゃ恋するだろう」って思ってしまいがちだけれど、我々の実社会で恋愛関係にない男女が普通に歩いていたり、打ち合わせしたり、遊んでいることはいくらでもあるわけで。単に、物語にしづらい。物語はどうしても不可逆な構造を持っているものなので、始まりも終わりも曖昧な友人関係は、なかなか表現しづらいんだと思います。あとは、性別を超えた者同士が普通に一緒に働く話を普通に描くことを、今の時代だからこそやってみたいと思っていました。今回はそれができたと思います。
━━見どころを教えてください。
三宅:『夜明けのすべて』の面白さの多くは、瀬尾まいこさんの原作にあると思うので、それをさも自分の手柄のようには語ることはできないんだけれど、そこからひとつ、宣伝だと割り切って言えば、「登場人物がいいでしょ!」ですかね。意外と見たことないキャラクターじゃない? みたいな。でこぼこしているというか。僕もかれらが見たくて、監督を引き受けたので。かれらみたいないろんな側面のある人間は、未熟だった20代前半とかだったら撮れなかったなと思います。
━━未熟だといろんな人間を撮れないというのは?
三宅:こういう人を描くと格好悪いんじゃないかとか、恥ずかしいんじゃないかとか。あるいは自分とは違う存在に対する恐れが出て、登場人物を1人の人間として見られないとか。40歳を目前にすると、20代の時と比べて、どんな人間であっても「そういう人もいるよね」と面白がれる機会が増えたと思います。藤沢さんも山添くんも少し変なキャラクターなんですよね。「でも、変でいいじゃん」って思える魅力が2人にはある。

━━藤沢さんと山添くんが働く会社の人たちが、2人の変な部分を受け入れているところに優しさを感じました。でこぼこして、社会にマッチできてないことに対してネガティブな感情を抱えている人が、世の中多そうですよね。そんな人たちに響く映画なのかなと感じています。
三宅:そうなればいいですけどね。
世の中に変じゃない人なんていないはずですもんね。映画監督だからこうしなきゃいけないなっていうのもないはずだし、男性カメラマンはこんな格好しなきゃいけない、女性記者だからこういう考えしなきゃいけないなんてことがあるわけない。でも、なんとなく我々は「それは変かな」と思ってしまうことがある。それが少しでもほどけていけば、単純に自由になれるのだと思います。
━━俳優さんとは、どんな風に関係を築いていくのですか。
三宅:俳優たちは、芝居をするのが仕事だからこそなのか、人を見る能力がすごく高い方たちだと思うんですよね。目の前の人が「あ、いま嘘ついているな」とか、「この人は本当のことを言っているな」とか、敏感に感じとることができる。いい俳優であればあるほど、そういう感受性が強い人たちだと思うので、そこで、カマかけたり騙そうと思ったり、駆け引きしようとしても、まあ絶対に勝てない。
若い時は、悩んでいると監督としてはダメなんじゃないかと思って、隠すように振る舞ってもみましたが、多分、俳優たちには全部ばれていたと思うんですよね。なので、もう最初から「僕は悩んでいます」って言った方がどれだけ楽か。だから今は「俺のプランはこう」って最初から手の内を見せています。「すごく話せる。オープンな人なんだな、駆け引きをしない人なんだなって思わせられた時点で、俺は駆け引きに勝っているんだ」って、敢えて言葉にして言います。ここまでがひとセット。

━━主演俳優お二人の印象はどうでしたか。
三宅:本気の人たちだったなと今となっては思います。本気と言っても、別に汗かいて歯を食いしばるだけが本気じゃない。ユーモアを忘れないことも、他人に優しくすることも、真剣に悩むことも、本気だからこそ、そうなんだと思います。2人とも、本当に人当たりの柔らかい人ですけど、柔らかいから柔らかいんじゃなくて、人に対して本気だからこそ柔らかいんだなと思います。
━━この作品は、監督として納得がいくものになりましたか。
三宅:はい。やれることはやって全部うまくいったと思いますし、語弊を恐れずに言えば、次はもっと面白い映画が撮れるだろうってことも、同時に思っています。
先ほど、映画制作を始めても最初にメッセージがあるわけじゃないと話しましたが、どんな題材でも、色々と考え抜いていけば、いろんなメッセージがそこから生まれる瞬間がやってくると感じています。それは結果的に世界平和や人間は自由に生きようみたいな、いわゆる凡庸なものかもしれない。それが初めからメッセージとして僕の中にあるというよりは、物語を一緒に通過していく中で、自分の体の中から本当に納得して言えるものとして出てくる。最終的にはそれがお客さんに伝わればいいなと思っています。 (了)

三宅唱(みやけ・しょう)
1984年生まれ、札幌市出身。一橋大学社会学部卒、映画美学校フィクションコース初等科修了。映画『きみの鳥はうたえる』やNetflixオリジナルドラマ『呪怨:呪いの家』、星野源さん『折り合い』ミュージックビデオなど、手がける領域は多岐にわたる。『ケイコ 目を澄ませて』が、第72回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に正式出品され、第77回毎日映画コンクールでは日本映画大賞・監督賞など最多5部門を受賞した。最新作は『夜明けのすべて』。2月9日より全国で公開。
映画公式ホームページ:https://yoakenosubete-movie.asmik-ace.co.jp/
【この記事もおすすめ】







































































































































