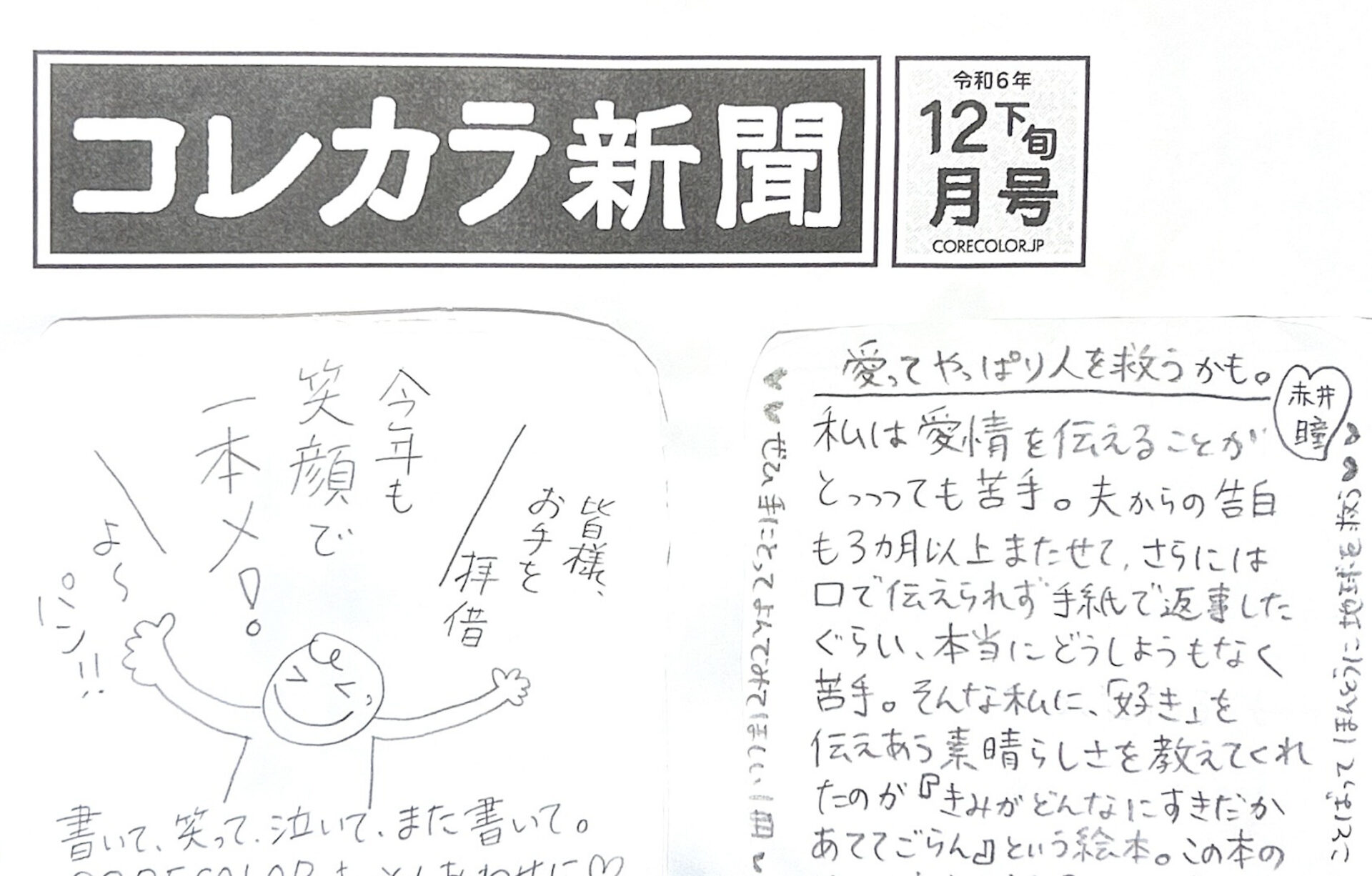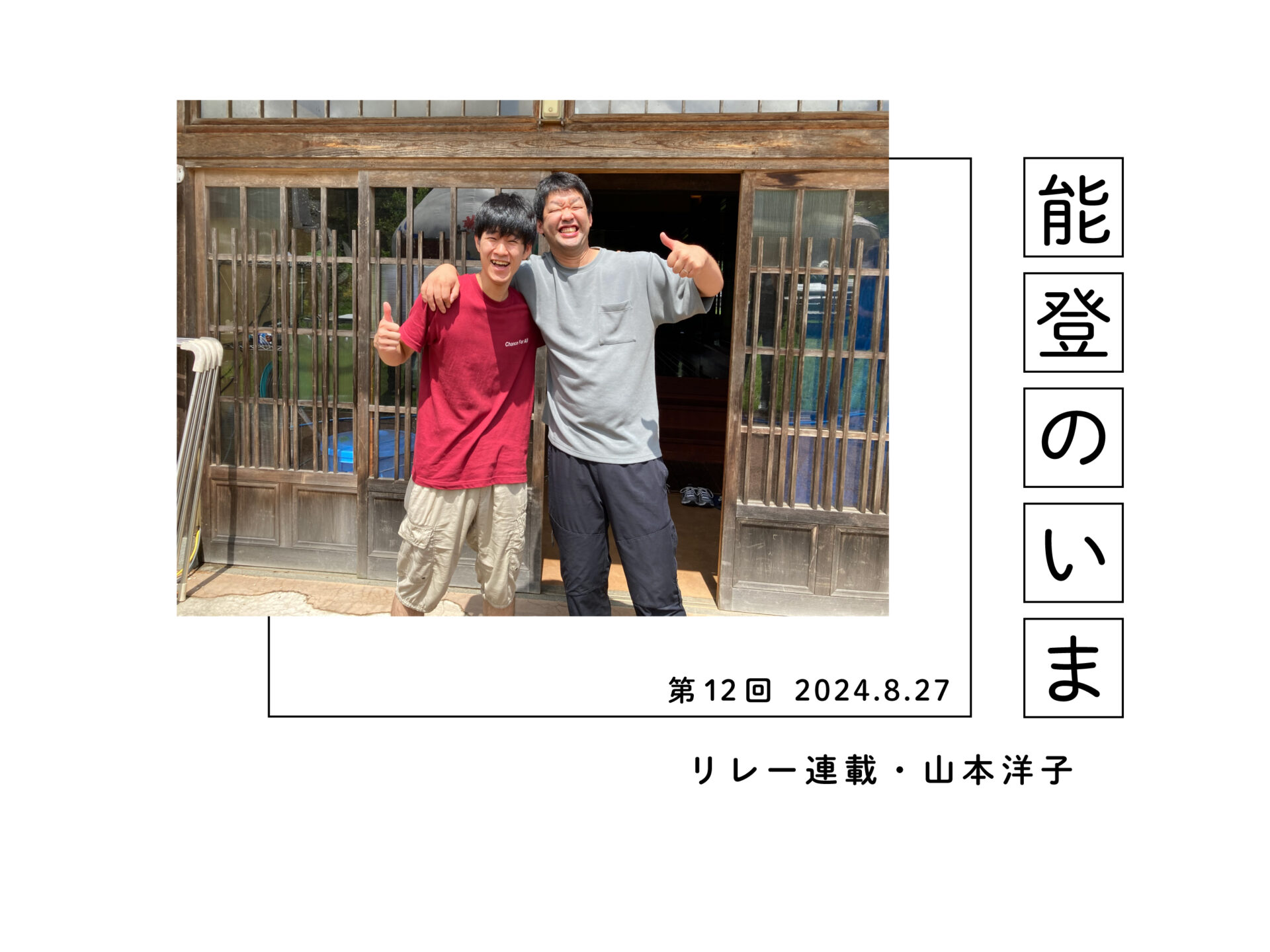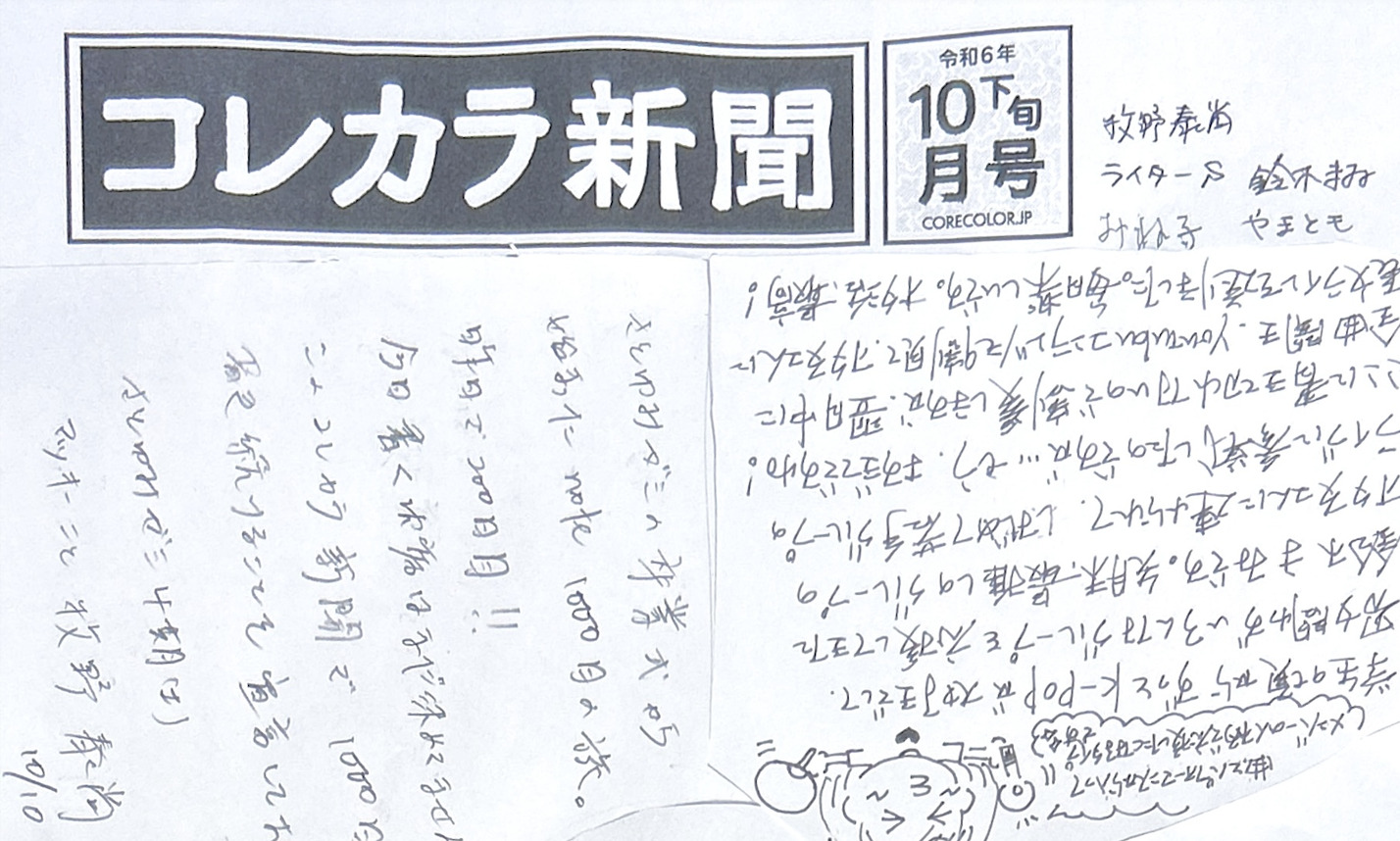#もう来てもいいよ能登〜被災地への移動自粛からの転換【能登のいま/第2回】
石川県輪島市に住む、二角(ふたかど)です。今年1月1日の能登半島地震で被災し、現在は金沢市のアパートで避難生活を送っています。震災に対する報道が少なくなってきている今、いまだ復興の遠い「能登のいま」をお伝えできればと思っています。
ゴールデンウィーク中に国の名勝である輪島市の白米千枚田に行きました。海底が隆起した部分は白く浮き上がっていて地震の暴力に驚きます。それでも、被災しても能登は美しい。いまはそんな情報に安堵しますが、発災当時は美しさなど考える余裕はありませんでした。
1月1日に能登半島地震が発生すると、石川県や国土交通省北陸地方整備局は被災地方面への不要不急の通行は控えて、と呼びかけました。
当時私は近くの小学校に避難していました。正月だったので親戚も帰省しており、彼らはいつ輪島から帰れるのかネットをチェックしていました。X(旧Twitter)では、自動車が走行した後にGPSが使用されたポイントを図示するサービスが紹介されていたので、広く使われていたのを覚えています。輪島市内で通行実績を示す青い点が繋がっていない箇所がある、通行止めなのだ、などと判断していました。タイムラグや抜け道もあるので正確ではないことは分かっていましたが、これ以外に根拠とできる情報がなかったのです。
1月3日には輪島市から脱出する青い点が繋がり、親戚一家は避難所を出発しました。普段なら1時間半もあれば到着できる道のりを8時間以上かけて帰りました。道中は土砂崩れや倒木で道がふさがれ、現場で作業員の方が必死に復旧しながらの経路確保です。片側通行の箇所も多く、待ち時間は膨らんでいきます。避難所を出る前に持参したおにぎりは尽き、用を足そうにも断水でトイレは使えない。ようやくたどり着いたコンビニでトイレに駆け込んだら、汚物があふれていて悲惨な状況だったそうです。
現代の災害ではネットの影響力が大きくなっています。石川県や国土交通省から能登への通行自粛が呼びかけられると、Xは被災地に来ないでという投稿で溢れ返りました。私も必死に投稿したのを覚えています。能登と石川県の県庁所在地である金沢市を結ぶ道路は2系統。自動車専用道ののと里山海道は崩落のため全面通行止め、一般道はかろうじて片側通行で目的地にいつたどり着けるか分かりません。自衛隊や警察・消防・給水の車両が一般道にひたすら並び、ピクリとも動かない時間が続きました。私のいた避難所は、ようやく渋滞を乗り越えた自衛隊の車両がずらりと並び、ここは自衛隊が管理していると勘違いした人がいるくらいでした。避難所は市役所の管理なのでそんなことはないのですが。能登へ来ないでの呼びかけは、一般車両が特殊車両の通行を妨げないようにするためのものでした。
2週間も経つと状況は変わりました。のと里山海道は通行止めのままでしたが、一般道は迂回路を使いながら通行できるエリアも増えました。それでもこんな田舎に首都高速道路かと揶揄された渋滞は続いていました。「地元住民の車両は、朝と夕方の通行を避けるように」と国土交通省からのメッセージも変わっていきます。被災地は水が使えず宿泊できる拠点が少ないので、日中作業してくれている緊急車両は午前に被災地に向かい、夕方に金沢市方面へ帰っていくことで渋滞が起こっていました。時間帯で自粛要請が出されるくらいには改善していたのです。
道路は日に日に良くなり、ゴールデンウィークの頃には通行に支障はなくなりました。のと里山海道は一部通行できないエリアがありますが、大渋滞を引き起こす程ではありません。4月に入った頃から、「#もう来てもいいよ能登」 というハッシュタグを見かけるようになりました。能登人らしく奥ゆかしい表現だと思います。私は、これまで来ないでと言ってきてごめんなさい。被災地は人手が足りていません。ぜひ来てください、という後ろめたさを感じながら発信していたのです。しかし、石川県は4月27日から5月6日に被災地を訪れるボランティアは、直前の1.7倍程度の1万人あまりと発表しています。私も自宅に帰りましたが、道路も被災地も人はまばらでした。報道によれば、発災後約3カ月間にボランティアをした延べ人数は、東日本大震災は約50万人、熊本地震は約10万人。それに対し、能登半島地震の被災地で活動したのは1万人あまりと桁違いに少ないそうです。
これがネットの影響力なのか。一度自粛を呼びかけた事実は消えず、#もう来てもいいよ能登 と呼びかけても、関心が薄れて多くの人には届かないのでしょう。このことを捉えて、発災当時自粛の呼びかけをしたことが良くなかったという声も聞きます。
確かに避難生活が始まってすぐに支援してくれたのは、自衛隊などの公的機関だけではありませんでした。炊き出しをしてくれたり援護が必要な高齢者の血圧を測ってくれたりした民間のボランティアは多くいたのです。通行が自粛されたことで、公的な緊急車両ではない彼らの移動は規制されて大変だったでしょう。大阪から12時間かかったと言った人もいました。実際に現地では民間ボランティアが活動していたにも関わらず自粛を呼びかけたのは無意味だし、その後の根拠のない自粛ムードを払拭できない事態を考えると、批判する人がいるのはある程度納得できます。
しかし、発災後数日は緊急車両の通行を優先し、一般車両の方の往来を規制したことはやむを得なかったと私は考えます。渋滞により、生命の危機にさらされた人がいたからです。私の高齢の親戚は元旦に肺炎にかかりましたが、病院を転々とし金沢市にある大学病院にたどり着いたのは10日以上も経ってからでした。かかりつけ医が駆けつけられなかったこともあり、渋滞だけが問題ではなかったかもしれませんが、陸路が駄目だからと言ってそうそうヘリを飛ばせるような時期ではなかったのは間違いありません。孤立集落の人たちが陸路をあきらめヘリで集団移転するまでに、発災後2週間あまりかかっていました。渋滞したらヘリを飛ばせばよい、というマリー・アントワネット的状況ではなかったわけです。
当時の現地では、助けに来ようとする遠方の家族の申し出を断る人がいるなど、通行自粛の呼びかけを支持している雰囲気を感じました。
さて、6月の状況はどうでしょう。石川県の奥能登地域では、開業医や総合病院が再開しています。地元で医療を受けられる環境が整ったのです。よほどの事態でなければ、輪島から金沢へ緊急搬送する必要はありません。ドクターヘリも使えます。
道路の渋滞も大幅に改善されました。被災地を往来する工事車両が多く見られますが、立ち往生することはありません。一般道はほぼ復旧し、自動車道であるのと里山海道や能越自動車道は、7月末までには対面通行できると発表されました。
「#もう行ったほうがいいよ能登」 というタグを使ってくれる新聞記者さんもいます。自粛を呼びかけていた頃と状況は変わりました。
ボランティアをしなければ被災地に行きにくいという声も聞きます。もちろん、ボランティアできてくださるのはとてもありがたいです。でも、ボランティアでなくても良いのです。被災地で暮らしている人たちに会いに来てください。輪島市に観光で宿泊するのはまだ難しい状況ですが、日帰りでもいいので見ていただきたい。見たら状況を周りの方に伝えてほしい。ぜひお願いします。
文/二角 貴博
主なボランティア募集先
石川県災害ボランティア https://prefvc-ishikawa.jimdofree.com
のと復耕ラボ https://www.facebook.com/p/のと復耕ラボ-61557664922857/
NRN 能登復興ネットワーク いやさか https://nrn-iyasaka.net
【この記事もおすすめ】