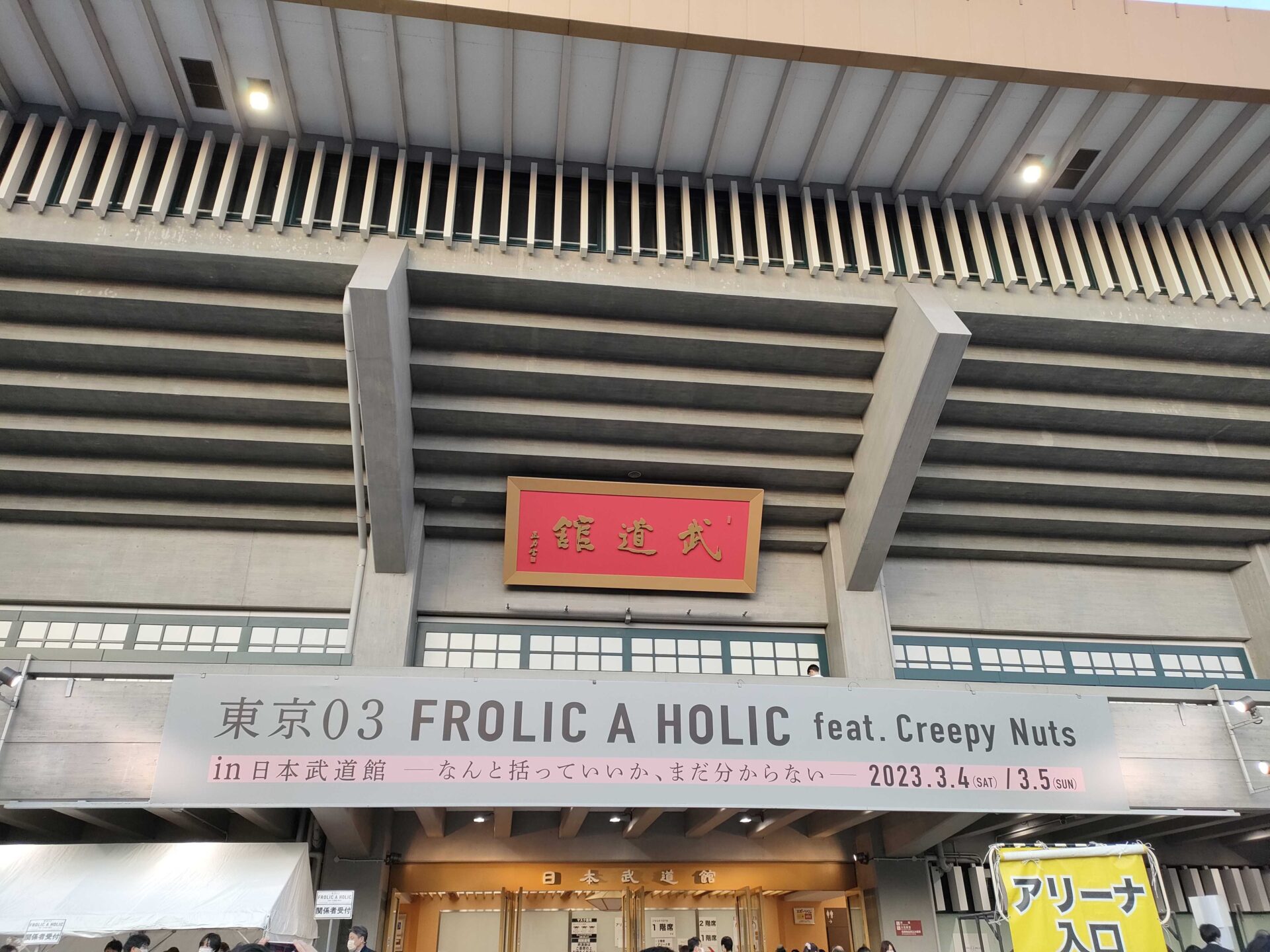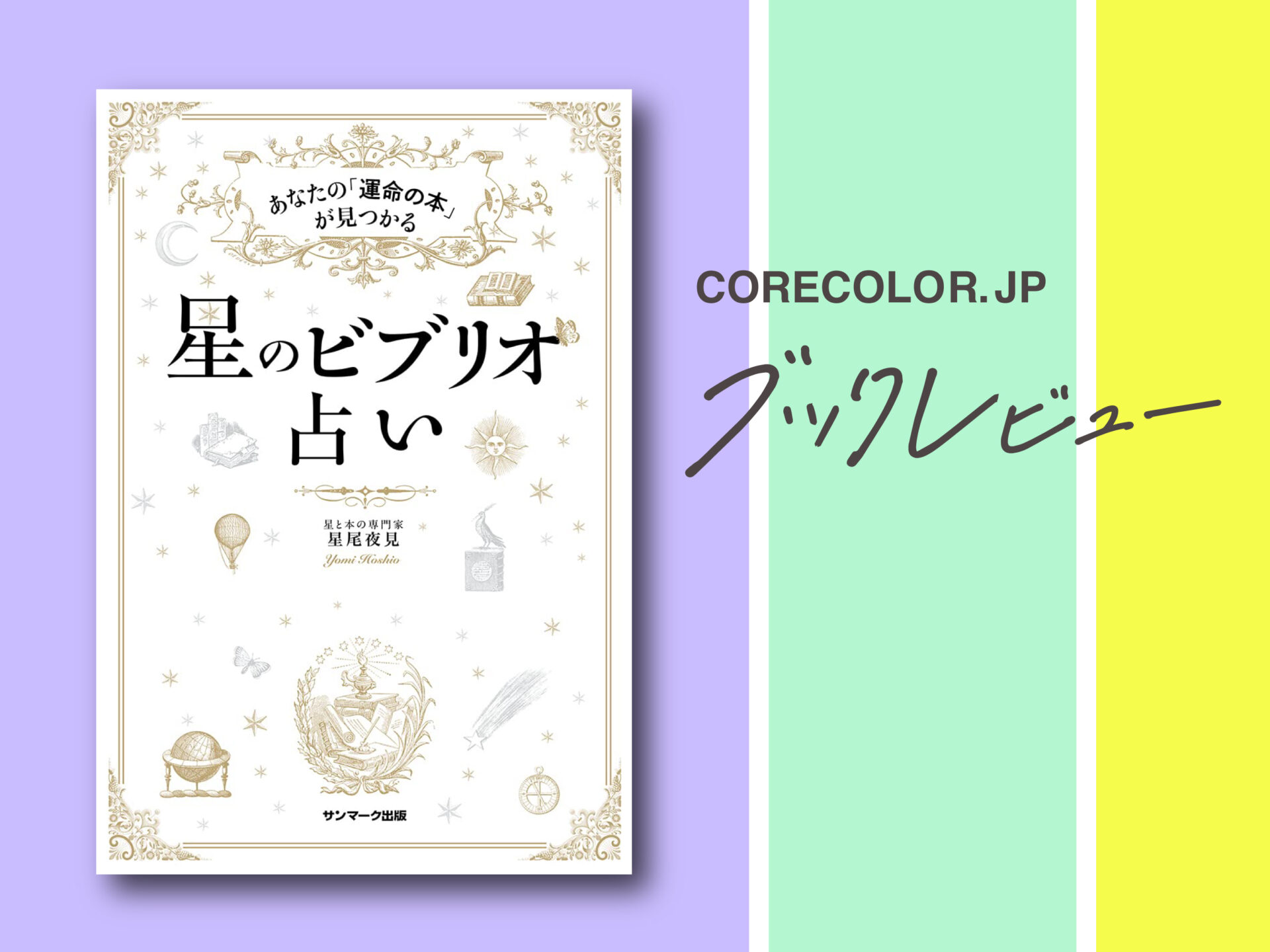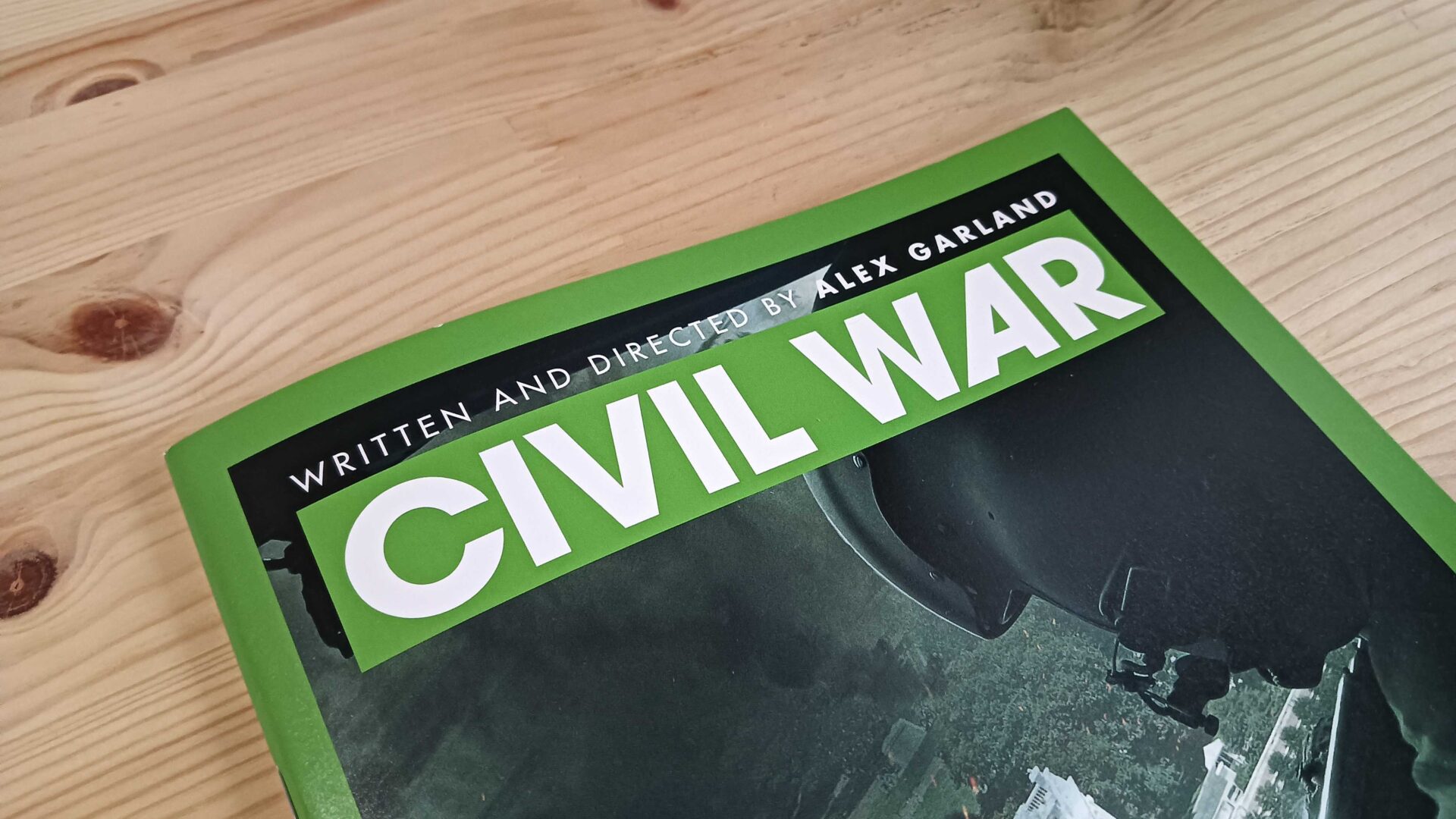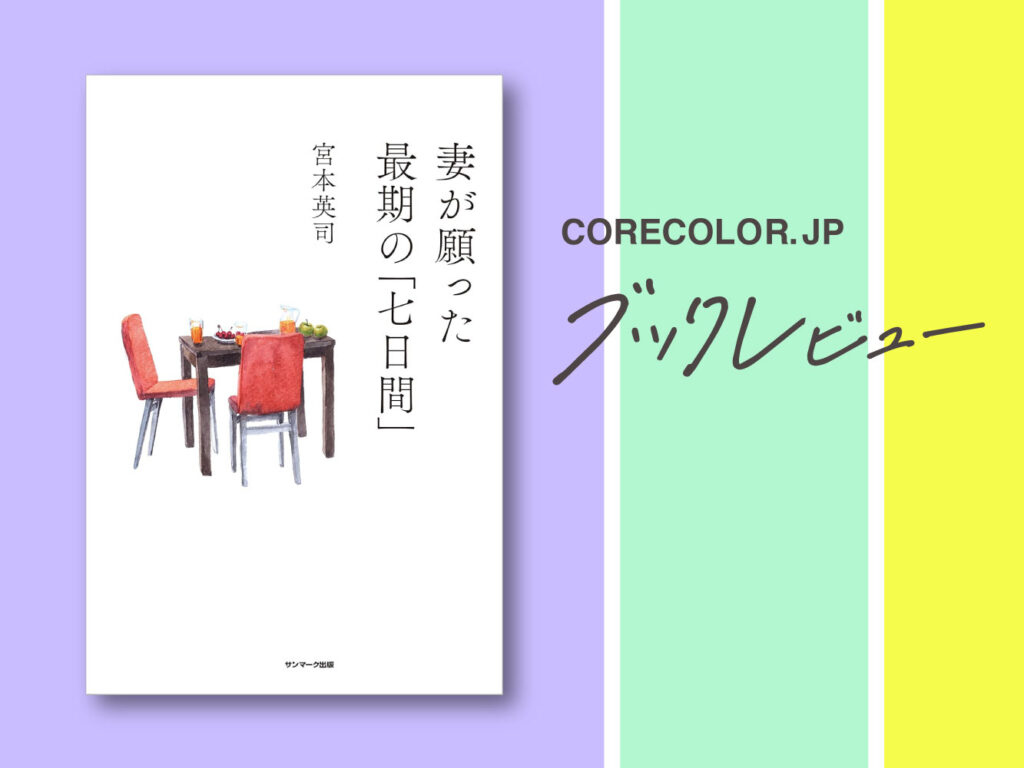
『妻が願った最期の「七日間」』がそっと肯定してくれた今
「いっさいの延命処置はお断りします」
目に飛び込んできた文字に、一瞬、息をするのを忘れた。
「私の病気が現在の医学では治すことができず、すでに最期が近いと診断された場合は、いっさいの延命処置はお断りします」と手紙にはきっぱりと書かれていた。見慣れた母の字だが、いつもよりかしこまった丁寧な文字だった。
その手紙を発見したのは偶然だった。母が昔使っていた資料の束を久々に見ていたら「お願い」と書かれた封筒が出てきたのだ。封もされておらず気軽に開けてしまったにしては、あまりにも内容が重すぎて、腰から背骨にそってゾワゾワしたまましばらく動けなかった。
2017年12月、母は癌と診断された。その2ヶ月前の10月、お腹の調子が悪いからとかかりつけの病院でレントゲンを撮ったところ、よからぬものが写っていた。すぐ別の病院を紹介され、精密検査の結果、癌が発覚したのだった。
それからほどなくして見つけたお願い文だ。あまりにリアルタイムすぎる。何度か読み返すうちに、ようやく最後に書いてある日付に気がついた。2011年7月、病気が見つかる6年も前だ。ん? どういうこと? 記憶をたどると、それは母と私の親子水入らずでマチュピチュ旅行に行く前月だった。旅先で不慮の事故なんかに遭ったときを想定して書いたのだろう。癌が発覚した後に書かれたものでなかったことに安堵するとともに、延命治療は希望しない母の気持ちを知った。
2018年3月、ある新聞記事のことを知った。『妻が願った最期の「七日間」』の表題にドキッとした。その新聞記事は、癌で亡くなった妻・宮本容子さんが闘病中につづった詩について、夫の英司さんが記したものだった。
「神様お願い この病室から抜け出して 七日間の元気な時間をください」から始まる詩は、癌を患った容子さんが、元気になったら何をしたいかが書かれている。料理、お片付け、ドライブ、家族の誕生会……どれもごくありふれた日常の出来事だ。特別なことは何もない。
仕事や雑事に追われて、健康も意識せずに淡々と日々を過ごす私にとっては、ありふれた日常をこんなにも切望するなんて想像できなかった。と同時に、どうしたって亡くなった容子さんを母に重ねてしまう。
当時、母の病状は深刻な状況ではなかったが、治療のせいで体が思うように動かず、家にこもっていることが多くなっていた。ひとりでの外出は不安そうだったので、遠出するときは私が付き添った。母も同じように元気な7日間が欲しいと思っているのかもしれないと感じた。母のお願い文を見つけてからというもの、遅かれ早かれ来る最期の日をどうやって迎えるのかが気になってしょうがなかった。
再び『妻が願った最期の「七日間」』に出会ったのは昨年、場所は本屋だった。迷わず購入したのは新聞記事を読んだ当時とは状況が変わっていたからだ。母は2022年11月に亡くなった。2年ほど経っているのに私は立ち直れていなかった。電車の中や食事中など、何の前触れもなくふと思い出してはため息をつく日々。早く前を向かなくてはダメだ。本を読むことで私の中で何か変わるかもしれないと、ほとんどすがるような気持ちだった。
本には詩そのものだけではなく、詩ができるまでのエピソードや夫婦の物語などの背景が書かれていた。私の目が止まったのは、容子さんが書いた日記のページだ。
2016年8月31日、容子さんは身体の中で癌が大きくなっていたことを明かし「大切なことだけあなたに伝えておきますね。延命治療は、しないでね」とつづった。偶然にも母のお願い文と同じ内容が書かれていてドキッとした。
別の日付の日記には「副作用の苦しかった治療でも、何もしないことへの不安感が出てきて、少しこわい」「日めくりを破くたびに、自分の命がけずられていくよう」など書かれていた。闘病中に書かれた日記であるがゆえの心の機微が感じ取れた。
比べることではないと思うが、私の母はもともと、自分の感情を露わにするタイプではなかった。母として子に弱みは見せないと思っていた気もする。だから癌を患った母の悲しみや苦しみといった負の感情をほとんど聞いたことがなかった。
もう聞けない母の苦悩を容子さんが代弁しているような気がしてならなかった。私が母の死から立ち直れないのは、母の気持ちに本当に寄り添えた実感がないからかもしれない……。
それだけではない。母が亡くなる瞬間、私は一緒にいられなかった。私はそのことをずっと悔いている。大切な瞬間に立ち会えなかったことを母は恨んでいるのではないだろうか。あの瞬間をやり直せるなら……ともう数え切れないくらい考えた。
実は、2016年8月31日の容子さんの日記には続きがある。
「もしあなたがいない時間に私が死んでも、決して後悔しないでくださいね。あなたと関わってきたそれまでの時間が大事なのだから。突然何があっても、私はあなたに感謝し、ずっと愛して、幸せですからね」
目が離せなかった。あぁ私、ずっとこの言葉が欲しかったんだ。容子さんの言葉なのに、まるで母が語ったかのようにすっと染み込んできた。
私は最期のときにばかり気を取られすぎていた。本当はそれまでにもっと楽しくて大切にすべき時間があったのだ。母との思い出を掘り起こす。
毎年春になるとリクエストした若竹煮。定期試験中に食べに行った鉄板ステーキ。こだわりが強い母が愛した秋限定ビールでの乾杯。誰よりも大声で応援してくれた運動会。「これは何?」と聞くとたいてい返ってきた花の名前。そして、花嫁の私よりもニコニコしていたバージンロード。
それは容子さんが欲した七日間の日常と重なった。最期にだけ目を向けるのではなく、楽しい時間にも目を向けることこそが、私の後悔を和らげるのではないか。そんな気がした。
過去の記憶をたどっていたときにもうひとつ思い出したことがある。母の病状が重くなり、治療方針をどうするかなどの命に関わる選択を自身で判断できなくなるときがくる。その判断がひとりっ子である私にゆだねられると知った母が、私に言ってくれた言葉だ。
「もし私に何かあっても、あなたがしてくれた判断なら、どんな結果になっても受け入れるし後悔しないからね。思うようにしていいよ」
どんな結果になっても後悔しないという言葉を、最期のときを一緒に迎えられなくても後悔しないという意味にとらえるのは軽はずみすぎるだろうか。でも未来に私が苦しまないように私をおもんばかってくれたのだ。そんな発言をする人が、最期に一緒にいられなかった私を責めることなどあるだろうか? いや、ないと信じたい。
本の最後には英司さんの、まだ気持ちの整理がついていない心情も語られている。まさに今の私だ。でも故人との向き合い方は人それぞれで、急に前向きになれない人だっている。葛藤の渦の中にいるままでもいいのだと気付かせてもらい、固まっていた身体と心がふっとほぐれた気がした。いつか母への想いと適度な距離感を保てる日がくるのだろうか。母との楽しい思い出も最期のときもまるっと抱きしめて一緒に歩んでいく。それが今の自分にできる精一杯なのだ。
文/田川 りえ
【この記事もおすすめ】