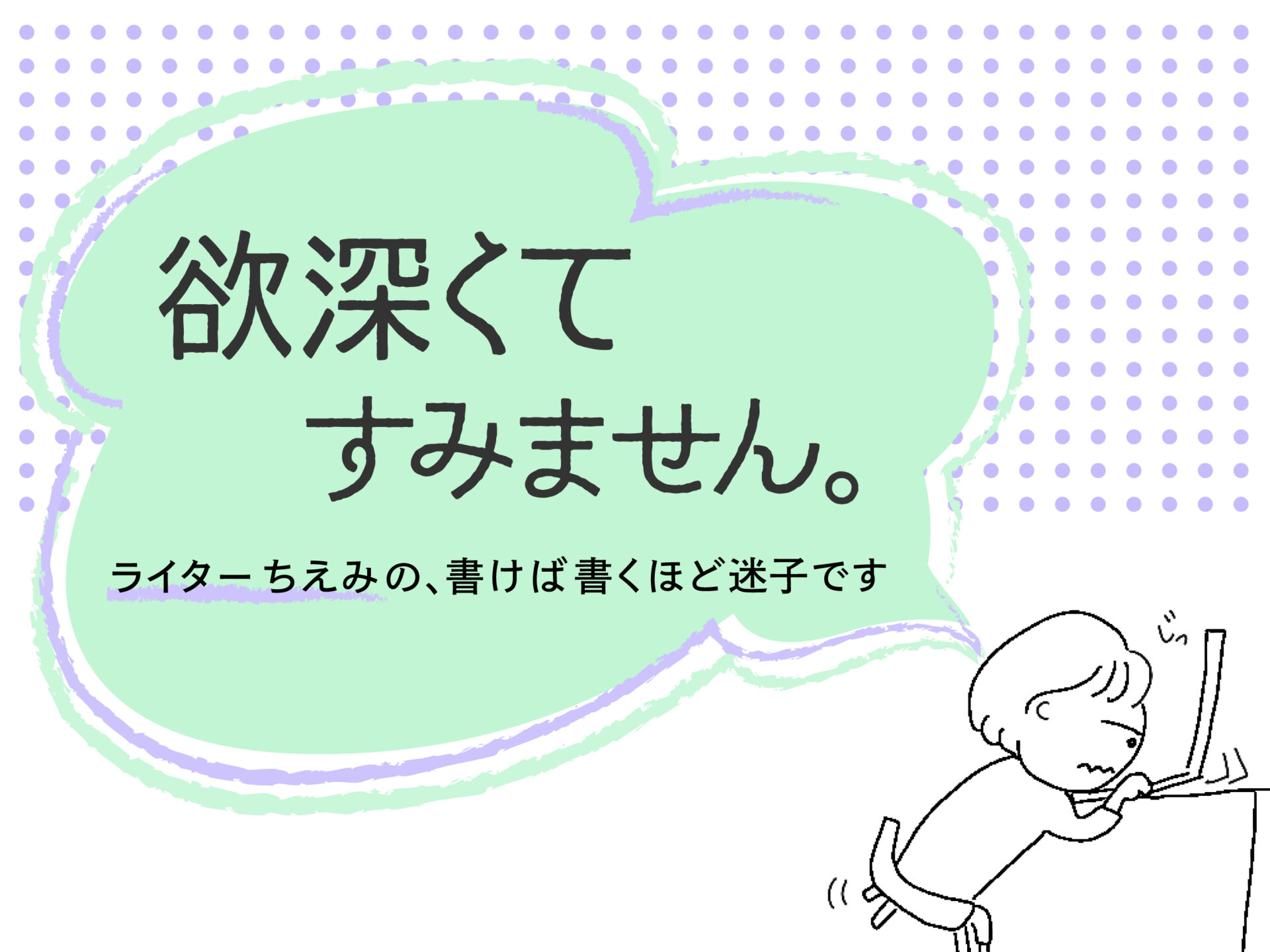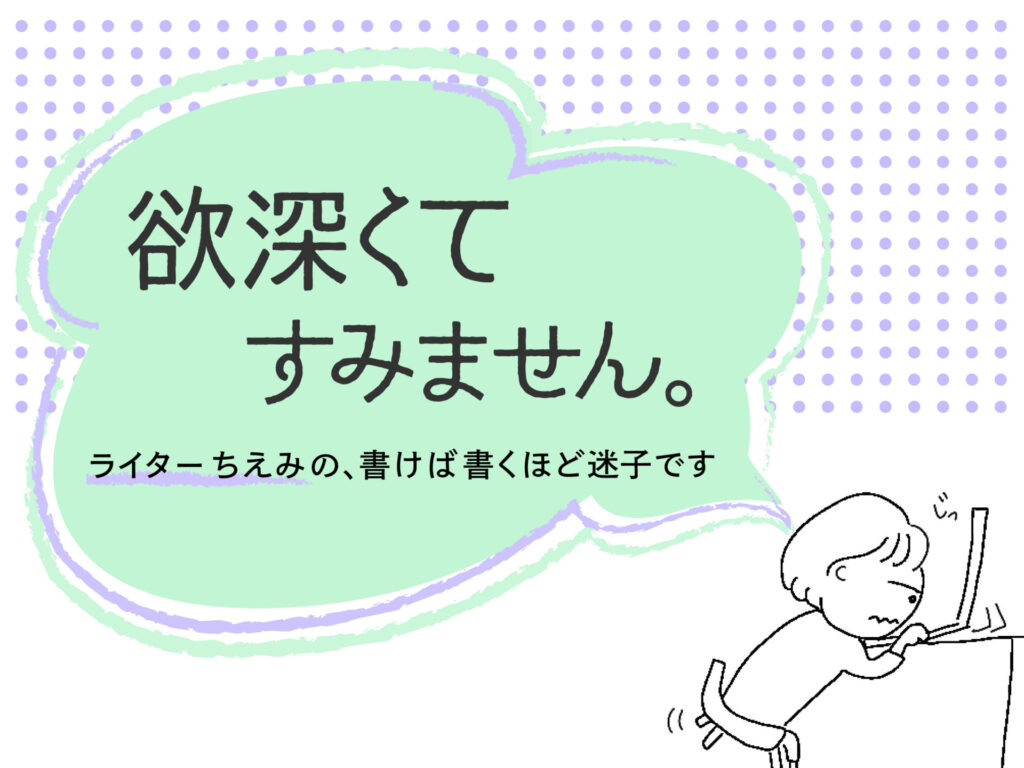
こうして文脈は変えられた。悪意なく起きる「捏造」と、その裏にある吸引力高めの欲とは【連載・欲深くてすみません。/第31回】
元編集者、独立して丸9年のライターちえみが、書くたびに生まれる迷いや惑い、日々のライター仕事で直面している課題を取り上げ、しつこく考える連載。今日は、人の話の文脈を改変することについて考えています。
事実と虚構の見分けがつかないような情報が飛び交い、選挙の結果すら左右する時代である。ささやかながら文章を書いて生活している身としては、ありもしないことをさも事実のように語る、いわゆる「捏造記事」を書くことのないように、できる限りの事実確認をせねばと思う。
ただし捏造とは、できごとや発言、事実のでっちあげだけではない。もっとナチュラルに、悪意もなく行われる捏造がある。
「文脈」の捏造。
これ、すごく厄介ですよねえ、という話をこれからします。
*
つい先日も、捏造の瞬間にばったり遭遇した。
仕事先の方、仮に山口さんとする。お会いするのは何度目かの、たいへん性格のよい山口さんと、会議室で打ち合わせをしていたときのこと。雑談の流れから、お互いが育った家庭環境の話になった。
私は何気なく「そういえば、我が家は子どものときから児童書や図鑑をたくさん買ってもらっていましたね。朗読のテープを家の中で流していたのか、ナントカ君がどこかを旅する話(うろ覚えだな)を繰り返し聞いていたのを覚えています」なんて話をした。
へえ、そうなんですねえ、と山口さんが相槌を打ったところで、山口さんの上司が会議室に入ってきた。仮に坂本さんとする。坂本さんと私は初対面。山口さんが、私を坂本さんに紹介してくださる。
「こちらの方はライターさんで、子どもの時から本をたくさん買ってもらって育ったから、文章を書く仕事に就かれたそうですよ」
はいっ、それ、捏造です!
審判、今すぐピピーっと笛を吹いて!
あえて指摘するほどでもない、とその場はやり過ごしたのだが、どうにも気になってしまい、山口さんと二人きりになったときに、私から打ち明けた。
「あの、細かくてすみませんなんですけど、私『本をたくさん買ってもらった』とは言いましたが、『本をたくさん買ってもらった“から”ライターになった』とは言ってないんです。そこ、たぶん因果関係はないです」
ああ、わざわざ言うほどのことでもないのに、こういうの言ってしまう自分がいやだよ。しかし性格のよい山口さんは気分を害した様子もなく、そこそこ大きな声で「まあ!」と声をあげ、くすくすと笑い出した。えーっと、どうしました?
「以前からお仕事をご一緒していて『なぜ、この人は文章を書く仕事に就いたのだろう』と興味があったんです。それで、家に本がたくさんあったと聞いたときに『だから言葉に関わる仕事に就いたんだわ!』と安直に結びつけてしまったんですね」
今度は私が大声で「まあ!」と叫ぶ番だった。ちょっと、今あなたすごく大事な話してます、山口さん。
そうなのだ。人がもつ関心の中に「納得のできる理由を知りたい」という類の欲がある。そして「理由」を探していると、因果関係のないもの同士をつい線で結んでしまうことがあるのだ。
*
これはインタビューの現場で、本当に気をつけなければいけないことだと私は思う。
というのも、インタビューを受ける人物とは多くの場合「何かのプロフェッショナルの道に行き着いた人」「他の人のしていない体験をしている人」だ。すごくいやな言い方だが「成功した人」でもあることが多い。その人を前にしたとき「なぜ、この人は、ここまで行き着くことができたのだろう?」と興味がむくむく湧いてくることがある。
その興味自体は悪いことではない。成功のヒントらしきものや、自分にも真似できるエッセンスを求めて、誰かの話を聞きたいと思うのは自然なことだ。
しかし「なぜ」のハテナは、ものすごい吸引力をもっている。ドラマ『相棒』だって『科捜研の女』だって、「なぜ、そうなった」の答えがわからないまま物語の幕を閉じられたら、翌日テレビ局まで走っていって、プロデューサーの胸ぐらをつかみ「ねえ、なんであんなことが起きたのか教えてよお! こっちはすっきりしたいんだよおおお!」と答えを迫ってしまいかねない。
「あ〜、だからか」と気持ちよく納得できる答えが、今すぐ欲しい。この欲が行き過ぎると、無意識のうちに、目の前の言葉をきゅーっと引き寄せ、論展開のパズルに無理やり押し込んでしまう。
「子どもの頃から、機械やロボットのおもちゃが好きだった」と、取材相手が言う。あ〜「だから」ロボット工学の道に進んだんですね、と私は続ける。
「ひとつハマったら、とことん打ち込むほう」と、取材相手が言う。あ〜「だから」何度失敗しても、繰り返し実験を続けられたんですね、と私は続ける。
う〜ん、そう、ですね。と、取材相手は曖昧に笑う。
本当は、その人がロボット工学を専攻したのは、たまたま行きたかった研究室が定員オーバーで、そのとき空きがあったのがロボット工学の研究室だけだったのかもしれない。本当は、繰り返し実験を続けたのは、結果を出さないと研究費を打ち切られるため、何がなんでも続けるほかなかったのかもしれない。
しかし、私と違って奥ゆかしい取材相手は、わざわざ訂正してくれない。まあ、そう言われればそうだったかなと、思い込んでくれることもある。
そうして文脈は、わかりやすく納得感のあるほうに、静かに捏造されていく。
早く事件の種明かしをしてほしいと、テレビ画面の前でうずうずするのは勝手だが、「早く納得してすっきりしたい」と思いながら取材に行くのはよろしくない。点と点をつなげるのに必死になるのではなく、ただの点と点のままで見つめていると、ぼんやりと、別の形でつながりが見えてくることだってある。
焦るな、がっつくな。わかりやすい結論につなげる前に、待て!
その「待て!」の技術が結構大事な気がする、今日この頃である。
文/塚田 智恵美