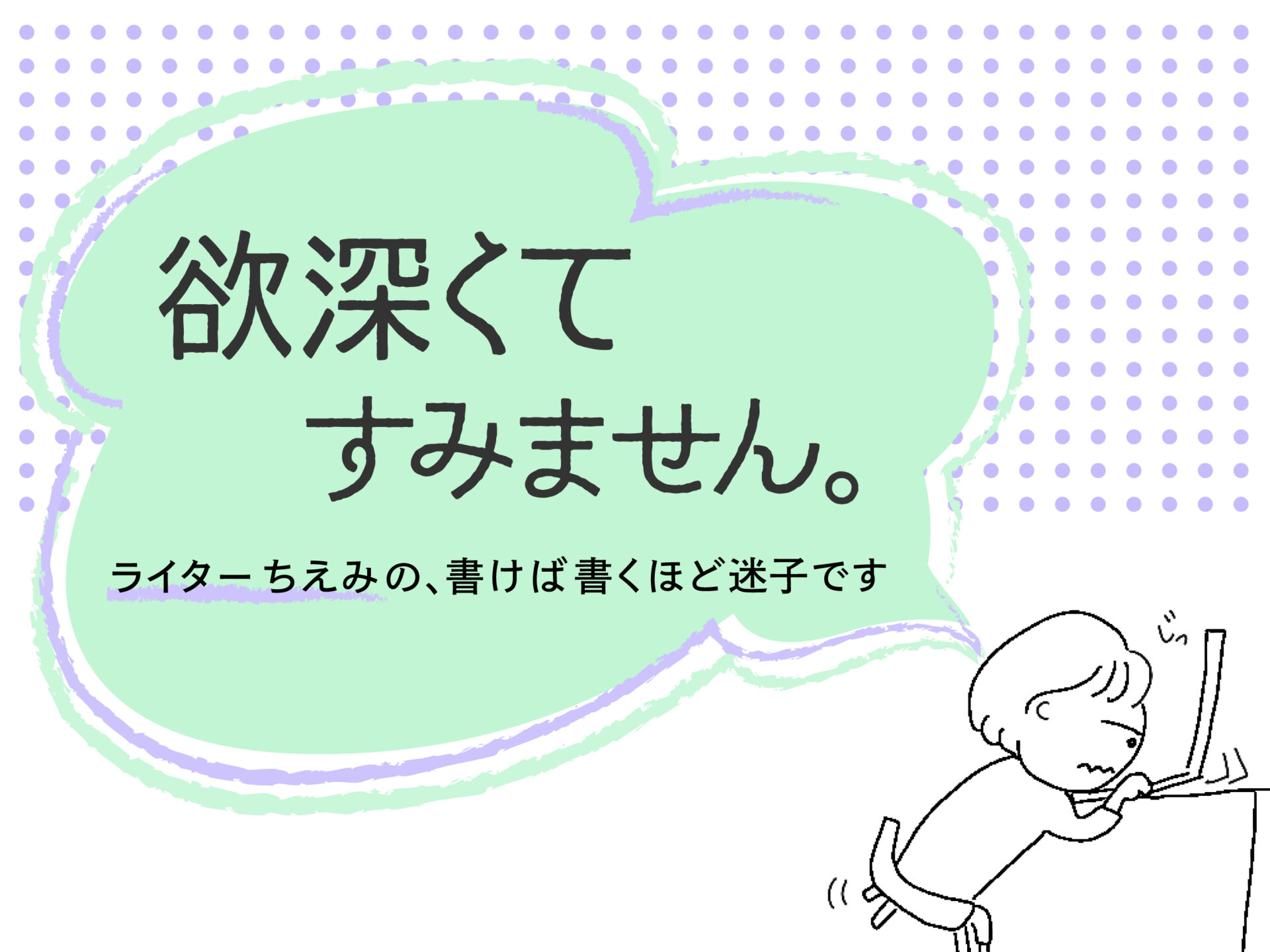罪悪の影に触れるとき。押見修造『罪悪』をめぐる私的考察【連載・あちらのお客さまからマンガです/第29回】
「行きつけの飲み屋でマンガを熱読し、声をかけてきた人にはもれなく激アツでマンガを勧めてしまう」という、ちゃんめい。そんなちゃんめいが、今一番読んでほしい! と激推しするマンガをお届け。今回は、ふと蘇る苦い記憶と向き合う中で響いた押見修造先生の『罪悪』について語ります。
<本文>
この季節になると、嫌になるくらい色々なことを思い出す。少し肌寒くなって、感傷的なムードが後押しするからなのか。それとも、今年ももう少しで終わるという区切りの気配がそうさせるのか。理由はよくわからないけれど、この時期の私は、電車を待つ間や、カフェで注文を待つ間、あるいは日課の散歩の途中など、ふとした瞬間に遠くへ意識が飛んでいることが多い。
そのときに思い出すのは、ずっと昔のことだったり、ここ数年のことだったり……。でも、それは決して楽しい思い出ではなく、かといって大きな傷跡というわけでもない。ただ、心の奥に静かに沈殿して、消えきらないシミのように残っている出来事たちだ。
例えば、うんと幼い頃に自分のせいで亡き祖母に惨めな思いをさせてしまったこと。10代の頃、姉に捻れた嫉妬をこじらせた挙句、自分が勝てる部分を必死に探して見下していたこと。損得勘定で友人を選んでいたこと。大人になってからは、忙しさにかまけて大切な人のヘルプを無視してしまったこと。大して親しくもない人に自分の手の内を明かすのが嫌で、本当は戦略的に積み重ねてきた努力を、偶然のご縁のように適当に語ってあしらったこと。
そうやって自分の奥に沈澱している苦い出来事を思い返すたびに思う。今、好きな仕事をして、好きなように生きて、そこそこ幸せに暮らしている私の足もとには、踏み倒してきた何かや、置き去りにした誰かの痕がある。罪に問われるようなことではなくとも、無数の傷や誰かの涙の上に今の自分が立っているのだと気づいてしまう。
そんな、決して清くも潔白でもない自分を嫌というほど認識して、そのたびに「だからこそ頑張らなければ」と、意味のわからない奮い立たせ方をしてみたりもする。自分のような人間が幸せになったり成功するはずがないから、せめて誠実であろうと足掻く。そんな、ちょっといびつな贖罪の努力をしながら生きている。
押見修造が描く「罪悪」という名の影
つまり、この季節になると、私はやたらと自分の罪悪と向き合い、身勝手な贖罪をすることになるのだが、そんな今の私に、他人事じゃないような気持ちで刺さった一冊がある。前置きがずいぶん長くなってしまったが、それが押見修造先生の『罪悪』だ。
『惡の華』や『血の轍』を代表作に持ち、現在は『瞬きの音』を連載中の押見修造先生。『瞬きの音』では、これまで封印してきたという実弟との記憶を掘り起こし、その記憶を通して自身の原点をえぐるように描き出している。
そんな押見先生が、『瞬きの音』の連載と並行して、昨年の今頃から「罪悪読切シリーズ」と題した作品群を次々と発表している。いずれもタイトル通り“罪悪”を題材にした読み切りで、それらを一冊にまとめたのが今回紹介する『罪悪』である。
本作には「ひろみ」「足の話」「美術部」「壁の向こう」の計4編の短編・中編が収録されており、それぞれが押見先生自身の中に沈む罪悪をもとに描かれた物語だという。私はそんな本作を読んだとき、率直に「罪悪にもジャンルがあるのか」と興味をかき立てられた。
例えば冒頭の「ひろみ」は、押見先生が小学生の頃に同級生へ抱いた罪悪をめぐる懺悔譚であり、まさに「人間関係の罪悪」と呼べる作品だ。一方、「足の話」は、自身の身体や生活にまつわるエピソードで、「生活系の罪悪」とでも呼びたくなる。ものすごく小さなレベルで言えば、ニキビができたら触らない方が良いし、大人しく薬を塗れば良いのに……なぜか傷めつけたり、放棄してしまいたくなるような、自分でも説明のつかない不完全さ。生き方や癖の中でふと生まれる、自己発電的な罪悪感とでもいうのか。そんな新鮮な罪悪の味を感じた。
さらに「美術部」で描かれるのは、他者の目とは関係のない「自意識由来の罪悪」だ。もしかすると周囲は何も思っていないのに、自分の中だけで膨らんでいくような後ろめたさ。押見修造作品に通底する人間の過剰な自己認識が、ここでは静かな痛みとして響いているようだった。
罪悪は、消えず、育たず、ただ残る
『罪悪』を読み終えたとき、罪悪感に共感して気持ちが軽くなる……なんて綺麗事は一切ない。むしろ本作は、許されることも、消えてなくなることもない苦い部分を、まるで標本のように淡々と並べてみせる。そうして、自分の心の奥に沈んでいる苦いものにそっとラベルを貼り、いま自分がどこに立っているのかを照らし出す。
また、読んでいて改めて痛感したのは、罪悪とは「成長の証」でも「反省の記録」でもないということだ。どちらかといえば、自分の中に確かに存在する嫌らしさや、浅ましさ、愚かさと対峙し続けるための“視点”のようなものだと思った。自分の醜い部分を直視して、「思い出したくない」と押し込めてきた感情を、あえてもう一度見つめ直す。その行為こそが、自分という生きもののあらゆる境界線を確かめ続けることなのだと思う。
そして考える。たとえ罪悪という色のついた記憶であっても、過去を思い出すこと自体は悪いことではない。思い出すたび、私は何度でもあの日に戻る。戻っては、何も変えられないまま、ただ“自分を見張っている”という事実だけが残る。
その往復運動こそが、私が私として生き続けるための、最低限の営みなのだと。そんなことを、最後に収録されている不思議な読み心地の「壁の向こう」を読み終えたとき、強く思った。
文/ちゃんめい
【この記事もおすすめ】