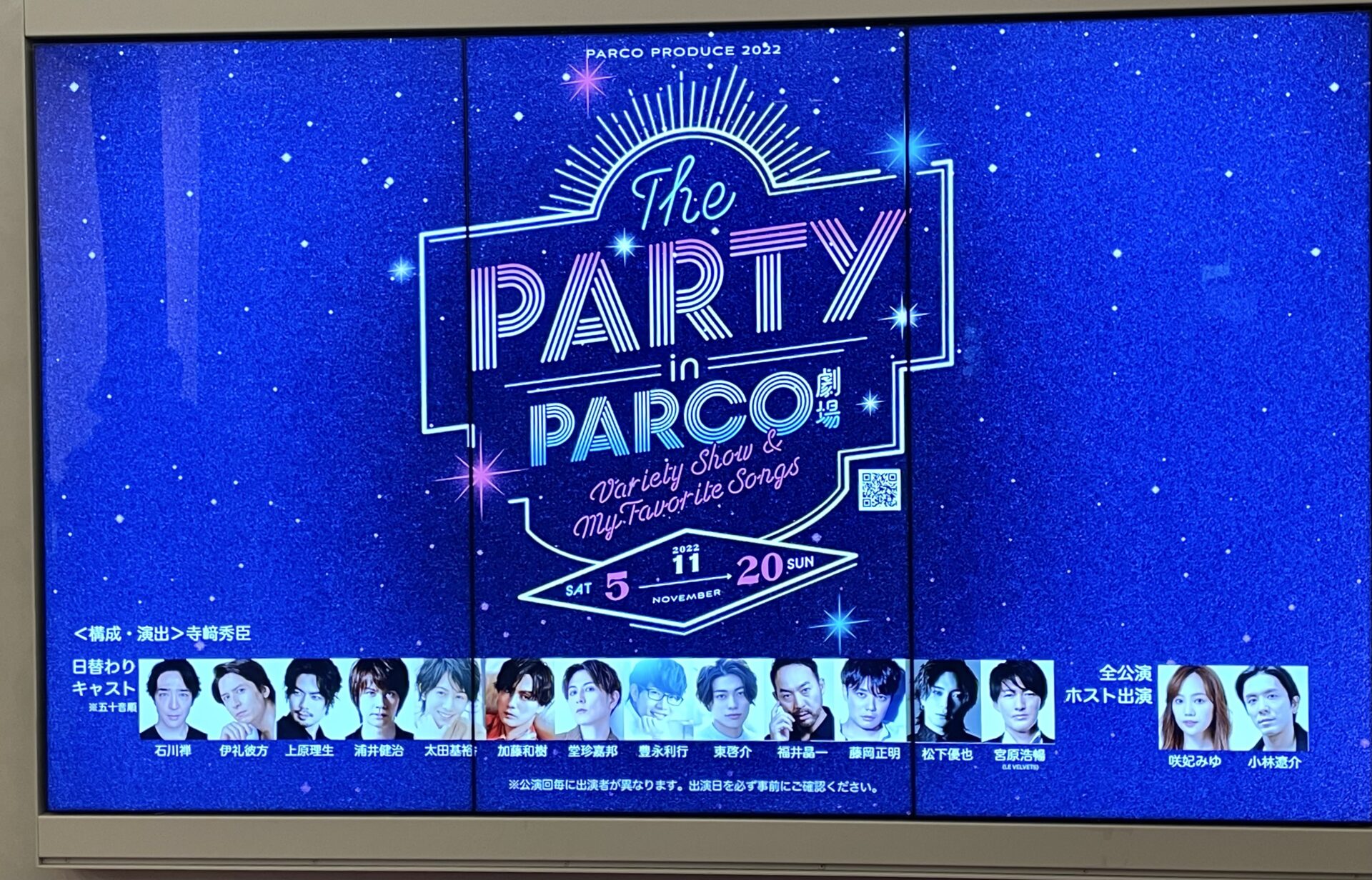何が、誰が、あの親子を「孤独」の闇に閉じ込めたのか。『子宮に沈める』上映&トーク&ワークショップイベント
二人の幼い子どもを夫に預け、向かった先は東京渋谷。ハチ公前から、スクランブル交差点を渡り会場へ向かう足取りは、軽やかとは言えなかった。それは、これから観る『子宮に沈める』という、2013年に公開された映画のテーマが、あまりにも、子育て中の私には重いものだったからだ。映画の元となった2010年に大阪で起きた育児放棄事件は、思い出すだけで同じ母親として許しがたいもので、イベント中冷静でいられるか自信がなかった。
会場のある建物に入ると、光が差し込む明るい空間に目を細めた。それまで心に持っていた重りが、ふと紛れるような、いったんゼロにしてくれるような感覚があった。受付では、この映画の主演でもあり、イベントのプロデュースをする伊澤恵美子さん本人が出迎えてくれた。映画の主演者が自分の映画のイベント企画をすることは、ほぼないのではないだろうか。本映画を通して、見た人とともに何かを考えていきたい、というイベントへの伊澤さんの強い意志を感じた。
30人程度入る会場は満席。大学生ぐらいの女性から、今まさに子育て中と思われる女性、子育てが一区切りついたぐらいの女性と年齢層は広かった。男性の姿も数名見られた。テレビで見る映画のイベントでは、舞台と観客の間に距離があることが多い。しかし、このイベント会場には、舞台のようなものは一切なかった。映画関係者もゲストも観客も、『子宮に沈める』という映画を囲んで、とてもフラットな空間を共有していた。
95分間の上映が始まった。冒頭のシーンは、母親が生理になり、経血がついた下着を洗い、洗濯機を回す様子が描かれていた。思わず、ぎょっとした。人の生理を映像で見ることに慣れていなかったからかもしれない。この生理のシーンに込められた、監督から投げられている問いを、その後90分間考え続けることになる。
前半のシーンは、幸せそのものの親子の生活が描かれていた。ピクニックのために、てるてる坊主を作る娘と、朝早く起きて鼻歌を歌いながらお弁当を作る母親。休日、子どもから「ピクニック行きたい~!お弁当作って!」と言われ、ため息が出てしまう私に比べて、絵にかいたような理想的な母親の姿だった。映画の元になっている事件を知っているので、この親子の結末は分かっている。しかし、どうしてもこの幸せな空間が、悲劇に変わる想像ができなかった。
映画の中盤から、次第に母親の心の状態が変わってきていることが分かる。セリフでは「離婚」「引っ越し」「シングルマザー」という言葉は一切出てこない。描かれている情景、人物の言葉遣いや表情を見て、「もしかして……」が徐々に、「やはり」という確信に変わっていく。
主人公の母親は、離婚後仕事を始め、忙しくなる。バタバタする朝に、子どもに「早くして」と声をかけ、わざと牛乳をこぼす娘にイライラする。夜は外で買ってきたお惣菜をテーブルに広げる。まるで、余裕がない時の私を見ているようだった。映画の前半は、完璧な母親の姿に、自分との距離感を感じていた。しかし、中盤のシーンでは、「私にも、あるある」と親近感を持つほどだった。この親近感に、子どもを産んで初めて、自分が母親であることが怖くなった。なぜなら、「私みたい」と自分を重ね合わせた母親が、ここから、後半にかけて、自分の欲を追い求め、育児を放棄し始め、子どもを死に追いやるという悲劇を生むからだ。
私自身を擁護するわけではないが、後半の母親の行動は、私の子育てとは大きくかけ離れている。この映画の元となった事件に対しても「なんでそんなひどいことを子どもにできるのか理解できない」と他人事に感じていた。しかし、上映後のトークイベントやグループワークを通してその想いは変わった。この母親は、決して特別で異常な人なのではなく、誰にでも、そうなる可能性があるのだと。
上映後は、監督の緒方貴臣さん、主演の伊澤恵美子さんのトークが始まった。また、中央区、渋谷区、品川区の女性議員の方もゲストで参加していた。「映画で投げかけられている問いに対して、アクションを起こして社会を変えるには、行政の大きな力が不可欠。そんな想いで女性議員の方をお呼びした」と、子育てアドバイザーであり本イベントの司会である河西景翔さんが話していた。
トークイベントでキーワードになったのは「母親の孤独」だった。シングルマザーで、水商売をし、ホストにおぼれ、育児放棄をし、子どもを死亡させた、という事象だけを見ると、「けしからん母親だ」と、母親個人の人間性を批判するだけに終わってしまう。でも、この映画を観た後、決して主人公の母親の人間性だけを批判する気になれなかった。それは、子育てを経験した人の誰もが、1度は感じたことのある「孤独」が描かれていたからではないだろうか。
この映画では、最初から最後まで、親子の生活が社会から閉ざされた家の中だけで描かれている。母親は24時間ずっと、家の中で子どもと過ごしている。母親の孤独は、子どもの孤独にもつながる。家の中しか知らない幼い子どもは、どんな母親であっても、世界でたった一人の母親に愛を求めるしかないのだ。閉ざされた家の中には、世間の声も情報も届かない。たった一言「助けて」と母親が外の誰かに言うことができれば、もしくは、外の誰かが声をかければ、救えた親子だったのかもしれない。
監督、主演、議員の方へ、イベント参加者から、次々と質問が投げかけられた。議論が白熱し、予定の進行スケジュールを超えたが、司会の方が議論を止めることはなかった。今回のイベントの一番の狙いは、映画を見た後に、自分の想いをアウトプットしシェアする場を作るという事だったからだ。最後に予定していたグループワークも、休憩なしで行われた。
このグループワークでは、全員が椅子を並べて囲み、それぞれの立場から意見を交わした。「わたしの意見なんて」と思うことなく、参加者が発言できる空気が、そこにはあった。
この映画の扱うテーマは、非常にセンシティブなもので、もしSNSで発言したら炎上する可能性すらある。でも、立場関係なく、お互いの想いや経験を話し、議論できたのは、何よりこのイベントの雰囲気が「安全」な場になっていることの表れだったのではないだろうか。これはイベント企画した方の、会場選びから、イベントの内容など、細部にわたる心配りがそうさせたのだと思う。
そもそもなぜ、映画公開から10年経って、このような参加型のイベントが開かれたのだろうか。イベントを企画した、主演の伊澤さんは、こう話していた。「この映画に出演した後、3年ぐらいは心を閉ざして、ずっと自分が罪を犯した気持ちを抱えていました」と。しかし、上映から10年経ち、当時は非難ばかりだった映画への世間の反応も、少しずつ、ポジティブなものに変わってきたそうだ。「この映画が、孤独で人に頼ることができず苦しんでいる人の助けになれば」と。だから、上映するだけではなく、映画のテーマについて、みんなで対話し、一人ひとりがアクションを起こすきっかけになる場を作りたかったと話していた。
映画は10年前のものだが、まさに今の社会課題を映し出しているように感じた。それは、コロナ禍で今まで以上に母親が社会から切り離され、「孤独」が高まっているからだ。はたして「孤独」はその人自身が生み出した、自業自得な状態なのだろうか。実は、「子宮に沈める」というタイトルには、社会が親子を「子宮=孤独な空間」に閉じ込めてしまった、という意味が込められている。
子宮は、女性の象徴的な「性」を表す臓器だ。子宮に命を宿し、この世に産み落とした瞬間に、社会からは「母親」と扱われる。「母親なのだから」という社会の見えない圧にどれだけの人が苦しんでいるのだろうか。日本社会では、人に助けを求めることは「甘え」や「人への迷惑」と捉えられることも多い。母親を「孤独」から解放するためには、社会の意識を変えることが大事だという、監督からのメッセージが、この短いタイトルに凝縮されている。
「自分には何ができるだろうか」というモヤモヤした想いを抱えながら、帰宅すると、二人の娘が「お母さん~」と駆け寄ってきた。その日も、いつもと変わらず子どもと遊び、洗濯し、食事をし、子どもを寝かしつけて1日が終わった。映画の主人公の母親と同じような日常だ。イベントが終わった後、映画のシーンと自分の日常が重なるたびに、心がざわついた。母親として過ごす当たり前の日常で、自分でも気づかないうちに「孤独」になってしまうのかもしれない。映画の親子の状況は、自分や周りの家庭でも起こる可能性がある。イベント直後よりも、日常生活に戻ってからの方が、映画が伝えるメッセージを、自分事としてかみしめるようになった。
今日、澄んだ冬空の下で、私は映画の母親と同じように「幸せなら手をたたこう」を子どもと歌っていた。どんな人の上にも平等に空はあってつながっている。この空のように、個人と社会のつながりを絶たないために、何が自分にできるだろうかと今もなお、問い続けている。
文/赤井 瞳
【この記事もおすすめ】