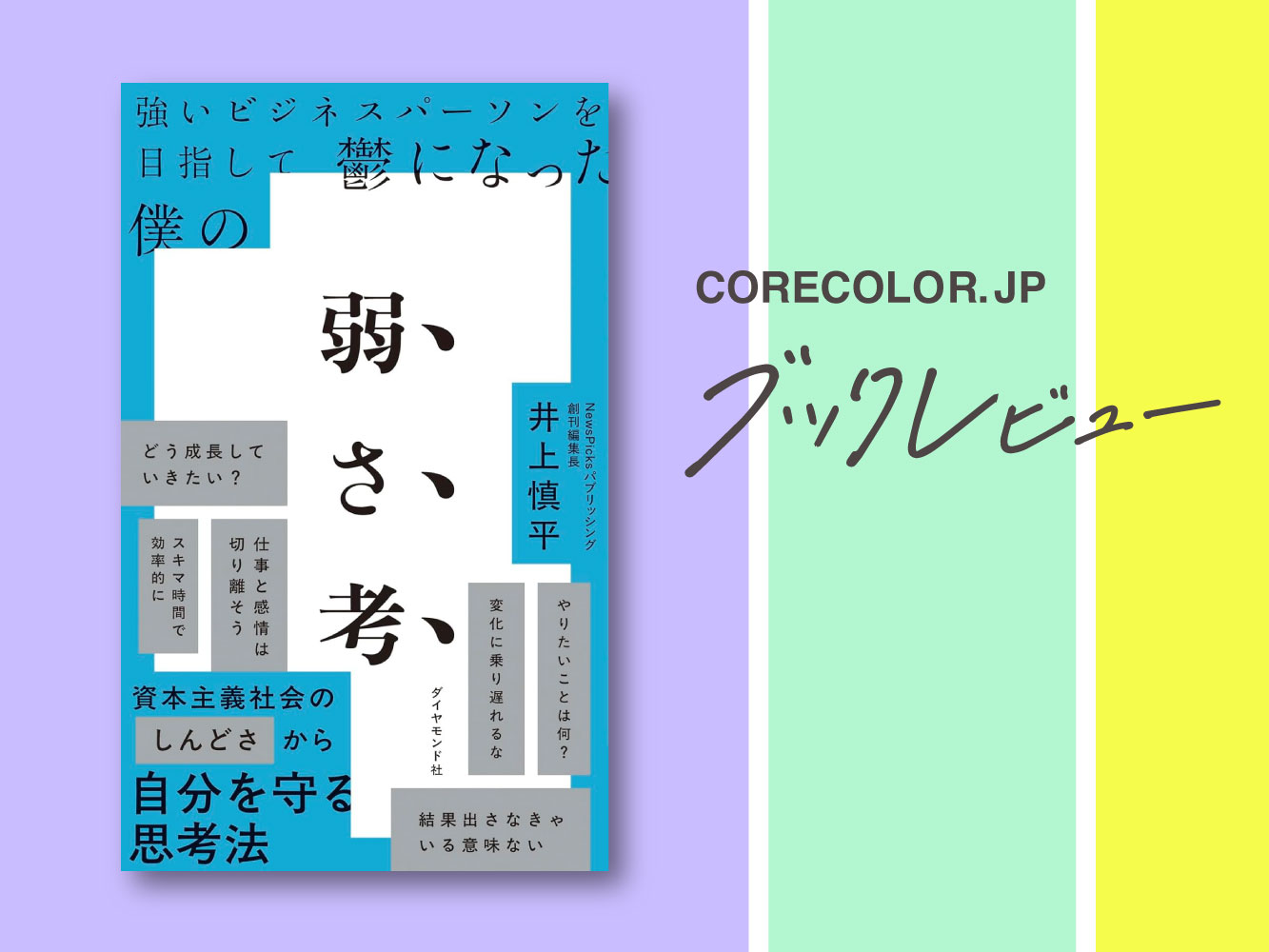あの危機を乗り越えた先にある『愛にイナズマ』
この映画のフォーマットは、自分が今まで観てきたものとは少し違った。「たのむから、この映画を観てくれ!」今僕は、人の足にすがりついてそう叫びたい。もしそれで観てくれたとしても、僕には何の得にもならないのに。なぜだろう? この作品のことを人に伝えたくてしょうがないのだ。
松岡茉優さんと窪田正孝さんが主演、助演に佐藤浩市さん、池松壮亮さん、仲野太賀さん、高良健吾さん、趣里さん。全員が主役を張れる俳優だ。なぜこの方たちがこぞって出演するのか。その理由は、この作品が訴えるメッセージにあるのかもしれない。
松岡茉優さん演じる花子と、窪田正孝さん演じる正夫は、人と話すときにマスクをしている。コロナ禍の様相だ。現実世界ではあの頃、人と人との距離は離れ、話す機会があってもマスクの下の表情は想像しながら会話するしかなかった。もどかしかった。
映画界も、あのとき多大なる被害を被った。いくつもの企画が止まってしまい、有名な俳優でさえ自宅待機する方もいたそう。ただ家でじっとするしかない日々に自分の無力さを感じたのは、私たちだけではなかったはずだ。自由に活動できるようになった今の状況は、当たり前ではない。きっと、映画界の皆さんも同じ気持ちなのだ。
この作品では、正面からコロナに言及することはほとんどない。その代わり、建前で人と接したり、自尊心が邪魔して嘘を伝えてしまうようなコミュニケーションによって、すれ違う人たちを見せる。マスクを付けていてもいなくても、コミュニケーションには隔たりが生まれてしまう。マスクの着用が個人の判断に任されるようになった今、「心のマスクをまだ被っていませんか?」とこの映画は問いかけてくるようだ。
花子は新人映画監督だ。花子の映画を担当するプロデューサーは、根拠のないシーンをカットさせたがる。しかしコロナ禍を経験した花子と私たちは、コロナがそうであったように、根拠のないことも突然起こることを知っている。映画の見やすさを優先して根拠のないシーンをカットするのか、現実に近い支離滅裂な映像を撮るのか。観客は現実を主張する花子に味方するが、商業上の都合を偶像化したプロデューサーが立ちはだかる。現実を目の当たりにしたのに現実を描けない映画人の悔しさが、スクリーンを突き抜けて観客にぶつかってくる。
日常が戻ってきた今、コロナ禍という日々はまるでカットされた1シーンのように遠くの記憶となりつつある。しかし映画人にとっては非常に悔しい記憶だろう。根拠のないシーンを残すべきか、消すべきなのかという議論は、「じゃあコロナ禍を無かったことにできるか?」という問いに近い。映画ではカットされるシーンでも、忘れてはならない。製作陣の切実な訴えが、 この映画には込められていた。
松岡茉優さんは物語の前半と後半で大きく環境が変わる本作で、場面によって豹変する花子というキャラクターを、しかし人間に一貫性を持たせながら演じている。自分とプロデューサーの考え、どちらが正しいのかを実家の家族との会話で見出すが、その瞬間を表情だけで観客に教えてくれる。物語全体をぐいぐいと推し進める情熱的なエネルギーのほとんどは彼女から発信されていて、体力と精神力を相当消耗しただろうと想像できる。しかし最初から最後まで、スクリーンから唾が飛んできそうなパワフルな演技も、凝視していないと見落としそうな細かい目の動きも、完璧に演じあげている。全ての演技に毛細血管が行き届き、彼女の意思が注がれきっているのを感じた。そんな天才的な演技でも凡庸な花子のキャラクターに則り、スクリーンには独特の優しさをともなった貫禄が漂う。
鑑賞中に少しこわくなったことがある。佐藤浩市さんは、ひょっとしたらこの作品を最後に引退すると言い出しやしないかと、観ていてハラハラしたのだ。花子の父親として登場するが、役柄と重なるように、次の世代へのバトンを渡すために本作品に出演しているような、そんな印象を受けた。それほどに、花子含む子供たちを見つめる眼差しは、日本の俳優界の若者たちを見つめるような、暖かくて大きなものに感じた。僕は監督でもないのに、この作品に出ていただいたことに対して「ありがとうございました!」と伝えたくなった。それは、この映画の訴えを援護して日本の映画界を次の世代に価値あるものとして残す、そんな意気込みを感じたからだと思う。
いや、携わった方全員に「ありがとうございました!」と伝えたくなってしまうのだ、この作品は。俳優に関しては、一人ひとりが主役を張れるような存在であるのにも関わらず、ほんの一部しか出演されていない方や、前半あるいは後半しか出演していない方も多く、この作品に対して「やるっきゃねえ!」と熱い情熱を持って取り組まれたことを感じずにはいられない。しかも、その多忙を極める俳優陣のスケジュールをなんとか調整し、撮影期間たった21日間でオールロケで撮りきったそうだ。英語タイトル『Masked Hearts』に乗せておくるこの作品は、演者もスタッフも関係なく全員の気持ちのたまものだと思う。
主題歌であるエレファントカシマシさんの『ココロのままに』。この曲がリリースされたのは1998年だが、花子本人にインタビューして書いたのでは? と思うほど、奇跡的に彼女のキャラクターにぴったりな歌だ。映画と楽曲が、運命的な出会いを果たしているように感じた。
本来なら重いテーマなのかもしれないが、軽快に、けれど水ぶくれしそうなほどにじんわりと赤くて熱い愛を伝えてくれた『愛にイナズマ』。コロナ禍で数々の映画の企画が頓挫していく中、1人の監督が書いたオリジナル脚本の映画だ。疎遠だった花子の家族たちにも、絆は確かにあった。スクリーンから飛び出してきそうなほどにエネルギッシュな花子が、失くしてはいけない何かを、不器用だけれどどっしりと伝えてくれる、そんな作品だ。
【この記事もおすすめ】