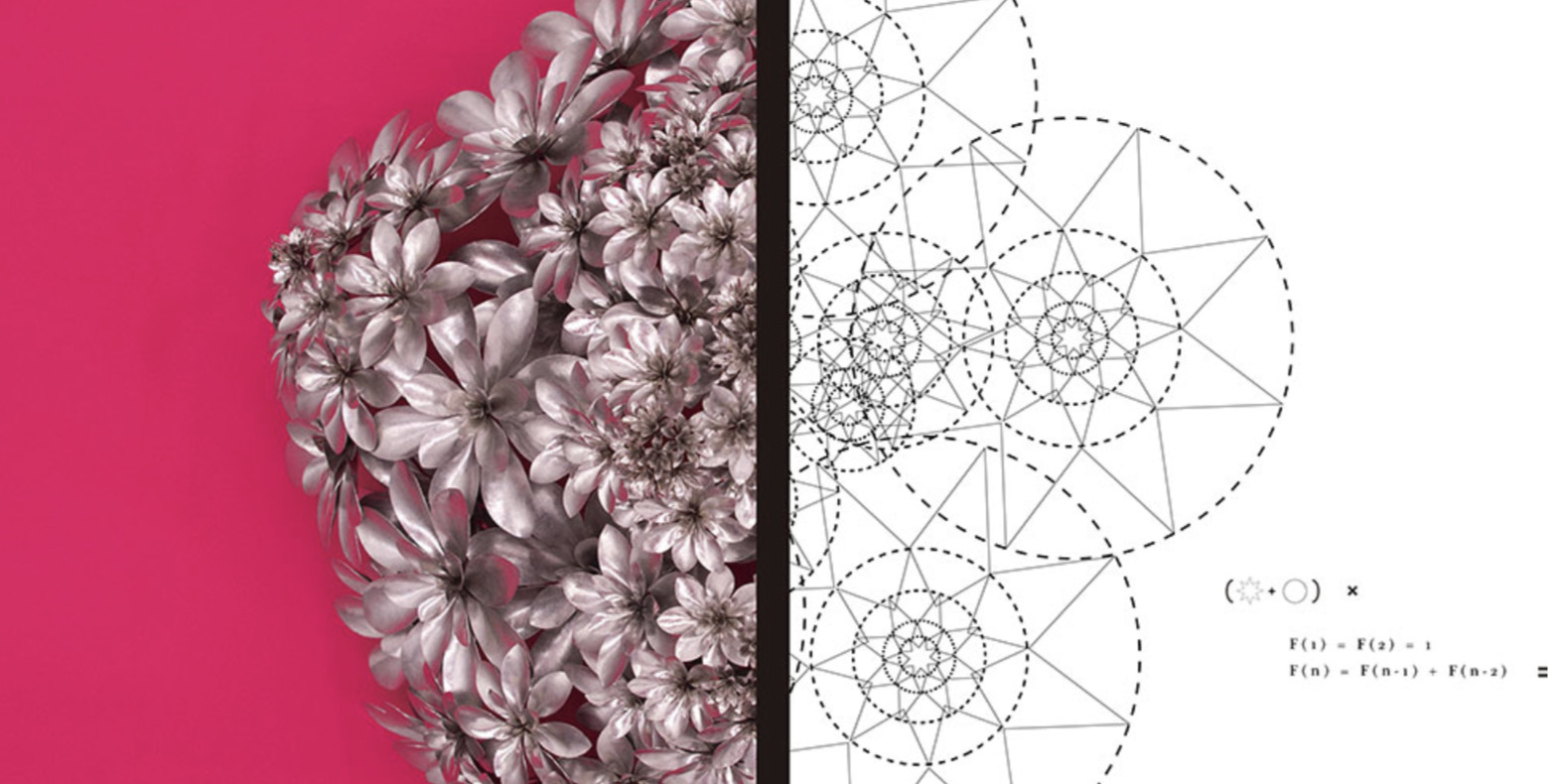私の一部が欠けても、大丈夫。私は私。『くもをさがす』
私には乳房が2つある。何をそんな、あたり前だろと思われるかもしれない。だけど、私の母と亡くなった祖母には1つしかない。正確には、2人とも40代半ばで1つ失った。
そして、作家の西加奈子さんには、2つともないという。西さんの著書『くもをさがす』でそれを知った。
乳がんサバイバーである母と祖母をもつ私は、「いつか自分も乳がんになる」というあまりよくない予感と、ずっと共存している。来るべきいつかのために、20代前半で相応の医療保険にも入った。年に1度の検診だって欠かさない。私と1歳しか違わない西さんの、乳がんの闘病記であろう『くもをさがす』を手に取ったのは、自然な流れだった。
でも、『くもをさがす』は私が想像していた本ではなかった。確かに本書は、西さんがカナダで浸潤性乳管がんを告知されてから治療までの過程が綴られている、闘病の記録だ。登場するカナダ人の医師や友人たちのセリフが関西弁で書かれているからか、何を読んでいるのか最初はとまどってしまった。この本は、日記ではないの? エッセイ? 物語?
「ああ、あるな。1センチのしこり。よく動くし、見つけにくかったやろ?」
読み進めたいのに、やけに生々しい関西弁がページをめくる手を緩める。でも、それでよかった。すらすらと読み進めてしまったら、母の闘病時の記憶の波にのまれてしまったかもしれない。
*
「乳がんがみつかって、リンパ節に転移してるって。手術するから、実家に帰ってきてくれん?」
25年前、電話で母からそう告げられ、泣いた。本書にも、西さんを心配し、涙する人たちが登場する。たくさんの友人たちが、抗がん剤投与を行う彼女を労い、子どもを預かったり食事を届けたりしている。術後も、しばらく自由のきかない体で日常生活を送る大変さは、母の側にいたのでわかるつもりだ。
なのに、なんだろう、このおもしろくない感じ。
今私が病に伏しても、手を差し伸べてくれる人はきっとそんなにはいない。そう、嫉妬だ。しんどい治療を受け続け、抗がん剤の副作用で口の中に膜のようなものが張り、髪の毛がパラパラと舞い散る彼女に嫉妬したのだ私は。
情けない。自分にがっかりしたのはそれだけじゃない。
あのとき、母を想って流したはずの涙は、自分のためだと気づいたからだ。母を失うかもしれない恐怖と、看病で帰省するために職を失う絶望感。私は「私が」かわいそうで泣いたのだ。母の闘病時の記憶がよみがえってつらいと感じたのは、そんな自分と対峙することだとわかったからだろう。
*
本書に、乳がんサバイバーである看護師が、西さんに問いかけるシーンがある。
「乳首って、いる??」
私の母は、もう痛い思いをしたくないという理由で「いらない」選択をし、乳頭も、乳房も再建しなかった。再発しないまま25年経つ。今は裸を目にするまで、母が乳がんだったことを忘れている。人の目がある温泉でも、母はまったく胸を隠さない。
ずいぶん前だが、母と妹と連れ立って実家近所の銭湯へ行ったとき、あまりにも多くの人と親しげに挨拶を交わしていて、驚いたことがある。妹いわく、「私たち有名人なんよ」と。そこは回数券を買うほど妹と母のお気に入りで、通いはじめたとき、母のない胸を見て銭湯の常連さんたちが次々と声をかけてきたそうだ。
「片胸がないおばあちゃんに、ガリガリの私。この2人がしょっちゅう来るようになったんやもん。目立つやろ? 今日、“また1人増えたわ”って思ってるよきっと」。
当時あるストレスが原因で体重が大きく減っていた妹は、ふっ、と目で笑いながら、そう言った。私の右の足指には、先天性疾患による大きな傷がある。乳房に、体重に、足指。何かしら足りない3人を、脱衣所でも、浴室でも、誰もじろじろと見てこなかった。いや、その日私が気づいていなかっただけかもしれない。
可笑しそうに話した妹のことも、「そうやね」と答えた私のことも、なんとなく好ましい記憶として残っている。あのときの私たちは、かわいそうではなかったと思う。
*
西さんは、治療の過程でさまざまな選択に迫られ、決断を繰り返す。家族や友人の支えがあっても、それを積み重ねていくのは簡単ではないだろう。だけど彼女はその度に「たまたま生まれたがんが右胸にあるだけ」、体の一部を失っても、私は私だと、自分の輪郭を確かめながら日常を送る。
その時、「私」は「自分」になった。離れていた場所にいた私が、自分の身体に根を下ろし、二重になっていた視線が、一つになった。私は私だ。私がニシカナコなのだと、その時、強烈に思った。(後略)
そういえば息子と、妹の子である姪は、母と私に胸や傷のことを詳しく聞いてきたことはない。きっと、生まれて物心ついたときから私たちにそれが「ない」のが、彼らにとって普通だからだろう。おばあちゃんはおばあちゃんであり、お母さんはお母さんなのだ。
私の足については、私自身も同じだ。何かを失っても、時に足りない自分に気づき、絶望しても、私は私なのだ。大丈夫。ほんとうにつらいときは、妹と笑い合ったあの日のことを思い出せばいい。
最終章で西さんは、『くもをさがす』は「あなた」に向けて書いた本だと言った。
(前略)これは「あなた」に向けて書いているのだと気づいた。(中略)
あなたは時に幸せで、時に不幸だった。あなたは時に健康で、時に健康を害していた。あなたは時に生きることそのものに苦しんでいて、あなたは時になんてことのない日常に無常の喜びを感じていた。
あなたに、これを読んでほしいと思った。
闘病記ではない。この本は、私のための本だ。
読み終えたあと、ふと気になって、蜘蛛の生態を調べた。蜘蛛は足を1、2本失っても、捕食行動に影響はないという。蜘蛛のたくましさに感心した頃、ぐう、とお腹が鳴った。最終章で流した涙はすっかり乾いていた。私も、けっこうたくましいのかもしれない。
文/高山 しのぶ
【この記事もおすすめ】