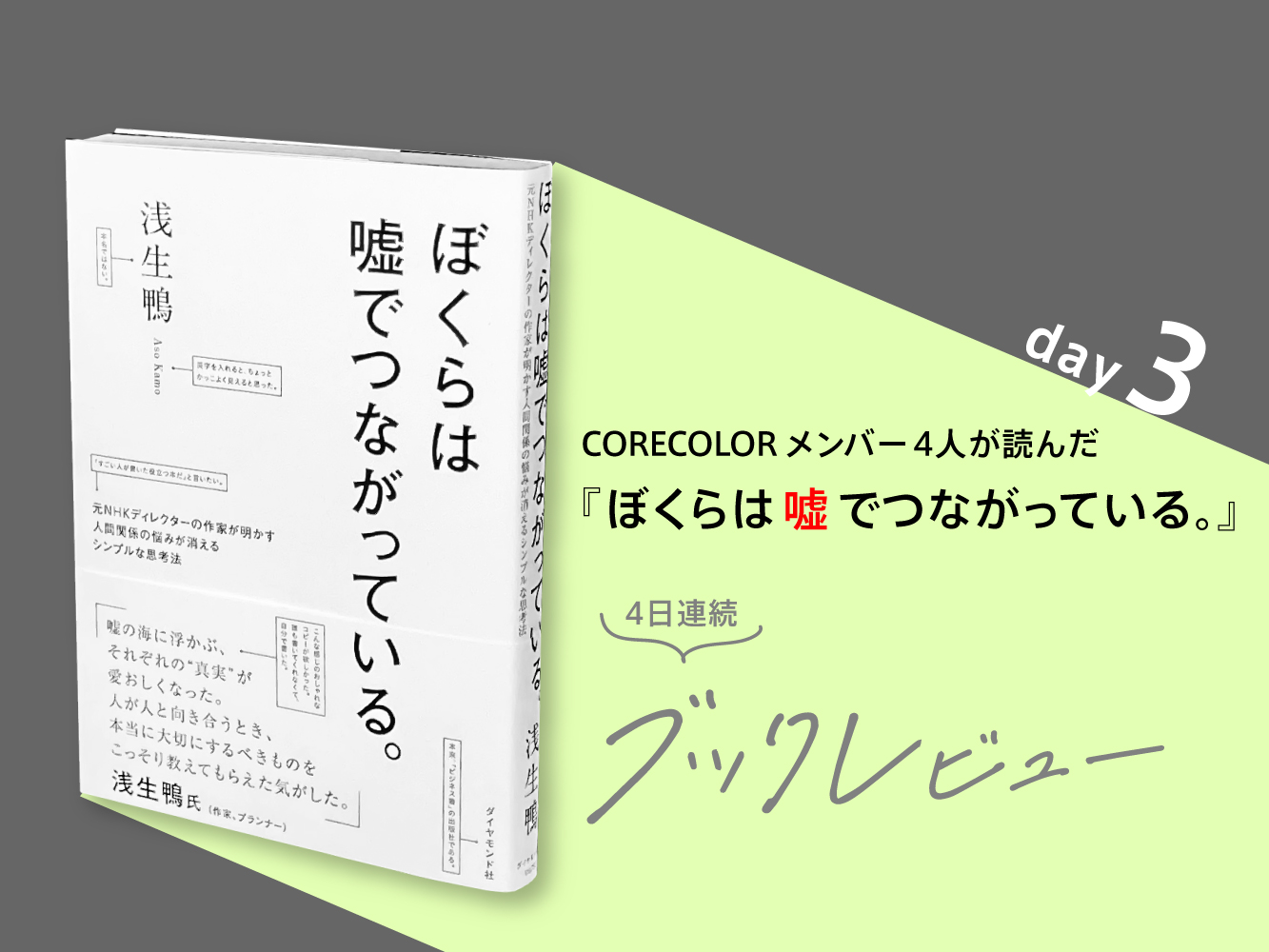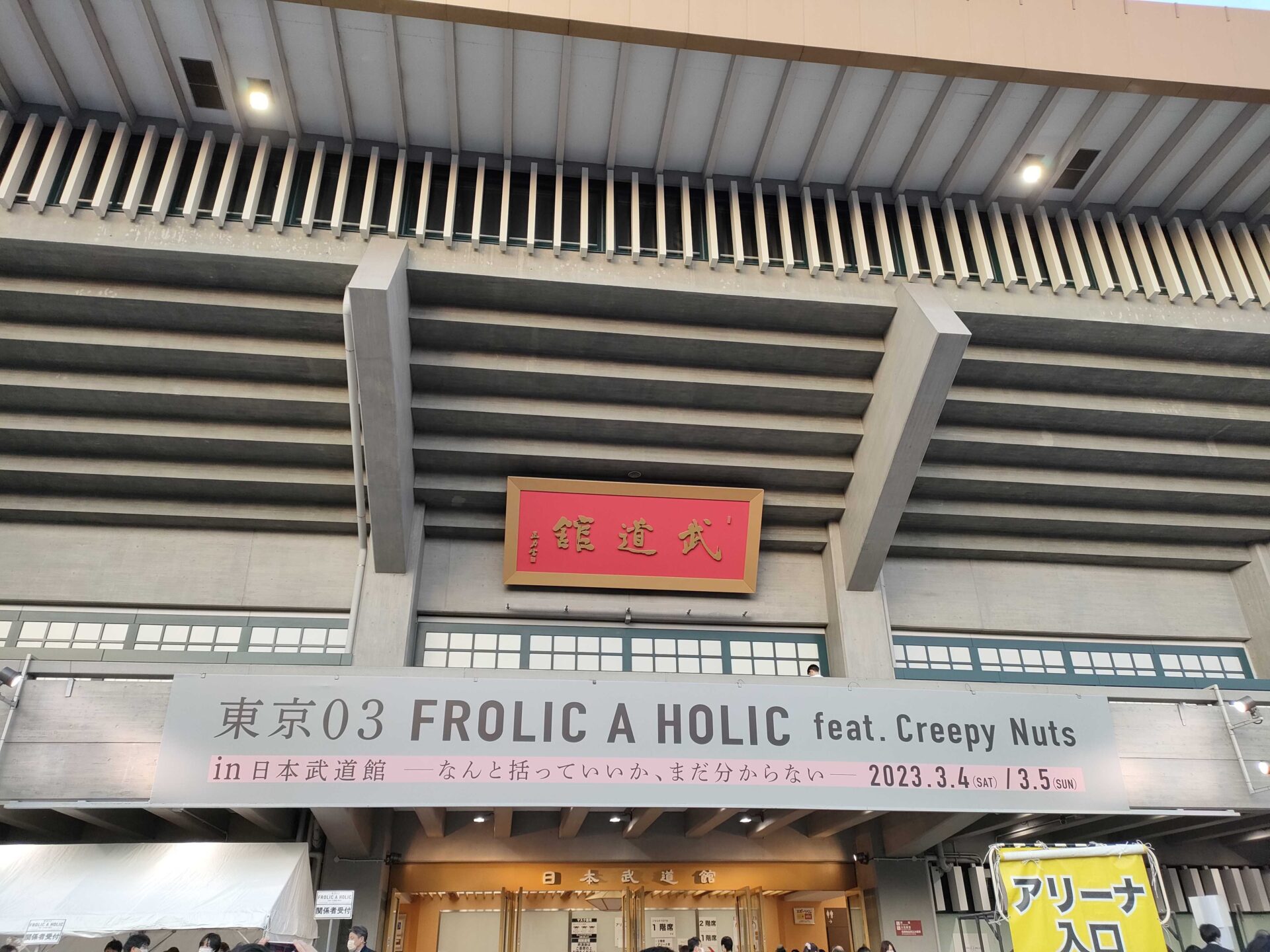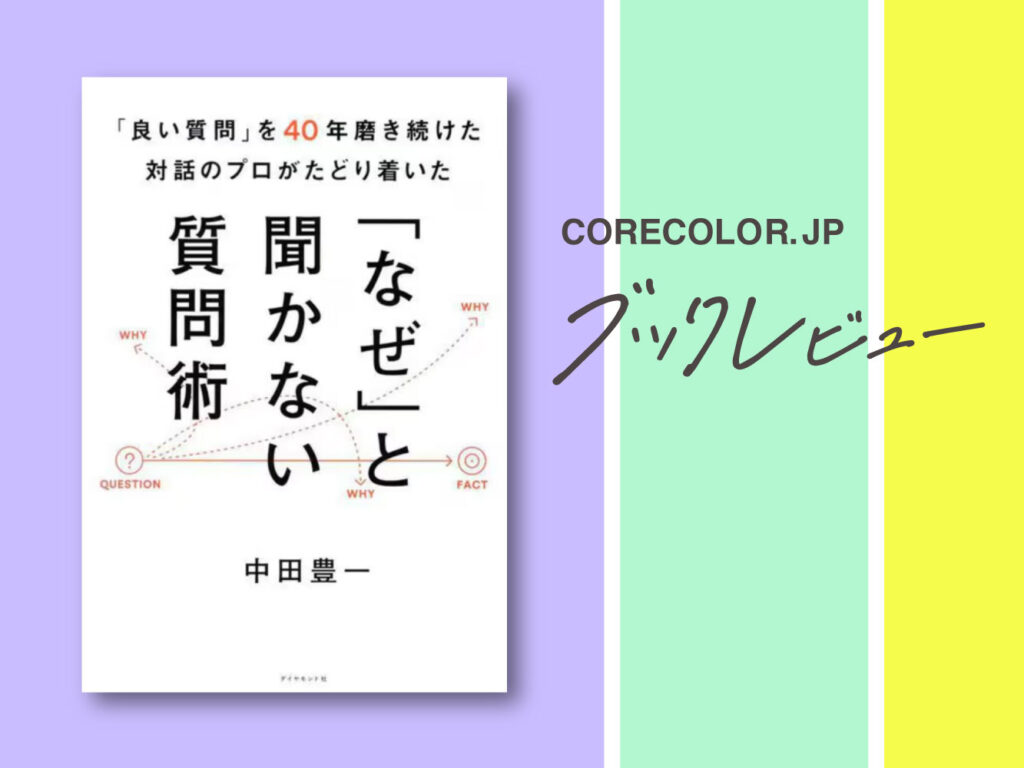
「なぜ」をやめたら、娘とのけんかが目に見えて減った。『 「なぜ」と聞かない質問術』
本書を手に取ったのは、インタビューの仕事に使える「質問術」が知りたかったからだ。
先日副業のライターの仕事で、ある企業の広報担当の方に1対1の対面インタビューをする機会があった。商品のPRの記事を書くため、「ブランドの立ち上げから、商品開発の経緯まで詳しく聞かせてください」と確保してもらっていた時間は1時間。ところが、相手の方は回答を用意してくれていたうえに話上手だったため、30分で準備をしていた質問がつきてしまったのだ。
そこから踏ん張る力が、私にはなかった。相手の「もう、よろしいんですか……?」と気遣う言葉に、自分の質問力のなさが際立ち、ちょっとだけ泣きそうになった。「インタビューの仕事を始めて2年以上もたつのに、質問が思いつかないなんて」と落ち込みながら、そそくさと部屋を出た。
そんな失敗を引きずりながら訪れた本屋で、ふと目に入ったのが本書だった。開発途上国支援をしている著者が、現地の人から本音を引き出すために20年かけて得た気づき、その後20年以上にわたって伝え続けてきた質問術が書かれているという。「なぜ」と聞かずにインタビューが成立するのだろうか? という疑問は抱きつつも、「とにかく、次回のインタビューの仕事までに、少しでも質問力をつけたい」とすがる気持ちで読み始めた。
だが、読み終わって一番に思ったのは、「これは仕事よりも、娘との会話を見直すための本だ!」ということだった。
最近、娘とは言い合いばかりしている。やってほしいことを何度伝えても、返ってくるのはあとでやるという生返事。もちろん待ってみたところでやらないので、「早くやりなさい!」と、「あとでやるってば!」の怒鳴り合いが日常茶飯事なのだ。小学2年生にしては早い気がするけれど、反抗期がきたのかなと半分諦めていた。けれど、毎日の娘とのいさかいは、私の方に原因があったらしい。
著者の中田さんによると、「なぜ」「どうして」といった英語でWhyの意味に当たる「なぜ質問」は、会話のねじれを生むのだという。「なぜ」と質問をしたときに相手から出てくる答えは、「その人が理由だと思い込んでいること」、または「理由に見せかけた自己防衛をするための言い訳」だからだそうだ。とりわけ、親と子、上司と部下、先生と生徒など、双方の力関係が対等ではない場合、それが顕著になるのだと中田さんはいう。
思い起こせば、私が娘にしてほしいことを伝えるとき、「なぜ質問」ばかりしていた。
「見ていいと決めた時間を過ぎているのに、なんでテレビを見ているの?」
「ご飯を食べたらお風呂に入ってって言ったのに、なんでまだ入っていないの?」
「寝るまでもう時間がないのに、なんで宿題をしてないの?」
これらを中田さんは「詰問型のなぜ質問」と呼ぶ。それをされた相手は、自分を守るために、とっさに言い訳をしてしまうのだそうだ。確かに私も、上司に「なんでこの仕事終わっていないの?」と聞かれたら、「他の仕事が忙しくて」などと言い訳をしてしまうだろう。つまり私は、「なんでしないの?」という質問の形でプレッシャーをかけて、娘に言い訳を強要していたのだ。
では、「なぜ」の代わりに何と言えばいいのか?
答えは、「いつ」なのだという。
例として、実際にあった父親と子どもの会話が挙げられていた。Side1がプレッシャーをかけているだけの「なぜ」バージョン。Side2が自然と自分の行動を見直させる「いつ」バージョンだ。
Side1
父「爪切っていないだろう。なんで早く切らないの?」
息子「うん、あとで切る!」
Side2
父「(子どもの爪が切られていないのを見て)爪切ったのいつだっけ?」
息子「(爪見て)あ、今から切るわ。」
この会話を読んでから私も、娘への「なんで?」の代わりに、「いつ?」と言うことを意識している。例えば本日(日曜日)の会話はこうだ。
私「(なんで明日の準備していないの? と言いそうなところをこらえて)いつ、明日の準備をするの?」
娘「明日の朝にする」
私「じゃあ、何時からやるの?」
娘「6時半に起きる(普段は7時起き)」
私「(おそらくそんなに早起きはできないだろうなと思うけれども)……わかった。じゃあ6時半に目覚ましセットしてね」
例の父と息子の会話ほど劇的な改善はされていないものの、毎日のようにあった言い合いが、「いつ」への言い換えを始めてからのここ数日は、ほとんどなかった。ただ、残念ながら娘に対する「なんでしないの?」は口癖になっているので、気を抜くとすぐに出てしまう。娘との良い関係を保つためにも、これからは言い換え修行を続けるつもりだ。
ところで、冒頭でインタビューの失敗から本書を手に取ったと書いたにもかかわらず、ここまで娘との会話の話ばかりしてしまった。しかしこの質問術は、インタビューでも参考になりそうだと感じている。
特に相手の考えや思いではなく、事実を聞きたいとき。「なぜ質問」だと、相手が事実だと思い込んでいる(が事実ではないかもしれない)ことを引き出してしまうと中田さんは述べていた。一方、「いつ」「何」「どこ」「誰が(誰と)」など、答えが1つに絞られる疑問詞なら、確実に事実を引き出すことができるのだという。
冒頭のインタビューで私は、相手の「考え」や「思い」まで、必ず聞かなければと考えていた。だが、あの場で最も大切だったのは、事実を引き出すことだったように思う。そして、「なぜ質問」を使わずに、「事実を聞くこと」に集中していれば、もっとスムーズに質問が出てきたような気がする。
本書の随所に出てくる「考えさせるな、思い出させろ」というワードをお守りに、次のインタビューに挑んでみようと思う。
文/朝野 めぐみ
【この記事もおすすめ】