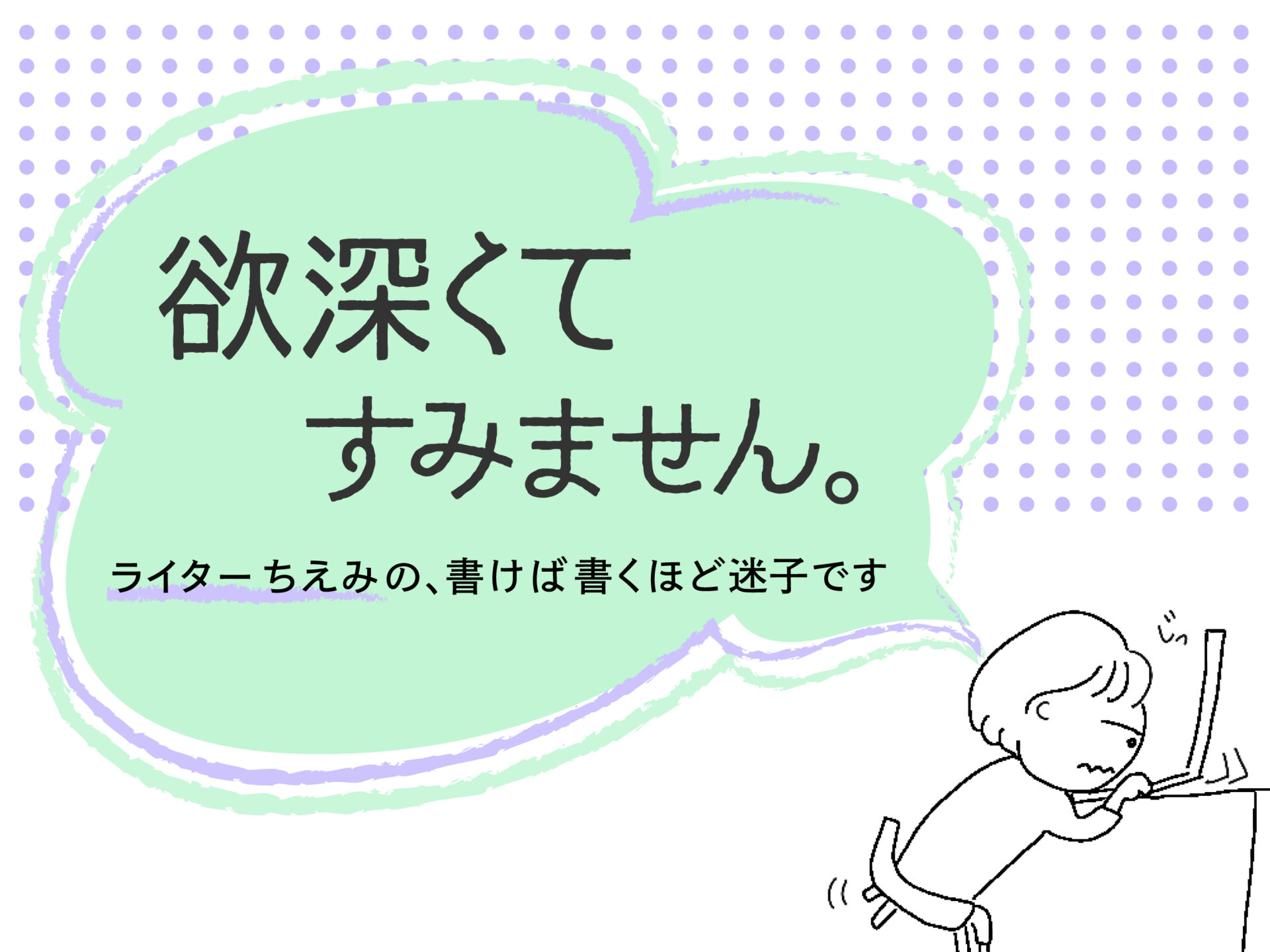ずっと目を逸らしてきた防災について、考えてみた。【連載・炭田のレシピ本研究室/第10回】
年間100冊以上のレシピ本を読むフードライターの炭田が、いま推したいレシピ本2冊を紹介する連載。今回は9月1日の「防災の日」にあわせて、防災レシピに挑戦します。
オシャレのためかと思ってたけど
友達が開いてくれた飲み会に参加した時のこと。はじめて会った年下の女の子が、レーシックを激推ししていた。「手術されてるとこ見えるの、怖くない?」とか「やっぱり高い?」とか「メイクっていつから出来るの?」とか、周りにいる女の子たちが口々に聞いている。オレンジっぽく染めたロングの髪が目を引く彼女は「10分くらいだから、意外と平気だよ」とか「焦げる匂いがするから、そっちの方が抵抗あるかも」と、一つひとつの質問に丁寧に答えていた。
私の視力は0.1を下回るし、小学1年生の頃から眼鏡を掛けているくらい目が悪いけど、怖いからやりたくないなぁと思って、みんなの話を聞くともなしに聞いていた。そしたらその女の子がクルッと私の方を向いて「地震が起きた時に、コンタクトとか眼鏡の人はすごく困ったって聞いたからやったんです」と言った。なるほど、防災……。この日から、3ヶ月が経った。まだレーシックをする勇気は出ない。
我が家は春先に引っ越しをした。その時「新居には防災グッズをしっかり揃えたいな」と思っていたのに、それすらまだ手を付けていない。でもせめて、いまの自分のまま出来ることからはじめたい。まずは食べ物だ。
マニアとはいえ、詳しくないジャンルもある
レシピ本と料理を愛する私だが、特別料理が上手い訳でも詳しい訳でもない。例えば家庭料理に馴染みのないフレンチなんかはパッパラパーであるからして、調理工程にさらりとパッセする、なんて書いてあっても「はにゃ?」である。
それでもそのジャンルの料理を作ってみたい時にどうやって本を選ぶかというと、まず「その分野のことを網羅的に知れるベーシックな1冊」に手を出す。そんなわけで今回のテーマである「防災」は、レシピサイトのクックパッドが出している『クックパッド防災レシピBOOK』をチョイスした。レシピだけではなく、在宅避難時の水の確保やトイレ対策などについても言及があり、防災のイロハがよく分かっていない私におあつらえ向きな本だ。
紹介されているレシピは、節水レシピや缶詰レシピなど災害時に役立つものながらも「いつもの料理」っぽいものばかりでホッとする。というのも、娘が小学1年生の頃に一緒に読んだ別の防災食の本は、切り干し大根やひじきなどの乾物や、コンビーフや豆などの渋めな缶詰を使用したレシピが多く、結局作らずじまいだった苦い思い出があるからだ。
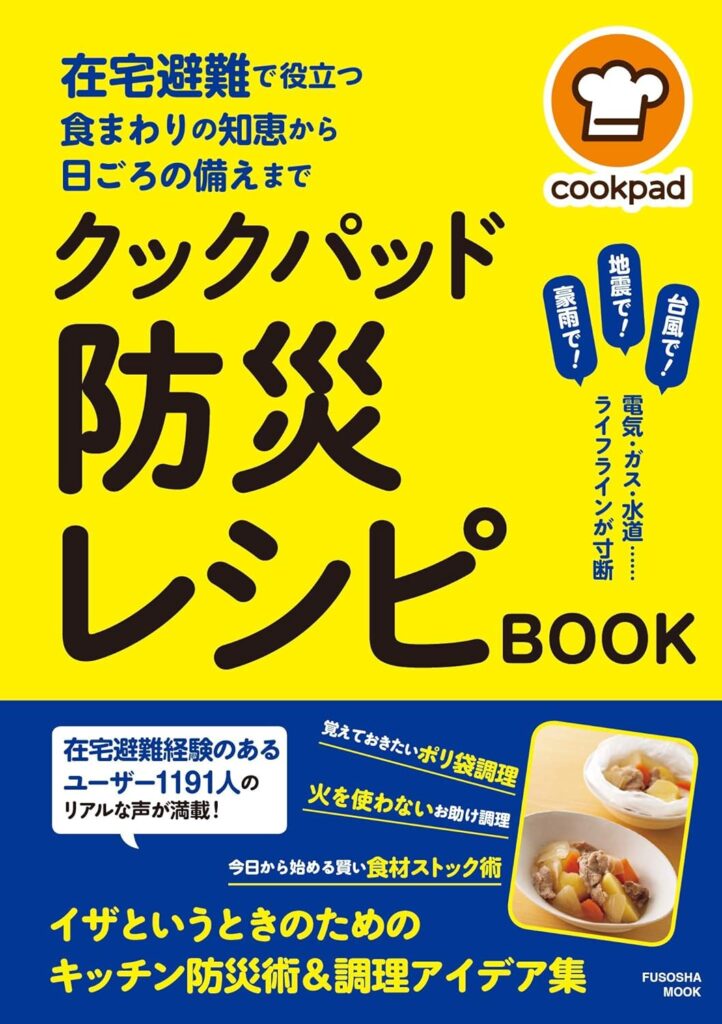
今回『クックパッド防災レシピBOOK』からいくつか作った中でのお気に入りは、電子レンジで作る「レンジ焼きそば」。はじめ作り方を見た時「え? 災害時なのにレンジ?」と思ったが、電気は水道とガスに比べると早く復旧するらしく、東日本大震災の時も3日後には約80%が復旧したそうだ。いままで防災食=缶詰やレトルト食品を食べる、というイメージだったので、災害時に「温かい食事」を食べられるのは有難い。そして「焼きそば」という子供が好きでいつもおいしそうに食べている料理を、水は1前大さじ1/2必要とはいえ火を使わずに作れるというのも心強い。本棚ではなく、防災バッグに入れておきたい1冊となった。
アイラップは予行練習必須!
ベーシックな1冊を手に取り気付いたのは、私は「いざ」という時、子供になるべく温かい食事を食べさせてあげたいと思っているということ。それにはどうやらアイラップの活用が良さそうだと思い至り、2冊目は『アイラップで簡単レシピ お役立ち防災編』を選んだ。
ただのポリ袋に見えるアイラップだが、耐熱温度が120℃ありレンジ調理や湯せん調理ができる。袋の中に食材を入れて調味、アイラップの口を結んでお湯にポチャンと投入すれば、洗い物無し&節水で料理ができる優れモノだ。サラダチキンなど茹でて作れそうな料理はもちろん、チャーハンやハンバーグ、オムレツなどもアイラップで作ることができる。度々Xなどでバズるのでその存在は知っていたが、実際に使ったことはなかったのでいざ初トライ。結果、平時にやっておいて良かったと、心底思った。
まず、我が家にある鍋の底のサイズに合う「耐熱皿」がなかった。どういうことかというと、高温になる鍋底にアイラップが直接つかないよう、調理時は鍋底に耐熱皿を敷く必要があるのだが、やってみると「このお皿はピッタリサイズだけど、高かったから湯せんしたくない……」とか「こっちは100均だけど、デカすぎる!」とか、調理前からてんやわんやだったからだ。災害時、耐熱皿がない場合は「ふきん」で代用OKとのことでやってみたが、ふわふわ浮いてきていつアイラップが溶けるか不安だったので、やはり耐熱皿を用意するのが安心だろう。後日、家にある鍋を持って100円ショップに行き、我が家の鍋にジャストサイズの耐熱皿(予備含め2枚)を購入した。
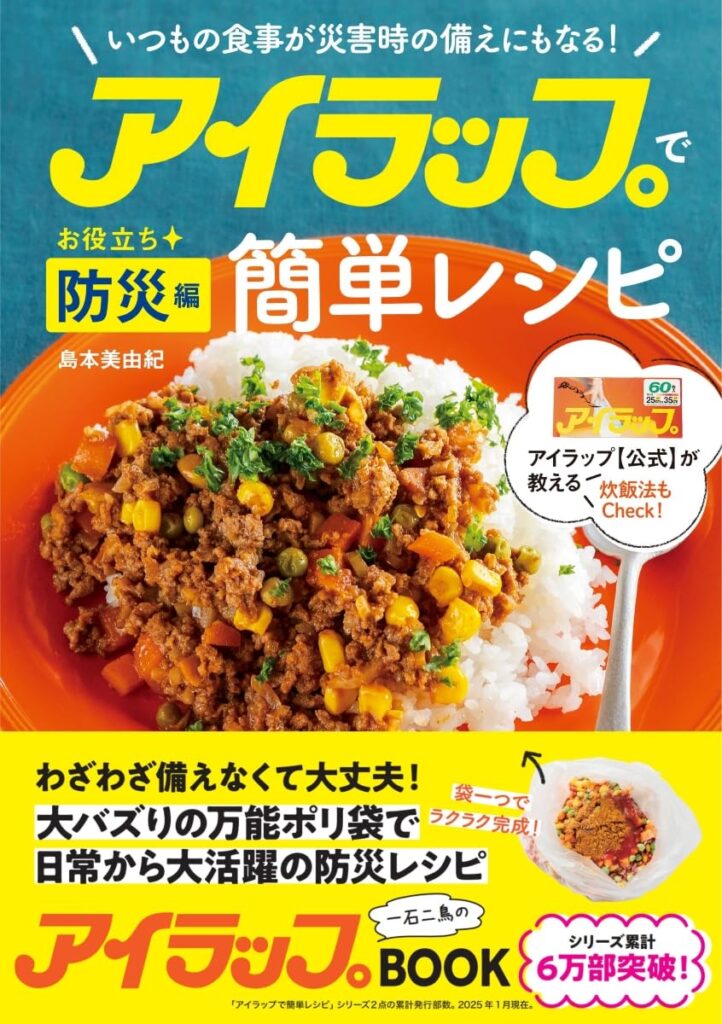
また、この本で役に立ったのが「災害時、まず優先すべきは冷蔵庫の中の食材」という考え方だ。確かに電気が使えなくなったからといって、冷蔵庫の中身がただちにダメになるわけではない。いきなり非常食を食べるのではなく、カセットコンロとアイラップを活用すれば、冷蔵庫の在庫で数日は凌げそうだと分かったのもよかった。そのためにも日頃からアイラップ調理に慣れておくべく、いまは慣らし運転中だ。こちらの本は、キッチンのすぐ手に取れるところに置いた。
一気にどうにかしようとしない
私はこれまで、防災のことを考えるのが億劫だった。たまに「今日こそやるぞ!」と思ってやおら立ち上がり、立ち上がったものの座り直してスマホで「防災リュック おすすめ」とかなんとか調べる。こっちはコンパクトで良さそう、こっちはお値打ちだな、あれ? これ100均でも揃うんじゃない? となって、今度は「100均 防災グッズ」で調べはじめる。そのうち比較するのが面倒になり「また今度にしよう……」と先送り。文字にするのも恥ずかしいが、ずっとこんな感じだった。
それがいまはアイラップ調理をしてみたり、家族が好きそうな味の缶詰をスーパーで探してみたり、毎日ほんの少しずつだがもしもの時に備えている。
こんなふうに日常で使うものを災害時にも活かすことで、いざという時に備える考え方を「フェーズフリー」と呼ぶらしい。今までの私は防災に対して、意気込み過ぎていたようだ。次の楽天ポイントアップデーには、おいしいと噂の防災食を取り寄せて、携帯トイレも買って試してみよう。この2冊をきっかけに、日々ちょっとずつ備えていきたい。
文/炭田 友望
【この記事もおすすめ】