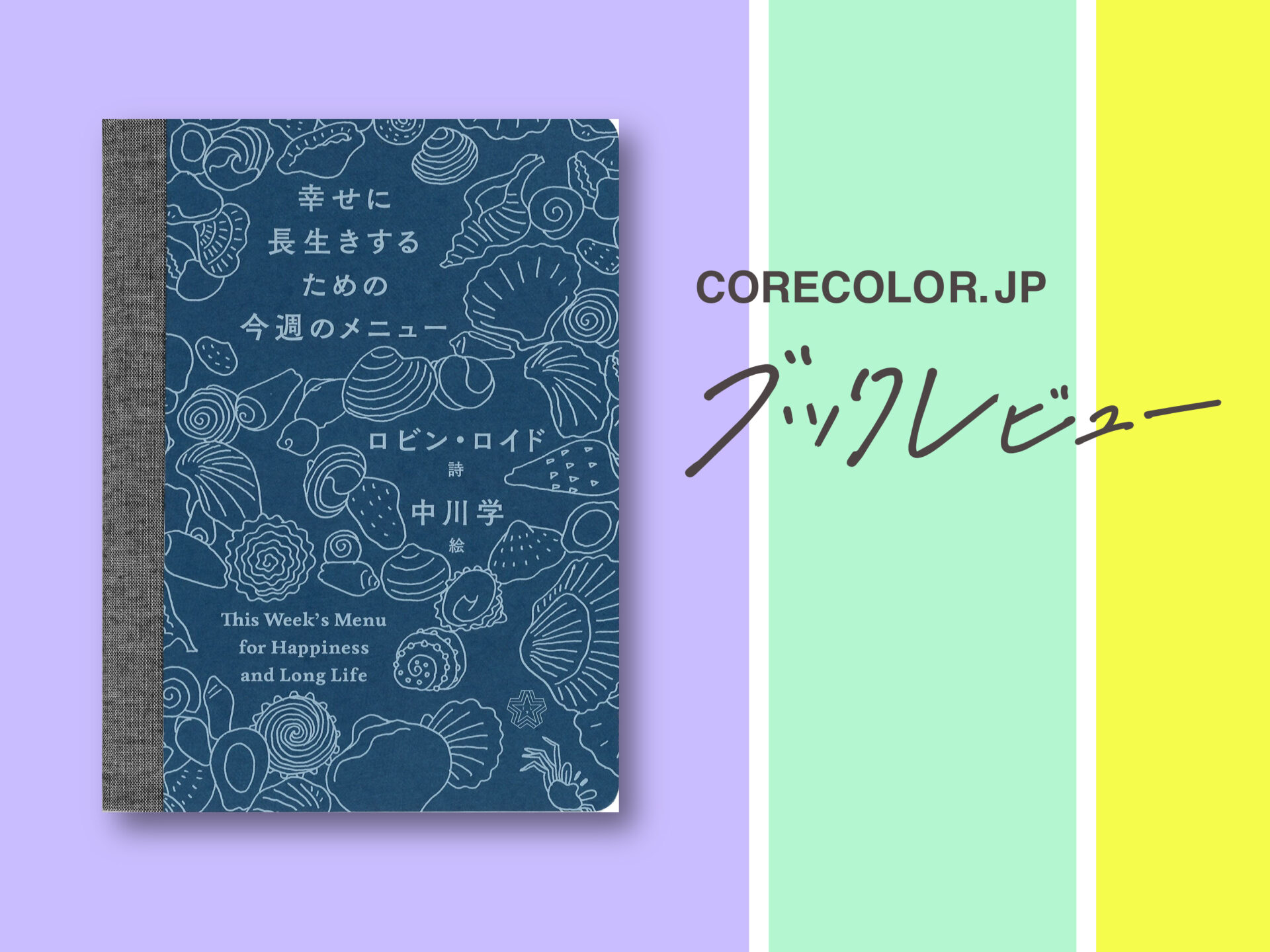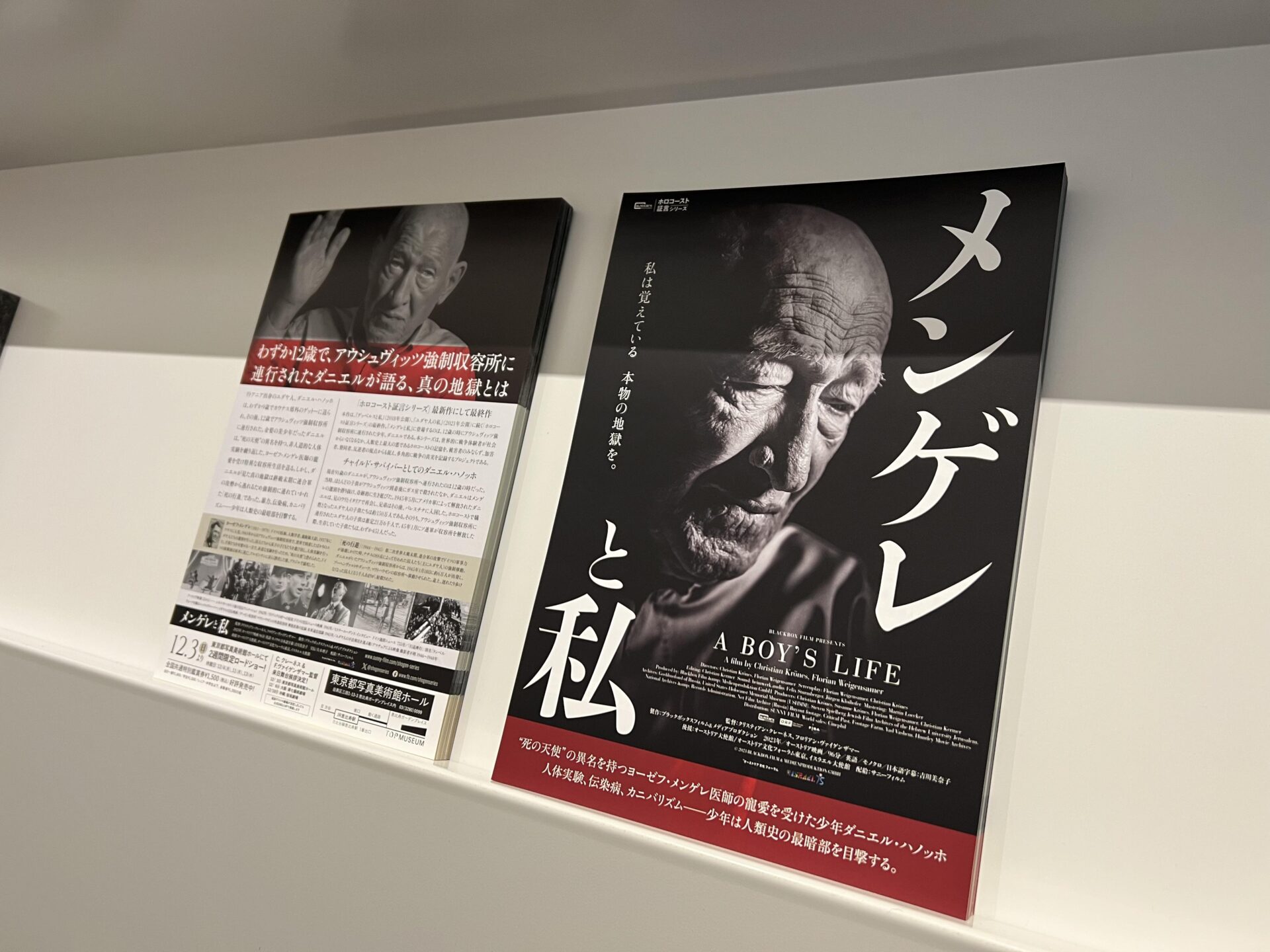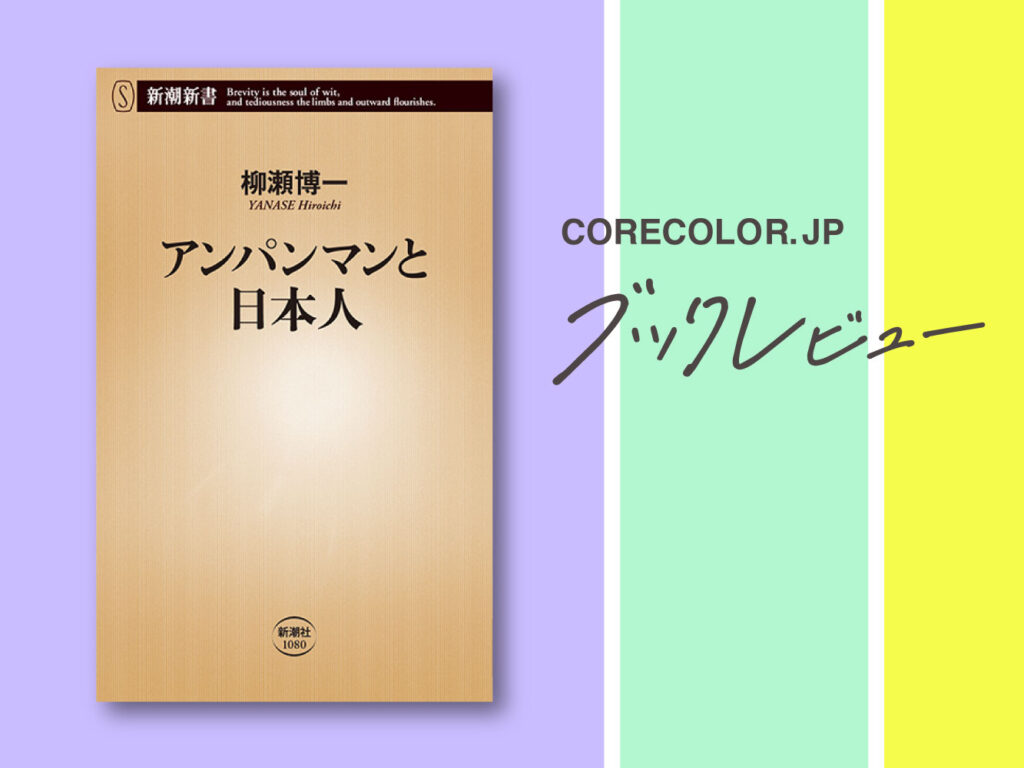
アンパンマンに2連敗した母は、パン工場から外に出た。『アンパンマンと日本人』
「あーぱ!」
そう言いながら次男が向かった先には、画面に映る「アンパンマン」の姿。テレビの前にあるベビーサークルにつかまって立ち、興奮気味に体を上下に揺らしながら画面をみつめている。言葉を話し始めたばかりの彼が発した「あーぱ」は、どうやら「アンパンマン」を指しているようだった。
アンパンマンに夢中になっている次男は、とてもとても愛おしい。ただ1つだけ、ちょっとだけ、納得のいっていないことがある。「おかあさん」とはまだ言わないのに、それより先に「あーぱ」と言えるようになるとは、一体どういうことなのか。お母さんは生まれたときから、何なら生まれる前からずっと一緒にいるのに。ぽっと出のアンパンマンを先に呼べるようになるなんて。
いや、待てよ。そういえば小学2年生になる長男も、はじめて喋った言葉は「あんまんまん(アンパンマン)」だった。「おかあさん」と呼んでくれるようになったのは、そのずっと後。もしかして私、アンパンマンに2連敗してる……?
長男も次男も、こちらから教えたわけでもないのに、いつの間にかアンパンマンを知り、いつの間にか大好きになっている。アンパンマンの何がそんなに子どもたちを惹きつけるのだろう。不思議に思っていたときに出会ったのが、『アンパンマンと日本人』だった。
本書では著者の柳瀬博一さんが、アンパンマンの生みの親である漫画家・やなせたかしさんの生涯をたどりながら、アンパンマンが子どもたちに大人気となった秘密を探っていく。
本には、私がアンパンマンに2連敗した理由が書かれていた。日本語圏の赤ちゃんが最初に話す言葉のランキングでは、第10位が「アンパンマン」だという。「おかあさん」は圏外。赤ちゃんは母音が「あ」の言葉が言いやすいらしく、「アンパンマン」や「ばいきんまん」はその条件にあてはまるとのことだった。
そうか。だから私はアンパンマンに2連敗したのか。仕方ない、素直に受け入れよう。私はアンパンマンへの嫉妬心をそっとしまい、本を閉じた。そして、スマホから地元のビジネスセミナーに申し込んだ。
何の話だと思うかもしれないが、よければ聞いてほしい。
この本で得られたのは、私がアンパンマンに2連敗した理由だけではない。原作者のやなせたかしさんの生涯を通じて、私のフリーランスとしての今後の生き方を考えるきっかけを得たのである。
これまで私は「やなせたかしさん=アンパンマンの原作者」のイメージしか持っていなかったのだが、それは違っていた。新聞記者、百貨店のアートディレクター、広告漫画家、舞台装置の制作者、ラジオの脚本家などなど……。やなせさんの活動は、アンパンマンどころか、漫画家の枠を超えて多方面に渡っていたのである。
こうした幅広い分野で活躍していた理由の1つが、「頼まれた仕事を断らなかったから」だという。なるほど! と思ったが、すぐに「いやいやいや、そんなわけないでしょう」と心の中で突っ込んだ。いくら断らないにしても、限度がありませんか。普通の人はまず、これほど幅広い仕事を頼まれる機会すらないのでは? その点に関して本書は、やなせさんが「未知の仕事に飛び込む勇気と好奇心の持ち主」だったことが関係していると述べる。
これまで経験がないどころか、世の中で誰も手掛けたことがない仕事でも全力で取り組み、お客さんからのオーダーに120%で応える。その姿勢こそが、「この人ならきっとどうにかしてくれるはずだ」と信頼され、次々に仕事が舞い込んできた理由だったという。
そうか、と納得すると同時に、私は少しだけ呼吸が苦しくなった。そのときの私は、仕事が思うようにいっていなかった。「やったことがない仕事にもチャレンジしてみよう! オーダーに120%で応えよう!」と思っても、そもそも相手がいないのである。情けなくて泣きそうになった。おこがましいのは重々承知だけれど、私もやなせさんのように信頼される人になりたい……。
悶々と考えている私にヒントをくれたのも、やなせさんの生き方だった。彼が多岐に渡る分野で「頼まれ仕事」を引き受けたのは、次の仕事が欲しかったからでも、人脈を広げたかったからでもない。ただ純粋に、出会った人の「困りごと」を助けたいと思ったからだという。
ああ、そうか。私はどこか、「自分のため」に仕事を引き受けていなかっただろうか。あからさまな言動は見せなくても、無意識に滲み出ていたかもしれない。「自分のスキルを向上させたい」「次の仕事に繋げたい」といった、自分の目的のために頼まれごとを引き受けるのではなく、相手に喜んでほしいという気持ちを原動力に、全力を傾ける姿勢が大切なのだ。この姿勢は、やなせさんが生み出した「お腹が空いて困っている人に無償で自分の顔を分け与えるヒーロー、アンパンマン」そのものだといえる。
だとしたら、私はもしかしたらばいきんまんなのかもしれない。「打倒アンパンマン」を掲げ、いつも悪だくみをしてはアンパンマンに懲らしめられている、ばいきんまん。ただ一方で、ばいきんまんがあの手この手でアンパンマンを倒そうと考えるように、自分の目的達成のために戦略を練るのが悪いことだとは、一概に言い切れないだろう。人間が働いて生きていくうえでは、アンパンマンのような見返りを求めない利他的精神と、ばいきんまんのような戦略性の両方のバランスが大事なのかもしれない。
実際、やなせさん自身も「ばいきんまんは完全悪ではない」と語っている。「アンパンマンの素となるパンも、酵母菌という菌がないと作れないから」だそうだ。とはいえ、いまの私にはばいきんまんが多すぎる。せめて7対3くらいにアンパンマン部分を増やせないだろうか。あれこれ考えを巡らせた末、「そもそも外に出なければ何もはじまらないのでは?」という結論に至った。
アンパンマンはいつも、困った人がいないか空を飛んでパトロールをしている。草原や海、砂漠や雪山まで、広い世界を隅々まで見て回る。お腹が空いた人がいたら自分の顔を分け与え、自分がピンチに陥ったときには周りの人に助けてもらいながら生きている。アンパンマンがパン工場の椅子に座り、「困っている人は来ないかな」と待っている姿なんて、一度も見たことがない。
一方、今の私はどうか。家と言う名のパン工場に閉じこもり、何か良いご縁はないかとうじうじしているだけではないだろうか。アンパンマンを見習うなら、まず外に出て、たくさんの人と自分から触れあわなければ。
アンパンマンは困った人を助け、相手に感謝されたとき、心が「ポカポカ」するそうだ。そのポカポカだけで十分幸せで、見返りは何一つ求めていない。私はまだまだアンパンマンには遠いけれど、そんな私でも相手が喜んでくれたときに感じる心のポカポカなら知っている。
そうか、あの感覚をもっと積み重ねていけたらいいんだな。そのためにも、まずはパン工場の外に出よう。とにかく人と会おう。そう思い、セミナーの申込ボタンを押した。
文/中道 侑希
【この記事もおすすめ】